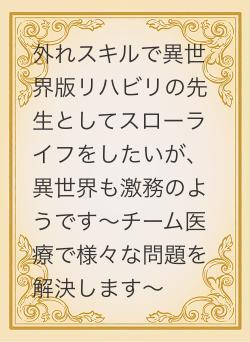屋根があるだけでも十分な生活。
食べる物があるだけでも、最低限生きていける確証があるだけで僕達には贅沢だった。
僕は小さい頃から妹のアリアと二人で暮らしている。両親は仕事に行ったきり帰ってこず、残されたのはわずかに風と雨が凌げる程度の家だけだ。
そんな僕達を襲ったのは妹の難病。
――魔力喰い
正式名称はわからないが、体の中にある魔力を少しずつ食らいつくと言われている。やがて体の中の魔力がなくなると、生命まで食らいついてしまうという病気だ。
「お兄ちゃんはいつ帰ってくるの?」
「んー、今度はダンジョンに探索に行ってくるから三日間ぐらいかな」
たくさんの食料を買い溜めて、ベッドの周囲に置いておく。すでに妹の魔力は減り、日常生活を送るだけでも体力が減ってしまうため、ベッドで過ごしている。
魔力を分け与える力があれば良いが、そんなことができるのは高位の魔術師ぐらいだ。
魔力ポーションも結構高いため、そんな簡単に変える物でもない。
そして、僕の外れスキル【ガチャテイム】では魔力喰いをどうすることもできない。
この世は10歳になるとスキルが与えられる。
僕のスキルは魔物を倒すと、稀に手に入れることができる変わったコイン。通称"ガチャコイン"を使うことで、テイムできる魔物が決まるというスキルだ。
ただ、魔物の使用制限も決まっているため、使用制限がない魔物を召喚するスキル【召喚士】と魔物を手懐ける【テイマー】と比べると劣化版のようなスキルだ。
聞いたことのない唯一無二のスキルで喜んだのは、スキルが与えられたあの時だけだ。
一度ガチャからゴブリンを手に入れたが、体臭が臭く回数制限が3回だった。そんな彼もすでにいなくなっている。
僕の目の前で僕を守るように命を失った彼と、再び会えることを夢見ているが、ガチャコインを手に入れることがないため、それっきりテイムしたことはない。
ガチャコインを手に入れるには、僕が魔物を倒さないといけないからだ。
戦う力がない僕が戦闘に参加するには、パーティーに参加する必要がある。だが、実際はそうもいかないのが現実だ。
「おい、荷物持ち早くしろ!」
「ごめんなさい」
戦う力がない僕は荷物持ちとして、パーティーに入れてもらっている。今回はいつもは持ち歩かないアイテムも持たされているため、歩くのに時間がかかってしまったようだ。
優しい冒険者であれば、トドメを譲ってくれる人もいたが、皆自分のスキルを成長させるために、そんなことはさせてくれない。
スキルを強くするには、そのスキルをたくさん使うか魔物をたくさん倒す必要がある。
スキルの発動もできず、魔物を倒せない僕に出来ることは荷物持ちという仕事だけだった。
そもそも孤児の僕を雇ってくれるところはないため、冒険者になるという選択肢しかなかった。
今日の仕事もダンジョン探索の荷物持ちだ。
僕はダンジョンの攻略のために、荷物持ちで雇ってくれたAランクパーティーの冒険者の後ろをついていく。
今回の冒険者はどこか身なりも良く、冒険者には珍しいタイプの人達だ。
彼らの話ではこのダンジョンには、ミスリルという鉱石が手に入るらしい。
戦う力がない僕でも、彼らのように強い冒険者であれば命が危険な目に遭うことはないのだ。
「おい、砥石を出せ」
僕は鞄から砥石を取り出す。大きな扉の前に到着した彼らは装備を整える。
ダンジョンの奥には、ダンジョンボスと呼ばれる強い魔物が存在している。
そのダンジョンボスを倒すことで、強い武器やアイテム。そしてミスリルのような鉱石が手に入るらしい。
僕の仕事は彼らの荷物をこのボス部屋の前まで運ぶことだ。
「おい、お前ら準備はできたか?」
「ああ、こっちも大丈夫だ」
扉を開けて中に入っていく彼らを、手を振りながら見送る。
「皆さん頑張ってください」
扉が少しずつ閉まっていくと同時に、パーティーメンバーは振り返りにやりと笑った。
その笑顔になぜか背筋がゾクゾクとした。
なぜか彼らはダンジョンの中に入ると同時に腰に下げている袋から、小さなツルハシのようなものを取り出した。
どこか違和感を感じると同時に、扉の奥から手が伸びてきた。後ろに下がって逃げようとするが、すでに遅かった。
「えっ……」
体が軽く僕はそのまま僕の体は宙を舞い、気づいた時には僕はボス部屋の真ん中に投げられていた。
受け身も取れないガリガリに痩せ細った僕の体が、地面に落ちるとどうなるだろうか。
そう、簡単に骨が折れてしまう。
あまりの痛みにもがき苦しむが、そんなこともできない。
「ははは、あとは時間稼ぎ頑張ってくれよ」
そこには大きなフェンリルが目の前にいた。
僕は元からフェンリルの餌として時間稼ぎをするために連れて来られたのだと、ここにきてわかった。
冒険者達はダンジョンの壁に光る石を掘り出そうと、袋から取り出したツルハシを叩きつけていた。
無知だからそんなことも気づかなかった。
鉱石はダンジョンボスからドロップするのではない。
ダンジョン部屋の壁から掘り出すことを。
――グルルルル!
フェンリルの威嚇が部屋中に大きく鳴り響く。咄嗟に耳を閉じたが、遅かったのか全身が震え出してしまう。
僕は必死に逃げようとするが、足がすくんで動かない。
「おい、あいつが逃げないようにしろ」
「わかったわ!」
風を切るように何かが近づく音が聞こえてきた。その瞬間、僕の足に痛みが走った。
「うっ……」
冒険者パーティーにいる弓使いが、僕の足を目掛けて弓を放ったのだ。ただでさえ、足の骨が折れているのに、矢の痛みで動くこともできなくなった。
ああ、きっとここで僕は死ぬのだろう。
目の前にいるフェンリルを見て死を覚悟した。
心残りがあるのは妹のアリアより先に死ぬことだ。
きっとアリアは今のままだと死ぬことになる。でも、兄の僕が先に天国にいたら、妹は迷わずに天国に行けるだろう。
「ははは、これで俺達も大金持ちだぜ! あいつが馬鹿な冒険者でよかったぜ!」
きっと鉱石を掘り終えたのだろう。荷物を持って急いで、冒険者達はダンジョン部屋から出て行く。
残されたのはフェンリルと僕の二人だ。
僕は食べられて死ぬ覚悟を決めた。
『小僧ちょっとわしの背中を掻いてくれないか?』
突然聞こえてきた声に僕はびっくりした。知能が高い魔物は話せると聞いたことがあったが、本当に話せるとは思ってもみなかったのだ。
「えっ?」
『ん? わしの声が聞こえなかったのか?』
いや、声は聞こえています。どちらかと言えば、魔物が話していることに驚いている。
「背中を掻いてほしいと……」
『そうじゃ! ずっと背中がムズムズしてさっき威嚇してしまったわ!』
どうやらフェンリルはただ背中が痒いだけらしい。あの全身が震えた威嚇が、ただ背中が痒いと嘆いていただけとは……。
「あのー、背中を掻きましょうか?」
『本当か? 助かるぞ!』
僕は血が出た右足と骨折した左足を引きずって近づく。だが、痛みですぐに転んでしまう。
『小僧遅いぞ!』
フェンリルは怒ったのか、大きな口を開けて僕を咥える。勢いよく持ち上げられ、空中を舞う。
ああ、このまま食べられるのか。
そう思ったが体に感じる感触は違った。
「ふわふわ……いや、もふもふ?」
僕はそのままフェンリルの背中に乗ると転がされる。怪我をした足でも、フェンリルの毛が緩衝作用となり痛みをあまり感じなかった。
行き着いたのは背中と尻尾の間くらいだ。
『その辺が痒いから掻いてくれないか?』
僕は言われた通りに掻いていく。柔らかくしっかりとした毛並みに、僕はついつい頬をスリスリしながら撫でる。
今まで感じたことのない幸福感にフェンリルの背中にいることを忘れてしまう。
『うぉ、うおおおお! そこそこじゃ!』
どうやらフェンリルは気持ち良いようだ。僕はその後もフェンリルの背中を堪能する。
せっかく死ぬなら、この幸福感を最大まで味わいたいと思ったのだ。
『ぬおおおお! このままじゃ昇天しちまう――』
気づいた時には僕は宙に浮いていた。さっきまでいたフェンリルは一瞬輝くといなくなり、僕は大量のお金とフェンリルのドロップ品とともに地面に落ちていく。
「うああああ!」
どうやら僕はフェンリルを倒したようだ。
食べる物があるだけでも、最低限生きていける確証があるだけで僕達には贅沢だった。
僕は小さい頃から妹のアリアと二人で暮らしている。両親は仕事に行ったきり帰ってこず、残されたのはわずかに風と雨が凌げる程度の家だけだ。
そんな僕達を襲ったのは妹の難病。
――魔力喰い
正式名称はわからないが、体の中にある魔力を少しずつ食らいつくと言われている。やがて体の中の魔力がなくなると、生命まで食らいついてしまうという病気だ。
「お兄ちゃんはいつ帰ってくるの?」
「んー、今度はダンジョンに探索に行ってくるから三日間ぐらいかな」
たくさんの食料を買い溜めて、ベッドの周囲に置いておく。すでに妹の魔力は減り、日常生活を送るだけでも体力が減ってしまうため、ベッドで過ごしている。
魔力を分け与える力があれば良いが、そんなことができるのは高位の魔術師ぐらいだ。
魔力ポーションも結構高いため、そんな簡単に変える物でもない。
そして、僕の外れスキル【ガチャテイム】では魔力喰いをどうすることもできない。
この世は10歳になるとスキルが与えられる。
僕のスキルは魔物を倒すと、稀に手に入れることができる変わったコイン。通称"ガチャコイン"を使うことで、テイムできる魔物が決まるというスキルだ。
ただ、魔物の使用制限も決まっているため、使用制限がない魔物を召喚するスキル【召喚士】と魔物を手懐ける【テイマー】と比べると劣化版のようなスキルだ。
聞いたことのない唯一無二のスキルで喜んだのは、スキルが与えられたあの時だけだ。
一度ガチャからゴブリンを手に入れたが、体臭が臭く回数制限が3回だった。そんな彼もすでにいなくなっている。
僕の目の前で僕を守るように命を失った彼と、再び会えることを夢見ているが、ガチャコインを手に入れることがないため、それっきりテイムしたことはない。
ガチャコインを手に入れるには、僕が魔物を倒さないといけないからだ。
戦う力がない僕が戦闘に参加するには、パーティーに参加する必要がある。だが、実際はそうもいかないのが現実だ。
「おい、荷物持ち早くしろ!」
「ごめんなさい」
戦う力がない僕は荷物持ちとして、パーティーに入れてもらっている。今回はいつもは持ち歩かないアイテムも持たされているため、歩くのに時間がかかってしまったようだ。
優しい冒険者であれば、トドメを譲ってくれる人もいたが、皆自分のスキルを成長させるために、そんなことはさせてくれない。
スキルを強くするには、そのスキルをたくさん使うか魔物をたくさん倒す必要がある。
スキルの発動もできず、魔物を倒せない僕に出来ることは荷物持ちという仕事だけだった。
そもそも孤児の僕を雇ってくれるところはないため、冒険者になるという選択肢しかなかった。
今日の仕事もダンジョン探索の荷物持ちだ。
僕はダンジョンの攻略のために、荷物持ちで雇ってくれたAランクパーティーの冒険者の後ろをついていく。
今回の冒険者はどこか身なりも良く、冒険者には珍しいタイプの人達だ。
彼らの話ではこのダンジョンには、ミスリルという鉱石が手に入るらしい。
戦う力がない僕でも、彼らのように強い冒険者であれば命が危険な目に遭うことはないのだ。
「おい、砥石を出せ」
僕は鞄から砥石を取り出す。大きな扉の前に到着した彼らは装備を整える。
ダンジョンの奥には、ダンジョンボスと呼ばれる強い魔物が存在している。
そのダンジョンボスを倒すことで、強い武器やアイテム。そしてミスリルのような鉱石が手に入るらしい。
僕の仕事は彼らの荷物をこのボス部屋の前まで運ぶことだ。
「おい、お前ら準備はできたか?」
「ああ、こっちも大丈夫だ」
扉を開けて中に入っていく彼らを、手を振りながら見送る。
「皆さん頑張ってください」
扉が少しずつ閉まっていくと同時に、パーティーメンバーは振り返りにやりと笑った。
その笑顔になぜか背筋がゾクゾクとした。
なぜか彼らはダンジョンの中に入ると同時に腰に下げている袋から、小さなツルハシのようなものを取り出した。
どこか違和感を感じると同時に、扉の奥から手が伸びてきた。後ろに下がって逃げようとするが、すでに遅かった。
「えっ……」
体が軽く僕はそのまま僕の体は宙を舞い、気づいた時には僕はボス部屋の真ん中に投げられていた。
受け身も取れないガリガリに痩せ細った僕の体が、地面に落ちるとどうなるだろうか。
そう、簡単に骨が折れてしまう。
あまりの痛みにもがき苦しむが、そんなこともできない。
「ははは、あとは時間稼ぎ頑張ってくれよ」
そこには大きなフェンリルが目の前にいた。
僕は元からフェンリルの餌として時間稼ぎをするために連れて来られたのだと、ここにきてわかった。
冒険者達はダンジョンの壁に光る石を掘り出そうと、袋から取り出したツルハシを叩きつけていた。
無知だからそんなことも気づかなかった。
鉱石はダンジョンボスからドロップするのではない。
ダンジョン部屋の壁から掘り出すことを。
――グルルルル!
フェンリルの威嚇が部屋中に大きく鳴り響く。咄嗟に耳を閉じたが、遅かったのか全身が震え出してしまう。
僕は必死に逃げようとするが、足がすくんで動かない。
「おい、あいつが逃げないようにしろ」
「わかったわ!」
風を切るように何かが近づく音が聞こえてきた。その瞬間、僕の足に痛みが走った。
「うっ……」
冒険者パーティーにいる弓使いが、僕の足を目掛けて弓を放ったのだ。ただでさえ、足の骨が折れているのに、矢の痛みで動くこともできなくなった。
ああ、きっとここで僕は死ぬのだろう。
目の前にいるフェンリルを見て死を覚悟した。
心残りがあるのは妹のアリアより先に死ぬことだ。
きっとアリアは今のままだと死ぬことになる。でも、兄の僕が先に天国にいたら、妹は迷わずに天国に行けるだろう。
「ははは、これで俺達も大金持ちだぜ! あいつが馬鹿な冒険者でよかったぜ!」
きっと鉱石を掘り終えたのだろう。荷物を持って急いで、冒険者達はダンジョン部屋から出て行く。
残されたのはフェンリルと僕の二人だ。
僕は食べられて死ぬ覚悟を決めた。
『小僧ちょっとわしの背中を掻いてくれないか?』
突然聞こえてきた声に僕はびっくりした。知能が高い魔物は話せると聞いたことがあったが、本当に話せるとは思ってもみなかったのだ。
「えっ?」
『ん? わしの声が聞こえなかったのか?』
いや、声は聞こえています。どちらかと言えば、魔物が話していることに驚いている。
「背中を掻いてほしいと……」
『そうじゃ! ずっと背中がムズムズしてさっき威嚇してしまったわ!』
どうやらフェンリルはただ背中が痒いだけらしい。あの全身が震えた威嚇が、ただ背中が痒いと嘆いていただけとは……。
「あのー、背中を掻きましょうか?」
『本当か? 助かるぞ!』
僕は血が出た右足と骨折した左足を引きずって近づく。だが、痛みですぐに転んでしまう。
『小僧遅いぞ!』
フェンリルは怒ったのか、大きな口を開けて僕を咥える。勢いよく持ち上げられ、空中を舞う。
ああ、このまま食べられるのか。
そう思ったが体に感じる感触は違った。
「ふわふわ……いや、もふもふ?」
僕はそのままフェンリルの背中に乗ると転がされる。怪我をした足でも、フェンリルの毛が緩衝作用となり痛みをあまり感じなかった。
行き着いたのは背中と尻尾の間くらいだ。
『その辺が痒いから掻いてくれないか?』
僕は言われた通りに掻いていく。柔らかくしっかりとした毛並みに、僕はついつい頬をスリスリしながら撫でる。
今まで感じたことのない幸福感にフェンリルの背中にいることを忘れてしまう。
『うぉ、うおおおお! そこそこじゃ!』
どうやらフェンリルは気持ち良いようだ。僕はその後もフェンリルの背中を堪能する。
せっかく死ぬなら、この幸福感を最大まで味わいたいと思ったのだ。
『ぬおおおお! このままじゃ昇天しちまう――』
気づいた時には僕は宙に浮いていた。さっきまでいたフェンリルは一瞬輝くといなくなり、僕は大量のお金とフェンリルのドロップ品とともに地面に落ちていく。
「うああああ!」
どうやら僕はフェンリルを倒したようだ。