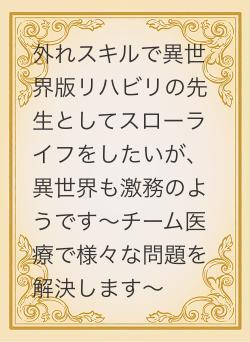俺達は食事を終えると2人ずつで野営の見張りをすることとなった。順番ずつに交代することになっているがなぜか俺とエヴァンが組むようにプリシラとニアに仕組まれていた。
「おい、お前」
「なんだよ」
俺はわざと関わらないようにしていたが、夜で何もやることがなくなったからなのかエヴァンが声をかけてきた。
「なんで獣人を家族って──」
「ロンとニアだ」
俺がエヴァンを睨むと彼は名前を言い直していた。
「なんで家族って言ってるんだ?」
確かに俺達の関係を知らない人であれば気になるのだろう。
「俺が森の中でロンとニアを助けて家族になることにした」
俺は出会った時から自分が家族になると決めた日や死んでも守ると決めた日など今まであったロンとニアが家族になった経由を話した。
「うっ……」
「おい!?」
「べっ、別に泣いてなんかいねーぞ!」
エヴァンは顔を伏せて鼻をすすっていた。
「まぁ、だからあいつらは俺の家族なんだよ。 俺は小さい頃から家族が居なくてさ……」
俺は小さい時のわずかな記憶はあるがはっきりと母と父の顔は覚えていない。ただ、覚えているのは笑顔で俺を何かの箱に入れて笑っていなくなった顔だけだ。
その後、箱を開けられた時には辺りは焼け野原になっており、俺を育ててくれたのは見知らぬおじいちゃんとおばあちゃんだった。
だから俺の中で見知らぬロンとニアが家族になることに抵抗はなかった。
また、その時の影響なのか真っ暗なところに長時間いるのも狭いところで閉じ込められるのも精神的にダメになった。
「うっ……もう俺ダメだわ」
エヴァンはこういう話に弱いのかさっきまで顔を伏せていたはずがいつのまにか隠さず泣いていた。
どこからか鼻をすする音が聞こえてきた。きっと次に交代するプリシラが聞いていたのだろう。
「だから俺は家族を馬鹿にするやつは許さないよ。 わかったか?」
「ああ、毎回すまない。 俺もカッとしていた」
「まぁ、わかればいいよ。 エヴァンもプリシラも家族がいるんだろ? アルジャンって名前につくぐらいだからどっかの貴族だろう?」
俺の言葉にエヴァンは驚いていた。以前ロビンからは鑑定を使った時に名前の後ろに苗字と呼ばれる名がつく場合は貴族の可能性が高いから関わるなと言われていた。
ロビンに苗字がないのは、今も公爵家と関わりがあるが冒険者になった後に迷惑をかけないように自身で抜けたと言っていた。
「お前いつから知っていたんだ?」
「初めから知ってるよ? 俺鑑定使えるもん」
俺はエヴァンとプリシラの名前、ステータス、スキルを知っている。
「俺のスキルも見たんか?」
「スキル【#器用貧乏__オールラウンダー__#】だよね。 何でも出来て羨ましいスキルだよな」
「おい、俺を馬鹿にしてるのか!」
さっきまで泣いていたはずのエヴァンが今度は怒っていた。本当に感情がコロコロと変わる男だ。
「なんでお前を馬鹿にしないといけないんだ? スキルの説明には習得するスピードが早くてなんでも卒なくこなすって書いてあるだろ?」
「俺はそれが気に食わないだ」
「えっ?」
「だから俺はそれが嫌なんだ。 貴族は基本的に誰かの上に立つ存在だって言われている。 小さい頃から勉強や魔法、剣技を教えてもらっても、初めは順調でも才能がない俺は誰にも勝てないんだ」
貴族は基本的に攻撃スキル持ちは騎士や魔法士、その他のスキル持ちは政治や領地の経営をやることになるらしい。
「でもステータスで見ると最大値は高いよ?」
「何を言ってるんだ?」
どうやらエヴァンに伝わらないため地面に今のステータスを書くことにした。
《ステータス》
[名前] エヴァン・アルジャン
[種族] 人間/男
[能力値] 力C/A 魔力C/A 速度C/A
[スキル] #器用貧乏__オールラウンダー__#
[状態] 虚無感
確かに今のステータスは高くはないが、限界値は高いため努力を続ければ問題ないはずだ。またこのステータスの高さで器用貧乏なら頭の回転や頭も良いはずだ。
「これってどういう仕組みだ?」
「どういう仕組みかって? 普通に鑑定したらステータスって見れるだろ?」
「お前……頭大丈夫か?」
「はぁん?」
せっかく鑑定を使ったのに俺がエヴァンに馬鹿にされていた。
「いやいや、言い方が悪かったな。 鑑定って名前やスキル、アイテム名の詳細はわかるけど能力の限界値は見えないぞ」
「……」
俺はどうやらまたやからしてしまったらしい。
モーリンは一度もそんなこと……いや、俺って鑑定については誰にも話したことがなかった。
「ははは、そっかー! そうか!」
そんな話をしていると突然エヴァンが大声で笑い出した。
「おい、お前の方が頭大丈夫か?」
「ははは、ウォーレンありがとう!」
そう言ってエヴァンは時間になったのか笑いながらテントに戻って行った。後ろ姿から見る彼の鑑定結果は[状態]虚無感が充実感に変化していた。
「おい、お前」
「なんだよ」
俺はわざと関わらないようにしていたが、夜で何もやることがなくなったからなのかエヴァンが声をかけてきた。
「なんで獣人を家族って──」
「ロンとニアだ」
俺がエヴァンを睨むと彼は名前を言い直していた。
「なんで家族って言ってるんだ?」
確かに俺達の関係を知らない人であれば気になるのだろう。
「俺が森の中でロンとニアを助けて家族になることにした」
俺は出会った時から自分が家族になると決めた日や死んでも守ると決めた日など今まであったロンとニアが家族になった経由を話した。
「うっ……」
「おい!?」
「べっ、別に泣いてなんかいねーぞ!」
エヴァンは顔を伏せて鼻をすすっていた。
「まぁ、だからあいつらは俺の家族なんだよ。 俺は小さい頃から家族が居なくてさ……」
俺は小さい時のわずかな記憶はあるがはっきりと母と父の顔は覚えていない。ただ、覚えているのは笑顔で俺を何かの箱に入れて笑っていなくなった顔だけだ。
その後、箱を開けられた時には辺りは焼け野原になっており、俺を育ててくれたのは見知らぬおじいちゃんとおばあちゃんだった。
だから俺の中で見知らぬロンとニアが家族になることに抵抗はなかった。
また、その時の影響なのか真っ暗なところに長時間いるのも狭いところで閉じ込められるのも精神的にダメになった。
「うっ……もう俺ダメだわ」
エヴァンはこういう話に弱いのかさっきまで顔を伏せていたはずがいつのまにか隠さず泣いていた。
どこからか鼻をすする音が聞こえてきた。きっと次に交代するプリシラが聞いていたのだろう。
「だから俺は家族を馬鹿にするやつは許さないよ。 わかったか?」
「ああ、毎回すまない。 俺もカッとしていた」
「まぁ、わかればいいよ。 エヴァンもプリシラも家族がいるんだろ? アルジャンって名前につくぐらいだからどっかの貴族だろう?」
俺の言葉にエヴァンは驚いていた。以前ロビンからは鑑定を使った時に名前の後ろに苗字と呼ばれる名がつく場合は貴族の可能性が高いから関わるなと言われていた。
ロビンに苗字がないのは、今も公爵家と関わりがあるが冒険者になった後に迷惑をかけないように自身で抜けたと言っていた。
「お前いつから知っていたんだ?」
「初めから知ってるよ? 俺鑑定使えるもん」
俺はエヴァンとプリシラの名前、ステータス、スキルを知っている。
「俺のスキルも見たんか?」
「スキル【#器用貧乏__オールラウンダー__#】だよね。 何でも出来て羨ましいスキルだよな」
「おい、俺を馬鹿にしてるのか!」
さっきまで泣いていたはずのエヴァンが今度は怒っていた。本当に感情がコロコロと変わる男だ。
「なんでお前を馬鹿にしないといけないんだ? スキルの説明には習得するスピードが早くてなんでも卒なくこなすって書いてあるだろ?」
「俺はそれが気に食わないだ」
「えっ?」
「だから俺はそれが嫌なんだ。 貴族は基本的に誰かの上に立つ存在だって言われている。 小さい頃から勉強や魔法、剣技を教えてもらっても、初めは順調でも才能がない俺は誰にも勝てないんだ」
貴族は基本的に攻撃スキル持ちは騎士や魔法士、その他のスキル持ちは政治や領地の経営をやることになるらしい。
「でもステータスで見ると最大値は高いよ?」
「何を言ってるんだ?」
どうやらエヴァンに伝わらないため地面に今のステータスを書くことにした。
《ステータス》
[名前] エヴァン・アルジャン
[種族] 人間/男
[能力値] 力C/A 魔力C/A 速度C/A
[スキル] #器用貧乏__オールラウンダー__#
[状態] 虚無感
確かに今のステータスは高くはないが、限界値は高いため努力を続ければ問題ないはずだ。またこのステータスの高さで器用貧乏なら頭の回転や頭も良いはずだ。
「これってどういう仕組みだ?」
「どういう仕組みかって? 普通に鑑定したらステータスって見れるだろ?」
「お前……頭大丈夫か?」
「はぁん?」
せっかく鑑定を使ったのに俺がエヴァンに馬鹿にされていた。
「いやいや、言い方が悪かったな。 鑑定って名前やスキル、アイテム名の詳細はわかるけど能力の限界値は見えないぞ」
「……」
俺はどうやらまたやからしてしまったらしい。
モーリンは一度もそんなこと……いや、俺って鑑定については誰にも話したことがなかった。
「ははは、そっかー! そうか!」
そんな話をしていると突然エヴァンが大声で笑い出した。
「おい、お前の方が頭大丈夫か?」
「ははは、ウォーレンありがとう!」
そう言ってエヴァンは時間になったのか笑いながらテントに戻って行った。後ろ姿から見る彼の鑑定結果は[状態]虚無感が充実感に変化していた。