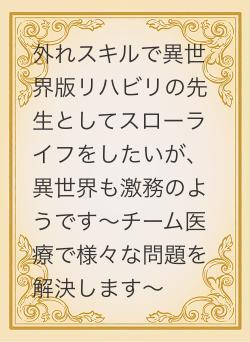俺の前にはなぜか酒が置いてあった。
しかも、その量は一つだけではなく大量に置かれている。
冒険者達の視線が俺に向いていた。
どこかお腹が痛く締め付けられている気がした。
「今日は新しい仲間が来たわよ! みんな仲良くしてあげてー! 乾杯!」
「乾杯!」
男の掛け声と共になぜか飲み会が始まった。
そんな雰囲気に俺達はついていけないでいると冒険者ギルドの扉が開いた。
「あら、ロビンちゃんも帰ってきてたのね」
「おっさんにちゃん付けはないだろう」
この状況をどうすればいいのかわからない俺はロビンに助けを求めた。
ロンとニアは馴染むのが早いのか、他の冒険者達に遊んでもらっている。
「ははは、こいつがお前達と仲良くしたいってさ」
「えっ!?」
ロビンはこっちを見てニヤッと笑っていた。そんなにお金を払わずに屋敷に泊まっていたのがダメだったのだろうか。
ひょっとして俺って嫌われている?
「あら、そうなの? じゃあ、どんどん飲みましょう」
「いや、さすがに――」
「か弱いオカマの酒が飲めないって言うのかしら?」
筋肉モリモリで逞しい姿のどこにか弱さがあるのだろうか。
とりあえず口をつけてみる。
「ほらほらグビグビいきましょう。オカマの酒が飲めないならーお尻の命はありません。はい!」
「一気! 一気!」
謎のコールを聞いて俺は急いで酒を飲む。
さすがにお尻は死守したいところだ。
「ほらほらもう一杯! オカマの酒が飲めないならーお尻の命はありません。はい!」
「一気! 一気!」
その後も記憶がなくなる手前まで永遠と酒を飲まされた。
♢
「あー、頭痛いし気持ち悪い」
俺は外に出て風に当たりながら自分自身に回復魔法をかけていた。
「スキル【回復魔法】を吸収しました」
脳内に響く声もさらに頭痛を助長していた。
あれから出される酒は飲み続けて、冒険者達はその場で倒れるように寝ていた。
ロビンも助けることなく、ずっとニヤニヤして俺をみていた。
「ウォーレン……おいおいそんなに睨むなよ。王都の冒険者ギルドはどうだ?」
俺に声をかけてきたのは裏切ったロビンだった。
「悪くはないです」
「ははは、そうか」
確かに他の冒険者ギルドではポーターという理由だけで蔑ろにされることが多かった。
しかし、王都の冒険者ギルドではそんな様子は一切なかった。
「ローガンはさ……あんな奴だから誰よりも仲間意識が強いんだよ」
「ギルド長のことですか?」
甲高い声をした屈強な体の男はまさかの王都で冒険者ギルドのギルド長をやっていた。
「そうだ。ポーターでも人種や地位が違ったとしても分け隔てなく接するのが王都の冒険者ギルドなんだよ」
王都の冒険者ギルドの話をするロビンの顔はどこかいつもより楽しそうだった。
「あら、ウォーちゃんとロビンちゃんはここにいたのね」
そんな中やってきたのはギルド長だった。少し変わった性格をしているが話してみると良い人だった。
酔っ払うと服を脱いで筋肉をアピールをするというさらに変わった人だった。
なんやかんやで俺の尻は無事だったしな。
気づいたら隣にはロビンの姿はなく、ギルド長が隣にいた。
ただ、今も俺の尻を撫で回している。
「ローガン──」
「痛っ!?」
「私のことはローナって言ったわよね?」
おいおい、俺の尻を持って怒るなよ。
さっきまで無事だったのに、今強く握られた影響で尻が取れるかと思った。
そして俺を見るギルド長の顔は怖かった。
俺は問答無用で頭を縦に振った。
本能的になぜか逆らってはいけないと脳内で警鐘が鳴っていた。
「おい、デカブツ痛いだろうが!」
ロビンはギルド長に飛ばされていた。
ズボンの砂を落としながらこっちに戻ってきた。
「あんたが私の名前を……」
「ローガンだろ?」
またロビンがギルド長の名前を言った瞬間、隣にいたはずのギルド長は姿を消していた。
実際は瞬間的にロビンの目の前に距離を詰めたのだ。
「おいおい、久しぶりに帰ってきたのに手荒いまねするなよ」
「ははは、何言ってんのよ! 喧嘩を吹っかけてきたのはそっちでしょ」
そこから二人は冒険者ギルドの前で争っていた。その速さは目で追うのもやっとだった。
「今日はご迷惑をおかけしてすみません」
声をかけてきたのは冒険者ギルドで働く女性のルーチェだった。
どこかリーチェに似ていると思っていたらリーチェの姉らしい。
「あの二人を止めなくても大丈夫なんですか?」
「はい! あの人達はいつもあんな感じでどちらかが動けなくなるまで、ああやって遊んでるんです」
目の前の男達からは"殺してやる"とか"死に損ない"と聞こえるがどうやら遊んでいるらしい。
今後はなるべく二人でいる時は、関わらないようにしようと俺は思った。
「さぁ、時間も遅いですし子供達には悪影響ですから帰りましょうか」
ロンとニアは冒険者達に混ざって一緒に寝ていた。俺はロンとニアを抱えてロビンの屋敷に帰ることにした。
「楽しかった……」
「にいちゃ……また行こう」
ロンとニアは余程遊んでもらったのが楽しかったのだろう。
俺の胸の胸中でずっと寝言を言っていた。
「王都に来てよかったかもな」
「王都に来てよかった?」
俺は後ろから良からぬ圧を感じとった。急いで振り返るとそこにはモーリンが立っていた。
「こんな時間まで子供を振り回して何やってるんじゃー!」
俺はその後もモーリンからこっ酷く怒られることとなった。
しかも、その量は一つだけではなく大量に置かれている。
冒険者達の視線が俺に向いていた。
どこかお腹が痛く締め付けられている気がした。
「今日は新しい仲間が来たわよ! みんな仲良くしてあげてー! 乾杯!」
「乾杯!」
男の掛け声と共になぜか飲み会が始まった。
そんな雰囲気に俺達はついていけないでいると冒険者ギルドの扉が開いた。
「あら、ロビンちゃんも帰ってきてたのね」
「おっさんにちゃん付けはないだろう」
この状況をどうすればいいのかわからない俺はロビンに助けを求めた。
ロンとニアは馴染むのが早いのか、他の冒険者達に遊んでもらっている。
「ははは、こいつがお前達と仲良くしたいってさ」
「えっ!?」
ロビンはこっちを見てニヤッと笑っていた。そんなにお金を払わずに屋敷に泊まっていたのがダメだったのだろうか。
ひょっとして俺って嫌われている?
「あら、そうなの? じゃあ、どんどん飲みましょう」
「いや、さすがに――」
「か弱いオカマの酒が飲めないって言うのかしら?」
筋肉モリモリで逞しい姿のどこにか弱さがあるのだろうか。
とりあえず口をつけてみる。
「ほらほらグビグビいきましょう。オカマの酒が飲めないならーお尻の命はありません。はい!」
「一気! 一気!」
謎のコールを聞いて俺は急いで酒を飲む。
さすがにお尻は死守したいところだ。
「ほらほらもう一杯! オカマの酒が飲めないならーお尻の命はありません。はい!」
「一気! 一気!」
その後も記憶がなくなる手前まで永遠と酒を飲まされた。
♢
「あー、頭痛いし気持ち悪い」
俺は外に出て風に当たりながら自分自身に回復魔法をかけていた。
「スキル【回復魔法】を吸収しました」
脳内に響く声もさらに頭痛を助長していた。
あれから出される酒は飲み続けて、冒険者達はその場で倒れるように寝ていた。
ロビンも助けることなく、ずっとニヤニヤして俺をみていた。
「ウォーレン……おいおいそんなに睨むなよ。王都の冒険者ギルドはどうだ?」
俺に声をかけてきたのは裏切ったロビンだった。
「悪くはないです」
「ははは、そうか」
確かに他の冒険者ギルドではポーターという理由だけで蔑ろにされることが多かった。
しかし、王都の冒険者ギルドではそんな様子は一切なかった。
「ローガンはさ……あんな奴だから誰よりも仲間意識が強いんだよ」
「ギルド長のことですか?」
甲高い声をした屈強な体の男はまさかの王都で冒険者ギルドのギルド長をやっていた。
「そうだ。ポーターでも人種や地位が違ったとしても分け隔てなく接するのが王都の冒険者ギルドなんだよ」
王都の冒険者ギルドの話をするロビンの顔はどこかいつもより楽しそうだった。
「あら、ウォーちゃんとロビンちゃんはここにいたのね」
そんな中やってきたのはギルド長だった。少し変わった性格をしているが話してみると良い人だった。
酔っ払うと服を脱いで筋肉をアピールをするというさらに変わった人だった。
なんやかんやで俺の尻は無事だったしな。
気づいたら隣にはロビンの姿はなく、ギルド長が隣にいた。
ただ、今も俺の尻を撫で回している。
「ローガン──」
「痛っ!?」
「私のことはローナって言ったわよね?」
おいおい、俺の尻を持って怒るなよ。
さっきまで無事だったのに、今強く握られた影響で尻が取れるかと思った。
そして俺を見るギルド長の顔は怖かった。
俺は問答無用で頭を縦に振った。
本能的になぜか逆らってはいけないと脳内で警鐘が鳴っていた。
「おい、デカブツ痛いだろうが!」
ロビンはギルド長に飛ばされていた。
ズボンの砂を落としながらこっちに戻ってきた。
「あんたが私の名前を……」
「ローガンだろ?」
またロビンがギルド長の名前を言った瞬間、隣にいたはずのギルド長は姿を消していた。
実際は瞬間的にロビンの目の前に距離を詰めたのだ。
「おいおい、久しぶりに帰ってきたのに手荒いまねするなよ」
「ははは、何言ってんのよ! 喧嘩を吹っかけてきたのはそっちでしょ」
そこから二人は冒険者ギルドの前で争っていた。その速さは目で追うのもやっとだった。
「今日はご迷惑をおかけしてすみません」
声をかけてきたのは冒険者ギルドで働く女性のルーチェだった。
どこかリーチェに似ていると思っていたらリーチェの姉らしい。
「あの二人を止めなくても大丈夫なんですか?」
「はい! あの人達はいつもあんな感じでどちらかが動けなくなるまで、ああやって遊んでるんです」
目の前の男達からは"殺してやる"とか"死に損ない"と聞こえるがどうやら遊んでいるらしい。
今後はなるべく二人でいる時は、関わらないようにしようと俺は思った。
「さぁ、時間も遅いですし子供達には悪影響ですから帰りましょうか」
ロンとニアは冒険者達に混ざって一緒に寝ていた。俺はロンとニアを抱えてロビンの屋敷に帰ることにした。
「楽しかった……」
「にいちゃ……また行こう」
ロンとニアは余程遊んでもらったのが楽しかったのだろう。
俺の胸の胸中でずっと寝言を言っていた。
「王都に来てよかったかもな」
「王都に来てよかった?」
俺は後ろから良からぬ圧を感じとった。急いで振り返るとそこにはモーリンが立っていた。
「こんな時間まで子供を振り回して何やってるんじゃー!」
俺はその後もモーリンからこっ酷く怒られることとなった。