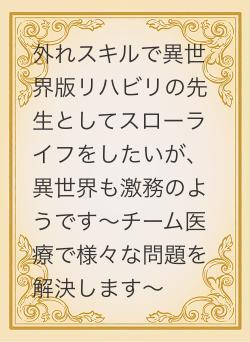せっかくの馬車の移動は少し記憶が曖昧だった。
覚えているのはロンとニアがいつもより引っ付いていたのと、ルースが親身になって話を聞いてくれていたことだ。
俺が少しずつ過去の話をすると、ルースは優しく"辛かったね"と言ってくれた。
俺の過去を話すと同時にルースは自身の秘密を話し始めた。
ルースは"転生者"と言われる存在で、今のルースが産まれる前の前世の記憶があるらしい。
日本というところで瑠衣という名前で看護師として働いていた。
なんでも以前は王都に行く理由も人間観察と言っていたが、詳しく問い詰めると勝手にカップリングして人生を楽しむという意味がわからないことを言っていた。
これ以上は俺の精神衛生上話せないらしい。
そもそもカップリングとはなんだろうか。
また俺にはわからない単語が出てきたが、とりあえず話を聞いていた。
「お前達着いたぞ!」
そんな馬車の旅もいつのまにか終わりを迎えた。王都に着いた。
王都は街を大きく囲うように外壁に囲まれており、その先が見えないほど大きく、都市ガイアスとは比べられないほどだ。
馬車を降りてからそのまま入り口に向かった。入り口は2箇所あり、ロビンのおかげで少ない方に並ぶことができた。
「身分証を提示していただいてもよろしいですか?」
俺達は冒険者ギルドのカードを渡した。王都では基本的に一定の年齢であれば身分を提示するものが必要らしい。
「獣人ですか……」
門番はロンとニアを見て馬鹿にしたように鼻で笑っていた。
なんとなく王都に入る前から視線が気になっていたが、王都の方が獣人への差別が酷いのだろう。
それでも問題なく入れたのは、ロビンがいたからだろうか。
「これはすごいね」
「ほー、お兄ちゃんすごいね」
「にいちゃ、あっちに行こう!」
俺達は王都の広さに驚いて空いた口が塞がらない。果てしなく広がる街中に唯一見えるのは奥の方にある外壁だ。
王都は3つの外壁に守られている。1つ目は平民街を守る外壁、2つ目は貴族街を守る外壁、3つ目は王族街を守る外壁だ。
「お前達は絶対に2つ目からの外壁にいる貴族達には関わるんじゃないぞ」
ロビンから王都での注意点をいくつか聞いた。基本的には奥の外壁には近づかないことと、貴族には関わらないということだった。
貴族は人種や自身より低い地位の人を馬鹿にする傾向がある。俺達みたいな平民やロンとニアのような獣人はその対象になるらしい。
唯一貴族と同様の権力があるのは平民でも"勇者"の称号を持つ冒険者だけだ。
だから、冒険者が勇者を目指す理由にもなるのだろう。
とりあえず俺達は宿屋を探そうとしたら、ロビンにどこに行くんだという顔をされた。
そのまま付いてこいと言われ、貴族街の外壁近くに行くと目の前には大きな屋敷が建っていた。
「ここが俺の王都の家だ」
俺達はロビンが何を言っているのかわからなかった。
ニアは屋敷やお城とかに興味があるのか目を輝かせていた。そんな俺達を見てモーリンとメジストは笑っていた。
「えっ……」
扉を開けると明らかに家の規模ではなく、執事のような使用人達が一列に並んで待っている。
「ロビン様おかえりなさいませ」
一度に頭を下げた人達に俺は驚きながらも、何事もなく歩いていくロビンについて行く。
「どういうことですか?」
「そんなにびっくりすることか?」
「まぁ、普通の人だとびっくりするじゃろな」
「私達はあなたの正体をしっているからね?」
ロビンは納得すると自身の話を始めた。
「ああ、そういうことか。俺はこのアルジャン王国の国王の親戚みたいなもんだからな」
「へっ?」
俺はそれでも言っている意味がわからなかった。
「ロビンは公爵家出身の三男なのよ! そしてロビンの父親のお姉様が現王妃を勤めているのよ」
俺は頭を整理するために、とりあえず地面に家系図を書くことにした。
「えーっと、ロビンさんが公爵家で……公爵家!?」
「まずそこから驚くんかい!」
あれだけ貴族に関わるなと聞いておきながら、俺はすでに貴族と関わっていた。
「俺は単純に貴族のしがらみから逃れたくて冒険者をやっているだけだ。ただ、それだけだ」
ロビンはそう言って屋敷の中に入っていく。何かその表情は思いつめたような顔だ。
「まぁ、ロビンにもいろいろ理由があるんじゃ」
「ロンとニアも行くわよ」
ロンとニアはモーリンの手を繋ぎ屋敷の中に入って行った。
「うん、これは深く考えないほうがいいやつだろうな」
俺は考えることを放棄した。とりあえず宿屋に泊まらず、良いベッドで寝られるのであれば、問題ないと思うことにした。
宿屋のお金がかからないなんて最高だ!
覚えているのはロンとニアがいつもより引っ付いていたのと、ルースが親身になって話を聞いてくれていたことだ。
俺が少しずつ過去の話をすると、ルースは優しく"辛かったね"と言ってくれた。
俺の過去を話すと同時にルースは自身の秘密を話し始めた。
ルースは"転生者"と言われる存在で、今のルースが産まれる前の前世の記憶があるらしい。
日本というところで瑠衣という名前で看護師として働いていた。
なんでも以前は王都に行く理由も人間観察と言っていたが、詳しく問い詰めると勝手にカップリングして人生を楽しむという意味がわからないことを言っていた。
これ以上は俺の精神衛生上話せないらしい。
そもそもカップリングとはなんだろうか。
また俺にはわからない単語が出てきたが、とりあえず話を聞いていた。
「お前達着いたぞ!」
そんな馬車の旅もいつのまにか終わりを迎えた。王都に着いた。
王都は街を大きく囲うように外壁に囲まれており、その先が見えないほど大きく、都市ガイアスとは比べられないほどだ。
馬車を降りてからそのまま入り口に向かった。入り口は2箇所あり、ロビンのおかげで少ない方に並ぶことができた。
「身分証を提示していただいてもよろしいですか?」
俺達は冒険者ギルドのカードを渡した。王都では基本的に一定の年齢であれば身分を提示するものが必要らしい。
「獣人ですか……」
門番はロンとニアを見て馬鹿にしたように鼻で笑っていた。
なんとなく王都に入る前から視線が気になっていたが、王都の方が獣人への差別が酷いのだろう。
それでも問題なく入れたのは、ロビンがいたからだろうか。
「これはすごいね」
「ほー、お兄ちゃんすごいね」
「にいちゃ、あっちに行こう!」
俺達は王都の広さに驚いて空いた口が塞がらない。果てしなく広がる街中に唯一見えるのは奥の方にある外壁だ。
王都は3つの外壁に守られている。1つ目は平民街を守る外壁、2つ目は貴族街を守る外壁、3つ目は王族街を守る外壁だ。
「お前達は絶対に2つ目からの外壁にいる貴族達には関わるんじゃないぞ」
ロビンから王都での注意点をいくつか聞いた。基本的には奥の外壁には近づかないことと、貴族には関わらないということだった。
貴族は人種や自身より低い地位の人を馬鹿にする傾向がある。俺達みたいな平民やロンとニアのような獣人はその対象になるらしい。
唯一貴族と同様の権力があるのは平民でも"勇者"の称号を持つ冒険者だけだ。
だから、冒険者が勇者を目指す理由にもなるのだろう。
とりあえず俺達は宿屋を探そうとしたら、ロビンにどこに行くんだという顔をされた。
そのまま付いてこいと言われ、貴族街の外壁近くに行くと目の前には大きな屋敷が建っていた。
「ここが俺の王都の家だ」
俺達はロビンが何を言っているのかわからなかった。
ニアは屋敷やお城とかに興味があるのか目を輝かせていた。そんな俺達を見てモーリンとメジストは笑っていた。
「えっ……」
扉を開けると明らかに家の規模ではなく、執事のような使用人達が一列に並んで待っている。
「ロビン様おかえりなさいませ」
一度に頭を下げた人達に俺は驚きながらも、何事もなく歩いていくロビンについて行く。
「どういうことですか?」
「そんなにびっくりすることか?」
「まぁ、普通の人だとびっくりするじゃろな」
「私達はあなたの正体をしっているからね?」
ロビンは納得すると自身の話を始めた。
「ああ、そういうことか。俺はこのアルジャン王国の国王の親戚みたいなもんだからな」
「へっ?」
俺はそれでも言っている意味がわからなかった。
「ロビンは公爵家出身の三男なのよ! そしてロビンの父親のお姉様が現王妃を勤めているのよ」
俺は頭を整理するために、とりあえず地面に家系図を書くことにした。
「えーっと、ロビンさんが公爵家で……公爵家!?」
「まずそこから驚くんかい!」
あれだけ貴族に関わるなと聞いておきながら、俺はすでに貴族と関わっていた。
「俺は単純に貴族のしがらみから逃れたくて冒険者をやっているだけだ。ただ、それだけだ」
ロビンはそう言って屋敷の中に入っていく。何かその表情は思いつめたような顔だ。
「まぁ、ロビンにもいろいろ理由があるんじゃ」
「ロンとニアも行くわよ」
ロンとニアはモーリンの手を繋ぎ屋敷の中に入って行った。
「うん、これは深く考えないほうがいいやつだろうな」
俺は考えることを放棄した。とりあえず宿屋に泊まらず、良いベッドで寝られるのであれば、問題ないと思うことにした。
宿屋のお金がかからないなんて最高だ!