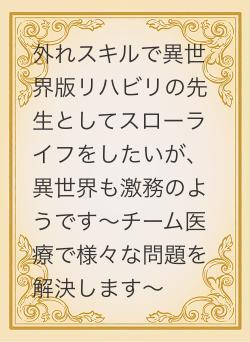異様に外が騒がしくて俺は目を覚ました。珍しくまだ寝ている2人を抱きかかえて食堂に向かう。
「ロビンさん今日何かあるんですか?」
「ああ、昨日言ってなかったか? 今から王都に向かうぞ」
なんと今日から王都へ向かうことになっていた。それを聞いていたのかロンとニアの耳はピクピクと動いている。
「王都に行くの!?」
「王都! 王都!」
2人は俺から飛び降りると急いで準備をしに部屋に戻った。
「実は私も一緒に行く予定になっているんです」
食事を運んできた宿屋の女性従業員であるルースも一緒に同行することになっていた。
彼女は王都で人間観察というものをするために働き先を王都に移動させるらしい。
王都みたいな都会には、変わった人達が集まるところなんだろう。
「あとモーリンさんとメジストさんも一緒にいくぞ」
「えっ、じいじとばあばも?」
「やったね!」
話を聞けば家族全員とルースの計7人で王都に行くことになっていた。あの2人はお店が大丈夫なのか疑問だが、ロビンの話ではどうにかなるらしい。
俺達は急いで準備をして、宿屋の店主にお礼の挨拶をしてから玄関の扉を開けた。
「うわー、豪華な馬車だね」
宿屋の前には大きな馬車と正装に身を包んだ男性が立っていた。
「うわぁ、リアル執事だ」
ルースは何か知っているのだろう。俺は執事って言葉を初めて聞いた。
「ロビン様お待たせしました。すでにモーリン様とメジスト様は中でお待ちしています」
執事と呼ばれる人はロビンに挨拶をしていた。その後、俺達も手を引かれながら馬車に乗った。
子供でも乗り降りしやすいように足台を置いてくれるほどしっかりした対応だ。
「うわー、中がすごいな」
馬車の中は外と比べて広くなっている。何でも回数無制限のスキル玉【空間魔法】を使った馬車らしい。
メジストが自慢げに話していたが、どうやら若い頃好奇心でメジストが作った馬車らしい。
俺達は王都に向かって馬車を走らせた。窓から見える外の景色はとても青く澄んでいる。
王都に向かって出発する日にはちょうど良い。
そんなことを思っていると急に馬車が停止した。すぐにロビンが確認しに行くと、外で何か揉めている声が聞こえた。
「アドルー、この馬車が私達の道を邪魔するわ」
「ははは、こいつらはここが俺らの道って知らないだけだろ?」
「さすがね。一層この馬車ごと火属性魔法で燃やしてあげようか?」
「アドルー、マリベルが怖いこと言ってる」
俺はねっとりと話す女の声と昔から聞き慣れた声に震えと鳥肌が止まらない。
なぜ、あいつらがここにいるんだ。
「お兄ちゃん大丈夫?」
「にいちゃ?」
そんな俺の様子がおかしいと気づいた2人は心配そうに顔を覗いてくる。
「ああ、ちょっと嫌な記憶が蘇ってきてな」
俺の中では今もあのパーティーの人達から言われた言葉が脳裏に焼き付いている。
「ほんとにお前は馬鹿だな。荷物も持てないポーターなんて勇者パーティーにはいらないんだよ」
「これで私達も勇者になったから使えないお荷物はいらないのよ! 女の私があんたみたいなお荷物を守らなくていいって思うと清々する」
「ほんとそうよね! 聖女の私ですら魔物と戦っているのに何もしないやつなんていらないわ」
「そもそも、男はアドルだけでいいのよ。いつも邪魔だったのよ」
俺の中では4人の声がずっと頭の中を駆け巡る。またあの時みたいに痛い思いをして一人になるんだ。
「俺はお荷物なんだ……消えてなくなればいいんだ……俺は死ねば……俺なんて――」
俺は次第に意識が薄れそのまま意識を手放した。
♢
あれから馬車は動き出したがウォーレンの心の中は重症だった。独り言を話し出したと思ったら、そのまま意識がなくなり身体中が痙攣していた。
私とニアで急いで回復魔法をかけていたらルースという女性がこの症状は"パニック障害"と "心的外傷ストレス障害"から来ている心の病気かもしれないと言っていた。
長いこと生きている私達でも知らない病名で戸惑った。回復魔法でも治らない病気らしい。
ウォーレンは常に泣きながら"死にたい"、"お荷物"、"助けて"とずっと言いながら唸っている。
ロンとニアが優しく撫でていると、どこか安心したのか優しい笑顔になるのが不思議だ。
以前冒険者ギルドでも家族が魔物に襲われた冒険者が、同じように苦しんでいるって話を聞いたことがあった。
結局その冒険者は魔物と戦闘中に、自ら食べられるように飛び込んで死んだ。生きるのが辛かったのだろう。
「ウォーレンは落ち着いたのか?」
メジストは心配そうにウォーレンを見に来た。
「やっと落ち着いたところじゃ」
ロンとニアのおかげでウォーレンはやっと落ち着いてきた。
「いつも笑顔だったけど辛い思いをしているんだな」
「いつまで経っても無力だ……」
大賢者で勇者の称号もある私でさえも何もできずに立ち尽くすだけ。心の中は無力感で襲われる。
「わし達は人であって神様でも何ものでもない。できるのは頑張って立ち向かっているウォーレンを応援するだけじゃ」
いつもふざけているモーリンの声が私の心に響いていた。こういう時は頼りになるんだから……。
「そうね……。今はそっとしておきましょう」
私はウォーレンと手を繋ぎながら隣で寝ているロンとニアに布団をかけて部屋から立ち去った。
「ロビンさん今日何かあるんですか?」
「ああ、昨日言ってなかったか? 今から王都に向かうぞ」
なんと今日から王都へ向かうことになっていた。それを聞いていたのかロンとニアの耳はピクピクと動いている。
「王都に行くの!?」
「王都! 王都!」
2人は俺から飛び降りると急いで準備をしに部屋に戻った。
「実は私も一緒に行く予定になっているんです」
食事を運んできた宿屋の女性従業員であるルースも一緒に同行することになっていた。
彼女は王都で人間観察というものをするために働き先を王都に移動させるらしい。
王都みたいな都会には、変わった人達が集まるところなんだろう。
「あとモーリンさんとメジストさんも一緒にいくぞ」
「えっ、じいじとばあばも?」
「やったね!」
話を聞けば家族全員とルースの計7人で王都に行くことになっていた。あの2人はお店が大丈夫なのか疑問だが、ロビンの話ではどうにかなるらしい。
俺達は急いで準備をして、宿屋の店主にお礼の挨拶をしてから玄関の扉を開けた。
「うわー、豪華な馬車だね」
宿屋の前には大きな馬車と正装に身を包んだ男性が立っていた。
「うわぁ、リアル執事だ」
ルースは何か知っているのだろう。俺は執事って言葉を初めて聞いた。
「ロビン様お待たせしました。すでにモーリン様とメジスト様は中でお待ちしています」
執事と呼ばれる人はロビンに挨拶をしていた。その後、俺達も手を引かれながら馬車に乗った。
子供でも乗り降りしやすいように足台を置いてくれるほどしっかりした対応だ。
「うわー、中がすごいな」
馬車の中は外と比べて広くなっている。何でも回数無制限のスキル玉【空間魔法】を使った馬車らしい。
メジストが自慢げに話していたが、どうやら若い頃好奇心でメジストが作った馬車らしい。
俺達は王都に向かって馬車を走らせた。窓から見える外の景色はとても青く澄んでいる。
王都に向かって出発する日にはちょうど良い。
そんなことを思っていると急に馬車が停止した。すぐにロビンが確認しに行くと、外で何か揉めている声が聞こえた。
「アドルー、この馬車が私達の道を邪魔するわ」
「ははは、こいつらはここが俺らの道って知らないだけだろ?」
「さすがね。一層この馬車ごと火属性魔法で燃やしてあげようか?」
「アドルー、マリベルが怖いこと言ってる」
俺はねっとりと話す女の声と昔から聞き慣れた声に震えと鳥肌が止まらない。
なぜ、あいつらがここにいるんだ。
「お兄ちゃん大丈夫?」
「にいちゃ?」
そんな俺の様子がおかしいと気づいた2人は心配そうに顔を覗いてくる。
「ああ、ちょっと嫌な記憶が蘇ってきてな」
俺の中では今もあのパーティーの人達から言われた言葉が脳裏に焼き付いている。
「ほんとにお前は馬鹿だな。荷物も持てないポーターなんて勇者パーティーにはいらないんだよ」
「これで私達も勇者になったから使えないお荷物はいらないのよ! 女の私があんたみたいなお荷物を守らなくていいって思うと清々する」
「ほんとそうよね! 聖女の私ですら魔物と戦っているのに何もしないやつなんていらないわ」
「そもそも、男はアドルだけでいいのよ。いつも邪魔だったのよ」
俺の中では4人の声がずっと頭の中を駆け巡る。またあの時みたいに痛い思いをして一人になるんだ。
「俺はお荷物なんだ……消えてなくなればいいんだ……俺は死ねば……俺なんて――」
俺は次第に意識が薄れそのまま意識を手放した。
♢
あれから馬車は動き出したがウォーレンの心の中は重症だった。独り言を話し出したと思ったら、そのまま意識がなくなり身体中が痙攣していた。
私とニアで急いで回復魔法をかけていたらルースという女性がこの症状は"パニック障害"と "心的外傷ストレス障害"から来ている心の病気かもしれないと言っていた。
長いこと生きている私達でも知らない病名で戸惑った。回復魔法でも治らない病気らしい。
ウォーレンは常に泣きながら"死にたい"、"お荷物"、"助けて"とずっと言いながら唸っている。
ロンとニアが優しく撫でていると、どこか安心したのか優しい笑顔になるのが不思議だ。
以前冒険者ギルドでも家族が魔物に襲われた冒険者が、同じように苦しんでいるって話を聞いたことがあった。
結局その冒険者は魔物と戦闘中に、自ら食べられるように飛び込んで死んだ。生きるのが辛かったのだろう。
「ウォーレンは落ち着いたのか?」
メジストは心配そうにウォーレンを見に来た。
「やっと落ち着いたところじゃ」
ロンとニアのおかげでウォーレンはやっと落ち着いてきた。
「いつも笑顔だったけど辛い思いをしているんだな」
「いつまで経っても無力だ……」
大賢者で勇者の称号もある私でさえも何もできずに立ち尽くすだけ。心の中は無力感で襲われる。
「わし達は人であって神様でも何ものでもない。できるのは頑張って立ち向かっているウォーレンを応援するだけじゃ」
いつもふざけているモーリンの声が私の心に響いていた。こういう時は頼りになるんだから……。
「そうね……。今はそっとしておきましょう」
私はウォーレンと手を繋ぎながら隣で寝ているロンとニアに布団をかけて部屋から立ち去った。