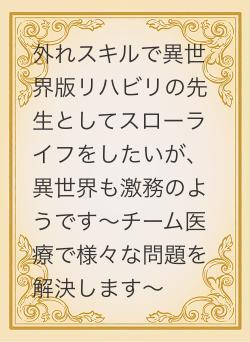昨日は散々子供達が泣いていたと聞いたので、今日はみんなで森の近くまで来ている。子供達はピクニック気分だが俺の内心は勝手にどこかに行かないか、魔物が襲ってこないかヒヤヒヤしていた。
二人は俺の外套の中に隠れて、顔だけ出して一緒に歩いている。
「にいちゃ、今日なにするの?」
「んー、薬草の採取かな」
「私達は何を手伝えばいい?」
子供達はキラキラした顔でこっちを見ていた。
ステータスだけで言えば俺と同程度だが、装備が強くないのが問題だった。念のためにポケットにはメジストからもらった風属性のスキル玉を忍ばせている。
いざとなった時に使えるよう、昨日は夜遅くまで教えた。
「じゃあ、ここらへんで薬草を探そうか」
俺が事前に薬草の特徴を伝えると二人は頷いて薬草を探しに行く。
「あっ、にいちゃあったよ!」
俺が見える範囲内で二人に作業をしてもらっているが、ロンがすぐに薬草を見つけられるのに比べ、ニアは全く見つけることができなかった。
これはロンのスキル【収集】が関与しているのだろう。
俺は子供達が見つけた薬草を匠の短剣で刈り取るだけの役割を繰り返している。それには理由があった。
「グルルルルル!」
物陰から出てきた魔物を隠れていた俺が仕留める。ロンのスキルが関与しているのは、薬草の採取だけではなく魔物も同様だった。
森の外にいるはずなのにロンに向かって、森から魔物が出てくることがあった。
基本的に森から追いかけて来なければ、魔物は外に出るはずがない。何かしらスキルの影響があるのは確実だ。ただのピクニックも命懸けだった。
宿屋から渡されたサンドイッチを食べながら休憩していると、ロンが魔物を倒したときに出てきた魔石を眺めていた。
「魔石が欲しいのか?」
「にいちゃもらっていいの?」
「ああ、何かに使う時が来るかもしれないしな。ニアもいるか?」
俺がニアにも聞くとニアは首を横に振っていた。この辺も収集が関係しているのか、ただ単に性別が男の子だからだろうか。
俺達はある程度仕事をしながらピクニックを終えると街に戻ることにした。
来た時は喜んでいた二人だったがロンは魔石をもらって喜んでいたが、反対にどことなくニアは元気がなかった。
俺は気になりながらも、魔石の買い取りをしてもらうためにメジストの錬金術店に向かった。
「お兄ちゃん……」
お店の扉を開けようと手を触れると、ニアは俺の服を掴んでいた。
ニアに話しかけたがどこか落ち着きがなく、チラチラとロンを見ていたため、ロンだけ先に店に入ってもらい話を聞くことにした。
「ニアどうしたんだ?」
「お兄ちゃんは私を捨てない?」
俺はニアの言っていることがわからなかった。どこでそんなことを思うようになったのか、全く気づかなかった。
「捨てるはずないだろ?」
「だってニアはロンと比べて薬草も探せないし、魔物も呼べない役立たずだよ」
きっとロンと比べて自分の存在価値がないと思ったのだろう。今まで奴隷畜舎でそうやって育てられたのが、身に染みている気がした。
こんな幼い子に対して、大人達は何をやっているのだろうか。
「ニアはスキルも使えないから捨てられたんだ。きっとニアなん――」
俺はそれ以上は聞けないし、言わせてはいけないと思い手で口を閉じさせた。涙を堪えてるニアはどこか震えている。
「別に俺は使えるかどうかでニアといるわけじゃないぞ。俺達はもう家族だ! だから使えないって言うなよ」
優しくニアに抱きつくと、そのまま俺の胸元で涙を流していた。嗚咽が出るほど何度も泣いていた。
それだけ今まで辛かったのだろう。兄妹だからこそ比べてしまうのは仕方ない。
「そんなに頑張らなくても大丈夫だ。俺はどんな時でもニアの味方だ」
今までロンより年下で妹のはずなのにしっかりしていたのはずっと捨てられないように強がっていただけかもしれない。
ただ、家族になったからこそ、しっかり子供達と向き合う必要性があると感じた。
「にいちゃ? ニア?」
俺らが入ってくるのが遅いと気づいたロンは扉を開けてこちらを見ていた。
「どうしたの? 誰かに痛いことされた? にいちゃもニアも泣かすやつはロンが守る!」
俺もいつのまにか泣いていたようだ。それを見たロンが心配して優しく背中から抱きしめていた。
舌足らずで猫舌なのに、シチューをかき込んでいたロンはしっかりとした兄だった。
「ロンもずっと一緒だぞ」
俺はロンを近くに寄せて抱きしめた。二人の温かさがどこか冷たくなっていた俺の心が溶けていくような気がした。
どことなく自分と被るこの子達の存在が、いつのまにか俺の中でも味方だと感じていたのだろう。
ニアに言っていた言葉も、心の奥底では自分に対して言っていたのかもしれない。
小さい時から家族がおらず独りぼっちの俺は家族を求めていたのかもしれない。
「ロンとニアはいつまでも俺の家族だからな。俺がお前達を守るからな」
決して父親になりたいわけではない。ただ、俺は心の底から守ってあげたい。守らなければいけないと思う家族ができた。
二人は俺の外套の中に隠れて、顔だけ出して一緒に歩いている。
「にいちゃ、今日なにするの?」
「んー、薬草の採取かな」
「私達は何を手伝えばいい?」
子供達はキラキラした顔でこっちを見ていた。
ステータスだけで言えば俺と同程度だが、装備が強くないのが問題だった。念のためにポケットにはメジストからもらった風属性のスキル玉を忍ばせている。
いざとなった時に使えるよう、昨日は夜遅くまで教えた。
「じゃあ、ここらへんで薬草を探そうか」
俺が事前に薬草の特徴を伝えると二人は頷いて薬草を探しに行く。
「あっ、にいちゃあったよ!」
俺が見える範囲内で二人に作業をしてもらっているが、ロンがすぐに薬草を見つけられるのに比べ、ニアは全く見つけることができなかった。
これはロンのスキル【収集】が関与しているのだろう。
俺は子供達が見つけた薬草を匠の短剣で刈り取るだけの役割を繰り返している。それには理由があった。
「グルルルルル!」
物陰から出てきた魔物を隠れていた俺が仕留める。ロンのスキルが関与しているのは、薬草の採取だけではなく魔物も同様だった。
森の外にいるはずなのにロンに向かって、森から魔物が出てくることがあった。
基本的に森から追いかけて来なければ、魔物は外に出るはずがない。何かしらスキルの影響があるのは確実だ。ただのピクニックも命懸けだった。
宿屋から渡されたサンドイッチを食べながら休憩していると、ロンが魔物を倒したときに出てきた魔石を眺めていた。
「魔石が欲しいのか?」
「にいちゃもらっていいの?」
「ああ、何かに使う時が来るかもしれないしな。ニアもいるか?」
俺がニアにも聞くとニアは首を横に振っていた。この辺も収集が関係しているのか、ただ単に性別が男の子だからだろうか。
俺達はある程度仕事をしながらピクニックを終えると街に戻ることにした。
来た時は喜んでいた二人だったがロンは魔石をもらって喜んでいたが、反対にどことなくニアは元気がなかった。
俺は気になりながらも、魔石の買い取りをしてもらうためにメジストの錬金術店に向かった。
「お兄ちゃん……」
お店の扉を開けようと手を触れると、ニアは俺の服を掴んでいた。
ニアに話しかけたがどこか落ち着きがなく、チラチラとロンを見ていたため、ロンだけ先に店に入ってもらい話を聞くことにした。
「ニアどうしたんだ?」
「お兄ちゃんは私を捨てない?」
俺はニアの言っていることがわからなかった。どこでそんなことを思うようになったのか、全く気づかなかった。
「捨てるはずないだろ?」
「だってニアはロンと比べて薬草も探せないし、魔物も呼べない役立たずだよ」
きっとロンと比べて自分の存在価値がないと思ったのだろう。今まで奴隷畜舎でそうやって育てられたのが、身に染みている気がした。
こんな幼い子に対して、大人達は何をやっているのだろうか。
「ニアはスキルも使えないから捨てられたんだ。きっとニアなん――」
俺はそれ以上は聞けないし、言わせてはいけないと思い手で口を閉じさせた。涙を堪えてるニアはどこか震えている。
「別に俺は使えるかどうかでニアといるわけじゃないぞ。俺達はもう家族だ! だから使えないって言うなよ」
優しくニアに抱きつくと、そのまま俺の胸元で涙を流していた。嗚咽が出るほど何度も泣いていた。
それだけ今まで辛かったのだろう。兄妹だからこそ比べてしまうのは仕方ない。
「そんなに頑張らなくても大丈夫だ。俺はどんな時でもニアの味方だ」
今までロンより年下で妹のはずなのにしっかりしていたのはずっと捨てられないように強がっていただけかもしれない。
ただ、家族になったからこそ、しっかり子供達と向き合う必要性があると感じた。
「にいちゃ? ニア?」
俺らが入ってくるのが遅いと気づいたロンは扉を開けてこちらを見ていた。
「どうしたの? 誰かに痛いことされた? にいちゃもニアも泣かすやつはロンが守る!」
俺もいつのまにか泣いていたようだ。それを見たロンが心配して優しく背中から抱きしめていた。
舌足らずで猫舌なのに、シチューをかき込んでいたロンはしっかりとした兄だった。
「ロンもずっと一緒だぞ」
俺はロンを近くに寄せて抱きしめた。二人の温かさがどこか冷たくなっていた俺の心が溶けていくような気がした。
どことなく自分と被るこの子達の存在が、いつのまにか俺の中でも味方だと感じていたのだろう。
ニアに言っていた言葉も、心の奥底では自分に対して言っていたのかもしれない。
小さい時から家族がおらず独りぼっちの俺は家族を求めていたのかもしれない。
「ロンとニアはいつまでも俺の家族だからな。俺がお前達を守るからな」
決して父親になりたいわけではない。ただ、俺は心の底から守ってあげたい。守らなければいけないと思う家族ができた。