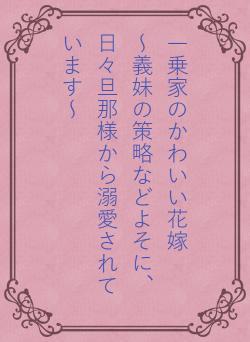1
『おぞましい化け物』とは誰が言ったのだったか。
夫となった黒王は、そんな言葉とは無縁の美しさをもっていた。
月明かりにしっとりと輝くひとつに結われた黒髪は、風に靡く瑞兆の尾のような優雅さがあり、精悍な目つきからは、女である自分よりも濃い色気が漂っていた。
こうして今思い出してみても、とても烏のあやかしだとは思えない。
年の頃は二十をいくつか過ぎたくらいか。
村で目にする同年の男よりも纏う空気に品があり、今まで見てきたどのような人間よりも、菊は彼こそが一番美しい人間だとすら感じたものだ。
深夜にひっそりと行われた、黒王と菊の二人だけの嫁入り。
誓約の口づけだけが交わされ、その後はもう遅いからと、連れられた部屋で休むようにと言われた。畳敷きの部屋には既に布団が敷かれており、そこが寝所だということがうかがえた。
このまま彼と初夜を過ごさなければならないのかと焦ったが、しかし、黒王は「おやすみ」とだけ言って、すぐに踵を返して部屋を出て行ってしまったのだ。
あまりのあっけなさに、菊は拍子抜けすると一緒に安堵した。
長らくの緊張から気が緩んだこともあり、菊は横になった瞬間、そのまま夢の世界へと旅だったのだった。
そして、今朝。
女の柔らかな声に起こされ、布団から出てきてからは驚くことばかりである。
まず、菊にはひとりの侍女と、いくらかの女官がつけられた。
今まで使用人として使われることはあっても、誰かに世話を焼かれることのなかった菊にとって、それは喜びよりも驚きや戸惑いのほうが大きかった。
食事の時も座っているだけで良く、最初、目の前に用意された食膳を見て、菊は首を傾げたものだ。
誰かの配膳を手伝えということなのだろうと思い、「どちらへは運べばよろしいでしょうか」と女官に尋ねれば、慌てて「花御寮様のです」と言われ驚いた。
もしかしたら寝ているうちに自分は食べられて、既に天国に来てしまったのではないかと、菊は本気で錯覚した。
天国とは自分でも図々しいとは思うが、そうとしか思えないような扱いなのだ。
『人を食べたいがために、花御寮を欲しがっているに違いない』と村では言われていたのに、食べられるどころか、菊に出された食事は古柴家の者達が食すものよりはるかに豪勢なものばかり。
丸々と太った鮎の塩焼き、蕗の煮付け、豆腐の山椒和え、冬瓜の煮物、蕪の味噌焼き、山盛りの木苺。どれもが生まれて初めて口にする味で、「美味しい」以外、気の利いたことも言えなかった。
立ち上がれば『どちらへ行きましょうか』と尋ねられ、座れば『本でもお持ちしましょうか。それとも、貝合でもなさいますか』と、とにもかくにも菊を下に置かぬ扱いなのだ。
さすがに、着替えを手伝われそうになった時は、恥ずかしいからとひとりで着替えさせてもらったが。
そして、驚きは身の回りのことだけに尽きない。
つるりと輝く板張りの廊下に、ひとりでは多すぎる部屋の数々。その中でも、東棟の一番奥にもうけられた庭に突き出た板張りの広間は特にだった。
広々とした広間には几帳がいくつも立ててあり、薄紅色の美しい織り地の几帳は、風が吹き込めば目にもあやな光景を作り出す。菊が座る場所には五色の縁が鮮やかな茵が敷かれ、つるっとした漆塗りの厨子や文机や唐櫃。
まるで、古の絵巻の世界のようだ。
黒王の屋敷はいくつもの棟が渡殿で繋がっており、うかつに歩き回れば迷子になってしまいそうなほどに広い。界背村の村長の屋敷など比べものにならない。
菊には、黒王の住まう母屋に繋がった東棟が与えられている。
東棟の中でもいくつもの部屋が連なっており、移動もちょっとした散歩気分だった。
「花御寮様、どうされましたか? 先ほどからずっと外を眺めておいでですが」
「あっ、わ、若葉さん……いえ、その……」
屋敷の説明を一通り聞き終え、広庇でぼうっとしていたら、侍女の若葉が隣にやってくる。前髪の一部が緑色になった特徴的な侍女だ。
「……夢のような場所だなって……」
菊はまじまじと、己の手首に絡む柔らかな袖を眺めた。
桃花色の生地に、純白の糸で小花が刺繍してある着物は美しいの一言につきる。上から紗の白羽織を纏えば、まるで目の前に見える桜から作られたようだ。
菊が座っている張り出した広庇からは、たくさんの桜の木が見えている。
霞のようにあちらこちらで芽吹き始めた桜に目を向ければ、若葉も「ああ」と一緒に目を向ける。
「三分咲きというところでしょうか。最近は我が郷も暖かくなって参りましたから、五分までくればあっという間に満開ですよ」
楽しみですね、と微笑まれ、菊は「そうですね」と曖昧な笑いしか返せなかった。
これも、菊が目を覚まして驚いたことのひとつである。
若葉や女官が見せる柔らかな笑みや気遣いや優しさは、菊が生まれて初めて受けるもので、正直どのような反応を返して良いのか分からないのだ。
――それに……彼女達の優しさは、本来私に向けられたものじゃないもの。
「どうされました、花御寮様?」
すっかり黙り俯いてしまった菊を、若葉が眉を下げて心配そうに覗き込んできた。後頭部の高い位置で結われた彼女の髪が、肩口でゆらゆらと揺れている。
――この心配も、〝私〟じゃなくて〝本物の花御寮〟へのもの……。
彼女達の優しさを嬉しく思う反面、心のどこかで『自分はニセモノなのだから』と引っかかって素直に喜べない自分がいた。
「私なんかにこんなに良くしてもらって、その……申し訳なくて」
「そのようなことを仰らないでください。花御寮様は、黒王様の妻となられる方で、わたくし共にとっても大切なお方なのですから。良くすることが当たり前で、花御寮様がそのように遠慮なさることはないのですよ」
膝に置いていた手を、若葉にギュッと握られた。
しっかりと五本の指があり健康的な色をしている若葉の手は、菊の手と同じ形をしている。違いといえばひとまわり大きいことくらい。
彼女もこの郷に住んでいるということは、烏のあやかしなのだろうが、頭の先から爪の先までどこをどう見ても同じ人間にしか見えなかった。
――不思議。人間の手よりもあやかしの手のほうが温かいだなんて。
村では、菊を無理矢理に引っ張る手や頬を叩く手は、どれも冷たかった。
そういえば、黒王の目は冷たかったが、触れられた手は温かかったな、などとその時の心地よさを思い出して、菊はハッと頭を横に振った。
――だ、駄目よ! あれは私が受けるべき温かさではないんだから。
そういえば、と昨夜彼に言われた言葉を思い出す。
「あの、若葉さん。黒王様との婚儀はいつになるのでしょうか。昨夜のは婚儀ではないと黒王様に言われたのですが」
「昨夜のは迎えの儀でしたからね」
「迎えの儀、ですか?」
「わたくし達鴉一族に伝わる婚儀までの儀式のひとつですよ。深夜、夫となる男がひとりで妻になる女のもとを訪ねるのです。そこで男は女に妻になってくれるかを問い、女は諾否を返すというものです。ここで女の承諾が得られてはじめて、婚儀が行えるようになるのですよ。黒王様より儀式のことは聞かれませんでしたか?」
「いえ、何も……」
それどころか、あの『俺の妻になるか』という言葉が、儀式の問いだとも思わなかった。当然、『いいえ』などという選択肢はないのだから、素直に『はい』と頷いたのだが。
黒王は一言もそのようなことは教えてくれなかった。
口づけの後、彼は『正式な婚儀は改めてする。着いてこい』と言ったきり、この東棟に入るまでずっと無言だったのだから。
おかげで気まずくて、俯いた視界にあった彼の白い足袋と、黒袴が揺れている姿しか覚えていない。
すると、若葉が耳元に顔を寄せてきて囁いた。
「婚儀の日と言えば初夜ですね、むふふ」
「――っ初夜ですか!?」
当然、結婚すればそのようなこともあると知ってはいたが、それよりも入れ替わりの事実がばれないかばかり気になって、すっかり忘れていた。
「あら、もしかして初夜のことも黒王様はお話になってないと……。まったく黒王様ったら、相変わらずの面倒くさがりやなんですから」
「ほう、誰が面倒くさがりだと?」
若葉が頬を膨らませて「もうっ」と言った瞬間、背後から厚みのある逞しい声が聞こえた。
それは当然、女官の声などではなく――。
「こ、黒王様!」と、菊は慌てて床に額をつける。
「そんなに畏まる必要はない。顔を上げよ」
菊は怖ず怖ずといった調子で上体は起こせたのだが、顔までは上げられなかった。
昨夜向けられた冷たい視線が、また頭上から向けられていると思うと、とても顔など上げられない。
菊の視界には、黒王の黒い袴の裾と白足袋だけが映っているのだが、しかし次の瞬間、ぬっと目の前に黒王の顔が現れた。
「ひゃっ!?」
驚きの声と一緒に菊の顔も跳ね上がる。
どうやら彼は、膝を折ってまで自分の顔を覗き込んできたようだ。目の前で胡坐をかいて、黒王という名に相応しい黒い瞳で、じっとこちらを見てくる。
――何かしたかしら。
視線に戸惑いを覚えていると、ぬっ、と黒王の手が伸びてきた。
男の大きな手に、過去の記憶が脳裏に再生される。
「――っ!」
次の瞬間、菊は首を竦めて身を強張らせた。
しかし、覚悟していた痛みはなく、代わりに髪を撫でるような感覚があっただけ。
「散り花がついていただけだ」
「あっ……も、申し訳ございません」
額を打ち付けそうな勢いで頭を下げる菊に、頭上からハッ、と鼻で笑う声が降ってくる。
「レイカ」
呼ばれた名前にツキリと胸が痛みつつも、怖ず怖ずと顔を上げる。
それでもやはり視線は上げられない。
「俺が怖いか?」
「そのようなことは……」
ある、とはさすがに言えない。
中途半端に切ってしまった言葉が、気まずく二人の間をただよっていた。
「――っあの、黒王様。婚儀の日取りはいつになりますでしょうか?」
言った後で菊は『あ』と後悔した。
話題を逸らさねばと思い、咄嗟に出てきたのは、まるで菊が黒王との婚儀を望むような言葉。
「ほう?」
案の定、黒王はニヤリと目を細め、興味が滲んだ声をだす。
「今、婚儀に相応しい日を選ばせている。決まったら言うからもうしばらく待て。それとも――」
「きゃっ!?」
突然、黒王に腕を引っ張られ、菊は彼の胸に飛び込んでしまった。そして、覆い被さるようにして耳元で囁かれる。
「そんなに早く俺と閨事をしたいのか?」
「ね、やご……と?」
言葉を雛鳥のように片言で復唱した菊だったが、次の瞬間、ぼっと顔が赤くなる。
「ね、閨――!? っと、とんでもありません! いえ、あの……っその……!?」
色気のある声で囁かれ、余計にそういうことを意識してしまった。
「黒王様、あまり花御寮様を揶揄われないでください。それに、急に手を引くのはおやめなさいませ。人間の身体はわたくし共妖と違って繊細なのですから」
「揶揄ってなどいない。俺はレイカの意思を確認しただけだ」
「左様でございますか」と、嘆息した若葉が菊を黒王の手から救出する。
「花御寮様、痛いところなどはございませんか」
揶揄われただけだと知り、菊はホッと安堵の息を吐いて大丈夫だと答えた。
それに痛いどころか、黒王が触れた手は驚くほどに優しく、引っ張られても痛くはなかった。
――昨夜も思ったけど、どうして黒王様の言葉や視線はちぐはぐなのかしら。
向けられる視線や言葉には冷たいものが含まれるが、反対に自分に触れる手は驚くほど優しい。
その違いはどこから来ているのだろうか。
しかし、菊には黒王の事など何も分からない。
おかげで少しの推察もできず、微かな疑問は瞬く間に思考の中にかき消えた。
「まあ、いい。たとえレイカが嫌がろうと、子は残してもらわねばならないからな。そのための花御寮だ。責任は果たしてもらうぞ」
腰を上げた黒王は、また温度のない昏い瞳で菊を見下ろしていた。
ゾクッと、背中に冷たいものが落ちる。
「……子供……」
菊は自分の腹に触れ、しかしすぐに腫れ物にでも触れたように拳を握った。
「ではな、俺の花御寮殿」と言って遠ざかっていく黒王の足音を聞きながら、菊は自分に残された時間についてを考えざるを得なかった。
――初夜でこの身体を見られてしまえば、全てが明らかになってしまうわ。
ニセモノとばれるまで――つまり自分の命は、長くても初夜までということか。
菊は、満開の桜は見られるだろうか、と欄干の向こうを眺めていた。
◆
鳥居の向こうから現れたのは、白無垢を纏った小柄な少女だった。
子供かと思ったが、奏上で述べられた年齢を思い出し、二十三の自分より五つも下なら当然かと納得した。
綿帽子の下から覗く、烏と同じ真っ黒な前髪。前髪以外は白に包まれ、月明かりの中、輝くように際立っていたのが印象的だった。
最初に思ったことは『これが俺の花御寮か』という、身も蓋もないことだった。
どうせ、人間には化け物だなんだと思われているのだし、最初から花御寮には何も期待していなかった。子供さえ産んでくれれば、あとは勝手にしてもらっていい。
しかし、綿帽子を脱がせ、見上げてきた彼女を見て驚いた。
『もしかして』という喜びがわきそうになったが、自分を見上げてくる彼女の目は怯え、胸元を握る小さな手が震えていれば、そのような甘い考えはたちまち消えた。
黒王は、東棟から戻ってきた私室でひとり自分の手を眺め、溜息を吐いた。
「なんて溜息を吐いてるんです。新婚が吐いて良いものじゃないですよ」
中性的な軽やかな声が聞こえたと思ったら、衝立の向こうからひょこっと顔を覗かせ、近侍の灰墨がやって来る。
灰がかった色の髪は、彼が歩く度にふわふわと揺れ、見るからに柔らかそうだ。
灰墨は目の前までやって来ると、ちょこんと黒王と対面して正座する。
「灰墨、部屋に入ってくる時はまず声掛けをとあれほど……」
「堅いこと言わないでくださいよ。僕と黒王様との仲じゃないですか」
「まったく、お前は」
灰墨は、近侍であると同時に、幼い頃から共に育ってきた四つ下の乳兄弟である。おかげで近侍だというのに、昔からの関係で他の者よりも言葉や態度に遠慮がない。しかし、今まで誰も矯正してこなかったのは、黒王自身がそれで良しとしてきたからだ。
大人になり肩書きがつくほど責任は重くなるのに、周囲との距離は開いていくばかり。そんな中、灰墨の態度は黒王にとって昔のままでいれる貴重なものだった。
「それで、黒王様。先ほどの憂鬱そうな溜息はなんなんですか。つい先ほどまで、花御寮様を訪ねられていたはずでしょう? 新婚初日とは思えないですね」
「まだ婚儀はあげてない」
「はいはい」と灰墨に適当にいなされ、黒王は今度はわざとらしく不満を訴えた溜息を吐く。
しかし、灰墨は気付いているのかいないのか、どこ吹く風とケラケラと笑っている。
「あー、やっぱり花御寮様のことがお嫌いなんですね? であれば、さっさと村に返しちゃいましょう! それが良いです! こんな古くさい因習なんか終わりにしましょうよ!」
「そう簡単にできることでもないし、そういう意味の溜息でもない」
「でも、黒王様は人間がお嫌いでしょう? 僕も嫌いですよ」
黒王は灰墨の問いに答えを窮した。
結局、黒王は否定も肯定もせず、話を続けることを選んだ。
「灰墨、お前が以前から花御寮について納得していないのは知っているが、俺の一存でなくせるものでもない。なくしたければ、お前が各里の里長達を集めて説得して回るんだな」
「えー! あんな頭が石仏と変わらない方達を説得だなんて、絶対無理じゃないですか!」
「そういうことだ。諦めろ」
納得できないのか、灰墨は「えー」と言いながら畳の上にぐでんと上体を倒していた。いつまでたっても、甘えたな弟気質は治らないようだ。
「お前、もう十九だろう。もっとしっかりしろ」
「いいんです、他ではしっかりしてるんで。これは黒王様の前でだけです」
「そんなこと言うのはお前くらいだよ。普通は逆だ」
思わず黒王もフッと小さく笑みを漏らしてしまう。
「それと、灰墨。花御寮についてだが、お前から聞かされた話と些か違う気がするんだが」
迎えの儀の前に、村からは花御寮の名前と、迎えの儀の日取りが書かれた紙が村の神社に奉納される。
あの神社は、鴉の郷から現世に行くための通路となっている。
常世側からしか繋ぐことはできず、人間にはただの神社でしかないのだが、まあ、妖の世と繋がっていると知っていて近寄る人間はいない。
灰墨が取りに行った紙には、花御寮の名前として『古柴レイカ』と記されていた。
別に誰が来ようと同じと思っていたし、名前を聞いても少しも興味は沸かなかったのだが、灰墨が『どんな女か見てやりますよ!』と勇んで出て行ったのは記憶に新しい。
そうして持って帰ってきた古柴レイカについての報告というのが――。
『村の顔役の娘ということもあり、性格が悪く高飛車であり、村娘達の中心的存在』
というものだった。
「僕は花御寮様と会ってないのでなんとも言えませんが、昨日の今日ですし、まだ猫被ってるだけかと思いますよ」
「いや」と黒王はすぐに否定する。
「そんな器用なことができる人間ではない」
これには灰墨がきょとんとした顔で首を傾げた。
「まるで良く知っているような口ぶりですね」
「あ、いや……今日接した感じからそう思っただけという話だ。露骨に俺を怖がっていたしな」
「ふぅん」と、灰墨はさほど追求せず流し、黒王は胸をなで下ろした。
黒王は、彼女を知っていた。
ただし〝花御寮〟という認識ではなく、名前も知らないただの界背村の村娘としてだが。
しかし知っていたことで、この現実に落胆を覚える羽目になっていた。
「……灰墨。人間は現世の烏にどんな感情を抱いている」
「ええー、またそれ言わせます? あまり気分の良いものじゃないですけど……不吉の象徴だの、死神だのと随分な言われようですよ。本当、勘違いもいい加減にしてほしいですよね! こちとら太古の昔から、神使として神の眷属に連ねられているってのに!」
「そうだ、烏は嫌われ者だ」
自分で言って、黒王は自嘲した。
「……その嫌われ者の烏よりも、俺達のほうが嫌いということか」
「ん? 今、何か仰いました?」
「いや、独り言だ」
灰墨がツラツラと鴉一族のゆえんをひとり熱弁しているのをよそに、黒王は開け放たれた障子から景色を眺めた。
桜の木の枝には、ぽつりぽつりと薄紅色の花が咲いている。
別に彼女の性格まで全て知っていたわけではない。
ただ、他の人間よりも少しは優しいのかもしれないと思っただけで。
しかし、やはり常世の者に向ける感情は違うのだろう。
ちょうどいい。性格が悪い娘をと望んでいたのは自分ではないか。
この夫婦関係はただの習わしでしかない。義務的に役割だけをこなせば良い。
胸に覚えた感情など、さっさと忘れてしまえ。
2
花御寮として嫁入って四日が経った。
菊は杉の香りが漂う湯殿で、ひとり風呂に浸かっていた。
初日、女官達が湯浴みの手伝いをすると言って、一緒に湯殿の中までついてこようとしたのだが、それは菊が必死に止めた。しばらく女官達はそれも仕事だからと譲らなかったが、三日も言い続ければ折れてくれた。
単純に恥ずかしいし、何よりこの身体は誰にも見られてはならない。
「やっぱり、私なんかが花御寮になるべきじゃなかったのよ」
元より、自分に花御寮になる資格などなかったのだから。
若葉をはじめ女官達は、菊にとても良くしてくれる。そんな彼女らを騙していると思うと、いつも心が痛くなるのだ。
「それに……」
菊はちゃぷっ、とお湯から出した自分の手を眺めた。彼の大きく骨張った手とはまったく違う手。
あのような大きな手を近づけられると、どうしても反射的に身構えてしまうのだ。
若葉達の手は大丈夫なのに、やはり自らの身に刻まれた恐ろしい記憶が蘇るからだろう。
「傷つけた……のかしら、やっぱり」
顔を見ることはできなかったが、頭上から振ってきた鼻で笑う声には、微かに哀感が籠もっているようにも聞こえた。
あれからも黒王は毎日菊を訪ねてくるのだが、彼は一度も触れようとしなかった。
おかげで、余計に悪いことをしてしまったという罪悪感が、菊の中でモヤモヤとわだかまったままなのだ。
菊は、湯気立つ温かなお湯の中に口元までを沈め、ぶくぶくと子供のように泡立てる。
こんなこと、古柴家ではしたこともなかった。いつも最後に入るお湯は冷めきっており、浸かると風邪をひくから拭うだけで、こんなにいっぱいの温かいお湯に浸かれることはなかった。
花御寮として迎えられ、菊はいくつもの『生まれて初めて』を経験していた。
当然、当初に抱いていた『食べられるかも』という恐怖は今はもうない。
しかし、どのように黒王に接したら良いかという迷いはまだある。
結局、この生活も周囲との関係も、いつか終わるものだから。
「ニセモノなのに、こんな良くしてもらって申し訳ないくらい。せめて花御寮でいる間は、何か役に立てるようなことを探さなくちゃ」
たとえ初夜までの命だとしても、少しでも罪悪感は減らしたかった。
「……こんな汚い女……誰も欲しがらないもの」
暖かなお湯の中で、菊は凍えたように身体を抱きしめた。
◆
ここ数日での春の陽光に空気も暖まり、日中、菊が過ごす場所は開放感あふれる広庇の広間ばかりになっていた。
桜は今ちょうど五分咲きといったところで、日々の移ろいが景色として目に見えるというのは感動的である。
「――え、花御寮様のできることですか?」
「ええ、皆さんにこんなに良くしてもらってばかりじゃ申し訳なくて。何かお役に立てたらと思いまして」
昨夜、自分のできることを色々と考えたのだが、これまでの人生経験が少なすぎて良いものが思い浮かばなかった。なので、本人達に聞くのはどうかと思いながらも、こうして若葉に何か自分にできることはないかと尋ねてみたのだが。
「家事は得意なんですが……」
「ふっ……あはははは! 花御寮様ったらとてもお優しい方ですのね」
笑われてしまった。
余程おかしいのか、若葉は身体を揺らしながら笑っては目尻に涙を浮かべている。
若葉は、ハキハキとした気持ちのいい女性だった。
洗練された凜とした空気をまとい、おそらく彼女に憧れる者は多いのではと予想できる。しかし偉ぶったところは少しもなく、菊の意思を汲んで、半歩ほど先回りして絶妙な手助けしてくれ、とても頼りになる。
おかげで、菊もすっかりと若葉には心を許していた。
「もう、若葉さん。私、本気で悩んでるんですよ」
「そんなこと、花御寮様は考えられなくてよろしいのですよ。わたくし達にとって、花御寮様が来てくださったこと自体が喜ばしいことですから。でもそうですね……」
若葉は手にしていた本を閉じると、文机の上にある菊の手を両手で包んだ。
「できることなら、どうか黒王様を怖がらないでください」
ぐっ、と菊の首が僅かにのけぞる。
「怖がっては……」
穏やかな苦笑顔で見つめられ、菊は取り繕うのを早々に諦めた。
カクン、と菊の顔が俯く。
「……すみません。少し……怖いです」
正直に言った後で、彼女達の長であり、自分の夫でもある黒王を怖いなどと言うのは、失礼だったかもしれないと後悔した。
しかし、伝わってきたのは、若葉がふっと微笑んだ気配。
「怒らないんですか? 怖いって言ったこと」
恐る恐る視線を上げて若葉の様子を窺えば、彼女はじっと菊を見つめていた。彼女の黒い瞳には怒りなど微塵も見えず、ただただ柔らかく笑まれている。
「わたくし達は、あやかしと呼ばれ常世に棲まう者。現世の者が恐怖を抱くのも無理はありませんから。確かにあやかしの中には人間を害する者達もおります。しかし、わたくし達鴉は、人間の血を半分受け継ぐ黒王を長と仰ぐ者達です。誰ひとりとして花御寮様に怖い思いをさせたいとは思っていないのですよ」
「黒王様も……ですか?」
「もちろんです」
嫁入りしてから毎日、黒王は菊に会いにやって来る。
朝一番の時もあれば、昼時や、夕暮れの時など時間はまちまちだが、しかしいつも菊の顔を見るだけで、これといった会話もなしに帰っていくのだ。
あっても最小限の様子伺いの言葉のみ。
――私に会いにっていうより、義務だから渋々来てるみたいな感じなのよね。
おかげで彼が何を考えているのか、何を自分に思っているのか分からず、それが恐れとなっているのも否めなかった。
「今は態度が冷たく感じられるかも知れませんが、黒王様は本当はとても温かなお方なのですから。花御寮様への態度が少々ぎこちなく感じられるのは、昔、とてもお辛い思いをされたからで……」
「昔?」
若葉は苦笑しただけで、その部分については話そうとはしなかった。
――そうよね。他人の過去は勝手に話すものではないもの。
しかも〝昔〟を思い出したのか、若葉は眉根をひそめ、苦痛を噛みしめるかのように口角を下げている。とても気軽に聞いて良いものではないと察せられ、菊は深追いせず口を閉ざした。
「花御寮様、黒王様をまっすぐ見てあげてください。わたくし達と接するように、何をしたいか、何が好きか、何を思っているか、ひとつずつ言葉を交わされてください」
願いを込めるように、包む若葉の手の力が増した。
「それは、花御寮様にしかできないことですから」
「私にしかできないこと……?」
不要と言われ続けた、忌み子である自分にしかできないこと。そんなものがあるとは。
胸の内側に、仄かなあかりが灯ったようだった。
「私にもできることがあるのでしたら、頑張りたいです」
意を決した顔で、菊がもう片方の手を若葉の手に重ねた時だった。
「いつの間にそれほど仲良くなったんだ」
声に驚き部屋の入り口に顔を向けると、そこには扉に肩をもたれかからせて立つ黒王の姿があった。
今日は珍しく黒羽織と袴の姿ではなく、紺鼠色の着流しと黒い帯という格好である。
すっきりとした出で立ちなのに華やかに見えるのは、きっと彼の高い腰位置と、無駄のない身体の輪郭のせいかもしれない。
そんなことを、彼の姿を目にしてぼうっと思っていれば、ギッとすぐそこで床板の軋む音がした。意識を現実へと引き戻せば、彼の黒い双眸がこちらを見ており、菊は反射的に視線を下げてしまう。
握られたままだった手を、まるで合図のようにギュッ、と一度強く握られた。
「あ……」
若葉と目が合えば、片目を閉じて目配せされる。
「ではでは、わたくしは仕事がありますので失礼させていただきます。どうぞお二人水入らずでお過ごしくださいませ」
「ああ、若葉。そういえばさっき灰墨が探していたぞ」
「灰墨が? かしこまりました。それではついでに訪ねてみましょう」
「え!? あ、わ、若葉さん……!?」
「ほほほー! 花御寮様、失礼いたしまーす」
菊の戸惑いの声を笑顔で受け流し、若葉は部屋から出て行ってしまった。
――そ、そんなぁ……まだ心の準備が……。
確かについ先ほど頑張ると言ったばかりなのだが、それにしてもこれはあまりに急すぎでは。
――せめて明日なら……もう一日くらい考える時間がほしかったのに。
まだ何を話せば良いか話題すら見つかってすらいないこの状況で、二人きりで取り残されるのは少々不安だっら。しかも黒王は立ったままで、いかにもすぐに帰るといった様子。
「変わりないか」
「は、はい」
「そうか」
相変わらず淡泊な、会話とも呼べないやり取り。ここからどうやって、若葉達と話すような雰囲気に持っていけば良いのか分からない。
「ではな」と、黒王が立ち去る気配がして、菊は慌てて黒王を引き留めた。
「お待ちください! あの、少しで良いんで一緒にお話しませんか」
焦っていて、思いのほか大声になってしまい、菊はパッと自分の口を手で押さえる。
「お話し……俺とか?」
菊は口元を隠したまま、コクコクと懸命に頷く。
目を丸くして、振り返ったままの体勢で固まっている黒王。やはり唐突すぎただろうか。
彼はしばし逡巡すると、ゆっくりと菊の元へと戻ってきて、隣に腰を下ろした。
――これは、『良い』ってことかしら。
しかし、これはこれで何を話せば良いのか。
――これじゃ、ただ呼び止めただけだわ。もし黒王様にお仕事とかあったのなら、むしろ迷惑だったんじゃ……っ。
今度は菊が固まってしまった。
――ええと、いつも若葉達とは何を話してたかしら。
あれでもないこれでもないと、頭の中がぐるぐるぐるぐると煮詰まっていく。
「読書か」
「え」
もうすぐで菊の頭から湯気が出そうになった時、黒王が床に置いてあった本を手に取った。それは先ほど若葉が持っていた和綴じの本。
「なんの本だ……って、『にじいろまがたま』? 子供が読むような童話じゃないか。大人のレイカが読む分には物足りないと思うが」
黒王は本の題名を読み上げて、片眉を訝しげに下げている。
「いえ、これはその、読んでいたわけではなく……」
「読まないのであれば何故ここに?」
彼は首を傾げ、顔はますます怪訝の色が濃くなる。それと一緒に、菊の顔はどんどんと俯いていった。胸の前で重ねられた手は、心許なさを隠すようにギュッと握られている。
菊の震える唇が開き、か細い声が漏れ出た。
「……私、文字が読めないんです」
顔が熱かった。
「書けもしないです」
界背村では菊と同じように文字を書けない女性もいた。特に使用人などがそうだ。
だが、皆文字を読むことはできたのだ。読みも書きもできないというのは、村でも菊ひとりだけだった。
こんな無知な娘が花御寮とは、やはり恥ずべきことだろう。
あやかしの世界の風習や規則などは分からない。だが、先ほど黒王は『子供が読むような』と言った。それは、子供でも菊のような者はいないということだった。
いっときのニセモノとは言え、一族の長の妻として、自分はやはり不釣り合いではないか。
「でも、花御寮も色々と婚儀の席で読むものがあると聞いて、若葉さんに文字の読み書きを教えてもらえるようお願いしたんです……付け焼き刃かもしれませんが……」
若葉は快く引き受けてくれたが、もしかして恥ずかしいと思われていたのではないか。どんどんと気持ちが塞がっていく。
やはり、ここでも自分だけひとりぼっちだ。
花御寮だから受け入れてもらっているだけで、その肩書きがなければ、誰にも見向きもされない存在なのだ。
菊は顔を上げることができなかった。
彼が、どのような目で自分を見ているのか知るのが怖かった。
――若葉さんに、真っ直ぐ見つめてって言われたけど……やっぱり無理だわ。
彼は、こんな自慢できないような女が嫁入りしてきたことを、疎ましく思ってはいないだろうか。軽蔑してはいないだろうか。
また、あの冷たい目で見られていたら……。
――あ、駄目……っ。
顔だけでなく、じわりと瞼の奥までもが熱くなってきた。
視界が歪みはじめ、慌ててぎゅっと目を閉じる。しかし、俯いているせいで、瞼を閉じてもじわじわと目の隙間からあふれそうになる。
「いい話だろう」
「へ?」
予想外の言葉に、菊は弾かれたように顔を上げた。
びっくりして、そこまで出てきていた涙も奥へと引っ込んでしまう。
「俺も昔、よく乳母に読んでもらった記憶がある。大人が読んでも面白い物語らしい」
黒王は、本を撫でたりひっくり返したりと、目を柔らかく細めて懐かしそうに眺めていた。
次の瞬間、彼は『どうだ』とでも言うように菊へと目を向ける。
その視線が、菊が想像していたよりも遙かに普通で、肩と一緒に鼓動が跳ねた。
「は、はい! とっても面白くて……虹色の勾玉を神様から貰った白烏が、野原に降り立って友達を探していくところが一番好きです! 特に最初のお友達の羽が片方なくなったのを、勾玉の烏が自分の白い羽をあげるところとか、あと他にも――あ……」
たがが外れたように喋り続けていた菊。だが、クッ、と笑いを堪える黒王の声で、我に返った。
黒王は俯いているが、肩が小刻みに揺れていた。絶対に笑っているに違いない。
「あ、わ、私ったら……その……」
小声で「すみません」と尻すぼみに呟くと、またクッと聞こえ、再び顔に熱が集まる。
「これは、俺達鴉一族について分かりやすく書いてある。手習いにもちょうど良いだろう。まあ、頑張ることだな」
「……あ」
黒王の言葉に菊の目が、これでもかと大きく見開いた。
「あ?」
「ありがとうございます、黒王様っ」
菊は瞳をキラキラと輝かせ、浮かされたような声で黒王に礼を述べた。
誰かに頑張れと言われる日が来ようとは、思ってもみなかったのだ。
黒王にそんなに深い意味はなくとも、生まれて初めて言われた、自分の背中を後押ししてくれる言葉は、菊にはとても嬉しいものだった。
そして、目を丸くしていたのは菊だけではない。
「礼を……言うのだな。人間も」
黒王も菊と同じような顔をして、ぼそりと口の中で呟いた。
しばしお互いが同じ表情で互いを見つめ合うという、不思議な時間が流れるが、それは、黒王が手にしていた本を床に取り落としたことで、不意に終わりを迎える。
ハッとして、菊は慌てて視線を黒王から正面の文机へと戻した。黒王も、なんとも言えないとばかりに後頭部を掻き乱しながら、落ちた本を文机へと戻す。
拍子に、黒王の横顔が菊の視界に入ってきた。
まつげの一本一本まで見える距離にある彼の横顔を見て、菊は「あ」と自分の勘違いに気付く。
「黒王様の瞳は黒ではなく、深い紫色だったんですね。黒だと思っていました」
よく見ると、彼の横顔に見えた瞳の色は紫だった。春光を受けてきらりと輝く深紫の瞳は、思わずまじまじと見入ってしまうくらいに美しい。
「それに、髪の毛先も色が違うのですね。そちらは淡い紫色で……」
「――っおい」
首後ろでひとつに結われた細い髪は、彼の背中で優雅な流水紋を描いている。ちょうど腰辺りにある毛先は、黒から紫へと変化していく濃淡が特徴的で目を惹いた。
「……綺麗……」
「それ以上見るな!」
自然と菊の手が背中に流れる毛先に伸びた瞬間、黒王が勢いよく立ち上がった。
驚きに、きゃっ、と菊から小さな悲鳴が上がるが、黒王は振り返ることもなく部屋を出ていってしまう。あまりに突然のことに、菊は呆然と部屋の入り口をしばらく見つめるばかりだった。
「私ったら、黒王様になんて失礼なことを……!」
勝手に髪に触れようとするのはさすがに無礼だっただろう。それに、今ま目の色や髪の色に気付かなかったというのも、気分が良いものではないはずだ。
「どれだけ私は黒王様を見ていなかったのかしら……花御寮失格だわ」
いくらニセモノでいつかはすげ替えられる身だとしても、こんなに良い暮らしをさせてもらっているのだから、せめてその日までは花御寮としての役目を全うしたいと思ったところなのに。
「……私ってやっぱり駄目な人間ね」
菊はわびしそうに俯いた。
3
ハッ、と唐突に覚醒した黒王は、腹の底に残る気持ち悪さに吐き出すように、天井に向かって息を吐き出した。
「……最悪だ」
しばらく布団に身を横たえたまま、起き上がることができなかった。
夢を見た。子供の頃の夢だ。
『お前はあたしの子じゃない!』
それが、覚えている母親に関する記憶の中で一番古いものだった。
五つくらいだろうか。それまで自分は母屋で父親と暮らしていて、ずっと乳母が母親だと思っていた。しかし、乳母とは別に本当の母親が東棟にいると聞いて、子供の自分はたまらなく会いたくなった。
東棟には近寄らないように、と父親には常々きつく言われていた。
いつも理由は教えてくれず、特に興味もなかったから素直に言いつけを守っていたが、本当の母親がいると聞けば話は別だ。
一目会いたい一心で、父親に見つからないように母屋を抜け出し、東棟へと渡った。
東棟は、母屋と比べ全ての装飾が華やかだった。
欄間の透かし彫りには花々が彫られ、格子戸の障子にも花の模様が漉き入れられている。
母屋を離れ、次第に建具が美しくなっていくのに、子供の時分は心躍らせていた。
しかし、母親の部屋に入った途端、踊っていた心は氷漬けにされたように止まった。
いや、止められたのだ。
『お前はあたしの子じゃない! 化け物めっ!』
金切り声で叫ばれると一緒に、こめかみに痛みが走った。
しばらく、自分の身に何が起こったのか分からなかった。
ただ、足元で陶器が割れる音がして、俯いた先に破片が散らばっているのを見て初めて、湯飲みを顔に投げられたのだと分かった。ポタポタと顎先からしたたる赤が交じった白湯はぬるく、いつまでも肌にまとわりつくようで気持ち悪かったのを覚えている。
他にも母親は何か叫んでいたが、騒ぎを聞きつけてやってきた女官達に引き離され、上手く聞き取れなかった。
ただ、ずっと『化け物』と叫んでいたのだけは覚えている。
「なんで今更こんな夢を……」
きっと、昨日レイカと長々と会話したせいだ。少し気が緩んだのかもしれない。
「ははっ……馬鹿か俺は」
人間は化け物を愛さない。
「ただの烏と妖の鴉では、全く違うだろ」
鉛でも背負ったように重い身体を無理矢理起こした黒王は、顔を覆った。不意に指先が触れたこめかみに痛みが走った気がしたが、とうに傷など治っているのだから、この痛みは偽物だろう。
「彼女の言葉も全て偽物だ」
乳母がよく読んでくれた懐かしい本を見て、一瞬ほだされそうになったが、所詮、彼女も人間だ。
この色を綺麗と言った心の中では、化け物だと罵っていたに違いない。
「必要以上に関わるな」
それでも、今日も彼女の元へと行かなければならない。
まだ、黒王としての地位は盤石とは言いがたいのだから、他の者達に隙などみせられない。今、つまらないことで足元を掬われるわけにはいかなかった。
黒王は手早く身支度を整えると灰墨を呼び、今日の予定の確認を終える。
そうして時間ができれば、己の花御寮のいる東棟へと足を向けた。
そこへ、黒王の背中へ声を掛ける者がひとり。
「これはこれは黒王様」
振り返ると、白髪白髭の老爺がまろやかな微笑顔で立っていた。
「玄泰か」
彼は、祖父の代から三代に渡って里長を務め、鴉一族を陰ながら支えてくれている最年長の重役である。
鴉一族は、ここ黒王が直轄する郷以外にも様々な場所に『里』を持っている。
各里には里長がおり、彼らは鴉一族の重役として会合などの時期は郷に留まることになっている。今ちょうど、黒王が交代したということで、今後の郷の方針などについて会合が開かれているのだが、この玄泰という老爺が中々の食わせ者なのだ。
「迎えの儀の日から毎日、花御寮様を訪ねられていると聞いておりますよ。仲睦まじいご様子で、よろしゅうございますなあ」
代々の花御寮が、決して夫である黒王を受け入れてきたわけではないと知っていて、この言いようなのだから皮肉以外のなにものでもないだろう。
「その花御寮へ会いに行く俺の足を止めたのだ。玄泰、それなりの用があってのことだろうな?」
「はは、お厳しい。そうそう、郷の外をうろついている妖についてですが、わたくしにお任せていただきたいと思いまして。里から若者を呼び寄せて対処させようかと」
この冬頃から、チラチラと郷の外でよその妖を見るようになっていた。
郷には結界を張ってあるから中まで入られることはないが、それでも目と鼻の先でうろちょろされるのは鬱陶しい。
妖にとって縄張りを侵すというのは、従属させるという意思表示と等しい。
普通ならば、縄張りに入らなくとも万が一を考えて、よその妖の縄張りには近付かないのが暗黙の了解なのだが。
さて、どこの妖がどのような意図でやって来ているのか。
「分かった。この件については玄泰に任せよう」
「感謝いたします」
玄泰が丁寧に腰を折り去って行くのを、黒王は眉をひそめて見送っていた。
◆
東棟を訪ねた黒王を迎えたのは、床にひれ伏した菊だった。
「……何をしている、レイカ」
踏み入った瞬間の光景に、黒王でもビクッと肩を揺らして足を止めていた。彼の声には、はっきりとした戸惑いが滲んでいる。
「若葉達はどうした。姿が見えないが」
「黒王様と二人だけで話たいと思い、席を外してもらいました」
「俺と二人きり、だと?」
訝しげな声が頭上から聞こえた。
無理もない。昨日まで己を怖がっていた者が、突然自ら二人きりになりたいと言い出したのだから。
しかし、菊は臆することなくはっきりとした声を出す。
「黒王様、昨日は不躾な態度をとってしまい、誠に申し訳ありませんでした」
「なんのことだ」
黒王がドスッと菊の前に座ると、菊の顔もゆるゆると上がる。
今日の黒王は着流しではなく袴姿で、あぐらをかいて片膝だけを立てていた。
「勝手に御髪に触れようとしたり、瞳をあんなにもまじまじと覗き込んでしまい……」
立てた方の膝に頬杖をついた黒王の口から、盛大な溜息が聞こえた。
「なんだ、そんなことか。別にその程度で気分を悪くしたりはしない」
黒王の溜息に眉を下げた菊だったが、黒王の言葉を聞いてすぐに眉間を開いて、ほっと胸をなで下ろす。
しかし、それでは昨日の唐突な去り方はなんだったのだろうか。
「では、昨日突然戻られたのは? てっきり私の無礼が原因かと」
「それは……」
たちまち、黒王の表情が厳しくなった。顔は菊ではなく明後日の方へと逸らされ、口元も頬杖で隠されてしまう。
――あ、また私、余計なことを。
先ほど謝ったばかりなのに、どうしてまた自分は同じ過ちを繰り返してしまうのか。
「申し訳ありません……私、人との距離の取り方があまり分からず……」
人と関わってこなかった。
関わることすら許されなかったのだ。
――いえ、誰かと関わりたいなんて思ったことがあったかしら。
物心つく頃には、使用人生活が身に染みついていて、自分は忌み子だからと諦めていたように思う。
今まではそれで良かったのだ。
しかしまさか、自分のその諦念を後悔する日が来るとは思ってもみなかった。
どうしても、彼のことを知りたいと思ってしまうのだ。
若葉に言われたからだけではない。
『頑張れ』と、生まれて初めて背中を押す言葉をくれた彼は、冷たい目と温かな手をした人だった。
最初から、彼の言動はずっとちぐはぐだったのだ。
その理由が知りたかった。
初めて胸に抱いた欲求に突き動かされるように、菊は真っ直ぐに黒王の瞳を見つめた。
黒王の喉が一度上下する。
「……俺のこの瞳や髪を……綺麗だと言ったな」
黒王の手が、背中に流れていた髪を肩口から引き出した。
ちょうど腹の辺りに落ちた毛先は、昨日見たのと同じように、胸の辺りで黒からだんだんと綺麗な紫に染まっている。
「はい、それはとても。まるで藤の花が飾られているようで、一足早く藤色を楽しめ得した気分です。目も紫水晶のように神秘的で、ずっと見ていたくなります」
黒王は「そうか」とだけ言って、また視線を逸らしてしまう。
何か気に障るような言い方をしただろうかと不安に思ったが、彼から怒気のようなものは感じられない。
それにしても、髪も目も紫とは不思議な色だ。現世でこのような色を持つ者を見たことがない。やはり、妖だからだろうか。そういえば、若葉も前髪の一部が緑色をしていた。 人には持ち得ない美しい色を持つ者達。色だけではない。彼ら彼女らは皆、総じて容姿も美しいのだ。
――本当、私みたいな嘘つきの忌み子には、相応しくない場所だわ。
黒王の美しさにそんなことを思っていると、「見ていたくなる、な」とポツリと彼が呟いた。
「レイカは、俺が怖かったんじゃないのか」
頬杖を外した黒王の顔が、正面――菊を真っ直ぐに見つめる。
咄嗟に「そんなことはない」と出かかった言葉を、菊はすんでで飲み込む。
彼のことを知りたいと言う自分は、彼に嘘を吐いている。ニセモノなのだ。
だからこそ、それ以外の部分では嘘を吐かず、彼には真摯でいたかった。
「確かに最初は怖かったです」
「素直だな。迎えの儀の夜、俺の着物を握るお前の手は震えていた。それからもお前は俺を見なかった……急にどうした、何か欲しいものでもあるのか? それとも村に帰りたいとお願いするためか!?」
言いながら感情が昂ぶっていっているのか、最後の方は叫ぶようであった。菊に向けられている顔も、片方の口端を皮肉めいてつり上げている。
――ああ、この顔には見覚えがあるわ。
嫌というほど村で向けられてきた、相手を蔑むときの顔だ。逃げたくなり、反射的に顔が俯こうとする。
しかし、菊は意思の力でそれを止めた。
『黒王様をまっすぐ見てあげてください』
若葉の声が耳の奥で響く。
「怖いと思ったのは、黒王様が分からなかったからです」
自分が怖いと思うことで彼を傷つけたのなら、少しでも彼を理解して、二度と彼を傷つけないようにしたかった。
それが、花御寮の資格も何も持たない自分が、唯一できることだと思うから。
「黒王様のことを私は何も知りません。ですので、教えてくださいませんか」
「ハッ……無理をしなくて良い。烏のくせに人間と同じ容姿をしている妖など、人間には化け物に見えるのだろうな」
自棄的に言う彼は、自分自身の言葉に傷ついているように見えた。
「人間と同じ姿をしているが、俺の中には妖の血が流れている。人間とは全くの別物だ」
「それは若葉さん達も同じなのでは?」
「違う。若葉達の本当の姿は烏だ。妖力を使った転化で人間の姿を真似ているだけで、元々人間の身体を持つ俺とは違う」
俺だけだ、と黒王は、床にたたきつけるようにまた自嘲を吐き出す。
「常世の者が現世の者の腹から生まれてくるのだ。お前の腹からも……」
菊の腹を黒王が指さした。
そのまま彼は顔を近づけてきて、もうすぐで唇が重なる、という距離で低く脅すような声音で囁く。
「どうだ、恐ろしいだろう? 気持ち悪いだろう? 腹の中で十月十日も化け物を育てるのは、どれほどの苦痛だろうなあ」
初めて彼の瞳の中に、温度のある感情を見た気がした。
それは今までの昏く冷めた瞳とも、紫水晶のようにただ綺麗な瞳とも違う。瞳の中に自分を映している彼の双眸は今、初めて感情らしい感情をあふれさせていた。
菊は、それがなんの感情か知りたくて、瞳を覗き込もうとした。
しかし次の瞬間、終わりだとでも言うように、瞳は瞼によって隠されゆっくりと遠のいていく。
「分かったら、二度と適当なことは言うな。子供さえつくれば、俺は二度と関わらないから安心しろ」
「安心などできません」
「…………は?」
目をぱちぱちと瞬かせる黒王の姿を可愛いと思ってしまったのは、失礼だろうか。
「だって、私には黒王様が一番苦しそうに見えますから」
菊は、黒王の瞳の揺らぎが〝怯え〟だったのだと気付いた。
いつぞやの夜、村の雑木林で出会った、羽を怪我した鴉と彼の姿が重なった。
それは、手負いの獣が怯えつつも威嚇する姿。
「黒王様が何をさして化け物と仰っているのかは分かりませんが、私は黒王様や若葉さん達皆さんを、そのように思ったことは一度もありません」
黒王の息をのむのが分かった。
「化け物とは、恐ろしいものを言うのでしょう? 確かに、黒王様に対しては怖いという感情を抱いておりました。しかしそれは、黒王様が何を思っているのか、私になぜ冷たい目を向けられるのか分からなかったからです」
それは、と黒王の口角が下がる。
分からないものは怖い。
だから昔から人々は何が潜んでいるか分からない闇を怖がり、克服するために火を灯してきたのだ。
闇の中に何があるか知るために。
「むしろ私は、化け物から救ってもらった身なのです。感謝こそすれ、黒王様達をそのように思いなどいたしません」
たとえ初夜までのわずかな命であろうと、あの村で、レイカ達の傍で一生生きていくことに比べたら、なんの苦痛も後悔もない。
「黒王様、私にできることはありませんか?」
「レイカに……できること……」
もう黒王からは、威嚇するような様子は感じられなかった。
幻想的な紫色の瞳が、戸惑ったように小さく揺れている。
「特になければ、お話でもしませんか? 私、黒王様のことが知りたいんです」
「はは……またお話か」
「はい。好きな食べ物やお花、本でもなんでもいいですよ」
「……急に言われても困る」
語尾がかすれていくにつれ、彼の顔も俯いていく。
しかし、菊はそれを拒絶だとはもう思わない。
「ではまず、私から。私はここで出されるお料理がどれも美味しくて好きで、花はもうすぐで見頃を迎える桜が好きで、あ、でも黒王様と同じ色の藤の花も好きで、本はにじいろまがたまが好きです。それしか読めないっていうのもありますけど……」
驚いたように、パッと黒王の顔が上がった。
「食事は……妖が作ったものだが」
「妖というのは、とてもお料理が上手なのですね。皆さん舌が肥えてらっしゃるのでしょうか? こんなに美味しいものを食べたのは初めてで、好きなものがひとつに絞れませんでした」
もしかして尋ねた意図と違う答え方をしてしまったのか、黒王は面食らったようにうっすらと口を開け固まっている。
あんなに冷徹そうに見えた彼から色々な表情が飛び出すのが面白く、菊は口を隠した袂の下でクスッと笑った。
「さあ、次は黒王様の番ですよ」
しばらく沈黙の時間が流れる。
菊が、やはり急には無理だったかと少しだけ寂しく思った時、うっすら開いたままだった黒王の口が微かに動いた。
「……好きなものは……分からないが、嫌いなものならある」
「なんでしょう」と、菊は小さな声音を邪魔しないよう、静かに耳を傾ける。
「冬が嫌いだ。あれは……寒い。凍えるほどに」
「黒王様は寒がりなのですね。まあ、でしたら今日は少し風が冷えますので、何か羽織りをお持ちいたしますね」
奥の部屋に自分の羽織があったなと思い出し、黒王の横を通り過ぎようとした菊だったが、不意にクンッと引き留められてしまう。
隣を見れば、黒王が菊の左手を握っていた。
「黒王様?」
「いい……行くな」
「でも、寒くありませんか?」
「寒くない」
彼はそっぽを向いたままで菊からは顔が見えないが、握られた手は確かに指先まで温かく、寒くはなさそうだ。
菊は出しかけた足を引っ込め、黒王の隣に静々と座った。
握られた手は、そのまま床の上で握られ続けている。おかげで左手と左手で繋いでいるため、互い違いを向いて座ることになってしまい、これでは会話ができない。
「あの、黒王様。手を……」
「ああ」
そうは言いつつも、彼の手は少しも動かなかった。
相変わらず彼の顔は、菊とは反対方向を向いていて見えない。
しかし、菊の手の輪郭を探るようにふわりと触れる彼の手は、まるで強く握ることを躊躇っているようで、妙にこそばゆく、変に心地よい。
力を入れて引けば、恐らく彼と手を離すこともできるだろうが、菊はそうしなかった。ここで彼の手から逃れるのは簡単だが、この状況を惜しく思ってしまったのだ。
「一緒にいろ」
瞬間、菊の顔が勢いよく黒王を向いた。
とはいっても、菊から見えるのは黒王の耳と後頭部だけで、顔など見えないのだが。
「一緒に……いても……?」
菊は心許なげに眉を下げ、涼やかな目を満月のように丸くして見つめていた。中に収まる黒い瞳は、風に揺れた湖面のようにキラキラと輝いている。
そこでようやく黒王の顔が少しだけ傾き、肩越しに彼の横顔が見えた。
「……話をしようと言ったのはレイカだろう。それとも俺ひとりで勝手に話していろと?」
彼の目尻が赤く染まって見えるのは、気のせいだろうか。
「いえ……っ、いえ、そのようなことはありません!」
菊は瞬時に首を横に振って否定した。あまりに強く振りすぎたために目の前がくらくらして、ふらりと黒王の肩にあたってしまう。
やってしまったと恥ずかしく思ったのも束の間、ふっ、と黒王が笑った気配がした。
「いいから……一緒にいろ」
菊は消え入りそうな声で「はい」と言うのがやっとだった。
朝の清涼な空気が広間に流れる、穏やかな日だった。
◆
「んっふふー、どうなることか心配したけど、さっき覗いたら花御寮様と黒王様、良い雰囲気だったし問題はなさそうねー。それにしても本当、花御寮様って素直で可愛らしい方だわぁ」
若葉は軽くなった心そのままに、軽快な足取りで東棟内を歩いていた。
「おい、若葉」
すると、自分の名前を呼ぶ声が聞こえ、若葉は足を止める。しかし、辺りに人影はなく、声がした廊下の欄干には、一羽の烏がとまっているのみ。
「あら、誰かしら? わたくしを呼ぶ生意気な声が聞こえた気がしたんだけど……どっこにもいないわねー空耳かしらー? ねえ、そこのちっこい烏さん、何か知らなぁい?」
「いだだだだだだ!? 脳出る脳出る! 頭を掴むなバカ葉!」
若葉が欄干にとまっていた烏の頭を朗らかな顔で鷲づかめば、烏はくちばしがついた口で、人と同じ言葉を吐いて騒ぎ立てた。
「年上への敬い方を知らないと、命取りになるって教えてあげなきゃねえ?」
「バカ葉、バカ葉」とギャアギャアうるさい烏の羽根を、若葉が無言で摘まむ。
「ぎゃああああ! 羽根は毟らないで!? 禿げたくないよー!」
イヤイヤと頭を左右に回しながら悲痛な叫びを上げる烏に、ようやく若葉も両手を離し解放してやった。解放された烏は、瞬時に若葉から距離をとり羽を大きく羽ばたかせると、次の瞬間には、人の姿になって旋風と一緒に廊下へと着地した。
そこにいたのは、柔らかそうな灰色の髪をした人間――灰墨であった。
「まったく……郷内で元の姿でいたってことは、あんた、花御寮様と黒王様をのぞき見してたわね?」
やれやれ、と腰に両手を当てた若葉が問えば、灰墨はばつが悪そうに唇を尖らす。
「気になるんなら、あんたも黒王様と一緒に堂々と来れば良いじゃない。近侍なんだし」
「やだ……人間なんか嫌いだ」
「あんた、人間と関わったことないわよね」
「それでも黒王様を傷つけた人間は嫌いだ」
〝黒王を傷つけた人間〟というのが、誰を指しているのか分かり、若葉は顔を曇らせた。
今、若葉は黒王の三つ、灰墨の七つ年上の二十六で、先代の花御寮のことも知っている。当然、彼女が黒王にどのようなことをしてきたのかも。
「その方と……今の花御寮様は別よ、一緒にするものじゃないわ。それに黒王様が受け入れられるのなら、近侍であるあんたも受け入れないさいよ」
灰墨も若葉の言っていることは分かっているのだろう。しかし、納得はしたくないようで、ずっと足元を見てむくれていた。
これ以上言ったところで仕方ないか、と若葉は肩をすくめると、暗くなってしまった場の空気を和ませるように一際明るい声を出す。
「それで、わたくしに何か用なの? ただ呼び止めたわけじゃないでしょう?」
「婚儀の日取りが出たらしい。正式な決定はもう少し先だろうけど」
「まあっ!」と若葉は喜びを表すように手を叩いて、喜色を全身にみなぎらせた。
「これでやっと、花御寮様と黒王様は本当のご夫婦になられるのね!」
嬉しさのあまり、若葉は灰墨に抱きついてぴょこぴょこと跳ねる。
「うわっ!? 急に抱きつくなって、バカ葉!」
「はいはい、それよりも日取りはいつよ、いつ!」
「はっ、半月後だってよ! 次の満月の日! 黒王様には俺から伝えるからな!」
灰墨は若葉の肩を押してベリッと身体から引き離すと、ぶつぶつ恥じらいがどうのこうのと言いながら崩れた着物を整えていたが、一方の若葉は、東棟の奥――菊と黒王がいる部屋を、目尻をすぼめて嬉しそうな目で眺めていた。
「このままお二人には、どうか幸せになってほしいものだわ」
どーだかね、と拗ねたように言い放って、灰墨は再び烏姿になり母屋の方へと飛び去っていった。
4
書き取りをしていた菊の手が、ピタリと止まる。
「え、十日後……ですか……?」
昼下がりにやって来た黒王は、開口一番に婚儀の日取りが決まったと言った。
「ああ、満月の日だ。それで俺達は本物の夫婦になる」
「本物……」
たとえ正式な婚儀を行ったとしても、本物の夫婦になどなれないことは一番菊が知っている。元より花御寮自体がニセモノなのだから。
――それもだけど、つまり……。
止まったままの筆先からは墨がどんどんと滲み、紙に大きな黒いシミを作っていく。
「不安か?」
気付いた黒王が菊の右手を優しく開いて筆を抜き取り、筆置きへと置く。そのまま菊の手を見つめ、指の一本一本に自分の指を絡めていく。
あの日から、黒王は菊を訪ねると、必ず手を重ねるようになっていた。
外の桜を眺めながらただ重ねている時もあれば、こうして手遊びのようにして指を絡めてくる時もある。
絡められる指や触れる肌はいつもとても温かで、結ばれている間、彼は穏やかな顔をするようになっていたのだが、今、菊の手を見つめ「不安か」と聞いてくる彼の眼差しの方が、どこか不安げに見えた。
彼は時折こうして寂しそうな目をすることがある。普段は威厳をまとって他者を圧倒している彼が、不意に子供のように見えるのだ。
その理由は、未だ分からない。
彼が今まで語った中には、原因と言えるようなものは何もなかった。
菊は左手を彼の手にそっと重ね、首を横に振る。
「これでやっと花御寮としのお役目を果たせるのですから、何も不安なことはありませんよ」
「ただ、奏上を間違えないかは心配ですけど」と、おどけて言ってみせれば、黒王の目から不安の色が消える。
「そうだ、レイカ。婚儀の日取りも決まったことだし母屋を案内しよう。東棟に籠もりきりも身体に良くないだろう」
黒王は「若葉」と入り口の外に向かって声を飛ばす。
すると、「はい」という返事と共に入り口の戸が開き、跪いた若葉が姿を現した。
ここ最近、黒王が訪ねてくると若葉や女官達は席を外す、というのがお決まりのようになっていた。皆ニヤニヤしながら出て行くものだから、いつも残された方には妙な気恥ずかしさが漂うのだ。
「レイカをしばらく連れて行くぞ」
「はいはいそれはもう、どうぞ心ゆくまでご自由に楽しんでらしてください」
「……含みのある言い方だな」
「はてさて、何のことでしょう?」
じとっとした重たげな眼差しで黒王が若葉を見遣るも、若葉はどこ吹く風とほほほと笑うのみ。
そのちょっとしたやり取りを見ても、黒王が周囲からどれだけ慕われているのかが分かって、菊はいつも少しの羨ましく思ったりする。まだ、自分と黒王の間には
絡ませていたままの手を黒王が引いた。
「了解ももらったし行こうか、レイカ」
そうして、菊は黒王に手を引かれながら広間を後にした。
黒王の一歩後ろを、手を引かれながらついて歩く。
「広いとは思っていましたが、想像以上ですね」
菊はキョロキョロと視線を巡らしながら、はぁと感嘆の溜息を漏らす。
東棟から渡殿を渡った先が母屋なのだが、一直線に伸びた長い廊下に、傍らから見える屋根の数々。突き当たりで廊下が終わったと思えば、右に左にと曲がってまだ先まで続いてる。母屋の中にも渡殿や池泉があり、松や青紅葉、枝垂れ梅に椿と多くの植栽でにぎわっている。母屋だけで小さな村のようだった。
「迷子になってしまいそうです」
「俺と一緒にいれば良い」
「……はい」
手を握る黒王の力がほんのわずかだけ増し、菊は彼の背後で密かに頬を緩める。
言葉以外で伝えられる気持ちが面映ゆかった。
「あ、ちょうど良かった。黒王様ー!」
そこへ、黒王を呼び止める声が前の方から飛んできた。
廊下を走るぱたぱたとした足音と、間延びした朗らかな男の声が段々と近付いてくる。「黒王さ――」
しかし、菊が黒王の広い背中からひょこっと顔を覗かせれば、男の声がピタリと止まった。
菊の目に映ったのは、丸い目がどこか子犬を思わせる灰黒い髪をした青年。
彼は菊と目をが合うと、開いていた眉間にぎゅっと皺を寄せ、たちまち苦々しい表情となる。
「黒王様……そちらはもしかして……」
「俺の花御寮だ、灰墨」
灰墨と呼ばれた青年は「ども」と、一応という感じで会釈するが、菊が反応する前にはもう視線を切って黒王に話しかけていた。
――あら? これはもしかして……。
花御寮として嫁入ってから初めて向けられる感情。しかしそれは、菊には随分と馴染みのあるものでもある。
菊は二人の会話に耳を傾ける。
どうやら婚儀の話のようで、儀式の段取りや必要な道具などについて話し合われていた。その中で、菊が読む奏上文についての話が出る。
「では花御寮様が読まれる奏上文は、通常より平易なものを用意するということで……」
「申し訳ありません、お手間をかけてしまいまして」
いたたまれず、菊はつい謝罪の言葉を挟んだのだが。
「あなたのためじゃなく黒王様のためですから。あなたが失敗するのは勝手ですけど、黒王様にまで泥を塗られちゃ困るんで」
チラとも目を向けられず、まるで俎上の鯉を包丁で一刀両断するかのごとく、無感情に淡々と言葉を返されてしまった。
「灰墨」と黒王が彼をたしなめていたが、彼の眉間の間に走った川がいっそう深度を増しただけだ。
「はいはい、すみませんね! お忙しいところお邪魔しましたよ!」
「あ、おい、灰墨」
彼は黒王の声に振り返ることもなく、ドスドスと足音激しく廊下の奥へと姿を消した。
あっという間のことに、菊はきょとんとして黒王を見上げれば、視線に気付いた黒王も菊を見て片眉をへこませていた。
「すまない、レイカ。俺の乳兄弟で近侍の灰墨だ。普段はあんな感じではないんだが……少し、人間嫌いなところがあって……嫌な気分にさせただろう」
やはり、と菊は心の中で納得に頷いた。
彼が向けてきた視線は、村でよく受けてきたものと似た類いだった。しかしだからと言って、今更それで傷つくこともないが。
「好き嫌いは人それぞれですもの。どうかお気になさらず」
申し訳なさそうに肩を落とす黒王に、菊は気にしていないと笑って首を横に振った。
しかし、黒王の曇った表情は戻らない。
形の良い美しい眉は今、険しさに形を崩している。俯けられていた彼の顔は暗く、視線は菊ではなく足元に落とされていた。
「あいつの人間嫌いは俺が原因なんだ……」
「黒王様が?」
そういえば、彼も最近までは、わざと自分を遠ざけようとしていた節があった。
――今はもう、そんなことはないけど。
菊の左手は、部屋を出た時から一度も離されていない。
「場所を変えようか」
「え――きゃっ!?」
言うと同時に、黒王は菊を横抱きにして庭へと下りた。
◆
母屋の庭を経由して二人がたどり着いたのは、東棟の広間からいつも見えている桜の庭だった。
桜の花は五分を過ぎ、もう枝の茶色よりも薄紅色のほうが多くなっている。
樹齢どのくらいだろうか。庭にはたくさんの桜の木が植わっており、空の半分を淡くとも薄紅色に染めていた。
「こ、黒王様……おろしてください……ぃ……」
耳の先まで真っ赤にした菊は顔を手で覆い、黒王の腕の中で小さくなっていた。
東棟と違い母屋はさすがに人が多く、ここまで来るまでに、菊はいろいろな人に、「まあ」やら「おっ」やらと好奇の視線を向けられ、顔から火を噴きそうだったのだ。
「すまない。外に出る予定ではなかったから、レイカの履き物がなかったんだ。レイカの足を汚したくはなかったし」
かすれた小声で、菊は何度も下ろしてくれと請うているのだが、黒王は菊を抱く手の力を強めはしても緩めることはない。
正直、子供のように抱かれ、それを周囲に後期の眼差しで眺められ恥ずかしいのだ。
指の隙間から熱に潤んだ目を向ける。
「あの、重いですから……私の足など気にせず……」
「ははっ、これしき重いものか! レイカならあと三人でも抱えられるさ」
大きな口を開けて愉快そうに笑う黒王に、菊は目の前にパチパチと光りが走った気がした。
いつも彼に向けられる笑みは淡いもので、こんなに彼が大きな笑い声を上げているのは初めてだった。思わず、まじまじと彼の顔を眺めてしまう。
しかし、笑いを収めた彼が向ける顔は、どこか寂しさが漂っていた。
顔に陰が落ちているからだろうか、口元は淡い笑みをたたえているのに、目元は愁いが滲んでいる。
「黒王様……」と、自然と菊の手が彼の顔に伸びようとしたところで、パッと黒王の顔が遠くを向いた。
「だが、確かにこのまま話をするわけにもいかないな」
黒王は一際大きい桜の木の麓で、菊を抱えたまま腰を下ろした。
菊は横向きのまま、胡坐をかいた黒王の足の中にすっぽりと収まり、背中を黒王の手が優しく支える。
見上げれば彼と目が会い、ふっと目を細められた。
「……っ」
これは、好意を持ってくれていると思ってもいいのだろうか。少なくとも、当初より関係は良くなっているとは思うが。
どうにも、この丁寧な甘さにまだ慣れない。
「灰墨の人間嫌いは俺のせいなんだ。いや、元々の原因は俺の母親かな」
空を仰いでいた黒王が、ポツリ、とこぼした。
まるで、空に語りかけているような静かな声。
「そういえば、黒王様のお母様はどちらに? 一度ご挨拶をと思ったのですが」
黒王の父親は亡くなったと聞いた。だから代替わりで彼が新たな黒王となり、村では花御寮が選ばれたのだから。
――その花御寮はニセモノだけどね……。
しかし、黒王の母親である先代花御寮は本物だ。自分と違い、正体がばれて罰せられるということもないはずなのに、未だ姿が見えなかった。
「もしかして、ご病気などで……」
以前、それとなく若葉に聞いたのだが、微妙な顔で濁されてしまった。
上を向いていた黒王の顔が、ゆっくりと下へ――菊へと向けられる。
俯いた黒王の顔が暗く陰った気がしたのは、空から降りそそいだ陽光の影だけとは思えなかった。
「母は自ら命を絶ったよ」
「え」
予想しなかった言葉に、上手く返事を返せなかった。
「俺を産んだことを受け入れられず、少しずつ心を病んでいって……最期は物見の塔から身を投げて亡くなった。俺が七つの時だ。明け方に薄雪がつもった姿で発見された」
「どうして……」
「化け物だと」
黒王の顔は、薄く笑っているようにも、今にも泣き出しそうなものにも見えた。
「自分は腹から化け物を生んでしまったんだと」
菊は絶句した。
きっと思い返すのも辛かっただろうに、黒王はとつとつと語ってくれた。
幼い頃から、父親には花御寮の住まいである東棟への立ち入りを禁じられていたこと。五つの時に、禁を破って母親に会いに行って、湯飲みを投げられたこと。その際に飛んできた、聞いている菊のほうが耳を塞ぎたくなるような、ひどい言葉の数々。
それでも幼い黒王にとって、母親は母親だった。
「その一件で、父親や乳母には二度と会わないようにと言われたが、実はそれからも、目を盗んでは東棟に忍び込んでいたんだ。心が疲れているから、ああなっているだけだと言われていたからな。だったら、その疲れを癒やせたら、優しい母になってくれると信じて……」
はは、と黒王が笑った。
疲れたような、かすれた声で。
いつも大きく見える彼が、今はひどく小さく見える。自分の背を支える手が子供のもののように、弱々しいものに思えた。
彼の声からするに、おそらく彼の願いは叶わなかったのだろう。
そして、おとずれた母親の最期……。
彼の話を聞いて、菊は今までの彼の態度が全て腑に落ちた。
なぜ、自分に触れる黒王の手は温かいのに、瞳には温度がなかったのか。
なぜ、近寄ろうとした時、何度も何度も遠ざけるように脅してきたのか。
「すまない。せっかくの春日和なのに暗い話をしてしまったな」
「いいえ、話してくださって嬉しかったです」
「灰墨は俺より四つ下だから、もちろん俺の身に何があったのか覚えちゃいないが、色々と周囲から聞いたらしくてな。一緒に育った分、俺への思い入れも強くて……あいつの中では、俺の母親がそのまま人間の印象になってしまってるんだ。だからその、レイカ自身を嫌いというわけではなく……」
どうにか両者を傷つけないようにと、懸命に言葉を選ぶ黒王の姿に、菊は肩を揺らす。
「ふふ、とても兄思いの弟さんなんですね」
「ああっ、生意気で騒がしくて猪突猛進なやつだが、優しい弟なんだ」
何か思い出したのか、彼は肩をすくめて渋るように笑った。しかし、どこか無理して空気を明るくしようとしているのがうかがえた。
「……黒王様」
菊は黒王の頬に手を伸ばした。
不意にそうしたいと思ったのだ。
一瞬、彼は目を瞠ったが、菊の手が肌に触れるのを拒みはしなかった。瞼を閉じた黒王は、触れている菊の手に頬を擦り付けるように、ほんの少しだけ頭を揺らす。
『化け物』と、母親に拒絶された黒王。
『忌み子』と、村から弾かれた菊。
二人は思わぬところで同じ痛みを抱えていた。
誰かに不要と突きつけられる苦しさはよく分かる。
人数など関係ない。ひとりにでもそのような思いを向けられると、残りの者達からも同じように思われているのではと思ってしまうのだ。常に疑って、なぜどうして、とずっと頭を悩ませ続けなければならないのだ。
そうして、心だけがどんどん疲弊していく。
彼の手や触れ方が温かかったのは、きっとかつて彼が母親に向けていた優しさの欠片。
優しくしたいと思いつつも、また拒絶されたらという恐怖で、彼の言動はああもちぐはぐになっていたのだろう。
そよそよとした柔らかな春風が黒王の前髪を揺らすたび、彼の顔に落ちる影もゆらゆらと動いた。遠くでは、ヒバリが甲高い声でキュルキュルとさえずっている。東棟の女官だろうか、女達の楽しそうな声も聞こえる。
穏やかな時が流れていた。
不意に、菊はなぜ自分が今ここにいるのか、分かった気がした。
いっときはレイカのためだからと思っていたが、そうじゃない。
――私は、この人を温めるために花御寮になったのね。
母親に与えられなかった言葉を、眼差しを、温もりを、同じ花御寮という自分が与えるために身代わりになったのだ。
――それが、花御寮の私にできること……。
菊の手と黒王の頬の体温が馴染んで、触れ合った境界線が曖昧になり始めてようやく、黒王の瞼が上げられた。
菊の真っ黒な瞳と、黒王の深紫の瞳が、互いの姿を瞳の中に収める。
黒王が僅かに眉根を寄せた。
「……この瞳と髪の毛の色は、人間ではあり得ない色なのだろう? 母はこの色を気持ち悪い色だと言っていた」
「そんなこと思ったことありませんよ。言ったでしょう、とても綺麗な色だと」
「本当か? 俺はその言葉を信じていいのか?」
毎日手を重ねても言葉を交わしても、まだ不安そうにしているのは、それだけ彼にとって母親から受けた仕打ちが根深いということ。
菊は頬から手を離し、そのまま彼の顔の前で小指のみを立ててみせた。
「な、なんだ?」
「黒王様、お約束します。私は決して嘘を吐きません。約束を破った時は、針千本飲ますなりなんなり、どうぞお好きに」
「……レイカ……やはり俺はお前が良い……」
控えめに伸びてきた黒王の小指は、菊の小指に触れた途端、力強く絡みついた。くっついてしまって二度と離れないかのように強く、強く、けれど、痛くはない優しい力で。
嘘吐きの身でありながら、嘘を吐かないとは自分でも苦笑ものだったが、ちゃんと罰はうけるから許してほしい。
――どこまでいっても、私はニセモノでしかないから。
だから、せめて口から出す言葉だけは本当でありたかった。
あと、十日。
せめてその間だけでも、彼を温めていたい。