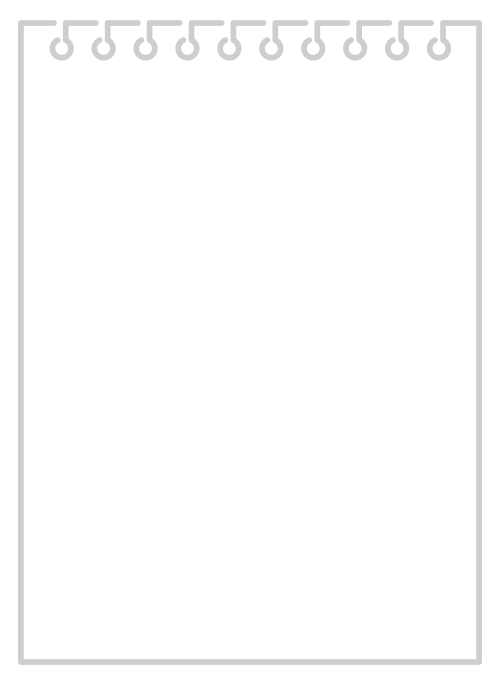「…までもうすぐだよ、今年もそんな季節だね」
ずっと、分かんなかった。どこまでもうすぐなのか。でも、思い出した。僕は。いや、僕と僕の家族は、祖父母の家に向かっていたんだ。夏休みが始まってすぐに行くという風物詩だった。その時、あぁ、そうだ。僕等は。
―事故にあった。
その後遺症で、僕はもうすぐ死ぬ。
医者には癌とか、言われてたけど。
思い出したくない記憶を、引き出さないためで。
「…私が…守るよ」
今僕がいるのは病院の屋上。目の前にいるのは―。
「お姉ちゃん―。」
僕の双子の姉だ―。
「葉月。」
「やっと思い出した。私、ずっと待ってた。でももう無理。」
「…え。」
「また家族になるのは無理。私には、感情がないから。それに、私。葉瑠真のこと、守りきれなかった。」
姉は、僕のために。僕を守るために、自分を犠牲にしてくれた。事故のショックで感情をなくした。そのせいで誰も好きになれない、何かあっても何も嬉しくない。僕はあの夏の日。
あの夏の日、僕が落としたもの。
落としただけじゃない。この手で、奪ってしまった。姉の、全てを。
生きる意味をくれた君は、かつて僕が生きる意味を奪ってしまった人―。
「ごめん…」
「葉瑠真…。ごめんね。守りきれなかった。私、私はこの先も生きれるのに、葉瑠真は―。」
そうだ。思い出した。
あの日のような、優しい声。
僕は本当は、長谷川春真なんかじゃない。長谷川は母方の祖父母の名字で、父方の祖父母の名字は吉川。そして僕は。
吉川 葉瑠真だ―。
僕らは双子で、8月に生まれた。先に生まれた姉。8月で、葉月。だから僕は春真じゃなくて、葉瑠真。ずっと一緒に、生きてきたんだ。だから、明るい黄緑色を大切なお守りのような存在にしていた。そうだ。あの病室。いつも飾ってある花は明るい黄緑色だった。姉も同じように、大切にしてくれていたのかもしれない。そして事故があったのは2年前の夏。中学生の夏。僕はその時の記憶全てを眠らせていた。覚えていなかった。でも、そうだ。全てが蘇る。眠っていた記憶、いや、眠らせておきたくてずっと閉ざしていたものが、開いていく。僕は普通の高校生じゃない。僕は姉の全てを奪った、最悪な弟。
「ごめん…葉月。」
その言葉が引き金だった。あれ以来、初めて。姉の頬に涙が伝った。
あの日のような、優しい涙。
相変わらず一点を見つめているし、笑わない。でもいつか、来るはず。僕がまた、姉と笑える日が。絶対、来る。そう信じて今、姉と夏の夜空を見上げている。そしてふと、姉が発した言葉が走馬灯のように蘇った。
『…まだいるよ。』
『…まだいるじゃん。』
姉は祖父以外にも自分がいることを伝えてくれたのかもしれない。姉は。こんな僕も家族として見てくれていたのかもしれない。もしもそうなら。もしもそうなら、この短い一夏の恋が実らなくても。僕は幸せ。
ごめんね、葉月。先に、両親のとこに行ってるね。僕の姉は、カッコいいでしょって、話してる。ずっと、待ってる。ゆっくりで良いから。家族で、待ってる。
―だから僕は、君を好きになれない。
ずっと、分かんなかった。どこまでもうすぐなのか。でも、思い出した。僕は。いや、僕と僕の家族は、祖父母の家に向かっていたんだ。夏休みが始まってすぐに行くという風物詩だった。その時、あぁ、そうだ。僕等は。
―事故にあった。
その後遺症で、僕はもうすぐ死ぬ。
医者には癌とか、言われてたけど。
思い出したくない記憶を、引き出さないためで。
「…私が…守るよ」
今僕がいるのは病院の屋上。目の前にいるのは―。
「お姉ちゃん―。」
僕の双子の姉だ―。
「葉月。」
「やっと思い出した。私、ずっと待ってた。でももう無理。」
「…え。」
「また家族になるのは無理。私には、感情がないから。それに、私。葉瑠真のこと、守りきれなかった。」
姉は、僕のために。僕を守るために、自分を犠牲にしてくれた。事故のショックで感情をなくした。そのせいで誰も好きになれない、何かあっても何も嬉しくない。僕はあの夏の日。
あの夏の日、僕が落としたもの。
落としただけじゃない。この手で、奪ってしまった。姉の、全てを。
生きる意味をくれた君は、かつて僕が生きる意味を奪ってしまった人―。
「ごめん…」
「葉瑠真…。ごめんね。守りきれなかった。私、私はこの先も生きれるのに、葉瑠真は―。」
そうだ。思い出した。
あの日のような、優しい声。
僕は本当は、長谷川春真なんかじゃない。長谷川は母方の祖父母の名字で、父方の祖父母の名字は吉川。そして僕は。
吉川 葉瑠真だ―。
僕らは双子で、8月に生まれた。先に生まれた姉。8月で、葉月。だから僕は春真じゃなくて、葉瑠真。ずっと一緒に、生きてきたんだ。だから、明るい黄緑色を大切なお守りのような存在にしていた。そうだ。あの病室。いつも飾ってある花は明るい黄緑色だった。姉も同じように、大切にしてくれていたのかもしれない。そして事故があったのは2年前の夏。中学生の夏。僕はその時の記憶全てを眠らせていた。覚えていなかった。でも、そうだ。全てが蘇る。眠っていた記憶、いや、眠らせておきたくてずっと閉ざしていたものが、開いていく。僕は普通の高校生じゃない。僕は姉の全てを奪った、最悪な弟。
「ごめん…葉月。」
その言葉が引き金だった。あれ以来、初めて。姉の頬に涙が伝った。
あの日のような、優しい涙。
相変わらず一点を見つめているし、笑わない。でもいつか、来るはず。僕がまた、姉と笑える日が。絶対、来る。そう信じて今、姉と夏の夜空を見上げている。そしてふと、姉が発した言葉が走馬灯のように蘇った。
『…まだいるよ。』
『…まだいるじゃん。』
姉は祖父以外にも自分がいることを伝えてくれたのかもしれない。姉は。こんな僕も家族として見てくれていたのかもしれない。もしもそうなら。もしもそうなら、この短い一夏の恋が実らなくても。僕は幸せ。
ごめんね、葉月。先に、両親のとこに行ってるね。僕の姉は、カッコいいでしょって、話してる。ずっと、待ってる。ゆっくりで良いから。家族で、待ってる。
―だから僕は、君を好きになれない。