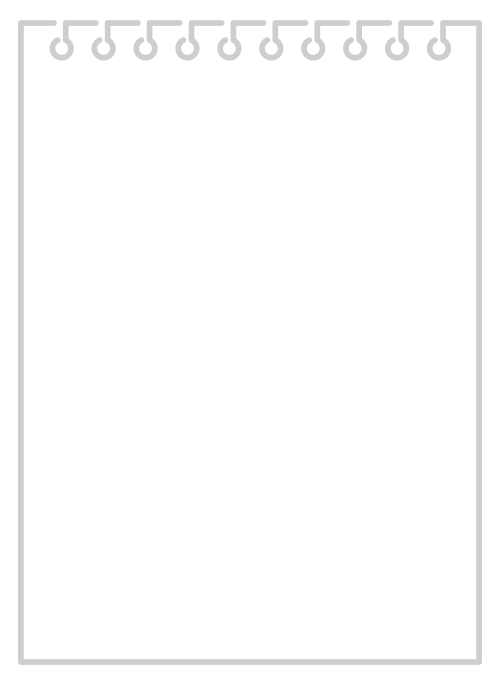それから僕は、夜の屋上で彼女に話を聞いてもらうようになった。なんとなく彼女といるとすべてをさらけ出してしまう。隣りにいるだけで、安心する。なんの同情もなく、ただ聞いてくれる感じ。それでも良かった。僕から何でも奪うこの世界。僕の命すら奪うこの世界で、彼女の存在はすごく心の支えとなっていった。
「あの…吉川さん。高校…いつから行ってないんですか。」
「覚えてない。」
「そっか。」
「…君は。」
「え」
「高校、行ってんの。」
「一応、行ってます。でももうすぐお葬式なんで休みますし、もうすぐ退学しちゃいますけど。」
「ん。」
こっそり家を抜け出し、病院に来る。これが日課となった僕は、彼女に会うのが楽しみになった。だからたぶん、この時から。
僕は君に、恋をした。
でも、知らない。僕が君のこと、好きになっちゃいけない。
それを僕は、知らない―。
「春真は1人じゃないよ。」
それがおばあちゃんの口癖で、ハンカチや名前の刺繍は明るい黄緑色でしてくれた。何故かこそわからないけど、それが内気な性格の僕の支えになっていた。だから少しの勇気はあったし、頑張ったことだってある。だからおばあちゃん。おばあちゃんがいないと僕、生きていけないと思った。でも、彼女が聞いてくれる。苦しいけど、苦しいままじゃなくて、言わせてくれる。苦しみが溢れてるこの世に対する文句を、言わせてくれる。だから僕、生きてる。今日のお葬式だって、もちろん涙が溢れた。でも、前の僕なら生きる意味も見失って、あと少しだけでも生き続けれなかったかもしれない。だから、生きる意味をくれた彼女を僕は、好きになったんだと思う。僕は、1人じゃない。それだけを胸に、感情がない彼女へ届く言葉を必死に探している。感情がない彼女に、この僕の気持ちを伝えられるように。おばあちゃん、見てて。僕は、1人じゃないから。
「今日、お葬式だったんだ。」
「ん。」
いつものように夜の屋上で淡々と聞いてくれる彼女。
「祖母がいなくなっちゃって、気づいた。君がいてくれるから、この先も、この夏を生きていける。だから、君が大切で…これからも、ずっと一緒にいたいと思えた。君のこと…好きなんだ。」
「君は私のこと好きになっちゃ駄目だよ。」
「…え。」
「恋しちゃ、駄目。」
簡単には受け入れられない、言葉。何も言えずただ空を見上げる。
「なんで私が葉月なのか知ってる…?」
「…何のこと?」
「8月に生まれたから葉月。君も8月だよね、誕生石、橄欖石でしょ。」
理由もわからないことをただただ続ける彼女。いつものように無表情だけど、どこか悲しそうで、切ない表情を浮かべている気がした。
「橄欖石って、明るい黄緑色。覚えてないか、葉瑠真。」
そこからの言動は理解できなくて、何度も彼女の言葉を脳裏で繰り返した。
「君は、春真じゃない。春っていう字じゃない。葉瑠真。私と同じ、8月に生まれた。君は私のことを好きになっちゃ駄目。だって。」
「君と私は、家族だから―。」
「あの…吉川さん。高校…いつから行ってないんですか。」
「覚えてない。」
「そっか。」
「…君は。」
「え」
「高校、行ってんの。」
「一応、行ってます。でももうすぐお葬式なんで休みますし、もうすぐ退学しちゃいますけど。」
「ん。」
こっそり家を抜け出し、病院に来る。これが日課となった僕は、彼女に会うのが楽しみになった。だからたぶん、この時から。
僕は君に、恋をした。
でも、知らない。僕が君のこと、好きになっちゃいけない。
それを僕は、知らない―。
「春真は1人じゃないよ。」
それがおばあちゃんの口癖で、ハンカチや名前の刺繍は明るい黄緑色でしてくれた。何故かこそわからないけど、それが内気な性格の僕の支えになっていた。だから少しの勇気はあったし、頑張ったことだってある。だからおばあちゃん。おばあちゃんがいないと僕、生きていけないと思った。でも、彼女が聞いてくれる。苦しいけど、苦しいままじゃなくて、言わせてくれる。苦しみが溢れてるこの世に対する文句を、言わせてくれる。だから僕、生きてる。今日のお葬式だって、もちろん涙が溢れた。でも、前の僕なら生きる意味も見失って、あと少しだけでも生き続けれなかったかもしれない。だから、生きる意味をくれた彼女を僕は、好きになったんだと思う。僕は、1人じゃない。それだけを胸に、感情がない彼女へ届く言葉を必死に探している。感情がない彼女に、この僕の気持ちを伝えられるように。おばあちゃん、見てて。僕は、1人じゃないから。
「今日、お葬式だったんだ。」
「ん。」
いつものように夜の屋上で淡々と聞いてくれる彼女。
「祖母がいなくなっちゃって、気づいた。君がいてくれるから、この先も、この夏を生きていける。だから、君が大切で…これからも、ずっと一緒にいたいと思えた。君のこと…好きなんだ。」
「君は私のこと好きになっちゃ駄目だよ。」
「…え。」
「恋しちゃ、駄目。」
簡単には受け入れられない、言葉。何も言えずただ空を見上げる。
「なんで私が葉月なのか知ってる…?」
「…何のこと?」
「8月に生まれたから葉月。君も8月だよね、誕生石、橄欖石でしょ。」
理由もわからないことをただただ続ける彼女。いつものように無表情だけど、どこか悲しそうで、切ない表情を浮かべている気がした。
「橄欖石って、明るい黄緑色。覚えてないか、葉瑠真。」
そこからの言動は理解できなくて、何度も彼女の言葉を脳裏で繰り返した。
「君は、春真じゃない。春っていう字じゃない。葉瑠真。私と同じ、8月に生まれた。君は私のことを好きになっちゃ駄目。だって。」
「君と私は、家族だから―。」