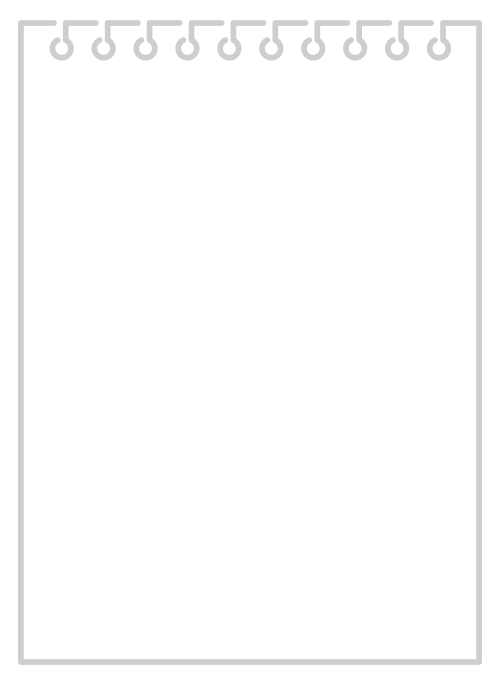「え。誰。」
「あえっと、すいません。同じ高校の長谷川春真です」
「…何の用。」
さっきまで綺麗だと感じた瞳は光を失っていた。なにも答えられず立ちすくんでいた時、看護師がやってきた。看護師というより、医師。
「吉川さん、大丈夫だよ。すみません、面会時間が過ぎてしまうので…。」
「あ。すいません。」
気がつけば祖母の命日の暑い夏の1日も終わろうとしていた。不思議な空気を纏った彼女。僕の心に、強く残った。でも、気づかなかった。彼女には、そんなものがないなんて。気がつくのはたぶん、もう少し先―。
病院の屋上。もうすぐ祖母の命日が終わる。そして僕の死ぬ日が近づく。家族が祖父の1人だけになってしまった苦しみを紛らわそうと夜風に吹かれる。その時、声をかけられた。
「さっきの人。」
振り向くと僕の目を見つめる、車椅子の彼女がいた。吉川葉月。
「どうも。」
それしか言えなくて、すこし顔が赤くなってしまった気がする。
「君、苦しいんだ。」
心を見透かす力があるのか分からない。でも自然と僕の口を開く力はあるんだろう。
「祖母が、死んじゃいました。2人しかいない家族だったから、苦しくて、苦しくて、耐えられません。それに。」
「…まだいるよ。」
「祖父しかいません。」
「まだいるじゃん。」
素っ気なく言う彼女。彼女はまた口を開いた。
「私には苦しいとかない。」
「…なんで…?」
「感情ないから。」
誰も何も言わず、ただ夏の夜空を見上げる。
「感情、どっかやっちゃった。」
納得した。彼女は、笑わなかった。看護師というより、医師が来た。感情が、ない。そうなんだ。感情が、ないんだ。信じられないほどの、真実。
「君も私も大変なんだ。…それに、何。」
相変わらず彼女は少しも笑わず、空を見上げたままそう言った。
「…僕、この夏生きたら、死んじゃうから。」
「あえっと、すいません。同じ高校の長谷川春真です」
「…何の用。」
さっきまで綺麗だと感じた瞳は光を失っていた。なにも答えられず立ちすくんでいた時、看護師がやってきた。看護師というより、医師。
「吉川さん、大丈夫だよ。すみません、面会時間が過ぎてしまうので…。」
「あ。すいません。」
気がつけば祖母の命日の暑い夏の1日も終わろうとしていた。不思議な空気を纏った彼女。僕の心に、強く残った。でも、気づかなかった。彼女には、そんなものがないなんて。気がつくのはたぶん、もう少し先―。
病院の屋上。もうすぐ祖母の命日が終わる。そして僕の死ぬ日が近づく。家族が祖父の1人だけになってしまった苦しみを紛らわそうと夜風に吹かれる。その時、声をかけられた。
「さっきの人。」
振り向くと僕の目を見つめる、車椅子の彼女がいた。吉川葉月。
「どうも。」
それしか言えなくて、すこし顔が赤くなってしまった気がする。
「君、苦しいんだ。」
心を見透かす力があるのか分からない。でも自然と僕の口を開く力はあるんだろう。
「祖母が、死んじゃいました。2人しかいない家族だったから、苦しくて、苦しくて、耐えられません。それに。」
「…まだいるよ。」
「祖父しかいません。」
「まだいるじゃん。」
素っ気なく言う彼女。彼女はまた口を開いた。
「私には苦しいとかない。」
「…なんで…?」
「感情ないから。」
誰も何も言わず、ただ夏の夜空を見上げる。
「感情、どっかやっちゃった。」
納得した。彼女は、笑わなかった。看護師というより、医師が来た。感情が、ない。そうなんだ。感情が、ないんだ。信じられないほどの、真実。
「君も私も大変なんだ。…それに、何。」
相変わらず彼女は少しも笑わず、空を見上げたままそう言った。
「…僕、この夏生きたら、死んじゃうから。」