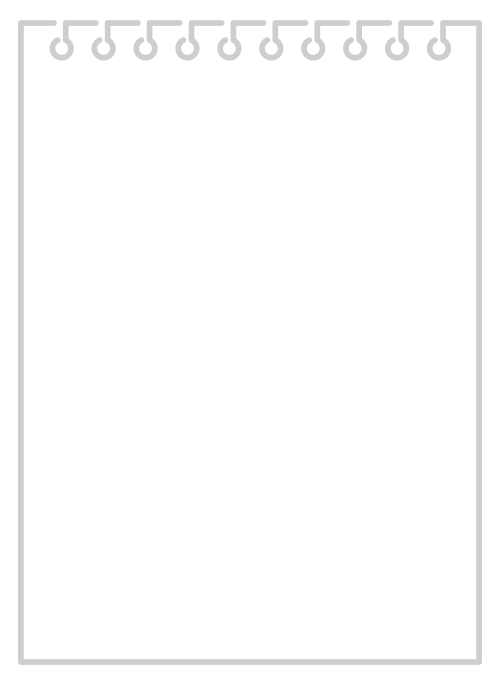僕に親はいない。幼い頃に事故で死んだらしい。思い出せないし、思い出したところで僕にプラスにはたらくことはないだろう。だから、もういい。母方の祖父母に預かられてもう10年を超える。慣れたものだ。平凡な田舎町の、平凡な高校に通っている。至って普通。それで良いし、それが良い。そんな男子高校生の僕。普通のはずの僕。長谷川 春真だ。でも、1つ普通じゃないことは。自分の命が尽きる時間が、わかってるってこと。余命、あとこの夏だけ―。
車なんて通らない、軽トラックしか通らない田舎道を何人もの高校生が同じ方向へ歩いていく。淡々と、淡々と。そのうちの1人の僕もまた、淡々と歩いていた。僕には親もいなければ、友達もいない。友達なんていらない。お父さんがなんの仕事をしているとか、お弁当にお母さんの得意料理が入っているとか、全部苦しいから。いらないから。だから誰にも声をかけられず、なんなら視界にも入れられず高校生活を送っている。でも僕にだって耳はあるから、聞こうとしなくてもある程度の情報は入ってきてしまう。誰と誰が付き合っているだとか、今の流行りは何だとか。そうだな、あと、入院生活をずっと続けている女子生徒がいるとか。あくまで噂にすぎないけど、名前は、吉川 葉月みたいな感じ。事故にあったらしい。詳細は僕にもわからない。
やっと高校の門が見えてきたところで、僕のスマホがけたたましい電子音を響かせて震えだした。
「大変だよ、春真。おばあちゃんが倒れちゃって…」
そこからはなんて言われたか覚えていない。おじいちゃんの一言目を聞いてからすぐ、病院へ走り出したから。でも、なんだろう。こういう時ってなんとなく着信音の時から勘づいてしまう。別に勘づきたくないのに。人ってそういうものだ。僕はたぶん、なんとなく察してしまったんだろう。
―おばあちゃんが、死んじゃうってこと。
小さい時から親がいないから、おばあちゃんの作る料理は格別。たぶん世界で1番美味しい。たぶんじゃない、絶対。でも、夏の初め。おばあちゃんは死んじゃった。だから、神様を妬んだ。そんなに僕を苦しめたい?じゃあ期待に応えてあと少しの命だが自殺してやろうかと思うほど。苦しんでいるところを、思う存分見せてやろうかと。でも僕は弱虫で弱虫で仕方がないほどだから、そんな対抗すらできない。この世の人間はみんな口を揃えて言った。可哀想な運命。運命って言った。しょうがないよって。そうだね。仕方がないのは知っている。でも駄目だった。僕は医師に祖母の死を告げられた時、狂ったように泣きじゃくった。たぶん、狂ったんだと思う。それからもう水分が抜けてしまって、泣きたくても泣けなくなったから落ち着こうと病院内を歩いていた時、見つけてしまった。入院患者が書いてある扉の前で。
吉川葉月の文字を。
好奇心とか、そういうのじゃない。たぶん、勘づいた。っていう表現が妥当かな。吸い込まれるように病室に入ってしまった。そこには1つのベッド。黄緑色の綺麗な花束。黒い髪を腰ほどまで伸ばした人。どこか一点を見つめている。一目見ただけだし、今までにそういうことがあったわけじゃないけど、吸い込まれる。そんな瞳だった。
車なんて通らない、軽トラックしか通らない田舎道を何人もの高校生が同じ方向へ歩いていく。淡々と、淡々と。そのうちの1人の僕もまた、淡々と歩いていた。僕には親もいなければ、友達もいない。友達なんていらない。お父さんがなんの仕事をしているとか、お弁当にお母さんの得意料理が入っているとか、全部苦しいから。いらないから。だから誰にも声をかけられず、なんなら視界にも入れられず高校生活を送っている。でも僕にだって耳はあるから、聞こうとしなくてもある程度の情報は入ってきてしまう。誰と誰が付き合っているだとか、今の流行りは何だとか。そうだな、あと、入院生活をずっと続けている女子生徒がいるとか。あくまで噂にすぎないけど、名前は、吉川 葉月みたいな感じ。事故にあったらしい。詳細は僕にもわからない。
やっと高校の門が見えてきたところで、僕のスマホがけたたましい電子音を響かせて震えだした。
「大変だよ、春真。おばあちゃんが倒れちゃって…」
そこからはなんて言われたか覚えていない。おじいちゃんの一言目を聞いてからすぐ、病院へ走り出したから。でも、なんだろう。こういう時ってなんとなく着信音の時から勘づいてしまう。別に勘づきたくないのに。人ってそういうものだ。僕はたぶん、なんとなく察してしまったんだろう。
―おばあちゃんが、死んじゃうってこと。
小さい時から親がいないから、おばあちゃんの作る料理は格別。たぶん世界で1番美味しい。たぶんじゃない、絶対。でも、夏の初め。おばあちゃんは死んじゃった。だから、神様を妬んだ。そんなに僕を苦しめたい?じゃあ期待に応えてあと少しの命だが自殺してやろうかと思うほど。苦しんでいるところを、思う存分見せてやろうかと。でも僕は弱虫で弱虫で仕方がないほどだから、そんな対抗すらできない。この世の人間はみんな口を揃えて言った。可哀想な運命。運命って言った。しょうがないよって。そうだね。仕方がないのは知っている。でも駄目だった。僕は医師に祖母の死を告げられた時、狂ったように泣きじゃくった。たぶん、狂ったんだと思う。それからもう水分が抜けてしまって、泣きたくても泣けなくなったから落ち着こうと病院内を歩いていた時、見つけてしまった。入院患者が書いてある扉の前で。
吉川葉月の文字を。
好奇心とか、そういうのじゃない。たぶん、勘づいた。っていう表現が妥当かな。吸い込まれるように病室に入ってしまった。そこには1つのベッド。黄緑色の綺麗な花束。黒い髪を腰ほどまで伸ばした人。どこか一点を見つめている。一目見ただけだし、今までにそういうことがあったわけじゃないけど、吸い込まれる。そんな瞳だった。