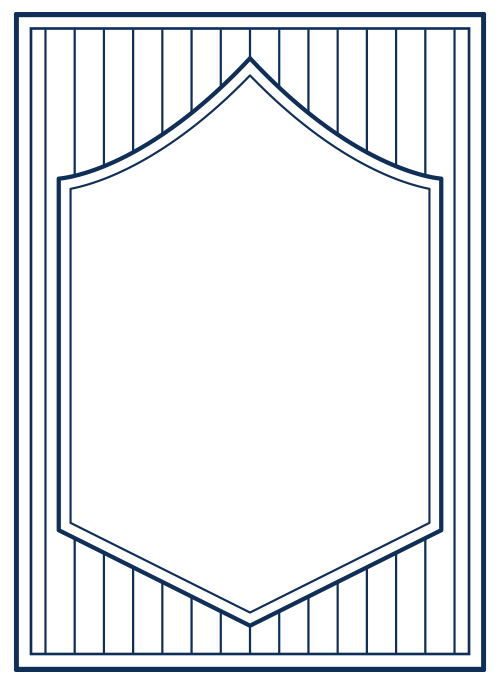如月六花が中学校から下校している時、不意に悪寒が走った。
振り返ると身の丈三メートルは有りそうな大きな鬼が立っていた。
巨大な体躯。赤い肌にボサボサの髪から突き出している二本の角。口から垂れている赤黒い液体。
鬼の手に握られてる物が何なのかは脳が考えるのを拒否していたる。
六花は思わず立ちすくんだ。
大鬼が六花の方に向かってくる。
捕まる!
そう思った瞬間、鬼の目に矢が突き立った。
鬼が叫び声を上げる。
六花が目を見張った。
そこに日本刀を持った少年が駆け寄る。
鬼が腕を振り上げた時、再度鬼に矢が突き立つ。
矢に気を取られた鬼に少年が刀を一閃させると鬼は絶叫を上げて跡形もなく消えた。
矢を放ったのは卜部季武、日本刀の少年は碓井貞光だった。
鬼から助けてもらった事が切っ掛けで六花は頼光四天王と知り合った。
〝異界〟
人間の世界より少し上の次元にある世界。
次元の違う世界なので本来は往き来出来ない。
それぞれの世界は壁に包まれているからだ。
だが人間は〝旨い〟と聞き付けた異界の者達の中に壁の裂け目を通って人間を喰いに来る者が現れた。
そこで異界の支配者達は人間界にやってくる異界の者を討伐する役目の者――討伐員――を人間界に派遣していた。
その討伐員の指揮を執っている者の一人が平安時代に源頼光である。
頼光自身は普段異界にいて部下達に指示を送っている。
その部下達というのが頼光四天王の〝渡辺綱〟、〝碓井貞光〟、〝坂田金時〟、〝卜部季武〟である。
異界の者には寿命がないので討伐員は昔から人間界に常駐していて今もいるとの事だった。
年を取って死ぬことがないため、周囲の人間達に怪しまれないように定期的に移動しているそうだ。
「ケーキ? クリスマスの?」
「うん、皆の好みを教えてもらえれば作るよ」
十二月の半ば、六花が季武に言った。
「時間は大丈夫なのか?」
季武が訊ねた。
六花は中学三年生で高校受験を控えている。
「ケーキはそんなに時間掛からないよ」
季武は六花の言葉に頷いた。
「てことで、料理作ってもらってるお礼に昔の話するね」
マンションの台所で綱が言った。
六花は昔話が好きで頼光や頼光四天王の名前も彼らと知り合う前から名前を知っていた。
頼光と頼光四天王は六花にとって伝説の英雄でありアイドルだ。
昔の話をすると六花が喜ぶからとケーキを作る合間に話してくれることになった。
平安時代、頼光は源満仲に暗示を掛けて長男だと思わせ貴族として生活していた。
綱も源宛の遺児だと思わせて源敦の養子になった。
季武、貞光、金時は郎等なので誰かの子供の振りはしなかったらしい。
綱も最初は郎等の一人だったのだが頼光が官職で忙しくなったため、もう一人貴族が必要になったので頼光の妹婿の源敦の養子になるために宛の遺児だと思わせたそうだ。
『今昔物語集』「頼光の郎等、平季武、産女に値う語」
頼光が美濃に赴任した時のある夜、季武は侍部屋で他の郎等達と宿直をしていた。
いつものように郎等達が雑談をしているうちに誰かが、
「そこの川に夜な夜な産女という妖怪が出るらしい。誰か行ってみないか」
と言い出した。
皆、
「お前行けよ」
「そういうお前こそ」
と言い合っていて誰も行くとは言わなかった。
その時、
「六郎、お前はどうだ?」
と誰かが季武に水を向けた。
六郎というのは季武の通称である。
「流石の六郎でも無理だろ」
他の者が言った。
「下らん。行って帰ってくるだけなら誰にでも出来るだろ」
季武が答えた。
「なら行ってみろよ」
「そうだ、行ってみせろ。行けると言うだけならそれこそ誰にでも出来るからな」
「なら賭けるか? 俺が行って来られるかどうかで」
「良いだろう。儂は六郎が行かれない方にこれを賭ける」
一人がそう言って太刀を出すと他の者達も次々と高価な物を賭けると言って出してきた。
どうせ行かれないだろうと高を括っているのだ。
調子に乗った郎等達が季武の前に様々な物を積み上げる。
「後悔するなよ」
季武はそう言って立ち上がった。
「ホントに行ったかどうかどうやって証明するんだ?」
誰かの言葉に季武は胡簶を手に取った。
胡簶というのは腰に付けて矢を入れておく物である。
季武は胡簶を腰に付けて矢を郎等達に見せた。
矢はそれぞれに特徴があるので誤魔化しが利かないのだ。
「この矢を対岸の地面に刺してくるから明日の朝にでも見にいって確かめてみろ」
季武はそう言うと部屋を出た。
真夜中に意味もなく川を渡る羽目になるとは……。
しかも渡ったあと戻ってこなければならないのだ。
売り言葉に買い言葉で部屋を出てきたもののすぐに後悔した。
無駄骨折りにも程がある。
せめて女が喜びそうな物でもあれば恋人への贈り物に出来るのに、賭の品として出されたのは太刀だの鎧だの兜だの、武士しか使わないような物しかなかった。
馬鹿馬鹿しいと思いながら馬に乗ると川に向かった。
川を渡って対岸に矢を立てるとまた川を渡って戻り始めた。
不意に川の途中で生臭い臭いが辺りに充満したかと思うと、
「これを抱け」
と言う女の声と赤ん坊の泣き声が聞こえてきた。
いつの間にか季武の側に女が来ていた。
女が泣いている赤ん坊を差し出してくる。
「貸せ」
季武が無表情のまま手を出すと女が赤ん坊を渡してきた。
赤ん坊を受け取った季武はそのまま川を進み始める。
「子供を返しておくれ」
と女が言うが季武は無視して川を渡る。
女が「子供を返せ」と言いながら追い縋ってくるが季武は無視した。
季武は赤ん坊を抱えて邸に帰った。
「ほら、産女から赤ん坊をとってきたぞ」
と季武が腕を開くと数枚の葉が下に落ちた。
そこへ季武の後を尾けていた男達が帰ってきて季武が間違いなく川を渡って産女から赤ん坊を受け取ったと証言した。
男達は顔を見合わせると渋々賭の品を差し出した。
季武は賭の品を総取りした。
「え!? 受け取ったの!?」
六花が驚いて声を上げた。
『今昔物語集』では受け取らなかったから賞賛されたと書いてあったのだが。
「夜中に川を渡ったんだぞ。当然の報酬だろ」
「ま、まぁ、そうだね……」
武勇伝と言えば武勇伝なんだろうけど……。
いくら相手が妖怪とは言え子供を誘拐……。
「季武って敵には容赦ねぇもんなぁ」
「人間にも優しくはねぇだろ」
金時と貞光が小声で囁きあっていた。
『赤染衛門集』
「美濃守殿、お世話になりました」
大江匡衡は頼光にそう礼を言うと妻の赤染衛門を伴って旅立っていった。
頼光が美濃守になったのと時を同じくして、大江匡衡は尾張守に任ぜられたのである。
匡衡は妻と共に赴任先の尾張に向かう途中で美濃にある頼光の邸に立ち寄ったのだ。
二人の赴任が決まって酒宴を催した後、匡衡が礼の文を送ってきたので、尾張に行くなら邸に寄ってくれと返事を出していた。
それで匡衡は妻の赤染衛門と共に訊ねてきたのである。
「殿」
匡衡を見送った頼光が邸に戻ると使用人がやってきた。
使用人に呼ばれて後に随いていくと大江夫妻が泊まった部屋の壁に、
草枕 露をだにこそ 思ひしか
誰がふるやとぞ 雨もとまらぬ
と書いてある。
「何か至らないところでもあったのでしょうか」
使用人が恐る恐る訊ねてくる。
「ここじゃなくて途中の宿だ」
頼光が安心させるように言った。
歌の内容は、
「夜露に濡れることを心配していたが露どころではない。雨漏りでびしょ濡れだ」
という愚痴だ。
この邸は雨漏りなどしないし何より匡衡達の滞在中、雨は降っていない。
歌を詠んだ時、手元に紙がなかったので最初に見付けた書けそうな所(頼光の邸の壁)に書いたのだろう。
「人の家の壁に……」
愚痴の落書きってなんの嫌がらせ?
六花はドン引きしたが、頼光によると当時、紙は貴重品で中々手に入らなかったそうだ。
そのため公文書以外はそうそう書くことが出来なかった。
だから人の家の壁などに書くことはよくあったとのことだった。
「そ、そうなんですか……」
そういえば勅撰和歌集に載っている頼光の歌のうちの一つは妻との連歌だ。
『金葉集』
頼光が赴任先から帰京する途中、朝、使用人が蔀を開けると目の前の川を舟が下ってくるのが見えた。
舟には何かが積まれている。
「あれは?」
「蓼という植物を刈ったものを運んでいるそうです」
頼光の問いに供の侍が答えた。
「たでかる舟のすぐるなりけり」
頼光がそう呟くと、側にいた妻が、
「朝まだき から櫓の音の 聞こゆるは」
と答えた。
頼光の呟きが下の句のようだったから妻が和歌になるように上の句を詠んだのである。
下の句(七七)みたいだからって奥さんまで歌を詠んじゃうなんて……。
和歌で日常会話をしていたのかと思えるレベルだ。
『源平盛衰記』「剣巻」
綱が頼光の使いで夜道を馬に乗って邸に戻る途中、一条堀川の戻り橋のたもとで、
「あの……」
女性の声に振り向くと、二十歳くらいの女性が供を連れず一人でいる。
おっ、綺麗な女性……。
「どうしました?」
綱が立ち止まって愛想良く訊ねると、
「五條渡に帰る途中で夜が更けてしまい怖くて……。送っていただけませんか?」
と女性が答えた。
綱はすぐに馬から下りて女性の側へ行くと、
「お安い御用です。どうぞ馬に乗ってください」
と女性を馬に乗せた。
そして自分も騎乗すると馬を五條渡に向けた。
歩き出してしばらくすると、
「あの……実は家は五條渡ではなく都の外なのですが……」
と女性が言った。
「構いませんよ。お送りします」
綱がにこやかに答えると、
「では愛宕山まで行こうか」
女性は突然鬼の姿になると綱の髻を掴んで飛び立った。
「あ~、やっぱなぁ……」
綱は溜息を吐くと太刀を抜いて鬼に斬り付けた。
鬼の腕が切れ、綱は鬼の手ごと下に落ちた。
綱が落下したのは北野神社の回廊の屋根の上だった。
屋根から飛び降り、まだ髻に付いている鬼の腕を外すと懐にしまって頼光の邸に帰った。
邸で頼光に戻ったことを報告すると、
「何があった」
と訊ねられた。
「あ、お気付きになられましたか。実は――」
綱は鬼の腕を取り出しながら事情を話した。
「いや~、鬼の気配に気付くとはさすが頼光様」
「馬鹿者! お前の髻が乱れていたから女のところにでもよってきたのかと思ったら!」
頼光が綱を一喝した。
「げっ! 藪蛇……」
綱は慌てて口を噤んだが遅かった。
「仕方ない、誰か播磨守を呼んでこい」
頼光がそう言うと使いの者が出ていった。
播磨守というのは安倍晴明のことである。
晴明はすぐにやってきた。
「どうしたらいいと思う?」
頼光がそう訊ねると、
「鬼の腕を封印し、綱殿は七日間の物忌みを」
と晴明が答えた。
「と言うことだから綱は宿所で謹慎だ」
と頼光が言い渡した。
がっちりと叱りつけた後で。
綱が宿所で物忌み――という名の謹慎をしていると、従者に綱を訪ねてきた者がいると告げられた。
「誰だ」
綱が門の近くで誰何すると、
「私よ」
という妻――の一人――の声がした。
「物忌みだと言ったはずだ」
「謹慎でしょ」
「ぐっ……」
「一人じゃつまらないだろうと思ってきてあげたのよ。二人だけで過ごす良い機会でしょ」
妻の言葉に綱は返事に詰まった。
綱には複数の妻がいるため必然的に一人一人の妻と過ごす時間が短い。
常々その事で嫌みを言われている。
追い返して機嫌を損ねたら家に入れてもらえなくなるかもしれない。
頼光のいる場所からは離れているし、妻と頼光が話す機会はない。
従者に口止めしておけば中に入れてもバレずにすむだろう。
綱は妻を中に入れた。
「それで、なんで謹慎になったの?」
「いや、物忌……」
「摂津守様の邸の女に手を出して怒らせたとかじゃないでしょうね」
「違うって」
綱は慌てて鬼の事を話した。
鬼が女性に化けていたことは伏せて。
「まぁ……では、ここに鬼の腕が? 見せて」
「いや、封印してあるから……」
「ホントに鬼に襲われたの? 本当は摂津守様の使用人に手を出して怒らせたんじゃないの?」
妻が疑わしそうな表情になった。
「嘘じゃないって!」
慌てて否定したが女に手を出した前科が(何度も)ある綱の言葉は信じてもらえそうにない。
押し問答の末、綱は仕方なく封印を解くと鬼の腕を妻の前に置いて見せた。
「まぁ、これは……正しく我の腕よ。返してもらうぞ」
妻に化けていた鬼は正体を現すと腕を掴んだ。
「貴様!」
綱が刀に手を伸ばしたが、その前に鬼は破風を蹴破ると空を飛んで行ってしまった。
平安時代版オレオレ詐欺……。
「普通、飛んでる時に斬んねぇだろ」
貞光が呆れたように言った。
「山まで行ったら帰るの大変じゃん。歩いて帰らないといけない時代だったんだぞ」
「愛宕山から堀川までなんて大した距離じゃないだろ。人間だって精々三時間半だぞ」
「神社の屋根壊してんじゃねぇよ」
「夜中に呼び出された播磨守も迷惑だったと思うぞ」
「しかも妻に化けた鬼にまた騙されて」
「あれで頼光様にこってり絞られたんだよな~」
綱が肩を落とした。
「自分が悪いんだろ!」
「なんで同じ鬼に二度も騙されるんだよ!」
「たった七日も一人で過ごせないのか!」
金時達が次々と突っ込む。
……あれ?
「声真似したのって義理のお母さんじゃ……」
「『平家物語』とかではそうなってるけどホントは妻だよ」
綱が言った。
そう言われてみれば義理の母が綱を騙して中に入れさせる時「生まれたばかりの頃から大切に育ててきたのに」と語ったと書いてあった。
だが綱は暗示で源宛の息子だと思い込ませただけだから赤ん坊の頃は無い。
だから、そんな話をするはずがないし、されたとしても引っ掛かる訳がない。
「えっと、その鬼って確か茨木童子ですよね」
「ああ、あれは宇治の橋姫だよ」
「茨木童子じゃないの? 大江山の仕返しに来たって……」
「それは別の話だ。綱を騙したのは宇治の橋姫だ」
「えっと……鬼が逃げたのは流石ですね」
苦し紛れの六花の言葉に、
「無理に擁護する必要ないぞ」
季武が言った。
確かにフォローのしようがないので六花は話題を変えることにした。
「播磨守って安倍晴明ですよね。そんなすごい人が夜中に来てくれたんですね」
「頼光様と播磨守の師匠が縁戚だったからな」
「え?」
「歌を詠んだ妻っていうのは賀茂忠行の孫娘なんだ」
賀茂忠行と言うのは晴明の師匠である。
その孫が産んだ娘――つまり忠行の曾孫――が相模という歌人として名高い女性である。
「へぇ。賀茂忠行って陰陽師だよね?」
「賀茂家も結構歌人を輩出してるんだ」
賀茂家〝も〟というのは頼光の子孫達も歌人として有名な者が多く歌人の家系だからである。
晴明の師匠は忠行ではなく忠行の長男の保憲という説もあるが、その保憲の娘も歌人として有名で『賀茂保憲女集』と言う歌集を出している。
相模の母の父は保憲の弟の慶滋保胤である。
振り返ると身の丈三メートルは有りそうな大きな鬼が立っていた。
巨大な体躯。赤い肌にボサボサの髪から突き出している二本の角。口から垂れている赤黒い液体。
鬼の手に握られてる物が何なのかは脳が考えるのを拒否していたる。
六花は思わず立ちすくんだ。
大鬼が六花の方に向かってくる。
捕まる!
そう思った瞬間、鬼の目に矢が突き立った。
鬼が叫び声を上げる。
六花が目を見張った。
そこに日本刀を持った少年が駆け寄る。
鬼が腕を振り上げた時、再度鬼に矢が突き立つ。
矢に気を取られた鬼に少年が刀を一閃させると鬼は絶叫を上げて跡形もなく消えた。
矢を放ったのは卜部季武、日本刀の少年は碓井貞光だった。
鬼から助けてもらった事が切っ掛けで六花は頼光四天王と知り合った。
〝異界〟
人間の世界より少し上の次元にある世界。
次元の違う世界なので本来は往き来出来ない。
それぞれの世界は壁に包まれているからだ。
だが人間は〝旨い〟と聞き付けた異界の者達の中に壁の裂け目を通って人間を喰いに来る者が現れた。
そこで異界の支配者達は人間界にやってくる異界の者を討伐する役目の者――討伐員――を人間界に派遣していた。
その討伐員の指揮を執っている者の一人が平安時代に源頼光である。
頼光自身は普段異界にいて部下達に指示を送っている。
その部下達というのが頼光四天王の〝渡辺綱〟、〝碓井貞光〟、〝坂田金時〟、〝卜部季武〟である。
異界の者には寿命がないので討伐員は昔から人間界に常駐していて今もいるとの事だった。
年を取って死ぬことがないため、周囲の人間達に怪しまれないように定期的に移動しているそうだ。
「ケーキ? クリスマスの?」
「うん、皆の好みを教えてもらえれば作るよ」
十二月の半ば、六花が季武に言った。
「時間は大丈夫なのか?」
季武が訊ねた。
六花は中学三年生で高校受験を控えている。
「ケーキはそんなに時間掛からないよ」
季武は六花の言葉に頷いた。
「てことで、料理作ってもらってるお礼に昔の話するね」
マンションの台所で綱が言った。
六花は昔話が好きで頼光や頼光四天王の名前も彼らと知り合う前から名前を知っていた。
頼光と頼光四天王は六花にとって伝説の英雄でありアイドルだ。
昔の話をすると六花が喜ぶからとケーキを作る合間に話してくれることになった。
平安時代、頼光は源満仲に暗示を掛けて長男だと思わせ貴族として生活していた。
綱も源宛の遺児だと思わせて源敦の養子になった。
季武、貞光、金時は郎等なので誰かの子供の振りはしなかったらしい。
綱も最初は郎等の一人だったのだが頼光が官職で忙しくなったため、もう一人貴族が必要になったので頼光の妹婿の源敦の養子になるために宛の遺児だと思わせたそうだ。
『今昔物語集』「頼光の郎等、平季武、産女に値う語」
頼光が美濃に赴任した時のある夜、季武は侍部屋で他の郎等達と宿直をしていた。
いつものように郎等達が雑談をしているうちに誰かが、
「そこの川に夜な夜な産女という妖怪が出るらしい。誰か行ってみないか」
と言い出した。
皆、
「お前行けよ」
「そういうお前こそ」
と言い合っていて誰も行くとは言わなかった。
その時、
「六郎、お前はどうだ?」
と誰かが季武に水を向けた。
六郎というのは季武の通称である。
「流石の六郎でも無理だろ」
他の者が言った。
「下らん。行って帰ってくるだけなら誰にでも出来るだろ」
季武が答えた。
「なら行ってみろよ」
「そうだ、行ってみせろ。行けると言うだけならそれこそ誰にでも出来るからな」
「なら賭けるか? 俺が行って来られるかどうかで」
「良いだろう。儂は六郎が行かれない方にこれを賭ける」
一人がそう言って太刀を出すと他の者達も次々と高価な物を賭けると言って出してきた。
どうせ行かれないだろうと高を括っているのだ。
調子に乗った郎等達が季武の前に様々な物を積み上げる。
「後悔するなよ」
季武はそう言って立ち上がった。
「ホントに行ったかどうかどうやって証明するんだ?」
誰かの言葉に季武は胡簶を手に取った。
胡簶というのは腰に付けて矢を入れておく物である。
季武は胡簶を腰に付けて矢を郎等達に見せた。
矢はそれぞれに特徴があるので誤魔化しが利かないのだ。
「この矢を対岸の地面に刺してくるから明日の朝にでも見にいって確かめてみろ」
季武はそう言うと部屋を出た。
真夜中に意味もなく川を渡る羽目になるとは……。
しかも渡ったあと戻ってこなければならないのだ。
売り言葉に買い言葉で部屋を出てきたもののすぐに後悔した。
無駄骨折りにも程がある。
せめて女が喜びそうな物でもあれば恋人への贈り物に出来るのに、賭の品として出されたのは太刀だの鎧だの兜だの、武士しか使わないような物しかなかった。
馬鹿馬鹿しいと思いながら馬に乗ると川に向かった。
川を渡って対岸に矢を立てるとまた川を渡って戻り始めた。
不意に川の途中で生臭い臭いが辺りに充満したかと思うと、
「これを抱け」
と言う女の声と赤ん坊の泣き声が聞こえてきた。
いつの間にか季武の側に女が来ていた。
女が泣いている赤ん坊を差し出してくる。
「貸せ」
季武が無表情のまま手を出すと女が赤ん坊を渡してきた。
赤ん坊を受け取った季武はそのまま川を進み始める。
「子供を返しておくれ」
と女が言うが季武は無視して川を渡る。
女が「子供を返せ」と言いながら追い縋ってくるが季武は無視した。
季武は赤ん坊を抱えて邸に帰った。
「ほら、産女から赤ん坊をとってきたぞ」
と季武が腕を開くと数枚の葉が下に落ちた。
そこへ季武の後を尾けていた男達が帰ってきて季武が間違いなく川を渡って産女から赤ん坊を受け取ったと証言した。
男達は顔を見合わせると渋々賭の品を差し出した。
季武は賭の品を総取りした。
「え!? 受け取ったの!?」
六花が驚いて声を上げた。
『今昔物語集』では受け取らなかったから賞賛されたと書いてあったのだが。
「夜中に川を渡ったんだぞ。当然の報酬だろ」
「ま、まぁ、そうだね……」
武勇伝と言えば武勇伝なんだろうけど……。
いくら相手が妖怪とは言え子供を誘拐……。
「季武って敵には容赦ねぇもんなぁ」
「人間にも優しくはねぇだろ」
金時と貞光が小声で囁きあっていた。
『赤染衛門集』
「美濃守殿、お世話になりました」
大江匡衡は頼光にそう礼を言うと妻の赤染衛門を伴って旅立っていった。
頼光が美濃守になったのと時を同じくして、大江匡衡は尾張守に任ぜられたのである。
匡衡は妻と共に赴任先の尾張に向かう途中で美濃にある頼光の邸に立ち寄ったのだ。
二人の赴任が決まって酒宴を催した後、匡衡が礼の文を送ってきたので、尾張に行くなら邸に寄ってくれと返事を出していた。
それで匡衡は妻の赤染衛門と共に訊ねてきたのである。
「殿」
匡衡を見送った頼光が邸に戻ると使用人がやってきた。
使用人に呼ばれて後に随いていくと大江夫妻が泊まった部屋の壁に、
草枕 露をだにこそ 思ひしか
誰がふるやとぞ 雨もとまらぬ
と書いてある。
「何か至らないところでもあったのでしょうか」
使用人が恐る恐る訊ねてくる。
「ここじゃなくて途中の宿だ」
頼光が安心させるように言った。
歌の内容は、
「夜露に濡れることを心配していたが露どころではない。雨漏りでびしょ濡れだ」
という愚痴だ。
この邸は雨漏りなどしないし何より匡衡達の滞在中、雨は降っていない。
歌を詠んだ時、手元に紙がなかったので最初に見付けた書けそうな所(頼光の邸の壁)に書いたのだろう。
「人の家の壁に……」
愚痴の落書きってなんの嫌がらせ?
六花はドン引きしたが、頼光によると当時、紙は貴重品で中々手に入らなかったそうだ。
そのため公文書以外はそうそう書くことが出来なかった。
だから人の家の壁などに書くことはよくあったとのことだった。
「そ、そうなんですか……」
そういえば勅撰和歌集に載っている頼光の歌のうちの一つは妻との連歌だ。
『金葉集』
頼光が赴任先から帰京する途中、朝、使用人が蔀を開けると目の前の川を舟が下ってくるのが見えた。
舟には何かが積まれている。
「あれは?」
「蓼という植物を刈ったものを運んでいるそうです」
頼光の問いに供の侍が答えた。
「たでかる舟のすぐるなりけり」
頼光がそう呟くと、側にいた妻が、
「朝まだき から櫓の音の 聞こゆるは」
と答えた。
頼光の呟きが下の句のようだったから妻が和歌になるように上の句を詠んだのである。
下の句(七七)みたいだからって奥さんまで歌を詠んじゃうなんて……。
和歌で日常会話をしていたのかと思えるレベルだ。
『源平盛衰記』「剣巻」
綱が頼光の使いで夜道を馬に乗って邸に戻る途中、一条堀川の戻り橋のたもとで、
「あの……」
女性の声に振り向くと、二十歳くらいの女性が供を連れず一人でいる。
おっ、綺麗な女性……。
「どうしました?」
綱が立ち止まって愛想良く訊ねると、
「五條渡に帰る途中で夜が更けてしまい怖くて……。送っていただけませんか?」
と女性が答えた。
綱はすぐに馬から下りて女性の側へ行くと、
「お安い御用です。どうぞ馬に乗ってください」
と女性を馬に乗せた。
そして自分も騎乗すると馬を五條渡に向けた。
歩き出してしばらくすると、
「あの……実は家は五條渡ではなく都の外なのですが……」
と女性が言った。
「構いませんよ。お送りします」
綱がにこやかに答えると、
「では愛宕山まで行こうか」
女性は突然鬼の姿になると綱の髻を掴んで飛び立った。
「あ~、やっぱなぁ……」
綱は溜息を吐くと太刀を抜いて鬼に斬り付けた。
鬼の腕が切れ、綱は鬼の手ごと下に落ちた。
綱が落下したのは北野神社の回廊の屋根の上だった。
屋根から飛び降り、まだ髻に付いている鬼の腕を外すと懐にしまって頼光の邸に帰った。
邸で頼光に戻ったことを報告すると、
「何があった」
と訊ねられた。
「あ、お気付きになられましたか。実は――」
綱は鬼の腕を取り出しながら事情を話した。
「いや~、鬼の気配に気付くとはさすが頼光様」
「馬鹿者! お前の髻が乱れていたから女のところにでもよってきたのかと思ったら!」
頼光が綱を一喝した。
「げっ! 藪蛇……」
綱は慌てて口を噤んだが遅かった。
「仕方ない、誰か播磨守を呼んでこい」
頼光がそう言うと使いの者が出ていった。
播磨守というのは安倍晴明のことである。
晴明はすぐにやってきた。
「どうしたらいいと思う?」
頼光がそう訊ねると、
「鬼の腕を封印し、綱殿は七日間の物忌みを」
と晴明が答えた。
「と言うことだから綱は宿所で謹慎だ」
と頼光が言い渡した。
がっちりと叱りつけた後で。
綱が宿所で物忌み――という名の謹慎をしていると、従者に綱を訪ねてきた者がいると告げられた。
「誰だ」
綱が門の近くで誰何すると、
「私よ」
という妻――の一人――の声がした。
「物忌みだと言ったはずだ」
「謹慎でしょ」
「ぐっ……」
「一人じゃつまらないだろうと思ってきてあげたのよ。二人だけで過ごす良い機会でしょ」
妻の言葉に綱は返事に詰まった。
綱には複数の妻がいるため必然的に一人一人の妻と過ごす時間が短い。
常々その事で嫌みを言われている。
追い返して機嫌を損ねたら家に入れてもらえなくなるかもしれない。
頼光のいる場所からは離れているし、妻と頼光が話す機会はない。
従者に口止めしておけば中に入れてもバレずにすむだろう。
綱は妻を中に入れた。
「それで、なんで謹慎になったの?」
「いや、物忌……」
「摂津守様の邸の女に手を出して怒らせたとかじゃないでしょうね」
「違うって」
綱は慌てて鬼の事を話した。
鬼が女性に化けていたことは伏せて。
「まぁ……では、ここに鬼の腕が? 見せて」
「いや、封印してあるから……」
「ホントに鬼に襲われたの? 本当は摂津守様の使用人に手を出して怒らせたんじゃないの?」
妻が疑わしそうな表情になった。
「嘘じゃないって!」
慌てて否定したが女に手を出した前科が(何度も)ある綱の言葉は信じてもらえそうにない。
押し問答の末、綱は仕方なく封印を解くと鬼の腕を妻の前に置いて見せた。
「まぁ、これは……正しく我の腕よ。返してもらうぞ」
妻に化けていた鬼は正体を現すと腕を掴んだ。
「貴様!」
綱が刀に手を伸ばしたが、その前に鬼は破風を蹴破ると空を飛んで行ってしまった。
平安時代版オレオレ詐欺……。
「普通、飛んでる時に斬んねぇだろ」
貞光が呆れたように言った。
「山まで行ったら帰るの大変じゃん。歩いて帰らないといけない時代だったんだぞ」
「愛宕山から堀川までなんて大した距離じゃないだろ。人間だって精々三時間半だぞ」
「神社の屋根壊してんじゃねぇよ」
「夜中に呼び出された播磨守も迷惑だったと思うぞ」
「しかも妻に化けた鬼にまた騙されて」
「あれで頼光様にこってり絞られたんだよな~」
綱が肩を落とした。
「自分が悪いんだろ!」
「なんで同じ鬼に二度も騙されるんだよ!」
「たった七日も一人で過ごせないのか!」
金時達が次々と突っ込む。
……あれ?
「声真似したのって義理のお母さんじゃ……」
「『平家物語』とかではそうなってるけどホントは妻だよ」
綱が言った。
そう言われてみれば義理の母が綱を騙して中に入れさせる時「生まれたばかりの頃から大切に育ててきたのに」と語ったと書いてあった。
だが綱は暗示で源宛の息子だと思い込ませただけだから赤ん坊の頃は無い。
だから、そんな話をするはずがないし、されたとしても引っ掛かる訳がない。
「えっと、その鬼って確か茨木童子ですよね」
「ああ、あれは宇治の橋姫だよ」
「茨木童子じゃないの? 大江山の仕返しに来たって……」
「それは別の話だ。綱を騙したのは宇治の橋姫だ」
「えっと……鬼が逃げたのは流石ですね」
苦し紛れの六花の言葉に、
「無理に擁護する必要ないぞ」
季武が言った。
確かにフォローのしようがないので六花は話題を変えることにした。
「播磨守って安倍晴明ですよね。そんなすごい人が夜中に来てくれたんですね」
「頼光様と播磨守の師匠が縁戚だったからな」
「え?」
「歌を詠んだ妻っていうのは賀茂忠行の孫娘なんだ」
賀茂忠行と言うのは晴明の師匠である。
その孫が産んだ娘――つまり忠行の曾孫――が相模という歌人として名高い女性である。
「へぇ。賀茂忠行って陰陽師だよね?」
「賀茂家も結構歌人を輩出してるんだ」
賀茂家〝も〟というのは頼光の子孫達も歌人として有名な者が多く歌人の家系だからである。
晴明の師匠は忠行ではなく忠行の長男の保憲という説もあるが、その保憲の娘も歌人として有名で『賀茂保憲女集』と言う歌集を出している。
相模の母の父は保憲の弟の慶滋保胤である。