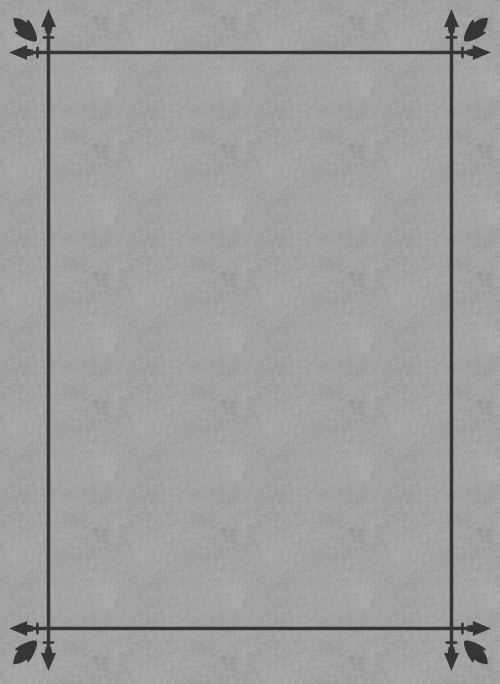「ひ、ひぃぃぃぃっ!!!」
「閉所では最低限の動きで最高の攻撃をするのがセオリーだ。ましてや、ここは公爵家の邸宅だから無駄な被害は極力出したくない。そうだろ?」
俺は怯えきっている爺さんにも理解ができるような、優しく柔らかい口調で言葉を紡いでいった。
特に魔法を使うことはしない。本当は一瞬で眠らせたり、最速で接近して意識を刈り取れば済む話なのだが、どうせならこの依頼をとことんまで楽しみ、様々な技を試すとしよう。
「……あ、ぁぁ……っ……」
「そんな長い杖は不要だし、先ほどのような動きの制限がある魔法も論外だ。であれば、何をするのが正解なのか。答えは簡単だ。よーく見ていろ」
俺はまるで影と一体化するかのようなイメージをしながら、無音で軽やかに足を動かした。
それから僅か一秒足らずのこと。
数メートル先で尻餅をついている爺さんは、何度も自身の瞳を擦り俺の姿を何度も見直していた。
「っ!! ぶ、分身した!?」
「知り合いに暗殺者がいてね……そいつから教えてもらったんだ。確かこの歩法は幻影乃影歩って言ったかな?」
自分自身ではよくわからないが、側から見れば今の俺は幻影を生み出して何人にも分身していることだろう。
これは幻影乃影歩。
魔法や魔力は一切用いていない単なる歩法の術だ。
数が増えたように見えるだけなので実体はなく、それぞれが本体と同じ動きをするだけである。
どういう原理なのかは不明で、一定時間を経て勝手に消えてしまうが、初見の相手を困惑させるのには十分と言える。
現に目の前の爺さんはわなわなと震えて吐く言葉が見つからない様子だ。
「……チャーリーはどこにいるか、改めて教えてもらえるか?」
俺は爺さんと視線を合わすようにして膝を曲げると、その動揺している瞳をじっと見つめて問いかけた。
すると、爺さんは年甲斐もなく涙をこぼして口を開く。
「ち、ちちち、地下室にいらっしゃいますぅ!」
爺さんはまるで乙女のように自分の体を抱き寄せながら答えてくれた。あんなに強気だったのに負けを確信した途端これだもんな。意思がふにゃふにゃすぎる。
「了解。んじゃ、もうゆっくりしていいぞ?」
「……あ、ぁぁ……」
俺が優しく声をかけると、爺さんは糸がぷつりと切れた人形のように力無く倒れた。
死んではいない。単純に恐怖と慄きから気を失っただけだ。
「やっぱり地下室があったのか。先に調べておくべきだったな。失敗した」
この最上階である三階に到達した時点でもしやと思っていたが、本当に地下室にいるとはな。
道理でどのフロアにもそれらしき部屋がないわけだ。
この爺さん以外にまともに戦闘できるヤツはいないだろうし、とっとと地下室に向かってみるか。
「閉所では最低限の動きで最高の攻撃をするのがセオリーだ。ましてや、ここは公爵家の邸宅だから無駄な被害は極力出したくない。そうだろ?」
俺は怯えきっている爺さんにも理解ができるような、優しく柔らかい口調で言葉を紡いでいった。
特に魔法を使うことはしない。本当は一瞬で眠らせたり、最速で接近して意識を刈り取れば済む話なのだが、どうせならこの依頼をとことんまで楽しみ、様々な技を試すとしよう。
「……あ、ぁぁ……っ……」
「そんな長い杖は不要だし、先ほどのような動きの制限がある魔法も論外だ。であれば、何をするのが正解なのか。答えは簡単だ。よーく見ていろ」
俺はまるで影と一体化するかのようなイメージをしながら、無音で軽やかに足を動かした。
それから僅か一秒足らずのこと。
数メートル先で尻餅をついている爺さんは、何度も自身の瞳を擦り俺の姿を何度も見直していた。
「っ!! ぶ、分身した!?」
「知り合いに暗殺者がいてね……そいつから教えてもらったんだ。確かこの歩法は幻影乃影歩って言ったかな?」
自分自身ではよくわからないが、側から見れば今の俺は幻影を生み出して何人にも分身していることだろう。
これは幻影乃影歩。
魔法や魔力は一切用いていない単なる歩法の術だ。
数が増えたように見えるだけなので実体はなく、それぞれが本体と同じ動きをするだけである。
どういう原理なのかは不明で、一定時間を経て勝手に消えてしまうが、初見の相手を困惑させるのには十分と言える。
現に目の前の爺さんはわなわなと震えて吐く言葉が見つからない様子だ。
「……チャーリーはどこにいるか、改めて教えてもらえるか?」
俺は爺さんと視線を合わすようにして膝を曲げると、その動揺している瞳をじっと見つめて問いかけた。
すると、爺さんは年甲斐もなく涙をこぼして口を開く。
「ち、ちちち、地下室にいらっしゃいますぅ!」
爺さんはまるで乙女のように自分の体を抱き寄せながら答えてくれた。あんなに強気だったのに負けを確信した途端これだもんな。意思がふにゃふにゃすぎる。
「了解。んじゃ、もうゆっくりしていいぞ?」
「……あ、ぁぁ……」
俺が優しく声をかけると、爺さんは糸がぷつりと切れた人形のように力無く倒れた。
死んではいない。単純に恐怖と慄きから気を失っただけだ。
「やっぱり地下室があったのか。先に調べておくべきだったな。失敗した」
この最上階である三階に到達した時点でもしやと思っていたが、本当に地下室にいるとはな。
道理でどのフロアにもそれらしき部屋がないわけだ。
この爺さん以外にまともに戦闘できるヤツはいないだろうし、とっとと地下室に向かってみるか。