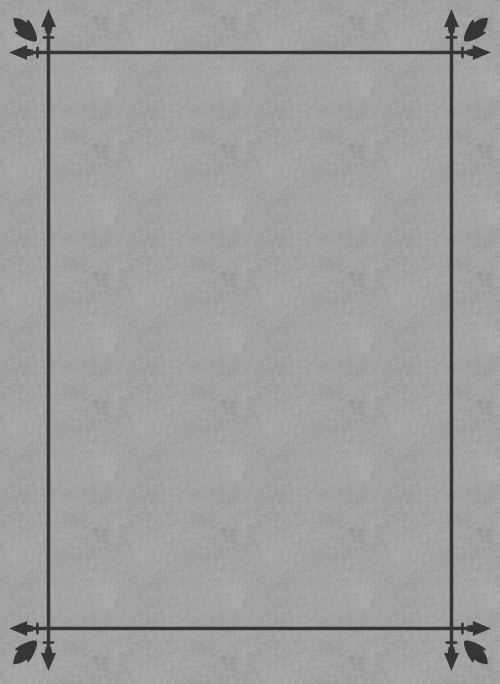「……こりゃまた中も立派だな」
俺は邸宅の中へと侵入して早々に、庭園もさることながら豪華絢爛な内装にも目を奪われた。
よくわからない絵画が壁にかけられており、長い廊下にはシワやシミの一つもない真紅色のカーペットが敷かれている。
また、夜間の光源として、壁には等間隔で埋め込み式の魔道具が設置されているため、外よりも僅かに明るく比較的視界は良好だった。
俺はざっと内部の概要を確認を済ませると、足音一つ立てることなく歩を進め始めた。
公爵は自身の権力を十分に理解しているからか、際立って強い警備を敷いているわけではないようだ。
普通に考えて王都で幅の効く公爵家を襲おうなんて考える酔狂なヤツはいないのだが、一人息子の日頃の行いや買われている恨みを加味するならば、俺みたいなやつが襲撃にすることも考えてほしいものだな。
「……」
特に騎士が彷徨いているような気配は感じない。
一階のフロアはどれも大規模な調理場と食堂、集会室しかなく、人気は全くない。
流れるようにして進んだ二階のフロアも同様だ。こちらは使用人と騎士が住まう部屋しかないようだ。
となると、この邸宅の大きさ的に後は三階より上が怪しくなるが、特に邪気を孕んだような怪しい気配は感じない。
「……ここにもいない」
一階と二階に続いて、三階のフロアも確認してみたが、三階のフロアにもチャーリーの姿はない。
見た感じここは最上階にあたる。
なぜこんなにも静寂に包まれているのだろうか。
先の時点で考慮した油断と慢心だけでは片付けられないような気がする。
「公爵もチャーリーもいないのはおかしいな」
全ての部屋の中を確認するために、俺は限定的な範囲で魔力探知を発動させながら歩を進めてきたのだが、それでもターゲットを見つけることはできなかった。
使用人や騎士はそれぞれの部屋にいて眠りについていたのに、どうして肝心のチャーリーが見つからないのだろうか。
上へと続く階段もないし、窓から外を見た感じここは最上階のフロアで間違いない。
チャーリーがこれまでに購入した多くの奴隷たちの姿もないし、となると、後考えられるのは……。
「———何やら怪しい魔力を探知したから顔を出してみれば……若いの、何か用事かね?」
俺が思考を続けていると、長い廊下の向こうから爺さんが現れた。
俺と同じような長いローブを羽織り、手にはこれまた長い杖を持っており、白髪混じりの長い髪を揺らしてこちらに近づいてきている。
「……来たか」
俺はふっと息を吐いて爺さんと向かい合った。
実は一階のフロアを突破した時点で、あまりにも静かで敵意がなさすぎるので怪しいと思い、あえて並の魔法使いにバレる程度の魔力をちらつかせながら進んでいたのだ。
「ふぉっふぉっふぉっ、そのような粗い魔力の隠し方では誰にでも気づかれてしまいますまい」
「あんたみたいな三流にも気づいてもらえるように、わざとそうしたんだよ。わからなかったか?」
俺は上品に笑う爺さんを挑発するように言葉を吐いた。
「……何が狙いかね?」
「チャーリーはどこにいる?」
「答える義務はありませんなぁ」
とぼけた様子で答える爺さんだったが、代々公爵家に仕える魔法使いが知らないはずがない。
旧知の中だろうし、互いに多くの情報を共有しているはずだ。
「わかった。なら実力行使で問題ないな」
正直、このまま誰にもバレないように邸宅内をふらふら彷徨くのは面倒だし、素直に教えてくれないのなら少々手荒な方法で聞き出すとしよう。
「やれるものならどうぞご勝手に」
爺さんはニッと口角を上げて長い杖を構えた。
杖を使う時点で三流の証だ。
短杖ならまだわかるが、そんなものを魔力を練り上げるための媒体として利用するのは精々開けた場所のみだ。バカでかい規模の魔法を放つときに限られる。
こんな邸宅でお飾りとして持っているのは愚か者のすることである。
俺は邸宅の中へと侵入して早々に、庭園もさることながら豪華絢爛な内装にも目を奪われた。
よくわからない絵画が壁にかけられており、長い廊下にはシワやシミの一つもない真紅色のカーペットが敷かれている。
また、夜間の光源として、壁には等間隔で埋め込み式の魔道具が設置されているため、外よりも僅かに明るく比較的視界は良好だった。
俺はざっと内部の概要を確認を済ませると、足音一つ立てることなく歩を進め始めた。
公爵は自身の権力を十分に理解しているからか、際立って強い警備を敷いているわけではないようだ。
普通に考えて王都で幅の効く公爵家を襲おうなんて考える酔狂なヤツはいないのだが、一人息子の日頃の行いや買われている恨みを加味するならば、俺みたいなやつが襲撃にすることも考えてほしいものだな。
「……」
特に騎士が彷徨いているような気配は感じない。
一階のフロアはどれも大規模な調理場と食堂、集会室しかなく、人気は全くない。
流れるようにして進んだ二階のフロアも同様だ。こちらは使用人と騎士が住まう部屋しかないようだ。
となると、この邸宅の大きさ的に後は三階より上が怪しくなるが、特に邪気を孕んだような怪しい気配は感じない。
「……ここにもいない」
一階と二階に続いて、三階のフロアも確認してみたが、三階のフロアにもチャーリーの姿はない。
見た感じここは最上階にあたる。
なぜこんなにも静寂に包まれているのだろうか。
先の時点で考慮した油断と慢心だけでは片付けられないような気がする。
「公爵もチャーリーもいないのはおかしいな」
全ての部屋の中を確認するために、俺は限定的な範囲で魔力探知を発動させながら歩を進めてきたのだが、それでもターゲットを見つけることはできなかった。
使用人や騎士はそれぞれの部屋にいて眠りについていたのに、どうして肝心のチャーリーが見つからないのだろうか。
上へと続く階段もないし、窓から外を見た感じここは最上階のフロアで間違いない。
チャーリーがこれまでに購入した多くの奴隷たちの姿もないし、となると、後考えられるのは……。
「———何やら怪しい魔力を探知したから顔を出してみれば……若いの、何か用事かね?」
俺が思考を続けていると、長い廊下の向こうから爺さんが現れた。
俺と同じような長いローブを羽織り、手にはこれまた長い杖を持っており、白髪混じりの長い髪を揺らしてこちらに近づいてきている。
「……来たか」
俺はふっと息を吐いて爺さんと向かい合った。
実は一階のフロアを突破した時点で、あまりにも静かで敵意がなさすぎるので怪しいと思い、あえて並の魔法使いにバレる程度の魔力をちらつかせながら進んでいたのだ。
「ふぉっふぉっふぉっ、そのような粗い魔力の隠し方では誰にでも気づかれてしまいますまい」
「あんたみたいな三流にも気づいてもらえるように、わざとそうしたんだよ。わからなかったか?」
俺は上品に笑う爺さんを挑発するように言葉を吐いた。
「……何が狙いかね?」
「チャーリーはどこにいる?」
「答える義務はありませんなぁ」
とぼけた様子で答える爺さんだったが、代々公爵家に仕える魔法使いが知らないはずがない。
旧知の中だろうし、互いに多くの情報を共有しているはずだ。
「わかった。なら実力行使で問題ないな」
正直、このまま誰にもバレないように邸宅内をふらふら彷徨くのは面倒だし、素直に教えてくれないのなら少々手荒な方法で聞き出すとしよう。
「やれるものならどうぞご勝手に」
爺さんはニッと口角を上げて長い杖を構えた。
杖を使う時点で三流の証だ。
短杖ならまだわかるが、そんなものを魔力を練り上げるための媒体として利用するのは精々開けた場所のみだ。バカでかい規模の魔法を放つときに限られる。
こんな邸宅でお飾りとして持っているのは愚か者のすることである。