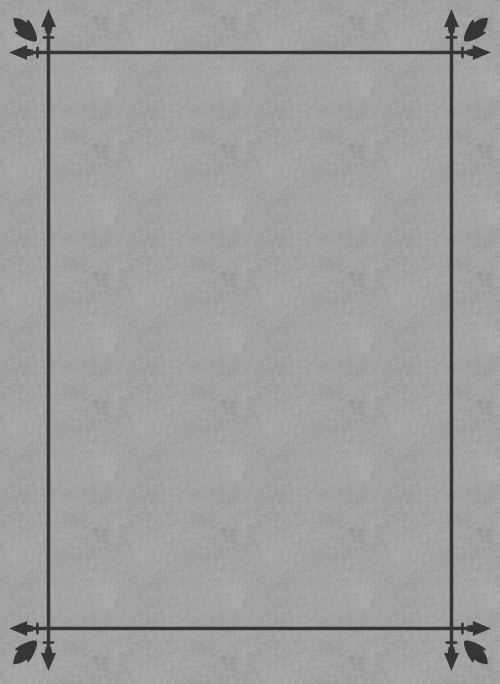そう思い立った俺は、眼前でダガーを振り続ける彼の腹に膝を入れた。
「グゥッッ……ッ!? い、いたい……けど、まだまだー!」
少年はダガーを落として腹を抱えて蹲るが、苦悶の表情を浮かべながらも立ち上がった。
良い根性だが、何度やっても意味はない。
「ワンパターンだから攻撃が読みやすい。キミはもう少し撚りを加えたほうがいいな。簡単な魔法でもいいから、覚えてみたらどうだ? 例えば、こんな感じの……氷縛結界」
俺は一つ指を鳴らして氷魔法を唱えた。
その瞬間。少年の足元に氷の結界が出現する。
脂汗をかいて痛みが抜けていないようだし、今は瞬間的に冷却された方がちょうどいいんじゃないか?
「え? う、うわぁ!?」
少年は慌ててその場から退こうとするが時既に遅し。
氷の結界が出現した時点で、少年の足首から脛の辺りまでを凍り付かせており、身動きを取ることはもうできない。
「これは少しばかり力が必要な規模になるが、覚えておいて損はない。たとえ足元を凍らせて突破されたとしても一瞬の時間を強制的に生み出すことは可能だからな……って、もう聞いてないか……」
俺は足元から徐々にゆっくりと氷に浸食されて行く少年の姿を見ながら教示してあげたのだが、チラリと彼の表情を確認すると、既に首から下が凍りついており、泡を吹いて気絶していることに気がついた。
まあ、いいか。
こういう経験は目が覚めた時に思い出して、必ず自身の糧となる。
俺のように一瞬にして相手の全身を凍らせるのは至難の業だろうが、少し手元を凍らせたり、僅かな冷気を放てるだけでも戦況に変化を与えることができる。
強くなれ、少年よ。
「むむっ……中々やるでないか。その者は稀代のスピードスターと呼ばれている逸材の若者であったのに……」
俺とダガー使いの少年の戦いが終了したことで、これまで傍観していた大剣使いの男が口を開いた。
少しばかり驚いているらしく、小さな唸り声を上げていた。
「確かに少しだけ速かったな」
失礼な言い方ではあるが、小蠅のような鬱陶しさを感じるようなスピード感ではあった。
「強がるな。速さがダメなら力で勝負だ」
大剣使いの男は片手で体験を横凪に振り払うと、辺りに強風を巻き起こした。
力で勝負か。
俺は魔法を主としていて体術や力の使い方はそこそこだが、どうせなら受けて立とう。
「かかってこい」
俺は一つ息を引いて返事をしてから、氷漬けになった少年のことを床を滑らすようにして部屋の隅へ追いやった。
連戦の方が流れるがままに戦えるので好都合だ。
さて、彼はどんな戦いを見せてくれるだろうか。
「グゥッッ……ッ!? い、いたい……けど、まだまだー!」
少年はダガーを落として腹を抱えて蹲るが、苦悶の表情を浮かべながらも立ち上がった。
良い根性だが、何度やっても意味はない。
「ワンパターンだから攻撃が読みやすい。キミはもう少し撚りを加えたほうがいいな。簡単な魔法でもいいから、覚えてみたらどうだ? 例えば、こんな感じの……氷縛結界」
俺は一つ指を鳴らして氷魔法を唱えた。
その瞬間。少年の足元に氷の結界が出現する。
脂汗をかいて痛みが抜けていないようだし、今は瞬間的に冷却された方がちょうどいいんじゃないか?
「え? う、うわぁ!?」
少年は慌ててその場から退こうとするが時既に遅し。
氷の結界が出現した時点で、少年の足首から脛の辺りまでを凍り付かせており、身動きを取ることはもうできない。
「これは少しばかり力が必要な規模になるが、覚えておいて損はない。たとえ足元を凍らせて突破されたとしても一瞬の時間を強制的に生み出すことは可能だからな……って、もう聞いてないか……」
俺は足元から徐々にゆっくりと氷に浸食されて行く少年の姿を見ながら教示してあげたのだが、チラリと彼の表情を確認すると、既に首から下が凍りついており、泡を吹いて気絶していることに気がついた。
まあ、いいか。
こういう経験は目が覚めた時に思い出して、必ず自身の糧となる。
俺のように一瞬にして相手の全身を凍らせるのは至難の業だろうが、少し手元を凍らせたり、僅かな冷気を放てるだけでも戦況に変化を与えることができる。
強くなれ、少年よ。
「むむっ……中々やるでないか。その者は稀代のスピードスターと呼ばれている逸材の若者であったのに……」
俺とダガー使いの少年の戦いが終了したことで、これまで傍観していた大剣使いの男が口を開いた。
少しばかり驚いているらしく、小さな唸り声を上げていた。
「確かに少しだけ速かったな」
失礼な言い方ではあるが、小蠅のような鬱陶しさを感じるようなスピード感ではあった。
「強がるな。速さがダメなら力で勝負だ」
大剣使いの男は片手で体験を横凪に振り払うと、辺りに強風を巻き起こした。
力で勝負か。
俺は魔法を主としていて体術や力の使い方はそこそこだが、どうせなら受けて立とう。
「かかってこい」
俺は一つ息を引いて返事をしてから、氷漬けになった少年のことを床を滑らすようにして部屋の隅へ追いやった。
連戦の方が流れるがままに戦えるので好都合だ。
さて、彼はどんな戦いを見せてくれるだろうか。