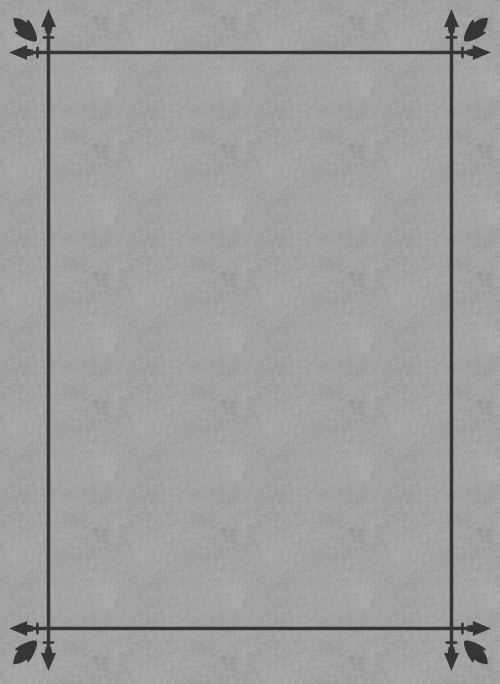「——一週間ぶりにきたな」
俺は転移魔法で王都の中心部に来ていた。
中心部とは言っても、目的の場所はジメジメとした路地裏にある黒々しい不気味な建物だ。
「早速、準備を始めるか」
俺の夢は二つある。
一つ目の夢はSランクパーティーに所属し、世界最強の魔法使い———賢者になること。
これはSランクパーティー『皇』に所属しているうちに、自然と呼ばれるようになっていたので、既に実現したと言える。
現に俺は自分こそが世界最強だと自覚しているし、『皇』を含めて世界に三組しかないSランクパーティーに所属している他のどの魔法使いよりも、魔法のレパートリーは豊富だし、魔力の量も桁違いに多い。
正直、魔法の扱いにおいては、誰であろうと負ける要素が見当たらない。
二つ目の夢はバーを経営することだ。
これは、ただ経営するのが夢ではない。
クールだが、どこか人情味のあるマスターになりたいという願望がある。
俺がまだ幼かった頃、今は亡き両親に連れて行かれたバーにいたマスターがカッコ良かったので、当時の俺はその姿に妙な憧れを抱いたのだ。
その憧れは成熟した今もなお胸に秘め続けている。
「大量の投資しただけあるな。相変わらず最高のデザインだ」
扉を開いて中に入った俺は安堵ともに呟いた。
冒険者活動で稼いだお金を惜しげもなく注ぎ込むことで、この土地と建物をいっぺんに買い占めている。
そして、内外装のデザインのために資材等を大量に買い込み、およそ半年前から地道に作業を進めてきた。
全ては念願のバーをオープンする為だ。
いつかは冒険者を引退して、完成したバーでマスターになろうと考えていたので、ルウェストに追放されたのは運命だったのだろう。
変な禍根を残すことなく、きっぱり退くことができた。
「灯りは暗めで、席はカウンター席のみで少なめに配置……距離は適度に取りつつも、寂しさを感じさせない程度に……よし! バッチリだな」
俺は自分でデザインした内装を大まかに確認していく。
いつ見ても素晴らしい出来だ。
凝りに凝ったおかげで、この場にいるだけでワクワクが止まらない。
「次は……いよいよだな」
そして、俺は奥の居住スペースに入っていき、一番の目玉を見に行く。
「二十二歳にして、やっと着ることができる。これこそがバーのマスターだ……」
俺がクローゼットからタキシードを取り出した。
色は真白いシャツが良く映える黒色だ。
加えて、少しばかりのアクセントとしてオレンジ色のネクタイを締める。
どれも試着して以来の着用になるので、パリパリとしていて新鮮で気持ちが良い。
「よしっ」
俺は手際良く着用したが、まだまだ鏡に映る自分の姿は見慣れない。まあ、特注でサイズはピッタリなので、そのうち着慣れてくると思う。
「初のオープンだ!」
俺は出入り口の扉に掛かる木の板を、クローズからオープンに変えた。
店名などは特に掲示していない。隠れ家的バーを目指しているので、ひっそりと佇んでいるくらいがちょうどいいのだ。
「順調すぎるな」
無事に店をオープンさせたのはいいが、とんとん拍子に事が運びすぎて不思議な気分だ。
以前からルウェストとは確執があり、衝突する機会も日に日に増えていたので、もう関わりを断てたと思うと開放的な気分にもなる。
残されたルウェスト以外の二人には悪いが、俺はお先にフェードアウトして次の夢を追わせてもらう。
「さて、お客様を待つとするか」
俺はグラスやテーブルを磨きながら、まだ見ぬ客の来店に備える。
隠れ家的バーを意識し、少ない常連客と親密な関係を築きたいという理念があるので、チラシ配りや大々的な告知は一切行なっていない。
そもそもこんな裏路地にバーを構えた時点で、頻繁に人が訪れることはないだろう。
しかし、そんな俺の予想とは裏腹に、早々にその時は訪れた。
新しい木材をあえて古臭く加工した扉が、小さな軋む音を立てながらゆっくりと開く。
「……ここは、何のお店?」
半分ほど開かれた扉からひょこっと顔を出したのは、魔法使いのような外見をした小柄な少女だった。
少し乱れた銀髪にほつれや汚れが目立つチャコール色のローブ。纏うオーラは、微弱だが人間ではない黒い何かを感じた。
危険性は一切ないので特に言及はしないが、そんなことよりも、表情が暗い気がする。
何か気を張っているような……いや、怯えている様子が見て取れる。
「いらっしゃいませ。こちらはバー【ハイドアウト】です。お酒や果実水、軽食からスイーツまで、幅広く取り揃えております」
俺は恭しく頭を下げてニコリと笑みを返した。
「じゃあ、適当なジュースをお願い」
「かしこまりました」
小柄な少女はカウンター席の端の方に座ると、退屈そうに言った。
「……」
俺は何か言いたげな様子の少女を一瞥してから、ピカピカのグラスの中に、南の国の果実を濃縮したジュースを静かに注に入れた。
これはアルコールが含まれておらず、甘くて飲みやすいのでオススメだ。
「お待たせ致しました。南国風ジュースになります」
果実水やジュース、幼い表現だと”甘いの”等……呼び方はそれぞれだが、基本的に客側の呼び方に合わせた方が印象は良くなる。
初対面の相手と話す際は、共感性を高めることが大切だ。
「ありがと……ねぇ、マスターに愚痴を溢してもいい?」
「どうぞ。絶対に他言はしないので」
俺は口元に人差し指を添えて小さく笑いかける。
どうやら少女には何か悩みがあるようだ。
これが俺の初めての仕事になる。
親身に寄り添うことで、俺の思い描くマスターとしての仕事を果たすとしよう。
俺は転移魔法で王都の中心部に来ていた。
中心部とは言っても、目的の場所はジメジメとした路地裏にある黒々しい不気味な建物だ。
「早速、準備を始めるか」
俺の夢は二つある。
一つ目の夢はSランクパーティーに所属し、世界最強の魔法使い———賢者になること。
これはSランクパーティー『皇』に所属しているうちに、自然と呼ばれるようになっていたので、既に実現したと言える。
現に俺は自分こそが世界最強だと自覚しているし、『皇』を含めて世界に三組しかないSランクパーティーに所属している他のどの魔法使いよりも、魔法のレパートリーは豊富だし、魔力の量も桁違いに多い。
正直、魔法の扱いにおいては、誰であろうと負ける要素が見当たらない。
二つ目の夢はバーを経営することだ。
これは、ただ経営するのが夢ではない。
クールだが、どこか人情味のあるマスターになりたいという願望がある。
俺がまだ幼かった頃、今は亡き両親に連れて行かれたバーにいたマスターがカッコ良かったので、当時の俺はその姿に妙な憧れを抱いたのだ。
その憧れは成熟した今もなお胸に秘め続けている。
「大量の投資しただけあるな。相変わらず最高のデザインだ」
扉を開いて中に入った俺は安堵ともに呟いた。
冒険者活動で稼いだお金を惜しげもなく注ぎ込むことで、この土地と建物をいっぺんに買い占めている。
そして、内外装のデザインのために資材等を大量に買い込み、およそ半年前から地道に作業を進めてきた。
全ては念願のバーをオープンする為だ。
いつかは冒険者を引退して、完成したバーでマスターになろうと考えていたので、ルウェストに追放されたのは運命だったのだろう。
変な禍根を残すことなく、きっぱり退くことができた。
「灯りは暗めで、席はカウンター席のみで少なめに配置……距離は適度に取りつつも、寂しさを感じさせない程度に……よし! バッチリだな」
俺は自分でデザインした内装を大まかに確認していく。
いつ見ても素晴らしい出来だ。
凝りに凝ったおかげで、この場にいるだけでワクワクが止まらない。
「次は……いよいよだな」
そして、俺は奥の居住スペースに入っていき、一番の目玉を見に行く。
「二十二歳にして、やっと着ることができる。これこそがバーのマスターだ……」
俺がクローゼットからタキシードを取り出した。
色は真白いシャツが良く映える黒色だ。
加えて、少しばかりのアクセントとしてオレンジ色のネクタイを締める。
どれも試着して以来の着用になるので、パリパリとしていて新鮮で気持ちが良い。
「よしっ」
俺は手際良く着用したが、まだまだ鏡に映る自分の姿は見慣れない。まあ、特注でサイズはピッタリなので、そのうち着慣れてくると思う。
「初のオープンだ!」
俺は出入り口の扉に掛かる木の板を、クローズからオープンに変えた。
店名などは特に掲示していない。隠れ家的バーを目指しているので、ひっそりと佇んでいるくらいがちょうどいいのだ。
「順調すぎるな」
無事に店をオープンさせたのはいいが、とんとん拍子に事が運びすぎて不思議な気分だ。
以前からルウェストとは確執があり、衝突する機会も日に日に増えていたので、もう関わりを断てたと思うと開放的な気分にもなる。
残されたルウェスト以外の二人には悪いが、俺はお先にフェードアウトして次の夢を追わせてもらう。
「さて、お客様を待つとするか」
俺はグラスやテーブルを磨きながら、まだ見ぬ客の来店に備える。
隠れ家的バーを意識し、少ない常連客と親密な関係を築きたいという理念があるので、チラシ配りや大々的な告知は一切行なっていない。
そもそもこんな裏路地にバーを構えた時点で、頻繁に人が訪れることはないだろう。
しかし、そんな俺の予想とは裏腹に、早々にその時は訪れた。
新しい木材をあえて古臭く加工した扉が、小さな軋む音を立てながらゆっくりと開く。
「……ここは、何のお店?」
半分ほど開かれた扉からひょこっと顔を出したのは、魔法使いのような外見をした小柄な少女だった。
少し乱れた銀髪にほつれや汚れが目立つチャコール色のローブ。纏うオーラは、微弱だが人間ではない黒い何かを感じた。
危険性は一切ないので特に言及はしないが、そんなことよりも、表情が暗い気がする。
何か気を張っているような……いや、怯えている様子が見て取れる。
「いらっしゃいませ。こちらはバー【ハイドアウト】です。お酒や果実水、軽食からスイーツまで、幅広く取り揃えております」
俺は恭しく頭を下げてニコリと笑みを返した。
「じゃあ、適当なジュースをお願い」
「かしこまりました」
小柄な少女はカウンター席の端の方に座ると、退屈そうに言った。
「……」
俺は何か言いたげな様子の少女を一瞥してから、ピカピカのグラスの中に、南の国の果実を濃縮したジュースを静かに注に入れた。
これはアルコールが含まれておらず、甘くて飲みやすいのでオススメだ。
「お待たせ致しました。南国風ジュースになります」
果実水やジュース、幼い表現だと”甘いの”等……呼び方はそれぞれだが、基本的に客側の呼び方に合わせた方が印象は良くなる。
初対面の相手と話す際は、共感性を高めることが大切だ。
「ありがと……ねぇ、マスターに愚痴を溢してもいい?」
「どうぞ。絶対に他言はしないので」
俺は口元に人差し指を添えて小さく笑いかける。
どうやら少女には何か悩みがあるようだ。
これが俺の初めての仕事になる。
親身に寄り添うことで、俺の思い描くマスターとしての仕事を果たすとしよう。