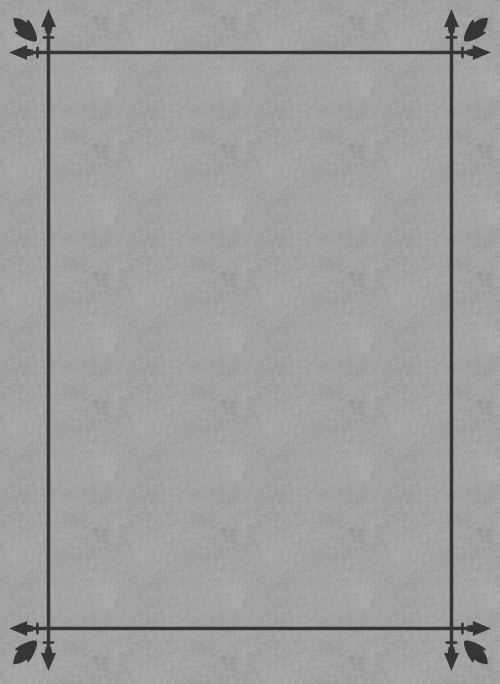「ふぅぅぅ……ボリュームたっぷりで最高だったぜ! 満腹でしばらくは動けそうにねぇ」
アレンはぐでっとだらしない格好でカウンターにもたれると、満足げな様子で頬を緩めていた。
「満足していただけたようで何よりです。お酒のおかわりはいかがなさいますか?」
「ん、ああ、頼む」
アレンがこちらにショットグラスを差し出してきたので、俺は流れるような手捌きでウイスキーを炭酸で割る。
彼はほんのり酒が回っているのか、顔がやや赤らんでいる。
「……ところで、アレン様」
「んぁ? どうした?」
「少し冒険者ギルドの受付嬢に関して聞きたいことがあるのですが、よろしいでしょうか?」
「いいぞ。なんだ、惚れた女でもいたか?」
俺の問いかけに対して、アレンはニヤニヤと悪どい笑みを浮かべて聞いてくる。
こうして話すと彼はごく普通のノリの良い若者にしか見えないが、一応警戒の念を解くことはしないでおく。
もし、万が一、アレンがあっち側の人間だった場合のことを考えて、慎重に探りを入れていく。
「いえ、実はルーナさんという金髪の方のことなのですが……」
「あー、ルーナねぇ……あいつぁちょっと変な噂も多いからオススメしないぜ?」
アレンは何か心当たりがあるのか、ぴくりと眉を顰めていた。
「変な噂ですか?」
「本当かどうかは知らねぇけど、色々と話を聞くぜ? 美人局みたいに冒険者の男を何人も唆して貢がせてるとか……まあ、受付嬢なのにあんな高級なアクセサリーをつけてたら不思議に思うのも無理はねぇ。ありゃあ相当なもんだぜ? ギルマスの俺でも何個も買えるもんじゃねぇな」
「そうなんですか」
「まあな。というか、マスター。隣に可愛いお嬢ちゃんがいるのに、他の女に手を出すつもりかい? ははっ、中々のプレイボーイだな!」
アレンは短く、それでいて甲高い声で笑うと、ぐいっとショットグラスを一気に煽った。
悪酔いはしないはずだが、酒に酔いやすいタイプなのか、すっかり楽しい気分になっているようだ。
また、いきなり可愛いと言われて悪い気はしていないのか、隣に立つシエルもどこか得意げな表情になっている。
単純すぎて困る。だから騙されるんだぞ?
まあいい。今なら何でも話してくれそうなので、適当に質問をぶつけていくことにするか。
「ちなみにですが……ルーナさんの装いや身につけるアクセサリーなどに違和感はございませんか?」
アレンがどこまで把握しているかはわからないが、この質問の答え次第で正解が導き出せるかもしれない。
「うーん……そう言われてみれば、大体半年に一回くらいの頻度でアクセサリーが増えてたり、変わってたりすることがあるな……」
「左様ですか。よく気が付きましたね」
ビンゴだ。一端の受付嬢の容姿の変化に気がつくとは、流石はギルドマスターである。
「まあ、これでもオレは一応ギルマスだし、ギラギラして目立つやつをつけてるってこともあって、よく覚えてるんだよ。それに、色んな男と日替わりで夜遊びしてるって噂もあるしな。歓楽街にほぼ毎日通ってるみたいだぜ? ありゃあ間違いなく太いバックがついてるな」
アレンは顎に手を当て記憶を探るような、ただどこか核心を突くような断定的な言い方をした。
「ほう……太いバックですか」
そう言われて真っ先に思いつくのは金使いの荒い貴族だったが、どのような手段を用いて単なる受付嬢が貴族と繋がりを持ち、高級なアクセサリーを買えるほどの大金を得ているのだろうか。
まだまだ不明点が多いな。
しかし、わかったこともある。
アレンのこと様子と口振りからして、彼はルーナと手を組んでいる黒幕的な何かではなさそうだ。
除外してもいいだろう。
嘘をついている様子も特になさそうだ。
「それよりマスターって、もしかして元々ルーナと親しい間柄だったりするのかい?」
アレンは疑いの余地を持つことなく、純粋な疑問をぶつけてきた。
本当に詳しいことを何も知らないらしい。
であれば、ここいらでこちらが持つ情報を開示して協力を仰いでみることにしよう。
「いえ、バーのマスターをやっていれば、様々な情報を自然と耳にするんですよ。例えば、ルーナさんが無知な初級冒険者を騙してわざと奴隷堕ちさせていたりとか……ですよね? シエル」
「え、えっ!? ここで私に振るの!?」
「……それは本当か?」
飛び跳ねて驚くシエルを横目に捉えたアレンは、ギロリと瞳を細めて息を吐いた。
おちゃらけた雰囲気から一転して、威厳のある重々しいものになる。
「ええ。彼女の名前はシエル。つい先日開かれた奴隷オークションから私が迎え入れた奴隷です。初級冒険者になってすぐにルーナさんとその御一行に騙されて、およそ一千万ゼニーの借金を背負わされています」
一介のバーのマスターがそんな奴隷を購入したら怪しまれると思い、俺は適当に言葉を変換させてアレンに真実を伝えた。
「一千万ゼニー!? おいおい、それが事実なら大問題だぜ? それに奴隷オークションって……成金の肥溜めスポットじゃねぇか。ルーナみたいなギルドの受付嬢からは程遠い場所だぜ」
そんな成金の肥溜めスポットである奴隷オークションの会場でシエルを購入しただなんて、口が裂けても言えない。
「ですが、シエルから聞いた話と私がルーナさんのリアクションを見た限りでは話の全ては真実に近いと思われます」
「はぁぁぁぁ……」
アレンは大きなため息を吐いて頭を抱えた。
まだ若そうに見えるのに、髪の毛には若干の白髪が混じっている。各所から重圧をかけられストレスの溜まる大変な仕事なのだろう。
リラックスを求めてバーに来てもらったのに申し訳ないな。
アレンはぐでっとだらしない格好でカウンターにもたれると、満足げな様子で頬を緩めていた。
「満足していただけたようで何よりです。お酒のおかわりはいかがなさいますか?」
「ん、ああ、頼む」
アレンがこちらにショットグラスを差し出してきたので、俺は流れるような手捌きでウイスキーを炭酸で割る。
彼はほんのり酒が回っているのか、顔がやや赤らんでいる。
「……ところで、アレン様」
「んぁ? どうした?」
「少し冒険者ギルドの受付嬢に関して聞きたいことがあるのですが、よろしいでしょうか?」
「いいぞ。なんだ、惚れた女でもいたか?」
俺の問いかけに対して、アレンはニヤニヤと悪どい笑みを浮かべて聞いてくる。
こうして話すと彼はごく普通のノリの良い若者にしか見えないが、一応警戒の念を解くことはしないでおく。
もし、万が一、アレンがあっち側の人間だった場合のことを考えて、慎重に探りを入れていく。
「いえ、実はルーナさんという金髪の方のことなのですが……」
「あー、ルーナねぇ……あいつぁちょっと変な噂も多いからオススメしないぜ?」
アレンは何か心当たりがあるのか、ぴくりと眉を顰めていた。
「変な噂ですか?」
「本当かどうかは知らねぇけど、色々と話を聞くぜ? 美人局みたいに冒険者の男を何人も唆して貢がせてるとか……まあ、受付嬢なのにあんな高級なアクセサリーをつけてたら不思議に思うのも無理はねぇ。ありゃあ相当なもんだぜ? ギルマスの俺でも何個も買えるもんじゃねぇな」
「そうなんですか」
「まあな。というか、マスター。隣に可愛いお嬢ちゃんがいるのに、他の女に手を出すつもりかい? ははっ、中々のプレイボーイだな!」
アレンは短く、それでいて甲高い声で笑うと、ぐいっとショットグラスを一気に煽った。
悪酔いはしないはずだが、酒に酔いやすいタイプなのか、すっかり楽しい気分になっているようだ。
また、いきなり可愛いと言われて悪い気はしていないのか、隣に立つシエルもどこか得意げな表情になっている。
単純すぎて困る。だから騙されるんだぞ?
まあいい。今なら何でも話してくれそうなので、適当に質問をぶつけていくことにするか。
「ちなみにですが……ルーナさんの装いや身につけるアクセサリーなどに違和感はございませんか?」
アレンがどこまで把握しているかはわからないが、この質問の答え次第で正解が導き出せるかもしれない。
「うーん……そう言われてみれば、大体半年に一回くらいの頻度でアクセサリーが増えてたり、変わってたりすることがあるな……」
「左様ですか。よく気が付きましたね」
ビンゴだ。一端の受付嬢の容姿の変化に気がつくとは、流石はギルドマスターである。
「まあ、これでもオレは一応ギルマスだし、ギラギラして目立つやつをつけてるってこともあって、よく覚えてるんだよ。それに、色んな男と日替わりで夜遊びしてるって噂もあるしな。歓楽街にほぼ毎日通ってるみたいだぜ? ありゃあ間違いなく太いバックがついてるな」
アレンは顎に手を当て記憶を探るような、ただどこか核心を突くような断定的な言い方をした。
「ほう……太いバックですか」
そう言われて真っ先に思いつくのは金使いの荒い貴族だったが、どのような手段を用いて単なる受付嬢が貴族と繋がりを持ち、高級なアクセサリーを買えるほどの大金を得ているのだろうか。
まだまだ不明点が多いな。
しかし、わかったこともある。
アレンのこと様子と口振りからして、彼はルーナと手を組んでいる黒幕的な何かではなさそうだ。
除外してもいいだろう。
嘘をついている様子も特になさそうだ。
「それよりマスターって、もしかして元々ルーナと親しい間柄だったりするのかい?」
アレンは疑いの余地を持つことなく、純粋な疑問をぶつけてきた。
本当に詳しいことを何も知らないらしい。
であれば、ここいらでこちらが持つ情報を開示して協力を仰いでみることにしよう。
「いえ、バーのマスターをやっていれば、様々な情報を自然と耳にするんですよ。例えば、ルーナさんが無知な初級冒険者を騙してわざと奴隷堕ちさせていたりとか……ですよね? シエル」
「え、えっ!? ここで私に振るの!?」
「……それは本当か?」
飛び跳ねて驚くシエルを横目に捉えたアレンは、ギロリと瞳を細めて息を吐いた。
おちゃらけた雰囲気から一転して、威厳のある重々しいものになる。
「ええ。彼女の名前はシエル。つい先日開かれた奴隷オークションから私が迎え入れた奴隷です。初級冒険者になってすぐにルーナさんとその御一行に騙されて、およそ一千万ゼニーの借金を背負わされています」
一介のバーのマスターがそんな奴隷を購入したら怪しまれると思い、俺は適当に言葉を変換させてアレンに真実を伝えた。
「一千万ゼニー!? おいおい、それが事実なら大問題だぜ? それに奴隷オークションって……成金の肥溜めスポットじゃねぇか。ルーナみたいなギルドの受付嬢からは程遠い場所だぜ」
そんな成金の肥溜めスポットである奴隷オークションの会場でシエルを購入しただなんて、口が裂けても言えない。
「ですが、シエルから聞いた話と私がルーナさんのリアクションを見た限りでは話の全ては真実に近いと思われます」
「はぁぁぁぁ……」
アレンは大きなため息を吐いて頭を抱えた。
まだ若そうに見えるのに、髪の毛には若干の白髪が混じっている。各所から重圧をかけられストレスの溜まる大変な仕事なのだろう。
リラックスを求めてバーに来てもらったのに申し訳ないな。