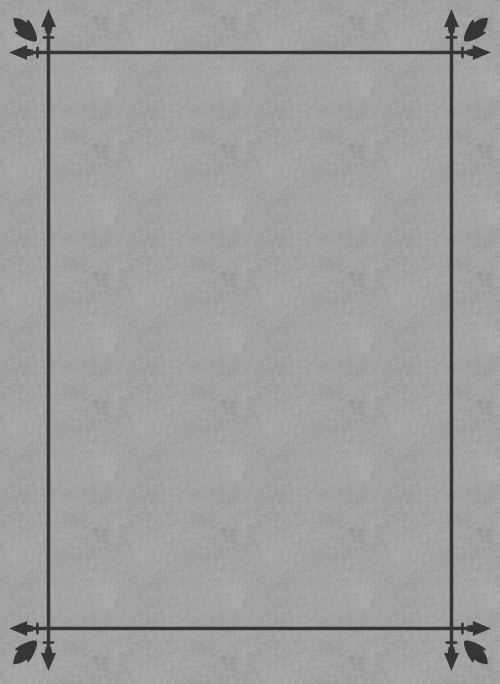「……」
すぐに閃いた俺は冷蔵庫の奥から大きな肉塊を取り出すと、静かにまな板の上に置いた。
そして、重さにして三百グラムほどの肉塊の上から、パラパラと塩胡椒を振りかけていく。
無駄な味付けは必要ない。
「おおっ! 肉だ!」
ちびちびお酒で口を潤していたアレンは、カウンター越しに肉塊を見て喜び混じりに驚いていた。
「ええ。結局はシンプルが一番だと思いましてね」
「よくわかってるじゃないか。ところで、それは何の肉だ? 牛や豚にしては筋張った無駄な脂身がかなり少ないように見えるが……」
アレンは肉塊を凝視しながら言った。
「こちらは子供のドラゴンのテール肉でございます。成長過程の途中のため、筋肉が少なく非常にジューシーな味わいになっております」
一般的に世間に出回る食肉は家畜化された牛や豚の肉になるが、冒険者はモンスターを食すことも少なくはない。
中でも子供のドラゴンはかなりの人気を博しているのだが、討伐が困難という理由で市場に流通することは滅多にない高級食材だ。
まあ、俺からすれば適当に魔法を撃ち込めば討伐できるし、彼らの尻尾は十数日程で再生するから手に入れるのは容易である。
余談だが、大人のドラゴンの肉は不味い。栄養価は高いのだが、筋肉が多すぎて固すぎるのでおすすめはしない。
「はぁ? お、おい。なんでそんな高級食材があるんだ? ギルマスのオレでさえ中々お目にかかれないんだぜ?」
「たまたま知り合いに譲ってもらったのですよ。それで……焼き方はいかがなさいますか? 私的にはカリッと香ばしく焼き上げるのをお勧め致しますが」
「たまたまねぇ……まあ、焼き方は任せるよ」
アレンははぐらかされたことが気になる様子だったが、同時に腹の虫を鳴いたからか特に追求はしてこなかった。
「かしこまりました。では……失礼致します。少々熱波が飛びますのでご注意ください」
俺はまな板の上に置かれる肉の上に右の掌を翳すと、すぐさま無詠唱で火の初級魔法を限定的な範囲で発動させ、肉全体を眩い炎で包み込んでいく。
「え?」
アレンがぽかんと口を開けて驚いていたが、俺は特に気にすることなく肉を火の魔法で焼き続けていった。
タイミングが命だ。肉の断面にしっかりと火を通し、表面にパリッとした焦げ目がつく絶好のタイミングを見逃してはならない。
「……」
やがて十秒ほど経過した頃、絶好のタイミングで俺は魔法を解くと、丁寧に分厚く切り分けていき、あらかじめ用意していた木製の皿の上に盛り付けた。
ちなみに、隣に立つシエルは口をあんぐりと開けて言葉を失っている。他の物に引火させることなく、肉塊のみを焼いた火魔法に驚いたのだろうか?
別にこれくらいはお手のものだ。
少し魔法をかじっていれば簡単にできると思う。
「……お待たせ致しました。ドラゴンのテール肉でございます。簡単に塩胡椒のみで味付けしておりますので、どうぞそのまま召し上がってください」
俺は丁寧な所作でアレンの前に皿を置き、併せてナイフとフォークを差し出した。
「っ……やべぇな、これ」
彼はごくりと唾を飲み込み、ステーキを見ながら舌なめずりをした。
立ち上がる香ばしい湯気は鼻腔の奥まで侵入し、誰であろうと空腹にしてしまうことだろう。
「どうぞ。お召し上がりください」
俺が微笑みかけると、アレンは右手に持ったフォークでステーキを突き刺し、ゆっくりと自身の口に運んでいった。
刹那。彼は目玉が飛び出そうなほど瞳を見開いた。
「っ!!」
一瞬にして肉の旨み自身の体を支配されたのか、アレンはそれから何も言葉を発することなく、無我夢中で手を動かしステーキを頬張続けていた。
満足していただけたようで何より。
さて、この間にシエルにはまな板と包丁を洗ってもらおうかな。
「シエル、これを頼む」
「……あ、う、うん!」
シエルはハッと我に返ると、洗い場に置かれたまな板と包丁をスポンジで洗い始めた。
手際は悪くない。少しばかりドジなところがあるが、愛嬌はあるし愛想も良いので問題ないだろう。
それにしても、たまたま子供のドラゴンの肉が手元にあって良かったな。アレンには少しばかり聞きたいこともあったし、料理で気分を昂らせた隙に質問を投げかけてみるとしよう。
すぐに閃いた俺は冷蔵庫の奥から大きな肉塊を取り出すと、静かにまな板の上に置いた。
そして、重さにして三百グラムほどの肉塊の上から、パラパラと塩胡椒を振りかけていく。
無駄な味付けは必要ない。
「おおっ! 肉だ!」
ちびちびお酒で口を潤していたアレンは、カウンター越しに肉塊を見て喜び混じりに驚いていた。
「ええ。結局はシンプルが一番だと思いましてね」
「よくわかってるじゃないか。ところで、それは何の肉だ? 牛や豚にしては筋張った無駄な脂身がかなり少ないように見えるが……」
アレンは肉塊を凝視しながら言った。
「こちらは子供のドラゴンのテール肉でございます。成長過程の途中のため、筋肉が少なく非常にジューシーな味わいになっております」
一般的に世間に出回る食肉は家畜化された牛や豚の肉になるが、冒険者はモンスターを食すことも少なくはない。
中でも子供のドラゴンはかなりの人気を博しているのだが、討伐が困難という理由で市場に流通することは滅多にない高級食材だ。
まあ、俺からすれば適当に魔法を撃ち込めば討伐できるし、彼らの尻尾は十数日程で再生するから手に入れるのは容易である。
余談だが、大人のドラゴンの肉は不味い。栄養価は高いのだが、筋肉が多すぎて固すぎるのでおすすめはしない。
「はぁ? お、おい。なんでそんな高級食材があるんだ? ギルマスのオレでさえ中々お目にかかれないんだぜ?」
「たまたま知り合いに譲ってもらったのですよ。それで……焼き方はいかがなさいますか? 私的にはカリッと香ばしく焼き上げるのをお勧め致しますが」
「たまたまねぇ……まあ、焼き方は任せるよ」
アレンははぐらかされたことが気になる様子だったが、同時に腹の虫を鳴いたからか特に追求はしてこなかった。
「かしこまりました。では……失礼致します。少々熱波が飛びますのでご注意ください」
俺はまな板の上に置かれる肉の上に右の掌を翳すと、すぐさま無詠唱で火の初級魔法を限定的な範囲で発動させ、肉全体を眩い炎で包み込んでいく。
「え?」
アレンがぽかんと口を開けて驚いていたが、俺は特に気にすることなく肉を火の魔法で焼き続けていった。
タイミングが命だ。肉の断面にしっかりと火を通し、表面にパリッとした焦げ目がつく絶好のタイミングを見逃してはならない。
「……」
やがて十秒ほど経過した頃、絶好のタイミングで俺は魔法を解くと、丁寧に分厚く切り分けていき、あらかじめ用意していた木製の皿の上に盛り付けた。
ちなみに、隣に立つシエルは口をあんぐりと開けて言葉を失っている。他の物に引火させることなく、肉塊のみを焼いた火魔法に驚いたのだろうか?
別にこれくらいはお手のものだ。
少し魔法をかじっていれば簡単にできると思う。
「……お待たせ致しました。ドラゴンのテール肉でございます。簡単に塩胡椒のみで味付けしておりますので、どうぞそのまま召し上がってください」
俺は丁寧な所作でアレンの前に皿を置き、併せてナイフとフォークを差し出した。
「っ……やべぇな、これ」
彼はごくりと唾を飲み込み、ステーキを見ながら舌なめずりをした。
立ち上がる香ばしい湯気は鼻腔の奥まで侵入し、誰であろうと空腹にしてしまうことだろう。
「どうぞ。お召し上がりください」
俺が微笑みかけると、アレンは右手に持ったフォークでステーキを突き刺し、ゆっくりと自身の口に運んでいった。
刹那。彼は目玉が飛び出そうなほど瞳を見開いた。
「っ!!」
一瞬にして肉の旨み自身の体を支配されたのか、アレンはそれから何も言葉を発することなく、無我夢中で手を動かしステーキを頬張続けていた。
満足していただけたようで何より。
さて、この間にシエルにはまな板と包丁を洗ってもらおうかな。
「シエル、これを頼む」
「……あ、う、うん!」
シエルはハッと我に返ると、洗い場に置かれたまな板と包丁をスポンジで洗い始めた。
手際は悪くない。少しばかりドジなところがあるが、愛嬌はあるし愛想も良いので問題ないだろう。
それにしても、たまたま子供のドラゴンの肉が手元にあって良かったな。アレンには少しばかり聞きたいこともあったし、料理で気分を昂らせた隙に質問を投げかけてみるとしよう。