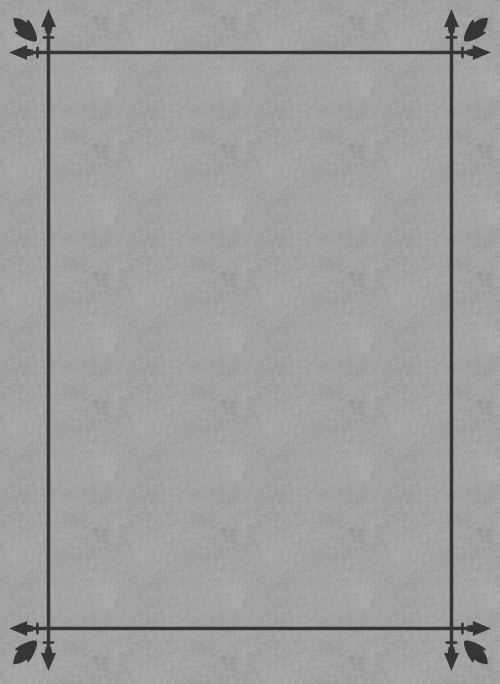目の前の光景は、まるでモンスターに蹂躙された森林のように散らかっていた。
脚の折れた椅子。
割れたグラス。
テーブルの上に溢れた大量の水。
「……どうしてこうなった」
間接照明に照らされる店内で、俺はポツリと呟いた。
食事を終えてから、シエルには洗い物と店内の掃除を任せていたはずだが……何をどうすればこんな惨状になるんだ?
「うぅぅ……ごめんなさい。私、実は不器用だからこういう細かい作業は苦手なの……それに、まだ緊張していてあまり上手くできなくて」
しゅんとして顔に影を落とすシエルは申し訳なさそうな様子で言った。
奴隷オークションにかけられた際のベージュ色の肌着の上から、黒い無地のエプロンを身につけており、手には箒が握られている。
「そうか……」
あまりの惨状にかける言葉が見つからない。
俺が彼女に任せたのは、簡単な床の掃き掃除と食器洗い、そしてグラス磨き、それだけだ。
不器用とかいうレベルを超えているような気がする。ほんの少し目を離した隙にとんでもないことになっていた。まあ、事情が事情なので今後少しずつ慣れていけば問題ないだろう。
「でも、私、マスターのために一生懸命頑張るから!」
シエルは箒を強く握りしめながら意気込んだ。
「よし。今日のところは細かい作業は全て俺がやる。いいな?」
「う、うん。じゃあ、私は何をすればいい?」
「そうだな。得意なことはあるか?」
「えーっと……なんだろう……?」
俺の質問に対してシエルは顎に手を当てて考えていたが、特に何も思いつかないらしい。
まだまだ自分の強みを知らないらしい。
「元々は魔法使いだろ?」
俺は断定的な問いを投げかけた。
シエルは冒険者ギルドで無償で支給される初心者魔法使い御用達のローブを着ていた。それに、胸元には僅かに膨らみがあったので、おそらくそこには短杖を持っていたと思う。
簡単な推理と答え合わせだった。
「え? 何で知ってるの!?」
「あー、まあ……何となく。勘だよ、勘。それで、どうして魔法使いなんてやってたんだ? 不向きなことくらい自分が一番よく分かっていたんじゃないか?」
俺は適当に誤魔化すと、核心に迫る聞き方をした。
少々嫌がられる問いであることは間違いないが、シエルの事を知るためなので我慢する。
「え……その、やっぱり向いてなかったのかな……」
「まず第一に、誰もが知っている程の一流の魔法使いたちは当たり前のように魔法をバンバン放っているが、実は簡単なことじゃない。魔法を放つ為には莫大な魔力の消費と魔法に関する知識の蓄積が必要不可欠なんだ。次に、体内の魔力を属性や形に変えて顕現させる為には、それ相応の器用さも求められる。まあ、簡単に言えば、魔法を扱うのは難しいってことだ」
“向いてない”という言葉一つで片付けてしまうのは好ましくないが、シエルに限っては魔法のセンスを全く感じなかった。
賢者と呼ばれていた俺だからこそすぐにわかったが、彼女には魔法使いとして必要な要素が全てが欠落している。
「……確かに私って魔法使いに憧れてギルドでローブをもらって安い杖も買ったんだけど、一度も魔法を使えたことなんてなかったの。それって、器用さと賢さが足りなかったってこと?」
「概ねその通りだ。魔法というのは生まれ持った才能にも左右されやすいからこそ希少なんだ。パーティーでは重宝されるし、少しでも魔法が使えれば引く手数多だな」
俺が続け様に説明すると、シエルは感心したように何度も首を縦に振っていたが、途端にハッとして目を開く。
脚の折れた椅子。
割れたグラス。
テーブルの上に溢れた大量の水。
「……どうしてこうなった」
間接照明に照らされる店内で、俺はポツリと呟いた。
食事を終えてから、シエルには洗い物と店内の掃除を任せていたはずだが……何をどうすればこんな惨状になるんだ?
「うぅぅ……ごめんなさい。私、実は不器用だからこういう細かい作業は苦手なの……それに、まだ緊張していてあまり上手くできなくて」
しゅんとして顔に影を落とすシエルは申し訳なさそうな様子で言った。
奴隷オークションにかけられた際のベージュ色の肌着の上から、黒い無地のエプロンを身につけており、手には箒が握られている。
「そうか……」
あまりの惨状にかける言葉が見つからない。
俺が彼女に任せたのは、簡単な床の掃き掃除と食器洗い、そしてグラス磨き、それだけだ。
不器用とかいうレベルを超えているような気がする。ほんの少し目を離した隙にとんでもないことになっていた。まあ、事情が事情なので今後少しずつ慣れていけば問題ないだろう。
「でも、私、マスターのために一生懸命頑張るから!」
シエルは箒を強く握りしめながら意気込んだ。
「よし。今日のところは細かい作業は全て俺がやる。いいな?」
「う、うん。じゃあ、私は何をすればいい?」
「そうだな。得意なことはあるか?」
「えーっと……なんだろう……?」
俺の質問に対してシエルは顎に手を当てて考えていたが、特に何も思いつかないらしい。
まだまだ自分の強みを知らないらしい。
「元々は魔法使いだろ?」
俺は断定的な問いを投げかけた。
シエルは冒険者ギルドで無償で支給される初心者魔法使い御用達のローブを着ていた。それに、胸元には僅かに膨らみがあったので、おそらくそこには短杖を持っていたと思う。
簡単な推理と答え合わせだった。
「え? 何で知ってるの!?」
「あー、まあ……何となく。勘だよ、勘。それで、どうして魔法使いなんてやってたんだ? 不向きなことくらい自分が一番よく分かっていたんじゃないか?」
俺は適当に誤魔化すと、核心に迫る聞き方をした。
少々嫌がられる問いであることは間違いないが、シエルの事を知るためなので我慢する。
「え……その、やっぱり向いてなかったのかな……」
「まず第一に、誰もが知っている程の一流の魔法使いたちは当たり前のように魔法をバンバン放っているが、実は簡単なことじゃない。魔法を放つ為には莫大な魔力の消費と魔法に関する知識の蓄積が必要不可欠なんだ。次に、体内の魔力を属性や形に変えて顕現させる為には、それ相応の器用さも求められる。まあ、簡単に言えば、魔法を扱うのは難しいってことだ」
“向いてない”という言葉一つで片付けてしまうのは好ましくないが、シエルに限っては魔法のセンスを全く感じなかった。
賢者と呼ばれていた俺だからこそすぐにわかったが、彼女には魔法使いとして必要な要素が全てが欠落している。
「……確かに私って魔法使いに憧れてギルドでローブをもらって安い杖も買ったんだけど、一度も魔法を使えたことなんてなかったの。それって、器用さと賢さが足りなかったってこと?」
「概ねその通りだ。魔法というのは生まれ持った才能にも左右されやすいからこそ希少なんだ。パーティーでは重宝されるし、少しでも魔法が使えれば引く手数多だな」
俺が続け様に説明すると、シエルは感心したように何度も首を縦に振っていたが、途端にハッとして目を開く。