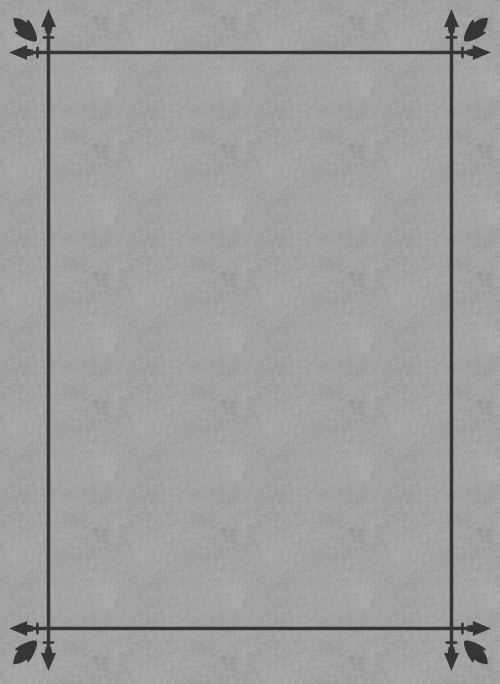「———いらっしゃいませ」
間接照明のみが照らす薄暗くシックな雰囲気が特徴的な店内に、静かだがよく通る声を響かせて、大切なお客様を暖かく迎え入れる。
「……」
「お好きな席にどうぞ」
誰もいない店内をキョロキョロと見渡している女性に、適当な席への着席を促す。
「……悲しい気持ちを忘れたいの。おまかせで頼めるかしら?」
女性は俺の目の前———カウンター席の真ん中に座ると、儚げな表情で言葉を紡いだ。
「かしこまりました。少々お待ちください」
「ここはいつできたお店?」
「つい一月ほど前に開店致しました」
俺は酒や果実水を適当な比率で混ぜ合わせながらも、丁寧に受け答えをしていく。
「ふーん。良い雰囲気ね。呼び方はマスターでいいのかしら?」
「嬉しいことに、皆様は私のことをマスターと呼んでくださいます」
俺は幼少の頃からバーのマスターに憧れていたので、マスターと呼んでもらうと心が躍る。
「そう……」
「———こちら、ブルージェイズです」
俺はテーブルに滑らせるようにして、女性の前に真っ青なカクテルが注がれたグラスを置いた。
小さな泡を立てる微炭酸は青く透き通っており、見ているだけで心が落ち着く。
「ありがとう。ちなみに、これにはどういう意味があるの?」
「『悲しみを乗り越えるよりも、悲しみと同居した方が楽』とでも言ったところでしょうか」
自身に降りかかる悲しみを無理に乗り越えるのが辛いのなら、そういうものだと割り切ってしまえ、ということだ。
本来は飲み物一つ一つに意味などはないが、俺が独断と偏見で意味を持たせている。
色や味わい、香りを参考にして、丁寧に考え抜いたものだ。
「……今の私にピッタリね———それに、とても上品で美味しい」
女性はグラスに口をつけると、満足そうに小さく笑った。
「ありがとうございます」
そんな女性の笑顔を見て俺も嬉しくなり、ついつい微笑み軽く頭を下げる。
「そういえば、このバーはなんという名前なの? 失礼だけど、裏路地で分かりにくいし、看板もなかったわよね」
よほど口にあったのか、女性はブルージェイズ大事そうに飲みながらも、おもむろに聞いてきた。
「ここは【ハイドアウト】です。是非、喧騒から逃れてゆっくりしていってください」
俺が王都の路地裏に構えるバーの名前は【ハイドアウト】。
一月前にSランクパーティーを追放されたことで始めた憧れのバーだった。
間接照明のみが照らす薄暗くシックな雰囲気が特徴的な店内に、静かだがよく通る声を響かせて、大切なお客様を暖かく迎え入れる。
「……」
「お好きな席にどうぞ」
誰もいない店内をキョロキョロと見渡している女性に、適当な席への着席を促す。
「……悲しい気持ちを忘れたいの。おまかせで頼めるかしら?」
女性は俺の目の前———カウンター席の真ん中に座ると、儚げな表情で言葉を紡いだ。
「かしこまりました。少々お待ちください」
「ここはいつできたお店?」
「つい一月ほど前に開店致しました」
俺は酒や果実水を適当な比率で混ぜ合わせながらも、丁寧に受け答えをしていく。
「ふーん。良い雰囲気ね。呼び方はマスターでいいのかしら?」
「嬉しいことに、皆様は私のことをマスターと呼んでくださいます」
俺は幼少の頃からバーのマスターに憧れていたので、マスターと呼んでもらうと心が躍る。
「そう……」
「———こちら、ブルージェイズです」
俺はテーブルに滑らせるようにして、女性の前に真っ青なカクテルが注がれたグラスを置いた。
小さな泡を立てる微炭酸は青く透き通っており、見ているだけで心が落ち着く。
「ありがとう。ちなみに、これにはどういう意味があるの?」
「『悲しみを乗り越えるよりも、悲しみと同居した方が楽』とでも言ったところでしょうか」
自身に降りかかる悲しみを無理に乗り越えるのが辛いのなら、そういうものだと割り切ってしまえ、ということだ。
本来は飲み物一つ一つに意味などはないが、俺が独断と偏見で意味を持たせている。
色や味わい、香りを参考にして、丁寧に考え抜いたものだ。
「……今の私にピッタリね———それに、とても上品で美味しい」
女性はグラスに口をつけると、満足そうに小さく笑った。
「ありがとうございます」
そんな女性の笑顔を見て俺も嬉しくなり、ついつい微笑み軽く頭を下げる。
「そういえば、このバーはなんという名前なの? 失礼だけど、裏路地で分かりにくいし、看板もなかったわよね」
よほど口にあったのか、女性はブルージェイズ大事そうに飲みながらも、おもむろに聞いてきた。
「ここは【ハイドアウト】です。是非、喧騒から逃れてゆっくりしていってください」
俺が王都の路地裏に構えるバーの名前は【ハイドアウト】。
一月前にSランクパーティーを追放されたことで始めた憧れのバーだった。