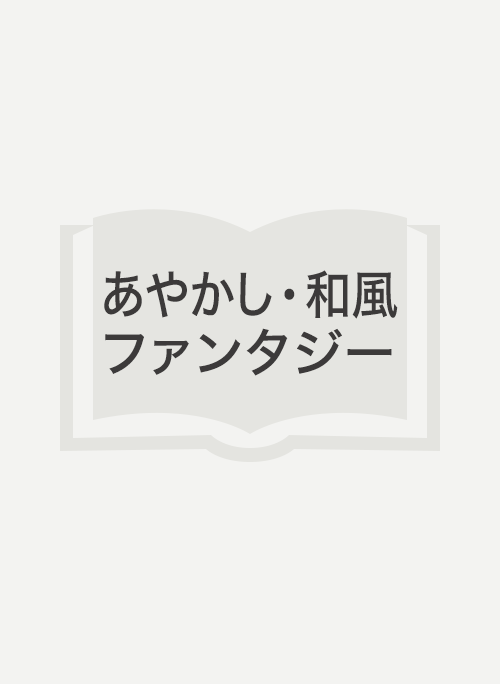「夢を渡って君に逢いに来た」
その言葉を聞いて綺世の腕の中にいた那美は大きく目を見開いた。
夢の中で『逢いに行くから待っていて』という彼の言葉。
それは叶わぬ希望なのだと諦めていて信じられずにいた。
今まで那美に優しくしてくれたのに。
沢山の想いを伝えてくれていたのに。
自分自身が愚かで情けなく感じて痩せた白い頬に一筋の涙が流れる。
「……那美?」
那美が泣いていることに気がついた綺世は抱きしめている腕の力を緩め、彼女の顔を覗き込む。
胸の中の想いを精いっぱい彼に伝えたくて震える唇を開く。
「夢の中で綺世さまが迎えに行くと仰ってくださったのにわたし、信じられなくて……。申し訳、ありません……」
消え入りそうな声だった。
一つ一つの言葉を紡ぐたびに涙が溢れる。
驚き、嬉しさ、罪悪感。
様々な感情が押し寄せる。
こんな自分など嫌いになっただろうか。
ただ、大切な彼には嘘はつきたくない、正直な自分でいたかった。
時間も冷たい夜風も家族の出迎えも今だけは忘れて伝えたい──。
(綺世の表情を見られない)
顔を上げて、確かめるのが怖くて俯き続ける。
「那美は私が怒っていると思ったのか?」
「だ、だって……」
無意識に顔を上げると、そこには花のように穏やかな綺世がいた。
予想外の反応に那美の身体はぴたりと止まる。
綺世は那美の頬に手を伸ばすと人差し指で涙をすくった。
「謝る必要はない。むしろ悪いのは私だ。那美に全てを話さなかったから」
「全て、ですか?」
夢の中での彼との会話を思い出す。
確かに綺世がどのような暮らしと仕事をしているのか知らない。
普段から那美がつらい生活を送っていることを知って励ますような楽しい話をして気遣ってくれた。
それに夢で逢える頻度はそんなに多いわけではないし、時間も短い。
那美自身も深く考えなかったし、彼なりの優しさが純粋に嬉しかった。
しかし綺世はそれだけが理由ではないようで──。
不思議そうな表情を浮かべ、首を傾げる那美に小さく頷いた。
「夢の中で私が白龍であると那美に伝えたら二度と夢でも現実でも逢えなくなるという龍の掟があるんだ。愛しい君を必ず迎えに行きたかったから、今まで黙っていた。すまない」
眉を下げ、つらそうな瞳をしている綺世を見て胸が苦しくなった。
「綺世さまこそ謝らないでください。守るべき掟があったのですから。それにこうして現実でもお逢いできて、わたしは嬉しいです」
「那美……」
ほんのりと頬を染め、笑みを浮かべる那美を見て綺世は安心したように小さく息をついた。
自然と見つめ合う形になり、途端に恥ずかしくなった那美は慌てて視線を逸らして次の話題を探す。
(えっと……。あ、そういえば)
那美は先日の綺世の別れ際の言葉を思い出す。
もし次に逢ったら質問しようと思っていたこと。
「どうかしたか?」
「あ、あの綺世さま。お聞きしたいことが──」
「確か、こっちに……!」
質問をしようとした矢先、慌ただしい足音が聞こえる。
すると血相を変えた両親と美桜が中庭に姿を現した。
「あ……」
出迎えを忘れていた那美は、また怒られてしまうと怖くなり綺世から距離をとった。
怯えている那美を見た綺世は三人から守るように立つ。
彼らは無能な那美など眼中にないようで綺世しか見ていない。
そして父がおそるおそる口を開き、問う。
「あ、貴方さまはもしかして……」
「私は龍王の一人、白龍の綺世。此度は那美を私の花嫁として迎えに来た」
「那美が白龍さまの花嫁……!?」
よほど衝撃を受けたのか普段は物静かな父が珍しく大声を出す。
そこでようやく、三人は那美の存在にも気がついたようで驚きに目を見開いたあと、彼女に視線を向けた。
「ですが白龍さま!先ほど龍夜の儀を執り行ったのは那美の姉である私です!何かの間違いでは……!」
「それに娘は巫女としての力がありませんわ。小さな式神でさえ動かせないのです」
まさか無能の那美が花嫁に選ばれるとは思ってもいなかったのか、美桜と継母も焦りながら口早に言葉を続ける。
(お姉さまたちが仰った通り何故、綺世さまはどうしてわたしを花嫁だと……)
三人がこちらに来る直前に那美が綺世に問おうとしたのは夢の中での『花嫁』という言葉の意味だ。
綺世が白龍だと知った今、巫女の力がない自分が選ばれる理由が分からない。
俯いていた那美は答えを聞きたくて目の前に立つ後ろ姿の綺世をそっと見つめた。
綺世は冷酷な眼差しで三人を見据えると全てを話し始めた──。
その言葉を聞いて綺世の腕の中にいた那美は大きく目を見開いた。
夢の中で『逢いに行くから待っていて』という彼の言葉。
それは叶わぬ希望なのだと諦めていて信じられずにいた。
今まで那美に優しくしてくれたのに。
沢山の想いを伝えてくれていたのに。
自分自身が愚かで情けなく感じて痩せた白い頬に一筋の涙が流れる。
「……那美?」
那美が泣いていることに気がついた綺世は抱きしめている腕の力を緩め、彼女の顔を覗き込む。
胸の中の想いを精いっぱい彼に伝えたくて震える唇を開く。
「夢の中で綺世さまが迎えに行くと仰ってくださったのにわたし、信じられなくて……。申し訳、ありません……」
消え入りそうな声だった。
一つ一つの言葉を紡ぐたびに涙が溢れる。
驚き、嬉しさ、罪悪感。
様々な感情が押し寄せる。
こんな自分など嫌いになっただろうか。
ただ、大切な彼には嘘はつきたくない、正直な自分でいたかった。
時間も冷たい夜風も家族の出迎えも今だけは忘れて伝えたい──。
(綺世の表情を見られない)
顔を上げて、確かめるのが怖くて俯き続ける。
「那美は私が怒っていると思ったのか?」
「だ、だって……」
無意識に顔を上げると、そこには花のように穏やかな綺世がいた。
予想外の反応に那美の身体はぴたりと止まる。
綺世は那美の頬に手を伸ばすと人差し指で涙をすくった。
「謝る必要はない。むしろ悪いのは私だ。那美に全てを話さなかったから」
「全て、ですか?」
夢の中での彼との会話を思い出す。
確かに綺世がどのような暮らしと仕事をしているのか知らない。
普段から那美がつらい生活を送っていることを知って励ますような楽しい話をして気遣ってくれた。
それに夢で逢える頻度はそんなに多いわけではないし、時間も短い。
那美自身も深く考えなかったし、彼なりの優しさが純粋に嬉しかった。
しかし綺世はそれだけが理由ではないようで──。
不思議そうな表情を浮かべ、首を傾げる那美に小さく頷いた。
「夢の中で私が白龍であると那美に伝えたら二度と夢でも現実でも逢えなくなるという龍の掟があるんだ。愛しい君を必ず迎えに行きたかったから、今まで黙っていた。すまない」
眉を下げ、つらそうな瞳をしている綺世を見て胸が苦しくなった。
「綺世さまこそ謝らないでください。守るべき掟があったのですから。それにこうして現実でもお逢いできて、わたしは嬉しいです」
「那美……」
ほんのりと頬を染め、笑みを浮かべる那美を見て綺世は安心したように小さく息をついた。
自然と見つめ合う形になり、途端に恥ずかしくなった那美は慌てて視線を逸らして次の話題を探す。
(えっと……。あ、そういえば)
那美は先日の綺世の別れ際の言葉を思い出す。
もし次に逢ったら質問しようと思っていたこと。
「どうかしたか?」
「あ、あの綺世さま。お聞きしたいことが──」
「確か、こっちに……!」
質問をしようとした矢先、慌ただしい足音が聞こえる。
すると血相を変えた両親と美桜が中庭に姿を現した。
「あ……」
出迎えを忘れていた那美は、また怒られてしまうと怖くなり綺世から距離をとった。
怯えている那美を見た綺世は三人から守るように立つ。
彼らは無能な那美など眼中にないようで綺世しか見ていない。
そして父がおそるおそる口を開き、問う。
「あ、貴方さまはもしかして……」
「私は龍王の一人、白龍の綺世。此度は那美を私の花嫁として迎えに来た」
「那美が白龍さまの花嫁……!?」
よほど衝撃を受けたのか普段は物静かな父が珍しく大声を出す。
そこでようやく、三人は那美の存在にも気がついたようで驚きに目を見開いたあと、彼女に視線を向けた。
「ですが白龍さま!先ほど龍夜の儀を執り行ったのは那美の姉である私です!何かの間違いでは……!」
「それに娘は巫女としての力がありませんわ。小さな式神でさえ動かせないのです」
まさか無能の那美が花嫁に選ばれるとは思ってもいなかったのか、美桜と継母も焦りながら口早に言葉を続ける。
(お姉さまたちが仰った通り何故、綺世さまはどうしてわたしを花嫁だと……)
三人がこちらに来る直前に那美が綺世に問おうとしたのは夢の中での『花嫁』という言葉の意味だ。
綺世が白龍だと知った今、巫女の力がない自分が選ばれる理由が分からない。
俯いていた那美は答えを聞きたくて目の前に立つ後ろ姿の綺世をそっと見つめた。
綺世は冷酷な眼差しで三人を見据えると全てを話し始めた──。