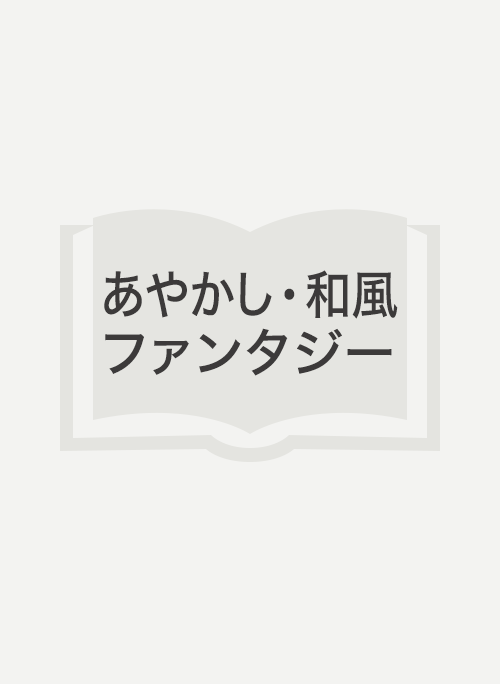それから数日後──。
夜空には大きく冴えて、眩いほどの光を放つ満月が浮かんでいる。
澄宮家の敷地内にある神楽殿に巫女装束を身に纏った美桜と継母の葉月、父の義郎が立っている。
『龍夜の儀』
満月が浮かんだ夜は巫女たちは天界に住まう龍に向けて祈りと舞を捧げる。
この儀式は古くからの伝統で長きに渡ってこの国を守ってきた大切な行事だ。
無能な那美は近くで見ることも許されず、神聖な場が穢れるからと、その夜は屋敷から出ることを禁じられている。
(ここの窓から少しだけ見えるわ)
自室で洗濯物を畳んでいると僅かに開いた障子から遠くに神楽殿と三人が見える。
那美の実母である雪葉が亡くなる前、舞を習ったことがある。
父は無能な娘に舞を教えても無駄だと怒っていたが、雪葉はそれに負けずに優しく手取り足取り指導してくれた。
要領の悪い那美はいつまでも下手だったが姉の美桜の舞は見蕩れるほど美しかった。
普段は意地悪だがその時だけはそれを忘れるほど魅入ってしまう。
(きっと龍さまの花嫁に選ばれるのもすぐね。もしかしたら龍王さまかも……)
龍たちの頂点である龍王の存在が那美の頭に浮かぶ。
黄龍、青龍、赤龍、黒龍、そして白龍。
圧倒的な力を持つ彼らは天帝に仕え、眷属である龍たちの取りまとめも務めている。
巫女は充分な力が身につくと龍の花嫁に選ばれる。
舞と月の導きによって選ばれた巫女は一生、愛され何不自由なく幸せに暮らせるという。
しかし龍王の花嫁になればその比ではない。
豊潤な富に注ぎ込まれる愛、絶対的な権力、極上の幸せ。
龍に選ばれるだけでも大変名誉なことだが、どんな巫女も是非とも龍王の花嫁に、と願うものだ。
(きっとお姉さまは女学院を卒業したら龍さまか龍王さまに嫁いで家を出る。幸せな未来が待っている。それじゃあ、わたしは……?)
遠くを見据えると神楽殿で舞っている美桜の姿が分かる。
美しいと思うと同時に胸が切なくなった。
那美も高校を卒業するまでは澄宮家で使用人の扱いを受けるだろう。
ただその後が分からない。
きっと進学などもってのほか。
(遠い地に就職すればこの生活からも抜け出せるかもしれない)
それが那美にとって最善なのだが両親がそれを許すかどうか不明だ。
もしかしたら澄宮家の正式な使用人として一生働けと言われるかもしれないと嫌な想像をしてしまう。
俯きかけたとき、微かな鈴の音が耳に届く。
不幸な未来が待っているのなら家族がいない、この時間だけは。
(少しだけ──)
那美は畳んだ洗濯物を箪笥に入れると部屋の中心に立つ。
静かに深呼吸をすると幼い記憶をたぐり寄せ、舞い始めた。
たどたどしい舞は誰がどう見ても見てはいられないものだろう。
時々振りを間違いながらも那美は続ける。
(鈴の音が聞こえるこの時だけは舞っていたい)
次の『龍夜の儀』は当分先だ。
それまでは、こうして一人でゆっくりと過ごす時間もない。
きっと姉の舞を見て両親は柔やかで誇らしく思っているだろう。
それとは真逆に何とも寂しい部屋の明かりだけが那美を照らしている。
しかしその状況でも不思議と何故か心が弾んだ。
(どうしてかしら。久しぶりに舞えたから?)
微笑みながらそっと目を閉じると、ふと脳裏に綺世の顔が浮かぶ。
「え……?」
那美は突然のことに驚き、思わず足を止める。
(どうして綺世さまが?)
一瞬、夢で逢っただけの彼の姿がはっきりと見えたのだ。
起きている時間でのこんな現象は初めてで戸惑う。
同じタイミングで鳴り続けていた鈴の音が終わる。
慌てて窓から外の様子を見ると龍夜の儀を終えた三人が屋敷に戻ってくるのが分かった。
(急いでお出迎えをしないと!)
必ず家族が帰宅するときは使用人総出で出迎えなければいけない。
もちろん那美もだ。
勢いよく襖を開けた瞬間、夜空に浮かんだ満月が一層、眩しい光を放った。
「え……?」
その月光は一直線に那美の部屋の前にある中庭のみを照らす。
花壇がある他の家族の中庭とは違う、何とも殺風景な場所だ。
普段ならば。
しかし今は手入れしきれていない雑草も偶然に咲いた小さな花も冴えていて息を飲むほど美しかった。
「これは一体……」
中庭用のサンダルに履き替えて外に出る。
空を見上げ、差し込む眩い光に耐えきれず手をかざしたとき──。
一体の龍がこちらに降りてくるのが分かった。
目の前で起こる全てが信じられないが、『龍夜の儀』・『巫女の舞』という言葉が線のように繋がる。
(もしかしてお姉さまの舞を見初めて花嫁として迎えに来られたの?でもそれなら神楽殿に光が差すはず)
困惑している間にも龍はどんどんとこちらへ向かってくる。
そしてついに那美の目の前にふわりと降り立つ。
白く輝く鱗に宝石のような赤い瞳。
初めて見る高貴な姿に圧倒されながらもすぐに分かった。
「白龍さま……」
そう。
紛れもなく龍たちの頂点に君臨する龍王、白龍だ。
白龍は那美の呟きを聞いて瞳を細める。
(あれ?この瞳どこかで……)
龍にましてや龍王に会う機会などないと思っていたのに既視感を覚える。
「私だ。那美」
「え?」
白龍が口を開いて初対面のはずの那美の名前を呼ぶ。
それは何度も聞いた大好きな声で──。
白龍の周りが光で包まれたかと思うと一瞬にして人の姿に変わる。
「あ、やせさま……?」
途切れ途切れの問いかけにも嬉しそうに頷く人物は綺世だった。
綺世はゆっくりと那美に歩み寄ると小さな身体を抱きしめた。
そして耳元に唇を近づけて囁く。
「夢を渡って君に逢いに来た」
夜空には大きく冴えて、眩いほどの光を放つ満月が浮かんでいる。
澄宮家の敷地内にある神楽殿に巫女装束を身に纏った美桜と継母の葉月、父の義郎が立っている。
『龍夜の儀』
満月が浮かんだ夜は巫女たちは天界に住まう龍に向けて祈りと舞を捧げる。
この儀式は古くからの伝統で長きに渡ってこの国を守ってきた大切な行事だ。
無能な那美は近くで見ることも許されず、神聖な場が穢れるからと、その夜は屋敷から出ることを禁じられている。
(ここの窓から少しだけ見えるわ)
自室で洗濯物を畳んでいると僅かに開いた障子から遠くに神楽殿と三人が見える。
那美の実母である雪葉が亡くなる前、舞を習ったことがある。
父は無能な娘に舞を教えても無駄だと怒っていたが、雪葉はそれに負けずに優しく手取り足取り指導してくれた。
要領の悪い那美はいつまでも下手だったが姉の美桜の舞は見蕩れるほど美しかった。
普段は意地悪だがその時だけはそれを忘れるほど魅入ってしまう。
(きっと龍さまの花嫁に選ばれるのもすぐね。もしかしたら龍王さまかも……)
龍たちの頂点である龍王の存在が那美の頭に浮かぶ。
黄龍、青龍、赤龍、黒龍、そして白龍。
圧倒的な力を持つ彼らは天帝に仕え、眷属である龍たちの取りまとめも務めている。
巫女は充分な力が身につくと龍の花嫁に選ばれる。
舞と月の導きによって選ばれた巫女は一生、愛され何不自由なく幸せに暮らせるという。
しかし龍王の花嫁になればその比ではない。
豊潤な富に注ぎ込まれる愛、絶対的な権力、極上の幸せ。
龍に選ばれるだけでも大変名誉なことだが、どんな巫女も是非とも龍王の花嫁に、と願うものだ。
(きっとお姉さまは女学院を卒業したら龍さまか龍王さまに嫁いで家を出る。幸せな未来が待っている。それじゃあ、わたしは……?)
遠くを見据えると神楽殿で舞っている美桜の姿が分かる。
美しいと思うと同時に胸が切なくなった。
那美も高校を卒業するまでは澄宮家で使用人の扱いを受けるだろう。
ただその後が分からない。
きっと進学などもってのほか。
(遠い地に就職すればこの生活からも抜け出せるかもしれない)
それが那美にとって最善なのだが両親がそれを許すかどうか不明だ。
もしかしたら澄宮家の正式な使用人として一生働けと言われるかもしれないと嫌な想像をしてしまう。
俯きかけたとき、微かな鈴の音が耳に届く。
不幸な未来が待っているのなら家族がいない、この時間だけは。
(少しだけ──)
那美は畳んだ洗濯物を箪笥に入れると部屋の中心に立つ。
静かに深呼吸をすると幼い記憶をたぐり寄せ、舞い始めた。
たどたどしい舞は誰がどう見ても見てはいられないものだろう。
時々振りを間違いながらも那美は続ける。
(鈴の音が聞こえるこの時だけは舞っていたい)
次の『龍夜の儀』は当分先だ。
それまでは、こうして一人でゆっくりと過ごす時間もない。
きっと姉の舞を見て両親は柔やかで誇らしく思っているだろう。
それとは真逆に何とも寂しい部屋の明かりだけが那美を照らしている。
しかしその状況でも不思議と何故か心が弾んだ。
(どうしてかしら。久しぶりに舞えたから?)
微笑みながらそっと目を閉じると、ふと脳裏に綺世の顔が浮かぶ。
「え……?」
那美は突然のことに驚き、思わず足を止める。
(どうして綺世さまが?)
一瞬、夢で逢っただけの彼の姿がはっきりと見えたのだ。
起きている時間でのこんな現象は初めてで戸惑う。
同じタイミングで鳴り続けていた鈴の音が終わる。
慌てて窓から外の様子を見ると龍夜の儀を終えた三人が屋敷に戻ってくるのが分かった。
(急いでお出迎えをしないと!)
必ず家族が帰宅するときは使用人総出で出迎えなければいけない。
もちろん那美もだ。
勢いよく襖を開けた瞬間、夜空に浮かんだ満月が一層、眩しい光を放った。
「え……?」
その月光は一直線に那美の部屋の前にある中庭のみを照らす。
花壇がある他の家族の中庭とは違う、何とも殺風景な場所だ。
普段ならば。
しかし今は手入れしきれていない雑草も偶然に咲いた小さな花も冴えていて息を飲むほど美しかった。
「これは一体……」
中庭用のサンダルに履き替えて外に出る。
空を見上げ、差し込む眩い光に耐えきれず手をかざしたとき──。
一体の龍がこちらに降りてくるのが分かった。
目の前で起こる全てが信じられないが、『龍夜の儀』・『巫女の舞』という言葉が線のように繋がる。
(もしかしてお姉さまの舞を見初めて花嫁として迎えに来られたの?でもそれなら神楽殿に光が差すはず)
困惑している間にも龍はどんどんとこちらへ向かってくる。
そしてついに那美の目の前にふわりと降り立つ。
白く輝く鱗に宝石のような赤い瞳。
初めて見る高貴な姿に圧倒されながらもすぐに分かった。
「白龍さま……」
そう。
紛れもなく龍たちの頂点に君臨する龍王、白龍だ。
白龍は那美の呟きを聞いて瞳を細める。
(あれ?この瞳どこかで……)
龍にましてや龍王に会う機会などないと思っていたのに既視感を覚える。
「私だ。那美」
「え?」
白龍が口を開いて初対面のはずの那美の名前を呼ぶ。
それは何度も聞いた大好きな声で──。
白龍の周りが光で包まれたかと思うと一瞬にして人の姿に変わる。
「あ、やせさま……?」
途切れ途切れの問いかけにも嬉しそうに頷く人物は綺世だった。
綺世はゆっくりと那美に歩み寄ると小さな身体を抱きしめた。
そして耳元に唇を近づけて囁く。
「夢を渡って君に逢いに来た」