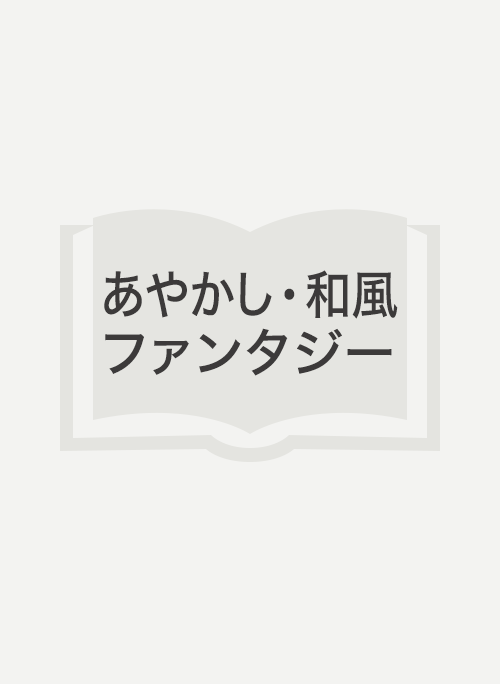「おはようございます。旦那さま、奥さま、美桜さま」
口角を一切上げず、無表情な父と黒色で蝶柄の美しい着物を纏った継母、可愛らしい制服のスカートをふわりとさせながら機嫌の良い姉が広間に入ってくる。
使用人頭が挨拶をすると同時に整列していた他の使用人たちも一斉にお辞儀をする。
その一番端に立っていた那美も当然のごとく、頭を下げる。
「おはよう」
継母たちは返事をすることなく席につき、澄宮家の当主である義郎がただ一言返すのみ。
那美は確かにこの家の娘だが、誰も見向きなどしない。
まるで存在しないかのように。
食卓に並べられている朝食は長年、この屋敷で働いている使用人たちのおかげで料亭のような仕上がりになった。
那美は広間の隅に控え、彼らが食事をとるのを静かに見守る。
「あつっ……!」
突如、広間に那美の姉である美桜が大きな声を出す。
視線を向けると味噌汁が入ったお椀を持ちながら片手で口元を抑えている。
「いかがなさいましたか……!?」
使用人頭が血相を変えて彼女に近づく。
美桜は大きな瞳をキッと吊り上げるとこちらを睨みつける。
「このお味噌汁、熱すぎるわ!火傷したらどうするの!?」
「も、申し訳ありません!今すぐ冷たいお水をご用意いたします……!」
使用人同士で目配せをしてその内の一人が慌てた様子で広間から出て行く。
「味噌汁を準備したのは誰!?」
美桜は落ち着くことなく、犯人を探すような目つきで辺りを見回す。
「わ、わたしです……」
おそるおそる手を上げたのは那美だった。
以前に温い味噌汁を出してしまい、怒鳴られたことがあった。
今度はしっかりと、と思ったのだがそれが裏面に出てしまったのだ。
列から一歩前に出ると両膝をつき絨毯に両手を添えて頭を下げる。
美桜は席から立ち上がると那美に近づく。
目の前で立ち止まり、鋭い目つきで貧相な妹を見下ろす。
「本当に学ばないんだから。これだから無能は」
そう言い放つと手にしていたお椀に入った味噌汁を那美の頭にかける。
「うっ……!」
急激な熱さが襲い、うめき声を上げる。
汁気が髪から滴り落ちながら今もなお、土下座をしている那美を見て美桜は可笑しそうに笑った。
「染みになる前に早く拭いてよね」
フンっと鼻を鳴らすと再び席につく。
まだ頭に残る熱さを我慢しながら布巾で絨毯を拭き始める。
普段から虐げている家族は誰も助けることなどせず、優雅に箸を進めている。
使用人たちも那美の手助けはするなと言われている為か見て見ぬふりだ。
那美自身もそれは承知しており、最初から諦めている。
「まったく。もっと自分の姉の存在価値を考えたらどうだ?」
「そうよ。美桜さんは星巫女なのだから」
父と継母が掃除をしている那美を一瞥する。
星巫女。
巫女には位があり、宿す力の大きさで決まる。
下から巫女、花巫女、星巫女、そして最も位が高いのが姫巫女。
姫巫女が誕生するのは極めて珍しく国内に数名しかいない。
継母の葉月と姉の美桜は二番目に位が高く、強き力を宿す星巫女。
有能な家族と無能な娘。
どうして力を何も持たない子が生まれてしまったのか誰も分からず、謎のまま。
『お前は一族の恥だ』と日々罵られている。
「役立たずのお前をここまで育て、高校にも通わせているのだ。恩を仇で返すな」
「美桜さんは天奈女学院でトップの成績を修めているのよ。見習ってほしいわ」
天奈女学院とは巫女だけが通える学校。
力の強さごとにクラス分けをされていて美桜は学院で一番優秀な生徒だ。
より専門的な授業を受けられる他、設備が整った校舎に可愛らしい制服は憧れの的。
当然のごとく力を持たない那美は入学出来ない。
それは巫女の家系であっても。
両親は周囲の目もあるのか不服だが那美は一般的な都立の高校に通わせている。
「さあ、美桜。そんな奴は放っておいて朝食の続きだ」
「はい、お父さま」
美桜は掃除をし続ける妹をにやりと口角を上げながら蔑んだ目で一瞬見ると足取り軽く席へ戻るのだった。
口角を一切上げず、無表情な父と黒色で蝶柄の美しい着物を纏った継母、可愛らしい制服のスカートをふわりとさせながら機嫌の良い姉が広間に入ってくる。
使用人頭が挨拶をすると同時に整列していた他の使用人たちも一斉にお辞儀をする。
その一番端に立っていた那美も当然のごとく、頭を下げる。
「おはよう」
継母たちは返事をすることなく席につき、澄宮家の当主である義郎がただ一言返すのみ。
那美は確かにこの家の娘だが、誰も見向きなどしない。
まるで存在しないかのように。
食卓に並べられている朝食は長年、この屋敷で働いている使用人たちのおかげで料亭のような仕上がりになった。
那美は広間の隅に控え、彼らが食事をとるのを静かに見守る。
「あつっ……!」
突如、広間に那美の姉である美桜が大きな声を出す。
視線を向けると味噌汁が入ったお椀を持ちながら片手で口元を抑えている。
「いかがなさいましたか……!?」
使用人頭が血相を変えて彼女に近づく。
美桜は大きな瞳をキッと吊り上げるとこちらを睨みつける。
「このお味噌汁、熱すぎるわ!火傷したらどうするの!?」
「も、申し訳ありません!今すぐ冷たいお水をご用意いたします……!」
使用人同士で目配せをしてその内の一人が慌てた様子で広間から出て行く。
「味噌汁を準備したのは誰!?」
美桜は落ち着くことなく、犯人を探すような目つきで辺りを見回す。
「わ、わたしです……」
おそるおそる手を上げたのは那美だった。
以前に温い味噌汁を出してしまい、怒鳴られたことがあった。
今度はしっかりと、と思ったのだがそれが裏面に出てしまったのだ。
列から一歩前に出ると両膝をつき絨毯に両手を添えて頭を下げる。
美桜は席から立ち上がると那美に近づく。
目の前で立ち止まり、鋭い目つきで貧相な妹を見下ろす。
「本当に学ばないんだから。これだから無能は」
そう言い放つと手にしていたお椀に入った味噌汁を那美の頭にかける。
「うっ……!」
急激な熱さが襲い、うめき声を上げる。
汁気が髪から滴り落ちながら今もなお、土下座をしている那美を見て美桜は可笑しそうに笑った。
「染みになる前に早く拭いてよね」
フンっと鼻を鳴らすと再び席につく。
まだ頭に残る熱さを我慢しながら布巾で絨毯を拭き始める。
普段から虐げている家族は誰も助けることなどせず、優雅に箸を進めている。
使用人たちも那美の手助けはするなと言われている為か見て見ぬふりだ。
那美自身もそれは承知しており、最初から諦めている。
「まったく。もっと自分の姉の存在価値を考えたらどうだ?」
「そうよ。美桜さんは星巫女なのだから」
父と継母が掃除をしている那美を一瞥する。
星巫女。
巫女には位があり、宿す力の大きさで決まる。
下から巫女、花巫女、星巫女、そして最も位が高いのが姫巫女。
姫巫女が誕生するのは極めて珍しく国内に数名しかいない。
継母の葉月と姉の美桜は二番目に位が高く、強き力を宿す星巫女。
有能な家族と無能な娘。
どうして力を何も持たない子が生まれてしまったのか誰も分からず、謎のまま。
『お前は一族の恥だ』と日々罵られている。
「役立たずのお前をここまで育て、高校にも通わせているのだ。恩を仇で返すな」
「美桜さんは天奈女学院でトップの成績を修めているのよ。見習ってほしいわ」
天奈女学院とは巫女だけが通える学校。
力の強さごとにクラス分けをされていて美桜は学院で一番優秀な生徒だ。
より専門的な授業を受けられる他、設備が整った校舎に可愛らしい制服は憧れの的。
当然のごとく力を持たない那美は入学出来ない。
それは巫女の家系であっても。
両親は周囲の目もあるのか不服だが那美は一般的な都立の高校に通わせている。
「さあ、美桜。そんな奴は放っておいて朝食の続きだ」
「はい、お父さま」
美桜は掃除をし続ける妹をにやりと口角を上げながら蔑んだ目で一瞬見ると足取り軽く席へ戻るのだった。