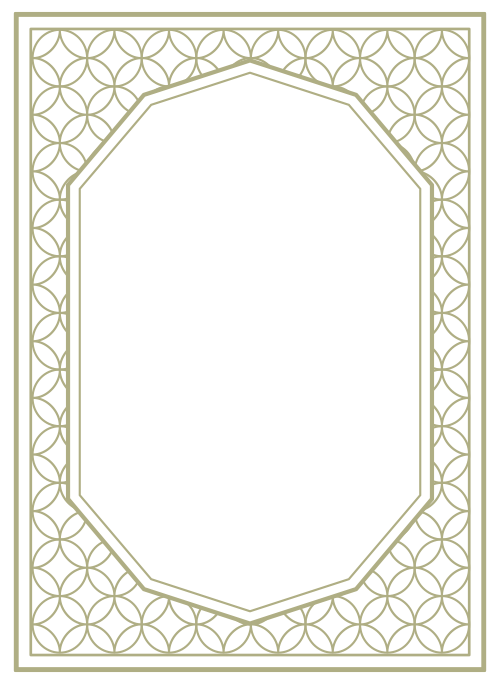「舞弥、なんでも言ってみろ。お前の望むことを、俺が叶えたい」
壱の口からするりと出てきた言葉。壱は誰彼優しくする性格ではない。
自分の心の中に場所を与えた者にしかそれは見せない。
舞弥は一度口を開きかけ――閉じた。
「………だめだ。言っちゃいけないこと言っちゃいそう」
自戒のように、舞弥は唇の端に笑みを乗せる。
「なんでも言っていい。今なら、熱で口にしたことだととらえておくから」
「……叶えようと、しないでね?」
「それは内容いかんによる」
壱が穏やかな声で言うと、舞弥は両ひざに顔をうずめた。
「……ここにいてほしい……」
小さな小さな声。小さくて欲張りな、舞弥の願い。
「? ここに?」
問われて、舞弥は一層膝に顔をうずめる。
「……壱と玉に、出て行かないでほしい……」
「―――」
……舞弥の願いと壱の希望は、重なっていた。
舞弥は壱と玉と暮らしていきたいし、壱は舞弥と玉の傍にいたい。
だがお互い、最初の言葉が枷となって本音を口に出来ないでいた。
怪我が治ったら出て行くという、たった一度、なんのけなしに口にしたことであっても。
「……舞弥」
壱に名前を呼ばれて、舞弥は顔をあげて慌てて手を振った。
「ほ、ほんと気にしないでっ。熱で頭おかしくなってるだけだから――」
「俺も、舞弥と一緒にいたいと思っている」
「……え?」
壱は少し恥ずかしそうに、照れたように――けれどまっすぐに言葉する。
「自分から出て行くと言っておいてあれだが、……舞弥といると玉が元気だししっかりしようと頑張っているし――何より俺が、舞弥とずっと一緒にいたいと考えるようになっていた。だが、俺たちはしょせんあやかしだ。人間ではないし、人間にもなれない。それでも――舞弥と一緒にいていいだろうか? ……いや、舞弥、俺と一緒にいてほしい。俺と、玉と」
あやかしと人間、その垣根はついて回る。
一緒にいることが難しいときがやってくるかもしれない。
それでも一緒にいたいと願う。……それは罪だろうか。
「……壱ってかっこいいね」
自分の頬に添えられている壱の手を取って、舞弥は唇を寄せた。
「ありがとう……嬉しい」