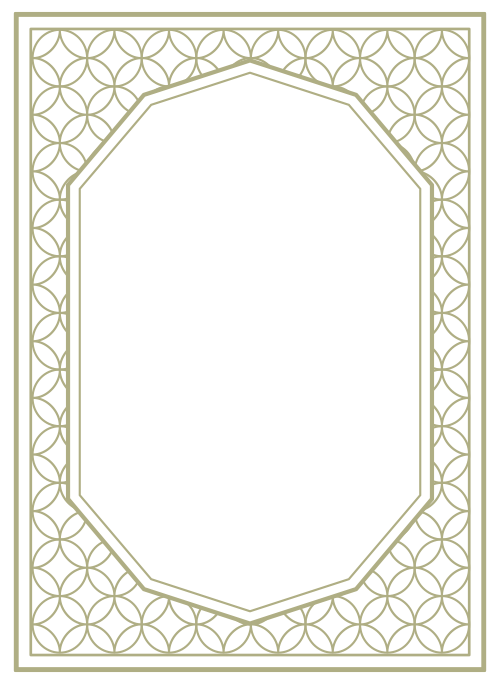舞弥が思わずぽつりと言ってしまうと、聞いた壱はあたふたしながらそう言った。やはり破廉恥だと言われた。
「そ、それで、熱はどうだ?」
誤魔化すように壱が早口で言った。
「三七度三分、だいぶ下がった~。ご心配おかけしました」
舞弥がぺこりと頭を下げると、壱の肩から力が抜けた。
「そうか。だが、まだ安静にしていた方がいい。今日のバイトは、玉が舞弥の分も出てくると言っていたから心配しなくていい」
「え? あっ、そうだカフェにも連絡しないとっ」
「落ち着け舞弥。玉が、舞弥が休むことも含めて伝えると言っていた。信頼していい」
「うわ~、ごめんね、壱、玉もありがとう。玉が帰ったら美味しいご飯作るね」
「今日は台所厳禁」
「えっ? なんで」
「熱ある奴に料理させられるか。俺も玉も、今まで毎食食べていたわけじゃないんだ。気にしなくていい」
「でも……」
「舞弥の分は俺が作る。簡単なものしか出来ないが、粥くらいなら作れる」
「……いいの?」
壱の提案に、舞弥はちょっと驚いた。壱は頑なに人の姿をとらないので、たぬき姿で料理をしている姿を想像して……いいのか? と不安にもなった。
「いいも何も、普段俺たちが世話をかけすぎているんだ。もっと俺たちにやることがあって当然なくらい。舞弥は抱え込みすぎだ」
壱がそういうと、舞弥は膝を抱えた。
「……だって、私しかいなかったんだよ?」
――この部屋には舞弥しかいなかった――。暗にそう言われて、壱は言葉を探した。
「……それは……そうだな。大家殿がいるとはいえ、この部屋にはひとりだったと思う」
「……」
舞弥の、膝を抱える手に力が入った。壱はまっすぐ舞弥を見上げる。
「だが、だから今ここにいる俺たちを好きなように使えということだ。俺たちは動物のたぬきじゃなくて、喋ることも舞弥の頭を撫でることも出来る。お得だぞ」
うまく伝わるか不安になりながら、壱は言った。
舞弥が孤独だと思っている場所が、今はそうではないと思ってほしかった。
「ふふ……ありがとう、壱」
目じりに涙を浮かべた舞弥の頬に手をのばす。
たぬきの手のままだが、触れると舞弥は嬉しそうな顔になる。