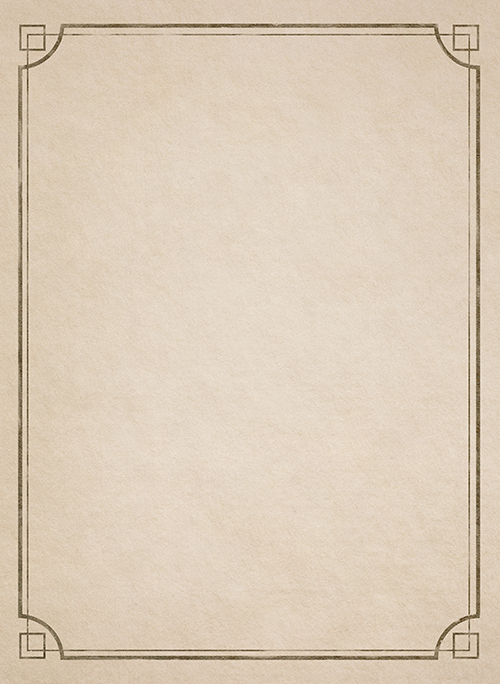下ですれ違うのは何度かあったと思うのだが、それ以上の何かは一つとして無い。振り返ってみれば、三年間で瑠夏と会話をした覚えもない。中学一年生の時以来になるはずだ。本当に約五年間も、目の前の少女は僕の事を想ってくれていたのだろうか。想像を巡らせるほど、現実感は無くなってくる。
腕を組んで、想像の幅を広げた。僕は高校を出て、家からそれほど遠くない公立の大学へ行く。流石に瑠夏がそこまで追いかけてくるとは思えない。となれば、恋人として暮らすにはある程度の物理的距離を置くというのが自然だ。瑠夏の進路次第では、世間がイメージするような遠距離恋愛になるかもしれない。都道府県を跨いでの恋愛という事だ。
正直に言って、僕を追って高校に入るような人間だから、どこかで僕の進路を把握していても不思議はない。自分自身の進学、或いは就職も、市内という範囲で行なっている可能性がある。そうなれば、違う場所へ向かうようになっても遠距離恋愛であるとは言い難い。
僕の価値観としては、二人の関係が遠距離になるかどうかに重きを置いていた。だから瑠夏が遠く離れた地に行くのか、行かないのかが重要になってくる。だがここで瑠夏に進路はどうするのかとは訊きづらい。返事を先にしなくては、なんだか不自然に感じられるのだ。
僕は一瞬だけ視線を逸らし、展望台からの街の景色に目をやった。あと一時間も経てば空にオレンジ色が目立つようになる。流石に日が沈むまでには帰らないといけない。何故なら、今日は自転車に装備するライトを家に置いてきている。長い間、公園にとどまるつもりはなかったから。
話を長引かせたら、七キロの道のりを自転車を押して歩かなくてはならない。あまり望ましくない帰宅の方法だ。
僕の頭はそんな調子で、ありとあらゆる思考が脳内に錯綜し、混乱状態にあった。そもそも恋人を作った試しがない。初めての恋人が、中学校以来初めて会話をする相手でいいのかも当然わからない。
握った手に汗が浮かんできた。答える側の人間がこれでは、告白する側というのは一体どんな気持ちでいるのだろう。今にも倒れそうなほど、鼓動が速くなっているのかもしれない。返答などどうでもいいから、すぐにでも逃げ出してしまいたいという衝動に駆られているのかもしれない。何にせよ、僕よりずっと、精神的な負担が大きいはずだ。
いち早く返事を返すのが、相手のためにも良い。僕はそう考えて、正しいか、正しくないかは別とした直感に基づく気持ちを伝えた。
それを聞いて瑠夏は、目尻に涙を浮かべた。涙は次々に溢れ、決壊寸前だった。決壊する前に、瑠夏は何も言わず僕の前から立ち去った。フラフラとした足取りだが、できるだけ速く、できるだけ遠くを目指して走った。
腕を組んで、想像の幅を広げた。僕は高校を出て、家からそれほど遠くない公立の大学へ行く。流石に瑠夏がそこまで追いかけてくるとは思えない。となれば、恋人として暮らすにはある程度の物理的距離を置くというのが自然だ。瑠夏の進路次第では、世間がイメージするような遠距離恋愛になるかもしれない。都道府県を跨いでの恋愛という事だ。
正直に言って、僕を追って高校に入るような人間だから、どこかで僕の進路を把握していても不思議はない。自分自身の進学、或いは就職も、市内という範囲で行なっている可能性がある。そうなれば、違う場所へ向かうようになっても遠距離恋愛であるとは言い難い。
僕の価値観としては、二人の関係が遠距離になるかどうかに重きを置いていた。だから瑠夏が遠く離れた地に行くのか、行かないのかが重要になってくる。だがここで瑠夏に進路はどうするのかとは訊きづらい。返事を先にしなくては、なんだか不自然に感じられるのだ。
僕は一瞬だけ視線を逸らし、展望台からの街の景色に目をやった。あと一時間も経てば空にオレンジ色が目立つようになる。流石に日が沈むまでには帰らないといけない。何故なら、今日は自転車に装備するライトを家に置いてきている。長い間、公園にとどまるつもりはなかったから。
話を長引かせたら、七キロの道のりを自転車を押して歩かなくてはならない。あまり望ましくない帰宅の方法だ。
僕の頭はそんな調子で、ありとあらゆる思考が脳内に錯綜し、混乱状態にあった。そもそも恋人を作った試しがない。初めての恋人が、中学校以来初めて会話をする相手でいいのかも当然わからない。
握った手に汗が浮かんできた。答える側の人間がこれでは、告白する側というのは一体どんな気持ちでいるのだろう。今にも倒れそうなほど、鼓動が速くなっているのかもしれない。返答などどうでもいいから、すぐにでも逃げ出してしまいたいという衝動に駆られているのかもしれない。何にせよ、僕よりずっと、精神的な負担が大きいはずだ。
いち早く返事を返すのが、相手のためにも良い。僕はそう考えて、正しいか、正しくないかは別とした直感に基づく気持ちを伝えた。
それを聞いて瑠夏は、目尻に涙を浮かべた。涙は次々に溢れ、決壊寸前だった。決壊する前に、瑠夏は何も言わず僕の前から立ち去った。フラフラとした足取りだが、できるだけ速く、できるだけ遠くを目指して走った。