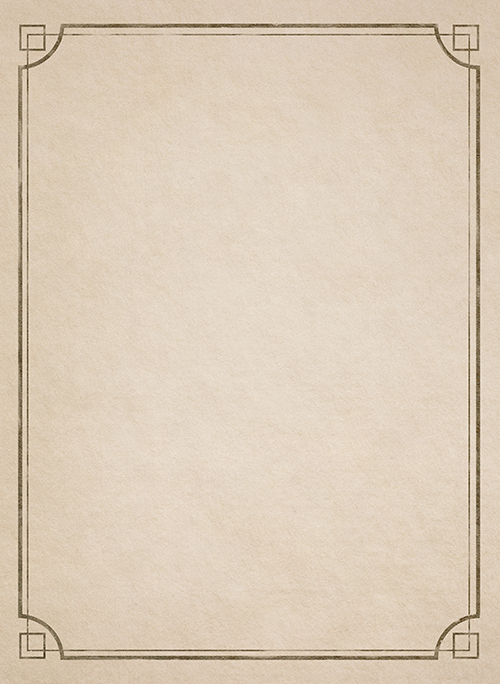らなのか、景色が綺麗だからなのか、理由はわからない。ただ一つ言えるのは、彼女の目はとてつもなく遠い場所を見つめているように思えた。遠いとは、物理的な距離の話ではない。過ぎ去ってしまった、遥か昔だ。現代の人間には到底辿り着けないほどの遠い場所に、瑠夏の目は向いている。
そして彼女は笑った。笑ったように見えた。
「正直な事を言うと、高校は砂川くんと同じところがいいなって思った。だから先生と砂川くんが話しているのを盗み聞きして、私も同じ学校に入ろうって決めた。砂川くんは頭が良かったから、勉強はとっても大変だった。でも無事に、同じ高校に入学できた」
「それは、本当? 嘘ついてない?」
「ついてない。本当だよ。高校生になったら、砂川くんに告白しようって思ってたの。今よりも立派な大人になって、一緒に隣を歩けるような人になってから、告白しようって思った。付き合ってからの事も考えて、いっぱい話せるようになるために、頑張って友達もたくさん作ったの。中学生の頃と同じなのは、嫌だったから。でも勇気が出せなくて、結局今日になっちゃったんだ」
真剣な顔をして話していた瑠夏だったが、自分の言っている内容を改めて理解したのか、また顔を赤くした。今度は耳まで赤くなるほどだった。一方で僕も、瑠夏に負けないくらいに顔が赤くなっていった。鏡で見ずとも、それくらいわかる。顔面が、とにかく熱くて仕方ないのだ。鼓動も、ものすごく速くなっている。
だが、ただ赤くなっているだけでは駄目だ。瑠夏から突如として持ちかけられた話に、結論を出すのが僕の役目だ。答えがイエスにしろ、ノーにしろ考えて出す。責務から逃れる術はない。
瑠夏は、僕の目を見ていた。気づけば、彼女の目は真っ直ぐと僕の方に向いて、返事を待っていた。
とりあえず返事までの繋ぎのため、僕は言った。
「僕は中学の途中から今まで、金城さんと仲良くしていたような人間じゃなくなってる。人と関わるのはできるだけ避けたいって思うようになってる。昔見たいに友達に恵まれるわけじゃないし、普段から暗い影みたいにして生きてる。それでもいいの?」
「うん。それでもいい。砂川くんが変わったなっていうのは、高校に入る前からなんとなくわかってたし。でも、だからこそ、今度は私が砂川くんの助けになりたい。砂川くんが話しかけてくれた時、学校に行くのがすごく楽しかった。恩返しができるならもちろんしたいし、何より今の砂川くんだって十分かっこいいと思う」
真剣な顔でそう言われたので、僕は真剣に考えてみた。金城瑠夏と付き合えば、どうなるのかを。
高校に入学してから、驚くべき事に瑠夏と同じクラスになった事は一度としてない。廊
そして彼女は笑った。笑ったように見えた。
「正直な事を言うと、高校は砂川くんと同じところがいいなって思った。だから先生と砂川くんが話しているのを盗み聞きして、私も同じ学校に入ろうって決めた。砂川くんは頭が良かったから、勉強はとっても大変だった。でも無事に、同じ高校に入学できた」
「それは、本当? 嘘ついてない?」
「ついてない。本当だよ。高校生になったら、砂川くんに告白しようって思ってたの。今よりも立派な大人になって、一緒に隣を歩けるような人になってから、告白しようって思った。付き合ってからの事も考えて、いっぱい話せるようになるために、頑張って友達もたくさん作ったの。中学生の頃と同じなのは、嫌だったから。でも勇気が出せなくて、結局今日になっちゃったんだ」
真剣な顔をして話していた瑠夏だったが、自分の言っている内容を改めて理解したのか、また顔を赤くした。今度は耳まで赤くなるほどだった。一方で僕も、瑠夏に負けないくらいに顔が赤くなっていった。鏡で見ずとも、それくらいわかる。顔面が、とにかく熱くて仕方ないのだ。鼓動も、ものすごく速くなっている。
だが、ただ赤くなっているだけでは駄目だ。瑠夏から突如として持ちかけられた話に、結論を出すのが僕の役目だ。答えがイエスにしろ、ノーにしろ考えて出す。責務から逃れる術はない。
瑠夏は、僕の目を見ていた。気づけば、彼女の目は真っ直ぐと僕の方に向いて、返事を待っていた。
とりあえず返事までの繋ぎのため、僕は言った。
「僕は中学の途中から今まで、金城さんと仲良くしていたような人間じゃなくなってる。人と関わるのはできるだけ避けたいって思うようになってる。昔見たいに友達に恵まれるわけじゃないし、普段から暗い影みたいにして生きてる。それでもいいの?」
「うん。それでもいい。砂川くんが変わったなっていうのは、高校に入る前からなんとなくわかってたし。でも、だからこそ、今度は私が砂川くんの助けになりたい。砂川くんが話しかけてくれた時、学校に行くのがすごく楽しかった。恩返しができるならもちろんしたいし、何より今の砂川くんだって十分かっこいいと思う」
真剣な顔でそう言われたので、僕は真剣に考えてみた。金城瑠夏と付き合えば、どうなるのかを。
高校に入学してから、驚くべき事に瑠夏と同じクラスになった事は一度としてない。廊