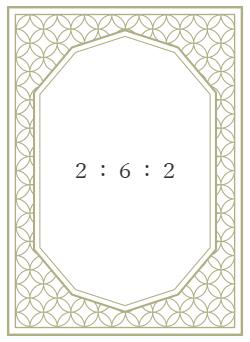その後、ゆうくんが「もうお前とはあんま遊ばねえかも」と言い出すまで、そう時間は掛からなかった。
「あいつが、嫌だって言うから」
まるで言い訳みたいに彼女を出してきたゆうくんに何も言えなかった。どれだけただの幼馴染みだと言い張ったところで、私は女で、そのうえ、ゆうくんを全く意識していないと言えば嘘になるから。
「ごめんな」
謝るくらいなら言わないでほしかった。それって謝るくらい自分の存在が私にとって大きいことを分かってて、それでも彼女を優先するってことでしょ。
言いたいことは頭にぽんぽん浮かんでくるのにどれも子供じみた我が儘でしかなくて必死に呑み込んだ。自分の気持ち全部殺して、「彼女と仲良くね」と思ってもいない言葉を吐き出した私は、物分かりのいいゆうくんの“幼なじみ”だった。
その時ようやく理解した。私は脇役なんだって。
私とゆうくんの距離は加速度的に開いていく。以前のように互いの家に出入りすることもなければ、一緒に出掛けることもなく、メッセージのやり取りをすることもない。ただ家が近いだけの他人。教室の窓から見える、誰よりも近かったはずのゆうくんの隣に並んで帰る女の子が私ではないことに、もう違和感を覚えなくなってしまった。
ゆうくんの隣にいるのはずっと私だと思ってたのに可笑しいな。部屋の片付けもゲームのラスボス退治も彼女のプレゼント選びも、ゆうくんが言うなら何だってしたのにね。
「また泣いてんの?」
放課後、誰もいない教室でぐずぐずと鼻水を啜っていると、課題を提出してきたらしい莉子ちゃんが机に突っ伏している私に近付いてきた。
今日も私は廊下でゆうくんと彼女が一緒に歩いているのを見てダメージを受けていた。いくら時間が経っても受けるダメージ量は変わらない。失恋の傷は時間が解決するなんて嘘じゃん、とネットの恋愛コラムに文句を言いたくなる。
「隣のクラスの女子から、カラオケ行かないかって誘われてるんだけど。あんたも来る?」
「莉子ちゃん、隣のクラスに仲良い子いたっけ?」
ああ、私は莉子ちゃんまで奪われるんだ……と落ち込んでいると、莉子ちゃんが即座に否定した。
「いや。仲良くないけど人数合わせでしょ。他校の男子と合コンするんだって」
「ご、合コン!?」
「あたし顔は良いから、こういうのよく誘われるのよね」
嫌味かよっと言いたいところだけど、実際莉子ちゃんは顔が良い。うちの学年で一番可愛いとすら言われている。
合コンなんていう大人イベントに私が行くの……? と返事を躊躇していると、莉子ちゃんが付け加えた。
「失恋には新しい恋。行くよ」
普段合コンなんて断っているはずの莉子ちゃんが私のために参加しようとしている。その善意を無駄にしたくなくて重い腰を上げた。
:
「うお~。今日レベル高くね?」
「みんなかわいーじゃん。何頼むー?」
見慣れない制服の男子が四人と、莉子ちゃん、莉子ちゃんを誘った隣のクラスの女子二人。何故か男女男女男女男女の順番で座ることになり、距離の近い隣の男の子と一緒に歌うことになった。隣の男の子はなかなかに歌がうまいし良い声だ。こういうところに女子はどきっとするものなんだろうけど、私は音程がずれているゆうくんの歌声を思い出して何故か泣きそうになった。
もうゆうくんとカラオケに来ることは二度とない。私はこうして見ず知らずの男の子と歌うしかないのだ。
「失礼します」
その時、店員が室内にポテトとドリンクを運んできた。なんか聞き覚えある声だな、と思って歌いながら入り口を見ると、ちょっと驚いたような顔をして私を見ているゆうくんがいた。カラオケの店員の制服を着ている。
(何で!?)
びっくりして音程がずれてしまった。
そういえば、彼女へのプレゼントを買うためにアルバイトを始める予定だと言っていた気がする。どこでバイトしているのかすら知らなかった。
ゆうくんは私に挨拶もせず黙ってポテトとドリンクをテーブルに置いて出ていく。歌ってる最中なんだから当然っちゃ当然だけど、その態度が少し寂しかった。
歌っていた曲が終わり、次は隣のクラスの女子たちが歌い始めた。おそらく平成に撮影されたであろう、画面の中の古い映像を眺めながらポテトを摘んでいると何だか虚しくなってきて、「私トイレ」と言って立ち上がった。
静かな所へ行きたい。莉子ちゃんは新しい恋って言うけど、どの男の子と喋っても歌っても、やっぱりそういう気分にはなれなかった。
トイレで手を洗ってハンカチをポケットから出していると、からんと床にシャープペンシルが転がった。あの日からお守りみたいに持っているそれは、ゆうくんとの思い出の品だ。私はそれを拾い上げ、溜め息を吐いて外に出た。
すると、さっきまで一緒に歌っていた男子が待ち構えていたかのように立っていた。正直ちょっとびっくりしたし怖くなったけど、さっきまで一緒だった同い年の男の子を怖いなんて思うのは失礼な気がして、平静を装って笑いかける。
「お、おつかれ。そっちもトイレ?」
「んーん? 君のこと待ってた」
「え、」
男の子の手がこちらに伸びてきて、私を壁に追い詰める。今私の表情は固まっているだろう。憧れの少女漫画で何度も見た胸キュンシチュエーションであるはずなのに、怖い。ぎゅっと手元のシャーペンを握り締めると、男の子は不思議そうに私の手を見つめてくる。
「何それ? シャーペン?」
「う、うん……」
「それ小学生とかが持ってるやつじゃん。そういうの好きなの?」
少しからかうように笑われた。
確かにこのシャーペンのデザインは子供っぽいもので、幼い子が好きな柄とも言える。でも、思い出の品を笑いのネタのように扱われるのは嫌だ。
「これは……私の大切なもの。これしかもう、残ってないから……」
私のゆうくんはいなくなってしまった。ちっちゃい頃から弟みたいに付いてきて、私の真似っ子ばかりしていた可愛いゆうくんはもういない。私が好きなゆうくんは私のものじゃなくて、あの人のものになった。あるのは思い出だけだ。
でも、必死に絞り出した言葉も嘲笑われてしまった。
「なにそれ、ウケる。それよりさ、一緒に抜けない?」
「え、でも、まだ莉子ちゃんたち歌ってるし」
「そんなんいいでしょ。そっちだってそういうつもりで来たんでしょ?」
シャーペンを持った手首を掴まれ、びくっと体が揺れた。
「や、やめて!」
「――何やってるんすか?」
私が抵抗するのとほぼ同時に、廊下の向こうから頼りがいのある声がした。
そちらを見れば、カラオケの制服姿のゆうくんがいた。
――嗚呼、やっぱり、この子はヒーローだ。
「店内での迷惑行為はやめてもらいたいんですけど」
「やだなー。ちょっと遊んでるだけじゃん」
「その人嫌がってますよ」
ヘラヘラと笑って言う目の前の男の子と違って、ゆうくんは一切笑っていない。身長は小さいのに顔は怖くて、男の子の顔から笑顔が消えた。そして、「何だよ。分かったよ」と言って私から手を離す。