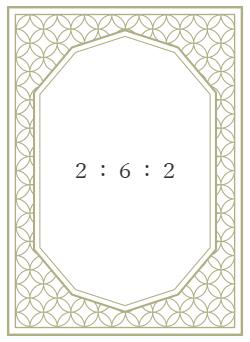家が隣で一個下の、ずっと一緒だった幼なじみのゆうくんに初めて彼女ができた。私より仲の良い女の子ができると思うとちょっと複雑だった。嘘、かなり複雑だった。「弟みたいなもん」とか「あんなバカ男として見たことないから」なんて言いつつ、年を経るごとに骨張って男の子らしくなっていく身体に、密かにドキドキしていた女の子の一人だったから。
部屋の片付けもゲームのラスボス退治も、昔は私がいないと何もできなかったくせに、彼女ができてからゆうくんが私の家に来る頻度は極端に少なくなった。別に喧嘩したわけでもなければ仲が悪いわけでもないのに、いつからかはっきり分からないくらい自然に、私たちの交流は減っていった。人間関係なんてちょっとしたことで変わっていくんだからこんなことを気にする自分が子供なのかもしれないと思いながら、やっぱり少しだけ寂しかった。
親からの伝言でゆうくんのクラスまでわざわざ行った時もゆうくんはずっとスマホをいじっていて、「んー? うん」なんていう、聞いてるんだか聞いてないんだか分からない答えを返してきた。私へのこういう態度は前からなのに、その時ばかりは何故かイライラして、脛を思いっきり蹴ってしまった。「っにすんだよ、」とむきになって蹴り返してくるゆうくんに内心ほっとした。あんたはそのままでいいよ、私を置いて大人にならないでって。
少女漫画なんてあっちもこっちも幼なじみ同士で恋愛してるのに、私とゆうくんはそんなことにはならなかった。何でだろう。
「そりゃあ漫画と現実は違うでしょーよ」
クラスメイトの莉子ちゃんが私の隣で呆れたようにツッコミを入れてくる。いつもゆうくんと登校していたのに最近はゆうくんが彼女と登校してるから、寂しすぎてわざわざ遠回りしてまで莉子ちゃんの家に寄り、一緒に登校してもらっているのだ。
「こんなに絵に描いたようなシチュエーションなのに? 家が隣で、親同士も仲良くてずっと一緒なんだよ? 思春期の年齢あたりでお互い意識し始めて……っていう王道展開、何で私には来なかったんだろう?」
「シチュエーションだけじゃ恋は始まらないってことじゃない? そろそろ“ゆうくん”卒業しなよ」
「ゆうくんには私がいないとだめなの」
「子離れできない親か。彼女のことは見たことあるの?」
「彼女できたその日にあいつが写真見せて自慢してきた。同級生だった。可愛かった。おしとやか系だった」
「じゃああんたには無理ね」
「どういう意味?」
莉子ちゃんがさらっと酷いことを言ってくる。確かに私はガサツな方だし、おしとやか系には勝てないけど……。
「でも、“幼なじみ”っていうのは強みだよね。関わりが切れることはないし、私の立場ならいつでも遊びに誘える」
「それ、彼女が嫌な気持ちになるんじゃない? やめなよ」
「…………」
それを言われると、何も言い返せない。だって立場が逆だったら絶対嫌だ。幼い頃から家が近くて仲が良いってだけで、異性の友達と二人で遊ばれるなんて。
「でも、私の方が先にゆうくんのこと好きだった……」
言葉通り“ただの弟”でしかなかったゆうくんのことを初めてかっこいいかもって思ったのは小学生の頃。私がいじめっ子のガキ大将に目を付けられて文房具を奪われたのを見て奪い返してくれた時だ。ママが買ってくれた可愛いキラキラが付いているシャープペンシルだけは壊されたくなくて泣いてたら、上級生の教室なのに中に入ってきたゆうくんが、まだ小さいのにガキ大将を殴って「返せよ」と言った。その威圧感が半端なくて、私は初めてゆうくんの背中に頼りがいみたいなものを感じた。結局ガキ大将がブチギレて殴られまくってたけど、そのせいで騒ぎになって先生が駆けつけ、ゆうくんもガキ大将も怒られた。後で「ごめんね、ゆうくん」って謝ったら、ゆうくんは「いーよ。それ大事なんだろ」って頬を痛そうに押さえながら何でもないみたいに笑った。
あの思い出のシャープペンシルは今も私の筆箱の中に入っている。
「いや、早く捨てなさいよ」
「ひどっ」
「あれもう壊れてんでしょ」
そう、あのシャープペンシルはもう使えない。分解して直そうとしたけど無理だった。
「いつまでも過去の思い出に縋ってないで、前に進みなさい」
莉子ちゃんの言うことはもっともだ。
でもまだゆうくんと一緒にいたい――。そう思ってしまう自分がいて、莉子ちゃんに返事できなかった。
後日、たまたまゆうくんの方から遊びに誘われた。
最初はどこへ行くんだろうとわくわくしたけれど、用件は“彼女の誕生日プレゼントを一緒に選んで欲しい”というものだった。
性格悪いけど、本当に性格が悪いけど、ちょっとだけ、ゆうくんが困った時にまず頼るのが私であることにくだらない優越感を抱いた。その週末は一緒に商店街をぶらぶら歩いて、ゆうくんの彼女の誕生日プレゼントを買って、バカみたいにゲラゲラ笑いながら二人で大きめのクレープを食べた。