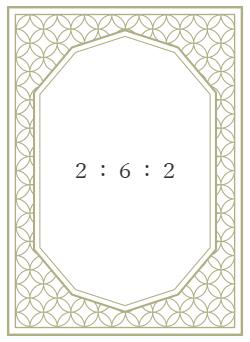中学三年間お世話になった音楽教師の結婚の知らせを聞いたのは、高校生になってすぐのことだった。中高一貫とはいえ校舎も変わればコース分けもあり、勉強も忙しくなるため新しい環境に慣れることに精一杯だった私は、その知らせに大した感情を抱かなかったし、それどころじゃないというのが正直なところだった。
生徒からはとても人気な人柄の良い先生で、お祝い事の好きな女子グループが大きなプレゼントを用意して放課後職員室へ突撃していたのだけは覚えてる。
私はその音楽教師のきつい香水の匂いがほんの少しだけ苦手だった。
*
「ねえ見て。佐伯くん、また告られてるよ」
「あの人ミスコンに出てた先輩もフったらしいよ」
「あんな美人でもフるって、誰だったらいいのって話だよね~」
廊下ですれ違う女生徒たちの声を聞いて、私の視線もそちらに奪われた。
中庭で女生徒からの愛の告白を受けているのは、佐伯空という同級生だった。とはいえ、これはそこまで珍しいイベントではない。ミステリアスだけど勉強も運動もできて顔も整っている人気者の佐伯くんは、二週間に一度のペースで告白されている。ドラマみたいな頻度だ。
中一から中三に至るまで偶然にも連続で同じクラスだった佐伯くんとは高校でも同じクラスだ。彼を意識したことは殆どなかったが、人数の多いこの学校で毎年同じクラスというのは珍しいためフルネームを覚えてしまった。
遠目から見て不思議な人だなと思う。同年代の他の男子より大人っぽくて飄々としていて、特定のグループには属さず気紛れな猫みたいにあっちへ行ったと思ったらこっちにいて他人と馴染む――かと思えばいなくなる。何となくだけど、佐伯くんは一人でいるのが好きなんだろう。あまり人と長く会話するのを好まないように見えた。今も、泣いている女生徒を前に少し面倒そうな顔をしている。
ぼんやり中庭を見つめていたら、佐伯くんと目が合ったので慌てて早足でその場を去った。告白現場をじろじろ見られるのは良い気がしないだろう。
私が授業外で佐伯くんの声をちゃんと聞いたのは一度だけ。生徒たちが学食や教室にいる昼休み、人気のない踊り場で、年下の女の子に告白されているところを見た。
「付き合ってほしいんです。私、佐伯先輩のこと凄く好きで」
「君のことはそういう目で見れん」
「今は見れなくても、私頑張りますから」
小学校高学年まで関西に住んでいたらしい佐伯くんには独特の訛りがある。
「……俺、好きな人おるんよ」
立ち聞きするなんて野暮だと分かっていたが、何故か聞き入ってしまった。だって私は、軽薄そうな佐伯くんが真剣な声音で喋っているのを初めて聞いたから。
「その人のことがほんまに好きで、他見る余裕とか、これっぽっちもないねん」
直接言われているわけでもない私がどきっとしたのだから、目の前でこんなセリフを言われた本人はもっと動揺しただろう。佐伯くんは、どうしても諦められないのかしつこく食い下がる女の子に対し、少し弱ったように言っていた。
「俺がそういう隙見せとったんやったら謝るから、これ以上俺のこと、困らせんといて」
ここまではっきり言って女子に諦めさせるってことは、優しい人なんだろうなって思った。
女の子が泣きながら走り去っていったので、私もそろそろ教室に戻らなければと階段を下りようとした。しかしその時、派手に転けてしまった。幸いにもそこまで痛くなかったが、踊り場にいた佐伯くんはこちらに気付いたようで私を見下ろしてくる。
「盗み聞き?」
何だか責められているように感じてぶんぶんと首を横に振った。
「いや、たまたま……」
「ふうん」
「……大丈夫?」
「何が?」
「声が辛そうだった」
私の言葉に、佐伯くんがちょっと驚いたような顔をした。
「あの女の子やなくて、俺の心配するんや」
佐伯くんは人気者だけど、一部のフラれた女子から逆恨みされている時もある。気取ってるとかモテてるからいい気になってるとか、たまに悪口を聞くこともある。そういうのも含めて辛いだろうなと思う。
「フる側もそれなりに体力いるでしょ」
「……まぁそりゃな。一生懸命勇気出してくれた女の子のこと悲しませとるわけやから」
「佐伯くんは優しいね」
「気持ちに応えてあげる男の方が優しいやろ」
「ううん。好きでもない女の子ととりあえず付き合ってみるような男の子より誠実」
佐伯くんは慰められていると感じたのか、「ありがと」とぽつりと小さな声で言って階段を上がっていく。私もわざわざ踊り場を避けて遠回りする必要がなくなったので、急いで階段を上がった。
私と佐伯くんがまともに会話したのはその時だけだった。
翌日、関東地方は夕方から夜にかけて酷い大雨が降ると予報されていた。
放課後残って自習していた私は、先生に質問しに行った際にその事実を伝えられ、少し早めに帰ることにして教科書を鞄に突っ込んで昇降口へ向かった。靴を履こうとして、折り畳み傘を教室に忘れたことに気付き溜め息を吐く。ここから高一の教室はかなり遠いのだ。まだ小降りとはいえ帰っている途中で雨が激しくなっては困るので、面倒だが戻ることにした。靴を戻し上履きを履く。雨のせいで外は暗く、廊下の照明が自動点灯している。
教室のドアを開くと、室内に残っていたのは部活終わりに教室へ寄ったらしい佐伯くんと、その部活仲間が数人いた。
「じゃーな佐伯~。俺らこの後予備校だから先帰るわ」
「今日大雨らしいから早く帰れよ」
佐伯くんの部活仲間たちが小走りで教室から出ていく。私は出てくる彼らの邪魔にならないようにドアの横で待機してから中に入った。
机にかけている予備の鞄を開いて奥の方にある折り畳み傘を探す。しばらく折り畳み傘を使っていなかったこともあってなかなか出てこない。いつも鞄に物を適当に入れているが故の弊害がこんなところで……。
苦戦していると、佐伯くんがこちらにやってきた。ふわりと女物の香水の匂いがした。
「何探しとるん」
出た、気紛れ。佐伯くんはこうやって気紛れに、大して仲良くもない子に話しかける。人懐っこい性格なのだと思う。そういう思わせぶりが駄目なんだよ、と思いながら見上げた先にいた佐伯くんが、中等部の頃より大人びているように感じて一瞬緊張した。こんなに間近で見るのは初めてかもしれない。平静を装って答える。
「傘」
「もうそない降っとる?」
「まだ小降りだよ。でも、これから酷くなるんだってさ」
そこで会話を終わらせたかったのに、佐伯くんがその場から退かないから、仕方なく何でもない会話を続けることにする。
「どうしよう。本当にない。前持って帰ったまんまだったかも」
「傘、貸したるよ」
「え? じゃあ佐伯くんはどうするの」
「俺は運動部やし、家近いから走って帰れる」
そう言ってブレザーを着て鞄を背負った佐伯くんは、ほぼ無理やりという感じで私に折り畳み傘を押し付けて教室を出ていってしまった。手元にある紺色で無地の傘を見つめて、こりゃモテるわと納得した。
週明けの月曜日、私は佐伯くんに傘を返すタイミングを見計らっていた。何せ人気者の佐伯くんである。私みたいな地味な女子が話し掛けたら「何あいつ、佐伯くんのこと狙ってんの?」などと他の女子たちから反感を買いそうだ。さすがに被害妄想かもしれないけど。
だから、佐伯くんがいい感じに一人になるタイミングを探して目で追っていた。佐伯くんは特別群れないから一人になることは多いのだが、一人でどこへ行っているのか全く予想がつかず、捕まえるのは難しかった。昼休みに教室から出て行ったので今だと思い追いかけたが見失った。
(本当、猫みたいな人……)
結局放課後まで佐伯くんは捕まらず、先週のように部活終わりならもしかしたら会えるかもしれないと思って自習をしながら教室で待っていたが、よく考えると月曜は部活ではなかったかもしれなかった。私はその事実に気付いて溜め息を吐き、傘を佐伯くんの机に置いて『ありがとう』と書き置きを残した。最初からこうしていればよかったと思った。