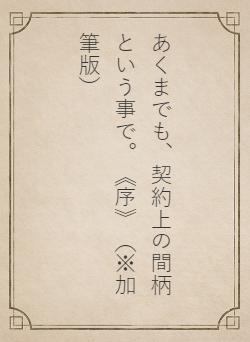「むしろ、出るべきだわ」
「承知致しました。瑛子伯母様」
このような次第となった。
施設から卯上邸に一時的に帰ってきた瑛子は、妹と姪の一家に言った。
「今年もまた、貴方達と一緒に新年を迎えられて嬉しく思います」
「瑛子伯母様、そして正頼も一緒で嬉しいです」
「瑛子様の調子が良く、このじいやも出てこられました」
正頼は、品の良い美しい顔を綻ばせた。瑛子に合わせて外見年齢を変化させている正頼は、正にロマンスグレーという言葉が似合う老紳士だ。瑛子が白峰学園に通っていた頃は、評判の美男子式神であったらしい。彼女達に対しては「どうか『じいや』とお呼び下さい」と言って、卯上家家中の事を請け負っていた。瑛子の体調によって表に出てこられない事は増えたものの、それこそ瑛子が若い頃は、執事のような存在であったと表現した方が想像し易いだろう。
「今日はじいやが支度を整えますので、お嬢様方もおっとりと構えていて下さい」
「ありがとうございます。でも、シルキーは動かしますよ」
彼女の言葉に応じて、折り紙で作られた人形達が忙しなく飛び交う。彼女が家事の為にと作成した存在『シルキー隊』だ。
そもそも彼女は、病弱で外に出る事ができない元輝の遊び相手にと、例えば作った折り紙人形に流行っていた特撮ヒーローの顔を描いて動かしていた。長じた彼女は「家の事を正頼だけに任せるのは悪いから」と言って、自分も学ぶ事は無論だが、現代風の表現をすれば家事機能をインストールした折り紙人形を作成し『シルキー隊』と呼んで使役している。つまり正頼を『単なる大伯母の作品で使役される存在』ではなく、意思や人格を持つ一人前の相手だと見做していたからに他ならない。
「ところでお姉ちゃん。『シルキー』って何?」
「ヨーロッパのお話に登場する、家事をしてくれる妖精さんだよ。絹の服を着ているから『シルキー』で、おいしい牛乳やお菓子をあげてお礼をするんだってさ」
「へえ。そんなのがいるんだなあ」
尤も、卯上邸母屋に住み着いた蹊子は、いい顔をしなかったが。
「そんなみっともない人形に頼って怠けるなんて、あたしは許さないからね!」
「みっともないとか怠けるとかって何さ。千代紙なんだし可愛いじゃん。これも私の才能だよ。人型の正頼と紙のシルキー隊の違いがあるだけで、何が悪いの?許さないとか言うけど、シルキー隊が作った物が気に入らないなら、祖母さんは食べなくていいよ」
蹊子は、かんかんになって怒った。当時既に施設に入っていた姉に、孫娘がどれだけ怠慢か、こんな年寄りに食事も与えようとしないそれは非道な孫なのだと、切々と訴えた。
瑛子は不思議そうに言った。
「人型の式神を使役する陰陽師なら、家事を任せるのは珍しくないわよ?折り紙の人形という違いがあるだけじゃない。あの子の立派な才能よ?」
「そうよねー!」
賀茂一家は、揃ってコントのように体勢を崩した。
「手のひら返しもいい所だな」
「お祖母ちゃん、立場が上だって見なした相手の言う事は聞くから…」
「それってまず人間としてどうかと思うけど」
つまり瑛子と一緒に正頼も不在な卯上邸が家として成り立っているのは、彼女のシルキー隊の活躍があってこそである。そのシルキー隊に対しては正頼も「お嬢様の立派な才能です」とにこやかだ。
さて良い機会だと、彼女は瑛子に『選定ノ儀』に出るべきか否かを訊いてみた。返答は先述の通りだ。瑛子にひたすら喋りかけていた蹊子は、鬼気迫る顔を孫娘に向ける。
「いい?卯上の娘として、絶対に主に選ばれるのよ!」
「いや選ばれるとか本人の資質とかで決まるものじゃないから。そもそも選定の基準がまるでわからないし」
彼女はこれまたコントのように崩しかけた体勢を立て直しながら言った。
「第一、やたら卯上の名前を出してくるけどさ。祖母さんは望月の祖父さんと結婚して、新しい家庭を築いた訳でしょ?祖母さんにとって卯上の名前の重さとかしがらみとかは、もう関係ないはずじゃん」
蹊子の時代だと『結婚する=その家に入る』事になるのだが、彼女はやはりジェネレーションギャップと言うべきか、『結婚する=2人で新しい家庭を築く』と言うように、考えが異なる。
「私は陰陽連に登録するにあたって通用しやすいから、瑛子伯母様も勧めて下さったし、卯上の関係者って事で在籍してるけど」
「あたしは本来なら御典医の部長先生と結婚するはずだったの!だけど、お見合いの写真に傷が付いちゃったから、望月に恥をかかせない為にお祖父様と結婚するしかなくって…」
「それも嘘」
彼女は、ばっさりと切り捨てた。
「御典医の末裔とのお見合いは本当だけど、若い頃は評判の男前だった祖父さんの顔で選んだんだって、大お祖母様と瑛子伯母様から聞いたよ」
「蹊子。貴方、昔から物凄い面食いじゃないの。第一、お母様もお父様も『写真に傷が付いたから』とか訳のわからない理由で娘を無理矢理嫁がせる人じゃないわ。何を言っているの」
姉にも静かに指摘を入れられて、蹊子は黙った。必然的に傍観に徹するしか無かった李子が、「ねえねえ」と遠慮がちに口を挟む。
「お母さん、全然知らないから訊きたいんだけど、『選定ノ儀』って、危ない事は無いの?」
「大丈夫だよ。『サーベルタイガーを単独で斃して一人前として認められる』みたいに、強い妖魔と戦わされるだとかの物騒な話じゃないから」
なお、遥か古代の人類が本当に『サーベルタイガーを1人で斃して初めて一人前の大人として認める』風習を持っていたかは不明だが、彼女は『危険な儀式ではない』と強調し母を安心させる為に、あえて極端な物言いをしている。
「確か『抜けない剣を抜いてみせろ』って、アーサー王みたいな事をやるんだよな?」
「そう。それだけだよ」
予備知識として少しだけ話を聞かされていた元輝の補足に、李子は「ならいいけど」と安堵の息をつく。やはり母としては、純粋に娘の身が心配だったのだ。
「まあ剣を抜ける『主』が登場するかはわからない。ただ、登場してもしなくても私は単に、下っ端アルバイトという身でも陰陽連の一員として、人類社会を裏側から守る為に妖魔や瘴気をどうにかしていくだけさ」
「ええ。その通りよ。とてもいい心がけだわ」
瑛子は姪孫の成長に眩しそうに目を細めて頷く。正頼も「お嬢様がご立派になられて、じいやも嬉しゅうございます」と満面の笑顔だ。
こうして「気負わずに行ってらっしゃい」と、彼女は送り出されたのである。
「承知致しました。瑛子伯母様」
このような次第となった。
施設から卯上邸に一時的に帰ってきた瑛子は、妹と姪の一家に言った。
「今年もまた、貴方達と一緒に新年を迎えられて嬉しく思います」
「瑛子伯母様、そして正頼も一緒で嬉しいです」
「瑛子様の調子が良く、このじいやも出てこられました」
正頼は、品の良い美しい顔を綻ばせた。瑛子に合わせて外見年齢を変化させている正頼は、正にロマンスグレーという言葉が似合う老紳士だ。瑛子が白峰学園に通っていた頃は、評判の美男子式神であったらしい。彼女達に対しては「どうか『じいや』とお呼び下さい」と言って、卯上家家中の事を請け負っていた。瑛子の体調によって表に出てこられない事は増えたものの、それこそ瑛子が若い頃は、執事のような存在であったと表現した方が想像し易いだろう。
「今日はじいやが支度を整えますので、お嬢様方もおっとりと構えていて下さい」
「ありがとうございます。でも、シルキーは動かしますよ」
彼女の言葉に応じて、折り紙で作られた人形達が忙しなく飛び交う。彼女が家事の為にと作成した存在『シルキー隊』だ。
そもそも彼女は、病弱で外に出る事ができない元輝の遊び相手にと、例えば作った折り紙人形に流行っていた特撮ヒーローの顔を描いて動かしていた。長じた彼女は「家の事を正頼だけに任せるのは悪いから」と言って、自分も学ぶ事は無論だが、現代風の表現をすれば家事機能をインストールした折り紙人形を作成し『シルキー隊』と呼んで使役している。つまり正頼を『単なる大伯母の作品で使役される存在』ではなく、意思や人格を持つ一人前の相手だと見做していたからに他ならない。
「ところでお姉ちゃん。『シルキー』って何?」
「ヨーロッパのお話に登場する、家事をしてくれる妖精さんだよ。絹の服を着ているから『シルキー』で、おいしい牛乳やお菓子をあげてお礼をするんだってさ」
「へえ。そんなのがいるんだなあ」
尤も、卯上邸母屋に住み着いた蹊子は、いい顔をしなかったが。
「そんなみっともない人形に頼って怠けるなんて、あたしは許さないからね!」
「みっともないとか怠けるとかって何さ。千代紙なんだし可愛いじゃん。これも私の才能だよ。人型の正頼と紙のシルキー隊の違いがあるだけで、何が悪いの?許さないとか言うけど、シルキー隊が作った物が気に入らないなら、祖母さんは食べなくていいよ」
蹊子は、かんかんになって怒った。当時既に施設に入っていた姉に、孫娘がどれだけ怠慢か、こんな年寄りに食事も与えようとしないそれは非道な孫なのだと、切々と訴えた。
瑛子は不思議そうに言った。
「人型の式神を使役する陰陽師なら、家事を任せるのは珍しくないわよ?折り紙の人形という違いがあるだけじゃない。あの子の立派な才能よ?」
「そうよねー!」
賀茂一家は、揃ってコントのように体勢を崩した。
「手のひら返しもいい所だな」
「お祖母ちゃん、立場が上だって見なした相手の言う事は聞くから…」
「それってまず人間としてどうかと思うけど」
つまり瑛子と一緒に正頼も不在な卯上邸が家として成り立っているのは、彼女のシルキー隊の活躍があってこそである。そのシルキー隊に対しては正頼も「お嬢様の立派な才能です」とにこやかだ。
さて良い機会だと、彼女は瑛子に『選定ノ儀』に出るべきか否かを訊いてみた。返答は先述の通りだ。瑛子にひたすら喋りかけていた蹊子は、鬼気迫る顔を孫娘に向ける。
「いい?卯上の娘として、絶対に主に選ばれるのよ!」
「いや選ばれるとか本人の資質とかで決まるものじゃないから。そもそも選定の基準がまるでわからないし」
彼女はこれまたコントのように崩しかけた体勢を立て直しながら言った。
「第一、やたら卯上の名前を出してくるけどさ。祖母さんは望月の祖父さんと結婚して、新しい家庭を築いた訳でしょ?祖母さんにとって卯上の名前の重さとかしがらみとかは、もう関係ないはずじゃん」
蹊子の時代だと『結婚する=その家に入る』事になるのだが、彼女はやはりジェネレーションギャップと言うべきか、『結婚する=2人で新しい家庭を築く』と言うように、考えが異なる。
「私は陰陽連に登録するにあたって通用しやすいから、瑛子伯母様も勧めて下さったし、卯上の関係者って事で在籍してるけど」
「あたしは本来なら御典医の部長先生と結婚するはずだったの!だけど、お見合いの写真に傷が付いちゃったから、望月に恥をかかせない為にお祖父様と結婚するしかなくって…」
「それも嘘」
彼女は、ばっさりと切り捨てた。
「御典医の末裔とのお見合いは本当だけど、若い頃は評判の男前だった祖父さんの顔で選んだんだって、大お祖母様と瑛子伯母様から聞いたよ」
「蹊子。貴方、昔から物凄い面食いじゃないの。第一、お母様もお父様も『写真に傷が付いたから』とか訳のわからない理由で娘を無理矢理嫁がせる人じゃないわ。何を言っているの」
姉にも静かに指摘を入れられて、蹊子は黙った。必然的に傍観に徹するしか無かった李子が、「ねえねえ」と遠慮がちに口を挟む。
「お母さん、全然知らないから訊きたいんだけど、『選定ノ儀』って、危ない事は無いの?」
「大丈夫だよ。『サーベルタイガーを単独で斃して一人前として認められる』みたいに、強い妖魔と戦わされるだとかの物騒な話じゃないから」
なお、遥か古代の人類が本当に『サーベルタイガーを1人で斃して初めて一人前の大人として認める』風習を持っていたかは不明だが、彼女は『危険な儀式ではない』と強調し母を安心させる為に、あえて極端な物言いをしている。
「確か『抜けない剣を抜いてみせろ』って、アーサー王みたいな事をやるんだよな?」
「そう。それだけだよ」
予備知識として少しだけ話を聞かされていた元輝の補足に、李子は「ならいいけど」と安堵の息をつく。やはり母としては、純粋に娘の身が心配だったのだ。
「まあ剣を抜ける『主』が登場するかはわからない。ただ、登場してもしなくても私は単に、下っ端アルバイトという身でも陰陽連の一員として、人類社会を裏側から守る為に妖魔や瘴気をどうにかしていくだけさ」
「ええ。その通りよ。とてもいい心がけだわ」
瑛子は姪孫の成長に眩しそうに目を細めて頷く。正頼も「お嬢様がご立派になられて、じいやも嬉しゅうございます」と満面の笑顔だ。
こうして「気負わずに行ってらっしゃい」と、彼女は送り出されたのである。