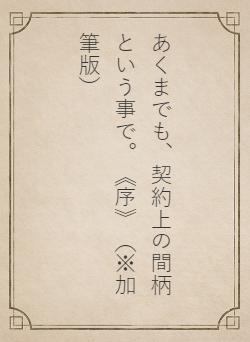「あれ?お母さん。どうしたの?」
「あ…ごめん」
彼女が自室に戻ったら、母が勉強机の抽斗を開けていた。彼女の姿を認めた李子は、気まずそうにさっと抽斗を閉めて手を引っ込める。彼女は溜め息をついて目を眇めた。
「何?またお金が足りないの?ボーナスは渡したでしょ?」
「…ごめん」
彼女は「まあ座りなよ」と李子に勉強机用の椅子を勧め、自分は床に座る。傍から見ると母親である李子に娘の彼女が叱られるような構図だが、実際は李子の方が彼女に委縮している雰囲気だ。
彼女があえて椅子を勧めたのは、理由があっての事だ。彼女は李子が若い頃にハイヒールが必須であった職場で腰や膝を傷めている事を知っている。なので李子を長時間立たせておく事も、床に座らせる事もできないのだ。
彼女は李子を見上げて切り出した。
「で?今度は何に使うの?」
「…お祖母ちゃんが、瑛子伯母ちゃんの所に通うのにタクシー代が足りないって」
ぼそぼそとした母の訴えを聞いた彼女は、げんなりとした顔で首を横に振り天を仰いだ。
彼女と元輝の祖父であり李子の父、蹊子の夫である望月成一郎が亡くなった後、卯上邸の母屋の主たる瑛子は「私ももう年だし、貴方達に迷惑をかけたくないから」と、自分から施設に入っている。その施設に、母屋に住み着いた蹊子は通い詰めている。時を同じくして、やれタクシー代が足りないだの、やれ瑛子姉さんとの食事代が必要だのと言って、蹊子は李子にお金を無心し始めた。李子は困り、アルバイトを始めた彼女のお金を、あろう事か彼女に無断で持ち出すようになった。当然だが彼女は気付き、理由と使用目的を訊いた。彼女は李子に言った。
「いやタクシーとか高いじゃん。バスだとかを使えばいい話でしょ。それとも瑛子伯母様の施設って、タクシーでないと行けないような場所だったっけ?」
「…お祖母ちゃん、バスなんて下賤の乗り物だって…」
「いや全世界の公共交通機関で働く人に謝れよ。失礼にも程があるだろ」
「…お祖母ちゃん、運転手付きの車が当たり前だったから、それがステータスなの…」
彼女の物言いではないが、公共交通機関で勤務する全ての人に、この場を借りて謝罪する。本当に申し訳ない。蹊子の価値観が特殊であるだけなのだ。何せ育ちがいわゆる乳母日傘なので、李子の言葉通り外出するならハイヤーかタクシーという常識だ。
「いやそれにしたって毎日通わないといけない訳じゃないでしょ。自分が病院にかかる訳でもあるまいし。瑛子伯母様だって、そんな無理は言わないお人だし」
「…お祖母ちゃん、お客様扱いされるのが大好きだから…」
瑛子が入っている施設は、高級ホテルさながらの設備と待遇だ。自分がおよそ入れないランクの施設だからこそ、蹊子は入り浸るのが好きなのだ。
「って、ちょっと待った。瑛子伯母様が全額負担しろとか言うつもりは無いけど、そもそも瑛子伯母様だったら、来てくれた人に車代とか食事代とか出すでしょ。瑛子伯母様の性格と言うか卯上イズム的に」
「…自分がお金持ちで気前のいい妹だって思われたいんだと思う…。お祖母ちゃん、見栄っ張りだから…」
彼女は頭痛を堪えるような顔で、片手の人差し指をこめかみに当てた。
「だからって、何でお母さんがお金をせびられないといけないの。瑛子伯母様の所に通うのも何かを奢ったりするのも、全部自分の懐でできる範囲ですればいい話でしょ。今すぐ祖母さんに言って、お金を返してもらうから。なんだったら、瑛子伯母様に言って祖母さんに話してもらおう」
「やめて!」
憤然として部屋から出ていこうとした彼女に、李子は声を上げて縋り付いて制止した。
「貴方からお金を借りたなんてわかったら、お祖母ちゃんに怒られる!」
「はあ!?」
心底訳がわからないという顔で、彼女は母を振り返った。
「『怒られる』って子供かよ!ってか、自分の母親の無理な浪費を止めるよりも、怒られない事が大事な訳!?」
「ごめん…」
李子は俯いた。
「貴方の言う通りなんだけど、お祖母ちゃん、お母さんが言うと怒るから…」
「いや無理なものは無理、無い袖は振れないでしょ」
「ごめん…。あるはずだって聞いてくれないの…」
「いっそ無視するのは?」
「ごめん…。無視したくても電話とか凄くかけられてきて、頭がおかしくなっちゃいそうなの…」
俯いたままでひたすら謝り続ける母親の姿に、彼女は片手で頭を抱えた。
「…借りたのはあくまでも祖母さんだから、お母さんにお金を返せと言うのは間違ってます」
顔を上げる李子を見ながら、彼女は淡々と続けた。
「なのでお母さんがお金を返す必要はありません。祖母さんに催促もしません。大人でも、ぽんと返せるような金額じゃないだろうからね。催促はしないけど、祖母さんからお金が返ってきたら私に渡してね」
「も、勿論だよ!」
李子は幾度も頷いた。彼女は「ならいいけど」と言ったが、半眼になって李子を見据えた。
「ただ、これからは無断でお金を持ち出すなんてやめてね。私がお金のありかだとかをお母さんに共有してるのは、私に言う暇も無い緊急事態に備えての事なんだから」
「ごめんなさい…」
項垂れた李子は、恐る恐るといった様子で顔を上げた。
「…それと、お願い。元輝には内緒にして欲しいの」
「自分の薬代が負担になってるって、元輝ならどうしても思っちゃうからね」
「…うん」
彼女は「わかったよ」と場を収めた。
そして彼女は待った。祖母から母を通してお金は返ってくると信じて、ひたすら待った。だが、祖母が『借りた』お金は1円たりとも返ってこなかった。単に毎月のように母を通して祖母からお金を無心され続けて、現在に至る。
李子は両手を合わせて娘に頭を下げた。
「お願い。貴方のボーナス、折角自分の為にとっておいたのはわかるんだけど、貸してくれない?」
「いや貸して貸してって、返してもらった覚えがまるで無いんだけど」
「ごめん…」
彼女は「あのさあ」と母を見据えた。睨み付けると言った方が近い眼差しで。
「そもそも、お金を勝手に持っていくなって言ったよね?」
「ごめんなさい…」
「何?ばれなければいいとでも思っていた訳?」
李子は勢いよく顔を上げて「違うの」と首を横に振った。
「お金の事で、また貴方に心配かけたくなかったから…」
「いや訳がわからないよ。第一、自分の財産がいきなり消えていたら、そっちの方が心配になるからね?一番最初のバイト代の時もそうだったけど」
「ごめんなさい…」
2年程前の出来事なのだが、彼女はよく覚えている。
アルバイトの初任給が入った彼女は、まず一部を母に渡した。誰に言われた訳ではないが、彼女にとって『実家にいる以上はお給料を家計に入れる』事は当たり前だった。続いて、弟にもお小遣いを渡した。『富は分け合うもの』という考えも、彼女には当然のものだった。
数日後、彼女は自分が使う分にと大切にとっておいたお給料を取り出そうとした。お給料を入れておいたはずの封筒は、空っぽだった。それからは先述の通りだ。当時の衝撃を、彼女は今でもありありと思い出す事ができる。
何より、如何に家族と言えど我が子は他人だ。その他人の机の抽斗を無断で開けてお金を探す母親の姿を想像すると情けない。ちょっと定規や鋏を借りる為とは訳が違うのだ。尤も、当の母親が一番情けなさを感じていると、彼女はわかっているのだが。
しかし、それはそれで、これはこれだ。
「謝ってれば私がお金を出すと思ってる?」
「思ってません…」
「私が頑張ってきたのは、決して祖母さんの見栄の為じゃないんだけど」
「それは本当にごめんなさい…」
彼女は片手の人差し指をこめかみに当てた。
「…私がお金を出すのは、まず巡り巡って家計に悪影響が出ないようにする為です。何より、変な所から借りられでもしたら困るし」
彼女は自分の分にとっておいたボーナスを渡しながら、母を見据えた。
「本っ当に、今月はこれ以上出せないから。無理だから。あと一応言っておくけど、お母さんが返す必要も無いから。これは決して馬鹿にしている訳じゃなくて、返済能力があるとは思ってないからね」
「ありがとう…!」
「って言うか、返済能力が無い相手になんて、普通は貸さないからね?私はアイスキャンディー…つまり高利貸しじゃないし、何より身内だからって事で、無期限・無利子だけど」
「はい…」
念の為に解説を入れると、アイスキャンディー=氷菓子=高利貸しだ。
李子は礼を言いながら退室した。閉まるドアを見ながら、彼女は遠い目で呟く。
「さようなら…。私の今月のイベントに限定グッズよ…」
スマートフォンの画面。こよなく愛するゲームの情報を発信する、いわゆる公式アカウント。例えばRPGに関しては「まあゲームだから命かけなくていいしやり直しも利くし気楽だワハハハ。それにしても人間の想像力って凄いな~」といった具合で、彼女はコンテンツを楽しんでいる。件のアカウントにて掲載されている『実装決定!』の文字が表示された華やかなイラストに、『期間限定!お申し込みはお早めに!』と書かれたグッズの写真。それらに虚ろな眼差しを向けた彼女だが、メッセージアプリからの着信の通知に目を見開いた。
「あ…ごめん」
彼女が自室に戻ったら、母が勉強机の抽斗を開けていた。彼女の姿を認めた李子は、気まずそうにさっと抽斗を閉めて手を引っ込める。彼女は溜め息をついて目を眇めた。
「何?またお金が足りないの?ボーナスは渡したでしょ?」
「…ごめん」
彼女は「まあ座りなよ」と李子に勉強机用の椅子を勧め、自分は床に座る。傍から見ると母親である李子に娘の彼女が叱られるような構図だが、実際は李子の方が彼女に委縮している雰囲気だ。
彼女があえて椅子を勧めたのは、理由があっての事だ。彼女は李子が若い頃にハイヒールが必須であった職場で腰や膝を傷めている事を知っている。なので李子を長時間立たせておく事も、床に座らせる事もできないのだ。
彼女は李子を見上げて切り出した。
「で?今度は何に使うの?」
「…お祖母ちゃんが、瑛子伯母ちゃんの所に通うのにタクシー代が足りないって」
ぼそぼそとした母の訴えを聞いた彼女は、げんなりとした顔で首を横に振り天を仰いだ。
彼女と元輝の祖父であり李子の父、蹊子の夫である望月成一郎が亡くなった後、卯上邸の母屋の主たる瑛子は「私ももう年だし、貴方達に迷惑をかけたくないから」と、自分から施設に入っている。その施設に、母屋に住み着いた蹊子は通い詰めている。時を同じくして、やれタクシー代が足りないだの、やれ瑛子姉さんとの食事代が必要だのと言って、蹊子は李子にお金を無心し始めた。李子は困り、アルバイトを始めた彼女のお金を、あろう事か彼女に無断で持ち出すようになった。当然だが彼女は気付き、理由と使用目的を訊いた。彼女は李子に言った。
「いやタクシーとか高いじゃん。バスだとかを使えばいい話でしょ。それとも瑛子伯母様の施設って、タクシーでないと行けないような場所だったっけ?」
「…お祖母ちゃん、バスなんて下賤の乗り物だって…」
「いや全世界の公共交通機関で働く人に謝れよ。失礼にも程があるだろ」
「…お祖母ちゃん、運転手付きの車が当たり前だったから、それがステータスなの…」
彼女の物言いではないが、公共交通機関で勤務する全ての人に、この場を借りて謝罪する。本当に申し訳ない。蹊子の価値観が特殊であるだけなのだ。何せ育ちがいわゆる乳母日傘なので、李子の言葉通り外出するならハイヤーかタクシーという常識だ。
「いやそれにしたって毎日通わないといけない訳じゃないでしょ。自分が病院にかかる訳でもあるまいし。瑛子伯母様だって、そんな無理は言わないお人だし」
「…お祖母ちゃん、お客様扱いされるのが大好きだから…」
瑛子が入っている施設は、高級ホテルさながらの設備と待遇だ。自分がおよそ入れないランクの施設だからこそ、蹊子は入り浸るのが好きなのだ。
「って、ちょっと待った。瑛子伯母様が全額負担しろとか言うつもりは無いけど、そもそも瑛子伯母様だったら、来てくれた人に車代とか食事代とか出すでしょ。瑛子伯母様の性格と言うか卯上イズム的に」
「…自分がお金持ちで気前のいい妹だって思われたいんだと思う…。お祖母ちゃん、見栄っ張りだから…」
彼女は頭痛を堪えるような顔で、片手の人差し指をこめかみに当てた。
「だからって、何でお母さんがお金をせびられないといけないの。瑛子伯母様の所に通うのも何かを奢ったりするのも、全部自分の懐でできる範囲ですればいい話でしょ。今すぐ祖母さんに言って、お金を返してもらうから。なんだったら、瑛子伯母様に言って祖母さんに話してもらおう」
「やめて!」
憤然として部屋から出ていこうとした彼女に、李子は声を上げて縋り付いて制止した。
「貴方からお金を借りたなんてわかったら、お祖母ちゃんに怒られる!」
「はあ!?」
心底訳がわからないという顔で、彼女は母を振り返った。
「『怒られる』って子供かよ!ってか、自分の母親の無理な浪費を止めるよりも、怒られない事が大事な訳!?」
「ごめん…」
李子は俯いた。
「貴方の言う通りなんだけど、お祖母ちゃん、お母さんが言うと怒るから…」
「いや無理なものは無理、無い袖は振れないでしょ」
「ごめん…。あるはずだって聞いてくれないの…」
「いっそ無視するのは?」
「ごめん…。無視したくても電話とか凄くかけられてきて、頭がおかしくなっちゃいそうなの…」
俯いたままでひたすら謝り続ける母親の姿に、彼女は片手で頭を抱えた。
「…借りたのはあくまでも祖母さんだから、お母さんにお金を返せと言うのは間違ってます」
顔を上げる李子を見ながら、彼女は淡々と続けた。
「なのでお母さんがお金を返す必要はありません。祖母さんに催促もしません。大人でも、ぽんと返せるような金額じゃないだろうからね。催促はしないけど、祖母さんからお金が返ってきたら私に渡してね」
「も、勿論だよ!」
李子は幾度も頷いた。彼女は「ならいいけど」と言ったが、半眼になって李子を見据えた。
「ただ、これからは無断でお金を持ち出すなんてやめてね。私がお金のありかだとかをお母さんに共有してるのは、私に言う暇も無い緊急事態に備えての事なんだから」
「ごめんなさい…」
項垂れた李子は、恐る恐るといった様子で顔を上げた。
「…それと、お願い。元輝には内緒にして欲しいの」
「自分の薬代が負担になってるって、元輝ならどうしても思っちゃうからね」
「…うん」
彼女は「わかったよ」と場を収めた。
そして彼女は待った。祖母から母を通してお金は返ってくると信じて、ひたすら待った。だが、祖母が『借りた』お金は1円たりとも返ってこなかった。単に毎月のように母を通して祖母からお金を無心され続けて、現在に至る。
李子は両手を合わせて娘に頭を下げた。
「お願い。貴方のボーナス、折角自分の為にとっておいたのはわかるんだけど、貸してくれない?」
「いや貸して貸してって、返してもらった覚えがまるで無いんだけど」
「ごめん…」
彼女は「あのさあ」と母を見据えた。睨み付けると言った方が近い眼差しで。
「そもそも、お金を勝手に持っていくなって言ったよね?」
「ごめんなさい…」
「何?ばれなければいいとでも思っていた訳?」
李子は勢いよく顔を上げて「違うの」と首を横に振った。
「お金の事で、また貴方に心配かけたくなかったから…」
「いや訳がわからないよ。第一、自分の財産がいきなり消えていたら、そっちの方が心配になるからね?一番最初のバイト代の時もそうだったけど」
「ごめんなさい…」
2年程前の出来事なのだが、彼女はよく覚えている。
アルバイトの初任給が入った彼女は、まず一部を母に渡した。誰に言われた訳ではないが、彼女にとって『実家にいる以上はお給料を家計に入れる』事は当たり前だった。続いて、弟にもお小遣いを渡した。『富は分け合うもの』という考えも、彼女には当然のものだった。
数日後、彼女は自分が使う分にと大切にとっておいたお給料を取り出そうとした。お給料を入れておいたはずの封筒は、空っぽだった。それからは先述の通りだ。当時の衝撃を、彼女は今でもありありと思い出す事ができる。
何より、如何に家族と言えど我が子は他人だ。その他人の机の抽斗を無断で開けてお金を探す母親の姿を想像すると情けない。ちょっと定規や鋏を借りる為とは訳が違うのだ。尤も、当の母親が一番情けなさを感じていると、彼女はわかっているのだが。
しかし、それはそれで、これはこれだ。
「謝ってれば私がお金を出すと思ってる?」
「思ってません…」
「私が頑張ってきたのは、決して祖母さんの見栄の為じゃないんだけど」
「それは本当にごめんなさい…」
彼女は片手の人差し指をこめかみに当てた。
「…私がお金を出すのは、まず巡り巡って家計に悪影響が出ないようにする為です。何より、変な所から借りられでもしたら困るし」
彼女は自分の分にとっておいたボーナスを渡しながら、母を見据えた。
「本っ当に、今月はこれ以上出せないから。無理だから。あと一応言っておくけど、お母さんが返す必要も無いから。これは決して馬鹿にしている訳じゃなくて、返済能力があるとは思ってないからね」
「ありがとう…!」
「って言うか、返済能力が無い相手になんて、普通は貸さないからね?私はアイスキャンディー…つまり高利貸しじゃないし、何より身内だからって事で、無期限・無利子だけど」
「はい…」
念の為に解説を入れると、アイスキャンディー=氷菓子=高利貸しだ。
李子は礼を言いながら退室した。閉まるドアを見ながら、彼女は遠い目で呟く。
「さようなら…。私の今月のイベントに限定グッズよ…」
スマートフォンの画面。こよなく愛するゲームの情報を発信する、いわゆる公式アカウント。例えばRPGに関しては「まあゲームだから命かけなくていいしやり直しも利くし気楽だワハハハ。それにしても人間の想像力って凄いな~」といった具合で、彼女はコンテンツを楽しんでいる。件のアカウントにて掲載されている『実装決定!』の文字が表示された華やかなイラストに、『期間限定!お申し込みはお早めに!』と書かれたグッズの写真。それらに虚ろな眼差しを向けた彼女だが、メッセージアプリからの着信の通知に目を見開いた。