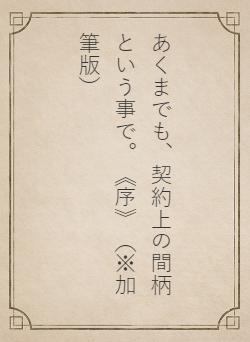「そういう訳だから、元輝にもボーナスのお裾分けだ」
「こんなにいいの!?」
給料日にして、ボーナス支給日当日。姉から渡された金額に、元輝は目を瞠った。彼女は腕組みをして大真面目に告げる。
「北欧のヴァイキングの物言いじゃないが、富は分け合うものだ」
「いや。お姉ちゃんの考えは知ってるけどさ…」
なお『富は分け合うもの』というヴァイキングの考えが基本となっているからこそ、北欧は『税金は高額だが福祉が充実している』社会が構築されたのだと言われている。
「でもさ。お姉ちゃん、自分が遊んだりする分はあるのか?」
「勿論あるとも。家計に入れるのは当然ながら優先だが、自分が使う分も確保した上で、元輝に分けているのさ」
元輝は片手を頭にやった。
「…何か、毎月毎月もらってばっかで悪いなあ。俺、お姉ちゃんに何も返せないのに…」
そう。彼女は元輝に「ほら。楽しい楽しいお給料日、即ち元輝のお小遣い日だ」と言って、お小遣いを渡している。今回はいつものお小遣いに加えて『ボーナスのお裾分け』も渡されるという、正に大盤振る舞いぶりだ。全くもって気前のいい話である。
働けるようになってからの姉は、名前は『げんき』だが病弱に生まれ付いてしまった弟に「先立つものがあれば、体力や体調の限界はあっても、遊びとか買い物とか外に出るきっかけになるでしょ」という持論の元に、お小遣いをくれる。元輝としては姉の気持ちは嬉しいのだが、やっぱり悪いと思ってしまうのだ。
その姉は腕を組んだまま、ふうーうと大きく息をついて弟を見据えた。
「何言ってんだ。何か見返りを求めて渡してる訳と違うわ」
「…うん」
「第一、その身体で勉強しつつ働けとか、鬼な事を言う私やお母さんじゃないのを、元輝は一番よく知ってるはずでしょ」
「…うん」
元輝は病弱さ故、小学校・中学校共に、まともに通う事ができなかった。姉は「家庭内家庭教師だ」とおどけて言って勉強を教えてくれたが、それが無かったら勉強についていく事ができなかった。
そんな元輝であったが、独学で高卒認定試験に合格し、今は通信制の大学に通っている。それは元輝の努力と勤勉さの賜物だと、母と姉は大いに褒めて、祝福してくれた。
「毎日毎日課題だ試験だレポートだでヒイコラ言ってるのに、その上働けとか土台無理なのわかってるし。折角学校に行けるんだから、元輝の最優先はまず勉強。働くのは就職を考える学年になってからでいいんだよ」
「…ありがとう。お姉ちゃん」
「まあ強いていうなら、お小遣いをくれるお姉ちゃんがいると、同級生に自慢してくれたまえ」
「あはは。そうする」
姉は「大事に使いなよ」と片手を振って退室した。
物心ついた頃には霊力が発現していた姉。あれは、いつか出かけた時の事だ。元輝が乗っていた子供用の車椅子を蹴り飛ばそうとした大人がいた。しかしその大人の足元に、透明な箱のような物が出現して足を止めた。むしろ件の大人は、勢いのまま箱のような物に脛を強打していた。続いて、元輝が持っていた人形。当時大好きだった特撮ヒーローのフィギュアが独りでに動いて、大人の顔面に力いっぱいパンチを食らわせた。フィギュアは車椅子の手すりに華麗に降り立ち、ポーズを決めてから動かなくなった。
「元輝。お母さん。大丈夫?」
これが、姉が元輝と母の前で初めて使った霊力だった。
姉はヒーローの人形を動かして、怖い人から自分を守ってくれた。そんな姉は正義のヒーローの仲間なのだと、幼かった元輝は心の底から信じていた。
「人形が動いたら、皆びっくりするから内緒ね」
正義のヒーローとは、押し並べて自分の正体を隠すものだ。元輝は姉との約束を守った。ヒーローの秘密を自分だけが知っているようで誇らしかった。痛い注射に苦い薬。どんな時も、自分にはヒーローがついているのだと心強かった。
今はもうヒーローに憧れるような年齢ではないものの、陰陽師の組織で大事な仕事をしている姉は、まるで少年漫画の主人公だと思っている。そんな姉に対し、同じ双子の姉弟であるはずの自分は、霊力を持たない一般人で病人。自分は家族の足を引っ張る役立たずだと言う元輝に、姉は文字通り目を丸くして、不思議そうに言った。
「普通に生まれて何が悪いのさ。霊力が無いって、つまり普通でしょ?あと、家族なのに役に立つ立たないで考えるのもおかしくない?元輝はいてくれるだけでいいんだよ?お母さんにも訊いてみたら?全く同じ答えが返って来ると思うけど?」
一点の反論の余地も無い言葉だった。
更に姉は「これは私達の大お祖母様と大お祖父様からの受け売りでもあるけど」と、母の祖父母たる卯上家前当主。卯上華子・慈朗の事を持ち出してきた。
「ほら。お祖母ちゃんは8人兄弟の中で1人だけ一般人じゃん?小さい頃に大お祖母様…華子お祖母様から聞いた話だけど、華子お祖母様は慈朗お祖父様と一緒に『普通に生まれたなら普通の幸せを掴めばいい』って言って、お祖母ちゃんを大事に育てたんだってさ」
因みに、この頃の彼女は祖母をまだ「お祖母ちゃん」と呼んでいた。
華子と慈朗の間に生まれた8人の子供達。4人の男児と3人の女児は、霊力に目覚めて人型の式神を作る事ができた。白峰学園では当然のように、全員が松クラスだった。立派な成績を修めて卒業した、正にエリート中のエリート姉弟だ。しかし兄達や姉達とは異なり、末娘である蹊子は式神を作る以前に、霊力そのものが発現しなかった。
そんな末娘を、当たり前の事ながら華子と慈朗は案じた。こと華子は、やはり自分がお胎に宿して育んで産み出した母親という立場であるからか、自分の身体に問題があったのではないかと思い悩んだ。しかし妻である華子を心から想っていた慈朗は言った。曰く「蹊子は間違いなく私達の子だ。たまたま霊力が無い事は、何も悪い事じゃない。普通に生まれ付いた事の何が悪い?妖魔とは関係ない所で幸せになれるように育てよう」と。そう言って、我が子達を分け隔てする事なく慈しんだ。
時は流れ、李子が15歳の頃に慈朗は永眠したが、夫の言葉を華子はいつまでも覚えていた。霊力が発現したばかりの曾孫である彼女に、夫への惚気が半分ではあったものの、話を聞かせた。彼女は幼いながらも華子の言葉を理解し、曾祖父母の理念を『卯上イズム』と呼んで尊重している。
「私も華子お祖母様達と同じ考えだよ。確かに元輝は病気がちで『普通』が遠いかもしれないけど、でも妖魔と命をかけて戦わないといけない訳じゃないから、いいじゃん。これはお母さんにも言える事だけど、元輝は普通に暮らしなよ。何かあったら、私が守るからさ」
このような事も、姉から言われた。
さてもさても勇ましい姉に、元輝は全くもって頭が上がらない。しかし決して不平等な間柄ではない。それが賀茂姉弟だ。
「こんなにいいの!?」
給料日にして、ボーナス支給日当日。姉から渡された金額に、元輝は目を瞠った。彼女は腕組みをして大真面目に告げる。
「北欧のヴァイキングの物言いじゃないが、富は分け合うものだ」
「いや。お姉ちゃんの考えは知ってるけどさ…」
なお『富は分け合うもの』というヴァイキングの考えが基本となっているからこそ、北欧は『税金は高額だが福祉が充実している』社会が構築されたのだと言われている。
「でもさ。お姉ちゃん、自分が遊んだりする分はあるのか?」
「勿論あるとも。家計に入れるのは当然ながら優先だが、自分が使う分も確保した上で、元輝に分けているのさ」
元輝は片手を頭にやった。
「…何か、毎月毎月もらってばっかで悪いなあ。俺、お姉ちゃんに何も返せないのに…」
そう。彼女は元輝に「ほら。楽しい楽しいお給料日、即ち元輝のお小遣い日だ」と言って、お小遣いを渡している。今回はいつものお小遣いに加えて『ボーナスのお裾分け』も渡されるという、正に大盤振る舞いぶりだ。全くもって気前のいい話である。
働けるようになってからの姉は、名前は『げんき』だが病弱に生まれ付いてしまった弟に「先立つものがあれば、体力や体調の限界はあっても、遊びとか買い物とか外に出るきっかけになるでしょ」という持論の元に、お小遣いをくれる。元輝としては姉の気持ちは嬉しいのだが、やっぱり悪いと思ってしまうのだ。
その姉は腕を組んだまま、ふうーうと大きく息をついて弟を見据えた。
「何言ってんだ。何か見返りを求めて渡してる訳と違うわ」
「…うん」
「第一、その身体で勉強しつつ働けとか、鬼な事を言う私やお母さんじゃないのを、元輝は一番よく知ってるはずでしょ」
「…うん」
元輝は病弱さ故、小学校・中学校共に、まともに通う事ができなかった。姉は「家庭内家庭教師だ」とおどけて言って勉強を教えてくれたが、それが無かったら勉強についていく事ができなかった。
そんな元輝であったが、独学で高卒認定試験に合格し、今は通信制の大学に通っている。それは元輝の努力と勤勉さの賜物だと、母と姉は大いに褒めて、祝福してくれた。
「毎日毎日課題だ試験だレポートだでヒイコラ言ってるのに、その上働けとか土台無理なのわかってるし。折角学校に行けるんだから、元輝の最優先はまず勉強。働くのは就職を考える学年になってからでいいんだよ」
「…ありがとう。お姉ちゃん」
「まあ強いていうなら、お小遣いをくれるお姉ちゃんがいると、同級生に自慢してくれたまえ」
「あはは。そうする」
姉は「大事に使いなよ」と片手を振って退室した。
物心ついた頃には霊力が発現していた姉。あれは、いつか出かけた時の事だ。元輝が乗っていた子供用の車椅子を蹴り飛ばそうとした大人がいた。しかしその大人の足元に、透明な箱のような物が出現して足を止めた。むしろ件の大人は、勢いのまま箱のような物に脛を強打していた。続いて、元輝が持っていた人形。当時大好きだった特撮ヒーローのフィギュアが独りでに動いて、大人の顔面に力いっぱいパンチを食らわせた。フィギュアは車椅子の手すりに華麗に降り立ち、ポーズを決めてから動かなくなった。
「元輝。お母さん。大丈夫?」
これが、姉が元輝と母の前で初めて使った霊力だった。
姉はヒーローの人形を動かして、怖い人から自分を守ってくれた。そんな姉は正義のヒーローの仲間なのだと、幼かった元輝は心の底から信じていた。
「人形が動いたら、皆びっくりするから内緒ね」
正義のヒーローとは、押し並べて自分の正体を隠すものだ。元輝は姉との約束を守った。ヒーローの秘密を自分だけが知っているようで誇らしかった。痛い注射に苦い薬。どんな時も、自分にはヒーローがついているのだと心強かった。
今はもうヒーローに憧れるような年齢ではないものの、陰陽師の組織で大事な仕事をしている姉は、まるで少年漫画の主人公だと思っている。そんな姉に対し、同じ双子の姉弟であるはずの自分は、霊力を持たない一般人で病人。自分は家族の足を引っ張る役立たずだと言う元輝に、姉は文字通り目を丸くして、不思議そうに言った。
「普通に生まれて何が悪いのさ。霊力が無いって、つまり普通でしょ?あと、家族なのに役に立つ立たないで考えるのもおかしくない?元輝はいてくれるだけでいいんだよ?お母さんにも訊いてみたら?全く同じ答えが返って来ると思うけど?」
一点の反論の余地も無い言葉だった。
更に姉は「これは私達の大お祖母様と大お祖父様からの受け売りでもあるけど」と、母の祖父母たる卯上家前当主。卯上華子・慈朗の事を持ち出してきた。
「ほら。お祖母ちゃんは8人兄弟の中で1人だけ一般人じゃん?小さい頃に大お祖母様…華子お祖母様から聞いた話だけど、華子お祖母様は慈朗お祖父様と一緒に『普通に生まれたなら普通の幸せを掴めばいい』って言って、お祖母ちゃんを大事に育てたんだってさ」
因みに、この頃の彼女は祖母をまだ「お祖母ちゃん」と呼んでいた。
華子と慈朗の間に生まれた8人の子供達。4人の男児と3人の女児は、霊力に目覚めて人型の式神を作る事ができた。白峰学園では当然のように、全員が松クラスだった。立派な成績を修めて卒業した、正にエリート中のエリート姉弟だ。しかし兄達や姉達とは異なり、末娘である蹊子は式神を作る以前に、霊力そのものが発現しなかった。
そんな末娘を、当たり前の事ながら華子と慈朗は案じた。こと華子は、やはり自分がお胎に宿して育んで産み出した母親という立場であるからか、自分の身体に問題があったのではないかと思い悩んだ。しかし妻である華子を心から想っていた慈朗は言った。曰く「蹊子は間違いなく私達の子だ。たまたま霊力が無い事は、何も悪い事じゃない。普通に生まれ付いた事の何が悪い?妖魔とは関係ない所で幸せになれるように育てよう」と。そう言って、我が子達を分け隔てする事なく慈しんだ。
時は流れ、李子が15歳の頃に慈朗は永眠したが、夫の言葉を華子はいつまでも覚えていた。霊力が発現したばかりの曾孫である彼女に、夫への惚気が半分ではあったものの、話を聞かせた。彼女は幼いながらも華子の言葉を理解し、曾祖父母の理念を『卯上イズム』と呼んで尊重している。
「私も華子お祖母様達と同じ考えだよ。確かに元輝は病気がちで『普通』が遠いかもしれないけど、でも妖魔と命をかけて戦わないといけない訳じゃないから、いいじゃん。これはお母さんにも言える事だけど、元輝は普通に暮らしなよ。何かあったら、私が守るからさ」
このような事も、姉から言われた。
さてもさても勇ましい姉に、元輝は全くもって頭が上がらない。しかし決して不平等な間柄ではない。それが賀茂姉弟だ。