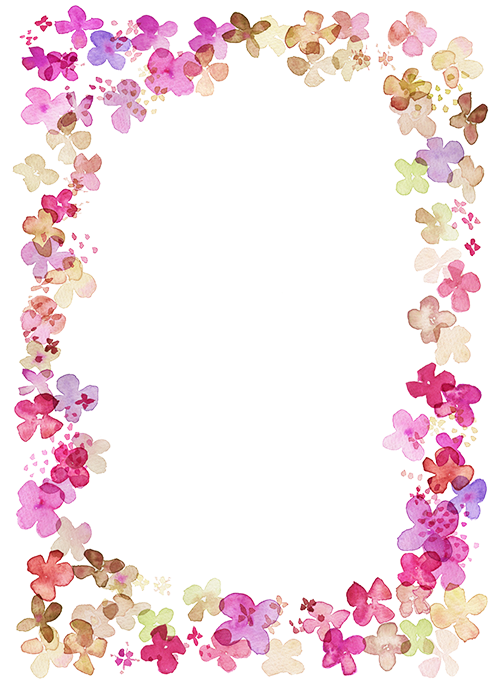「真矢さー、何で彼女つくんねーの?」
塩川が間延びした調子で言いながら俺を見た。自転車越しに視線を合わせると、「この前一年に告られてんの見たんだよね」と得意げな顔をする。奥で斎藤が目を見開いたのが見えた。
押している自転車のタイヤががヌルヌルと地面を滑る。
二人に足並みを揃えながら遠くの山の峰を眺めると、塩川が肩を叩いてきた。
「まさかお前かもう彼女いる?」
「いねえよ」
「じゃあ興味ないとか……こわっ」
「変な想像すんな」
塩川のいつもの軽口だと分かっているのに、背中から不快感が迫ってきた。
女も男も関係ない。
恋人なんてつくれるか。
家に吸血鬼が居るっていうのに。
「あ、じゃあさ」
斎藤の合唱部で練習を重ねた透き通った声が耳に届く。
前かごに入れていたペットボトルのスポーツドリンクを取り出して、片手でハンドルを操作しながら口に含むと、温くて喉に張り付くような味がした。
「猫でも拾ったとか?」
ぐげほっ、げほっ。
液体が気管に流れて盛大に噎せた。思わず立ち止まる。
何だ図星かよーつまんねー、と塩川が暢気に先を歩く。斎藤が鞄からポケットティッシュを出しながら、心配そうに眉尻を下げた。
「てか真矢んちのアパート、ペット大丈夫なの?」
「ばあちゃんの管理してるアパートだから」
「ああ、そうなんだ」
差し出されたティッシュで口とペットボトルを拭く。
寝ぐせを直さず来たような塩川の後頭部に追いつくように、斎藤と早足で進んだ。その髪を、
塩川はおしゃれだと言うが、信用に値しない。
「んじゃあな」
「また明日」
線路を超えた先のT字路で、二人と別れた。
サドルを跨ぎ、ペダルを踏む。県立大学と、香ばしい匂いのする焼肉店の前を通り過ぎ、レンタルビデオ屋、写真館などを過ぎて橋を渡る。横を通ったバスの排気が熱くて顔を顰めた。横断歩道で反対の歩道に着くと、道路沿いに外壁に蔦の這う、廃れたアパートが見える。
一階の一番奥の部屋が祖母の居室、他に二部屋あって、どちらも大学生が住んでいるようだ。
二階の道路側の部屋が俺が住まわせてもらっている部屋で、他は空室。
足を乗せるとギイギイと軋んだ音のする鉄階段を上り、足早に廊下を進んで自室の鍵を開けた。
「ただいま」
開け放たれた部屋の引き戸の奥、正面に見えるレースカーテンから、容赦のない陽射しが注ぎ込んでいる。その窓に背を向けるように、部屋の隅を陣取る吸血鬼は、膝を抱えて座っていた。
「ただいま」
整頓された四文字を繰り返す。
ジンは僅かに顔を上げて、呪いをかけるような視線を向け、再び膝に顔を埋めた。
畳に鞄を下ろし、制服をハンガーに掛け、長押に引っ掛ける。Tシャツとスウェットのズボンに着替え、座卓の前に腰を下ろしてジンを見た。朝見たままの体勢でそこに居る。
ジンが何を考えているのかなんて、考えるだけ無駄だ。ほとんどの問い掛けに反応せず、生存に必要な日常活動作さえ疎かにする。
暗い双眸が「死にたい」と訴えてくる。
夕飯まで時間があるので鞄から教科書を引っ張り出す。期末考査の期間は部活動は停止されるので、時間にはゆとりがある。
部屋で過ごす時間が増えるほど海底にいるような気持ちが続く。波の騒めきも届かない、墜落した先の解放感。
同じところにいると思うと安心する。
指先で赤ペンを回した。
ジンが食事をしているときの目は、仄暗い赤色をしている。
「おい」
声を出したか疑いたくなるほど、狭い景色はどこもかしこも変化がなかった。
「なあ」
ジンがどろりと顔を上げる。
俺の声は低くて、彼女に圧をかけているに違いない。
腰を上げてジンの傍まで行き、居座るように胡坐をかいた。
「何で喋らない」
問い掛けは、見えない壁にぶつかり呆気なく落ちる。ジンが俺を見据えたまま唇をきつく結んだ。
「こんなに陽射し入ってきても大丈夫なのか?」
答えない。
「血、本当に週一でいいんだろうな?」
答えない。
「睡眠は」
「……どうしてそんなこと聞くの」
ジンの声は怒気と疑念を含んで凛としていた。赤くふっくらとした唇が小さく動く。
「あなたには関係ない。私は、ここにいるのが嫌」
「じゃあ出て行けばいい。何で留まるんだ」
俺の言葉を、責められていると受け取ったであろうジンが立ち上がろうとしたので、腕を掴んで止めた。いきなり勢いを失ったジンの体が倒れてくるのを胸で受け止める。体は外見相応に軽かった。
「離してよ……!」
抱き締めた腕の中で、懐いてない子猫のように暴れる。そんな抵抗はまるで無意味なのに。
「嫌だ」
「意味が、分かんない」
声が震えていた。ジンは情緒不安定だ。普段表情を隠すくせに、感情がよく揺れる。
いや、俺のせいかもしれない。情緒を乱しているのかもしれない。
決断を、してしまえばいいのに。
「血を飲んだら落ち着くか?」
Tシャツの袖を捲り上げ、横線だらけの二の腕を見せる。至近距離で見たジンは、ホラー映画を見て怯える動作をするように、顔を背けた。
「やめてよ。そんなので、気落ちが変わるわけない」
「じゃあこうしてろ」
ジンの耳が俺の胸に当たるように引き寄せる。
ジンは僅かに体を動かしたが、すぐに大人しくなった。
「何これ……?」
呟く声を受けながら、力を込めれば折れてしまいそうな腰を片手で抱き締める。
「心臓の音。聞くと落ち着くらしい」
至って平静を装ったが、早鐘を打っているかもしれない。
ジンの表情は見えない。しかし耳をそばだてているのは分かった。
抵抗しないのをいいことに、髪を梳いてやる。会った当時艶のなかった髪は、さらさらと泳いでいた。
自分の体と違って柔らかい。
触れるといつもそう思う。特に胸元が。
こういった思考が浮かぶとき、淡白だと評価していた自分自身も、成長段階の男だということを思い知らされる。それ以上、何かを求めているつもりはないが。
「これ、止まると死ぬ?」
顎の下でジンが砂を掬うように言った。
「死ぬな」
返すと身動ぎをして、上目づかいで俺を見た。睫毛が長い。
「こわい」
「死ぬのが?」
「これが……聞こえなくなるのが」
ジンは再び俯いて、耳を傾け始めた。
肺から淀んだ息を吐いて、西日の入るレースカーテンの見る。
日は随分傾いていた。