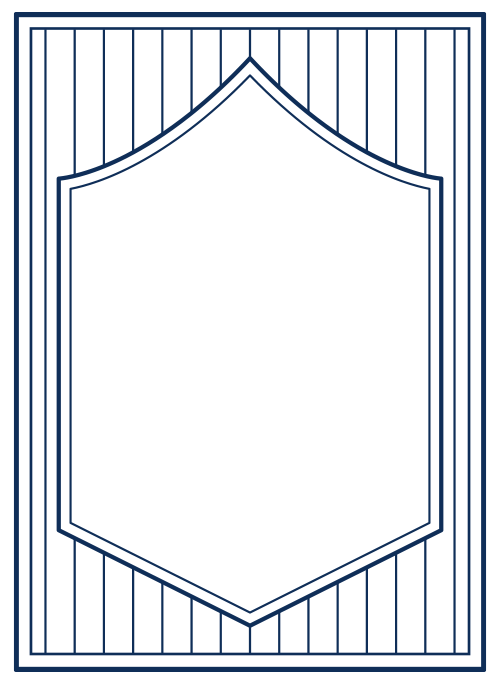その夜がきっかけとなり、それからたびたび幻夜が沙和の髪に、かんざしを挿してくれるようになった。
かんざしが挿せるならば、と沙和の髪を梳くのも幻夜がしてくれる。
かんざしや櫛を手にする幻夜の姿は、沙和の目にも普通に見える。鏡にだって映った。物だけが動いて見えるなんてこともない。
手のぬくもりこそないけれど、幻夜はいつも沙和の髪をていねいに扱った。沙和が気恥ずかしくなるほどに。
だからこれはそのお礼だ。
「辰野。お芋のお鍋、そろそろ火を止めたほうがいいかも。止めていい?」
「そうですか? まだ早い気もしますが……お願いします!」
今ではすっかり緊張も解けた口調で辰野に告げ、沙和はかまどの火を止めた。
辰野が隣で汁物に味噌を溶く。よい匂いが食欲をくすぐった。
ここで暮らすようになって、沙和は初めて醤油や味噌の匂いを幸せだと感じるようになったと思う。以前は、どの匂いも叔父家族のためにあるものであり、その家族の中に沙和はいなかったから。
着る物やかんざしをもらった翌日から、沙和は辰野と並んで台所に立つようになった。
最初は辰野に固辞されたし、沙和としても彼女の仕事を奪うつもりはない。けれど、味音痴だという幻夜の口に合うものを知るのは楽しかった。
離れの洋館には台所がないので、沙和が辰野と並ぶのは主屋の台所だ。作りは叔母たちの家の台所をひと回り広くした感じだろうか。なかには沙和が目にしたことのないものもあったが、思ったより動きやすかった。
辰野には驚かれたけれど、箕島でも下女だったのだから、沙和はすぐにてきぱきと動けるようになった。
今では、辰野と一緒に食事を作るのも毎日の楽しみのひとつになっている。
沙和は、気になっていたことを口にした。
「辰野は、幻夜さまがどうして冥府の番人というものになられたのか、知ってるの?」
「詳しくは存じません。ですが……幻夜さまはお若いころから高階家の当主として、家を空けられることが多かったのですが、あるとき高熱のお体で戻ってこられたことがありました」
「高熱……風邪ですか?」
「いえ、ほかの症状はまったくなく、ただ体が火のように熱いんです。そんな日が一週間ほど続いたと思ったら、けろりと元気になられて。そのときに、『冥府に片足を突っこんだ』とおっしゃいました。私は、死にかけになった状態のことをそうおっしゃったものとばかり思っていたのですが……それから数日して、旦那様のお召し物を替える際に」
辰野はそこで手を止めた。その手をじっと見おろす。
「……手が、旦那様の体をすり抜けてしまって。もう仰天してしまって、亡霊だと叫んでしまいました」
「そんなことが……」
沙和は先日、かんざしを挿してもらったときのことを思い出した。もし、辰野から事前に聞いていなかったら、沙和も似たようなことになっていたかもしれない。
痛みをこらえるようにした幻夜の顔が浮かび、胸がぎゅっとなった。
「でも、旦那様は覚悟を決めておいでですよ」
かんざしが挿せるならば、と沙和の髪を梳くのも幻夜がしてくれる。
かんざしや櫛を手にする幻夜の姿は、沙和の目にも普通に見える。鏡にだって映った。物だけが動いて見えるなんてこともない。
手のぬくもりこそないけれど、幻夜はいつも沙和の髪をていねいに扱った。沙和が気恥ずかしくなるほどに。
だからこれはそのお礼だ。
「辰野。お芋のお鍋、そろそろ火を止めたほうがいいかも。止めていい?」
「そうですか? まだ早い気もしますが……お願いします!」
今ではすっかり緊張も解けた口調で辰野に告げ、沙和はかまどの火を止めた。
辰野が隣で汁物に味噌を溶く。よい匂いが食欲をくすぐった。
ここで暮らすようになって、沙和は初めて醤油や味噌の匂いを幸せだと感じるようになったと思う。以前は、どの匂いも叔父家族のためにあるものであり、その家族の中に沙和はいなかったから。
着る物やかんざしをもらった翌日から、沙和は辰野と並んで台所に立つようになった。
最初は辰野に固辞されたし、沙和としても彼女の仕事を奪うつもりはない。けれど、味音痴だという幻夜の口に合うものを知るのは楽しかった。
離れの洋館には台所がないので、沙和が辰野と並ぶのは主屋の台所だ。作りは叔母たちの家の台所をひと回り広くした感じだろうか。なかには沙和が目にしたことのないものもあったが、思ったより動きやすかった。
辰野には驚かれたけれど、箕島でも下女だったのだから、沙和はすぐにてきぱきと動けるようになった。
今では、辰野と一緒に食事を作るのも毎日の楽しみのひとつになっている。
沙和は、気になっていたことを口にした。
「辰野は、幻夜さまがどうして冥府の番人というものになられたのか、知ってるの?」
「詳しくは存じません。ですが……幻夜さまはお若いころから高階家の当主として、家を空けられることが多かったのですが、あるとき高熱のお体で戻ってこられたことがありました」
「高熱……風邪ですか?」
「いえ、ほかの症状はまったくなく、ただ体が火のように熱いんです。そんな日が一週間ほど続いたと思ったら、けろりと元気になられて。そのときに、『冥府に片足を突っこんだ』とおっしゃいました。私は、死にかけになった状態のことをそうおっしゃったものとばかり思っていたのですが……それから数日して、旦那様のお召し物を替える際に」
辰野はそこで手を止めた。その手をじっと見おろす。
「……手が、旦那様の体をすり抜けてしまって。もう仰天してしまって、亡霊だと叫んでしまいました」
「そんなことが……」
沙和は先日、かんざしを挿してもらったときのことを思い出した。もし、辰野から事前に聞いていなかったら、沙和も似たようなことになっていたかもしれない。
痛みをこらえるようにした幻夜の顔が浮かび、胸がぎゅっとなった。
「でも、旦那様は覚悟を決めておいでですよ」