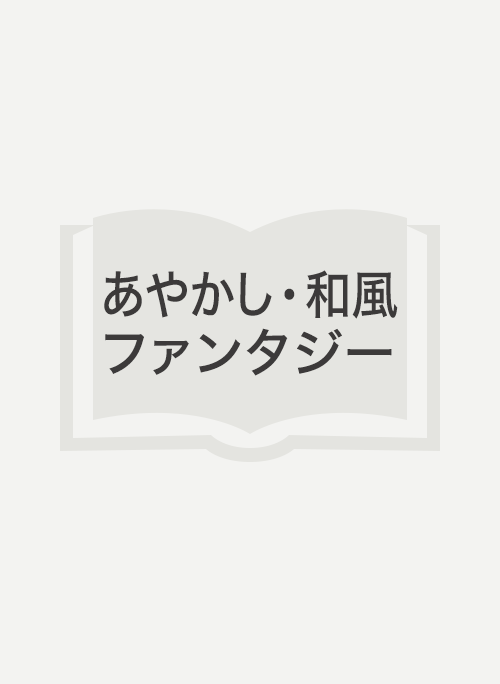「灯璃さま!」
自動車で待機していろと指示された蓮司も痺れを切らしたのか灯璃の元へ駆け寄ってきた。
流していた涙が止まったが、まだ瞳を潤ませながら灯璃の隣に立っている千冬を見て戸惑った表情を浮かべる。
「あの灯璃さま、こちらのご令嬢は……?」
蓮司の問いかけを聞いた灯璃は千冬の肩を抱き寄せた。
「私の花嫁だ」
「え……!?花嫁さまが見つかったのですか!?」
あまりの驚きに目を丸くし身体を硬直させている。
それもそのはず。
数十年見つからなかった人間の花嫁が突然現れたのだから。
灯璃は呆気にとられている蓮司を気にもせず千冬の顔を覗き込む。
「千冬、家はどこだ?もう夜も遅い。送っていこう」
「家は……その……」
勝手に屋敷を出た千冬にはもう帰る場所がない。
今頃、姿を消したことに気がついているだろう。
野垂れ死ぬのを待って探さずにいるか憎い娘を虐めるのが足りず必死に探し回っているかどちらかだ。
もし使用人総出で探しているのだとしたら、きっと見つかるのも時間の問題。
今、嶺木家に連れて行かれたら虐めが酷くなる明日を継母達は待たない。
灯璃はそんな顔を青ざめさせ恐怖に怯えている千冬を見て何かを察した。
そして安心させるように優しく笑いかけた。
「帰れない事情があるのなら私の屋敷で暮らさないか」
「え……!?で、でも……」
住む場所が出来るのは素直に嬉しい。
だが、かくりよ國の帝である鬼城家には嶺木家とは比べものにならないほどの使用人が働いているはずだ。
そこに突然、紫紺色の瞳をもつ花嫁が現れてここで暮らすと言われたら不安を与えかねない。
それに花嫁だからといって出逢った初日から共に暮らすだなんて、甘えるようなことをしていいのだろうか。
戸惑う千冬の気持ちを汲み取ったように灯璃は言葉を続けた。
「私の屋敷に勤める者は誰も千冬を咎めたり嫌ったりしない。それに遠慮などする必要もない。沢山甘えていいんだ」
「鬼城さま……」
誰かに頼ること、甘えることなんて微塵も許されなかった。
でもこれからは違う。
つらかったらつらいと、悲しかったら悲しいと言葉にして伝えていい。
人はそんなに簡単には変われない。
もしかしたら、また何か抱え込んでしまうかもしれない。
(こんなわたしでも願っていいのなら……)
少しの勇気を振り絞って千冬は口を開いた。
「では……よろしくお願い致します」
丁寧にお辞儀をすると灯璃はよほど甘えてくれて嬉しかったのか、顔をほころばせていた。
自動車で待機していろと指示された蓮司も痺れを切らしたのか灯璃の元へ駆け寄ってきた。
流していた涙が止まったが、まだ瞳を潤ませながら灯璃の隣に立っている千冬を見て戸惑った表情を浮かべる。
「あの灯璃さま、こちらのご令嬢は……?」
蓮司の問いかけを聞いた灯璃は千冬の肩を抱き寄せた。
「私の花嫁だ」
「え……!?花嫁さまが見つかったのですか!?」
あまりの驚きに目を丸くし身体を硬直させている。
それもそのはず。
数十年見つからなかった人間の花嫁が突然現れたのだから。
灯璃は呆気にとられている蓮司を気にもせず千冬の顔を覗き込む。
「千冬、家はどこだ?もう夜も遅い。送っていこう」
「家は……その……」
勝手に屋敷を出た千冬にはもう帰る場所がない。
今頃、姿を消したことに気がついているだろう。
野垂れ死ぬのを待って探さずにいるか憎い娘を虐めるのが足りず必死に探し回っているかどちらかだ。
もし使用人総出で探しているのだとしたら、きっと見つかるのも時間の問題。
今、嶺木家に連れて行かれたら虐めが酷くなる明日を継母達は待たない。
灯璃はそんな顔を青ざめさせ恐怖に怯えている千冬を見て何かを察した。
そして安心させるように優しく笑いかけた。
「帰れない事情があるのなら私の屋敷で暮らさないか」
「え……!?で、でも……」
住む場所が出来るのは素直に嬉しい。
だが、かくりよ國の帝である鬼城家には嶺木家とは比べものにならないほどの使用人が働いているはずだ。
そこに突然、紫紺色の瞳をもつ花嫁が現れてここで暮らすと言われたら不安を与えかねない。
それに花嫁だからといって出逢った初日から共に暮らすだなんて、甘えるようなことをしていいのだろうか。
戸惑う千冬の気持ちを汲み取ったように灯璃は言葉を続けた。
「私の屋敷に勤める者は誰も千冬を咎めたり嫌ったりしない。それに遠慮などする必要もない。沢山甘えていいんだ」
「鬼城さま……」
誰かに頼ること、甘えることなんて微塵も許されなかった。
でもこれからは違う。
つらかったらつらいと、悲しかったら悲しいと言葉にして伝えていい。
人はそんなに簡単には変われない。
もしかしたら、また何か抱え込んでしまうかもしれない。
(こんなわたしでも願っていいのなら……)
少しの勇気を振り絞って千冬は口を開いた。
「では……よろしくお願い致します」
丁寧にお辞儀をすると灯璃はよほど甘えてくれて嬉しかったのか、顔をほころばせていた。