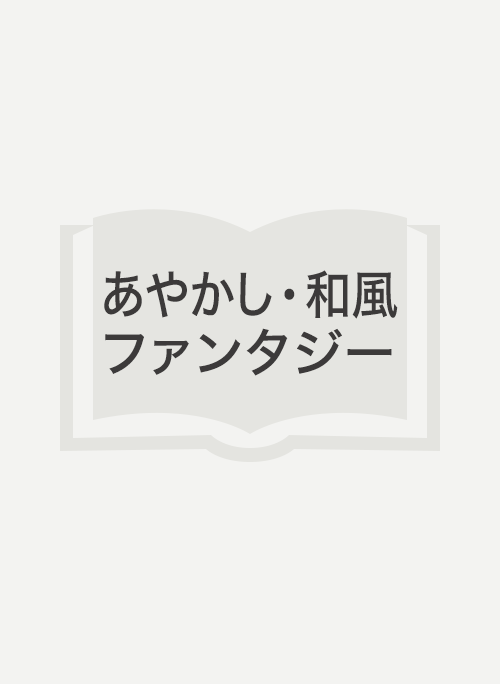継母達から虐げられていた千冬は自分には生きている価値がない、幸せな未来など待っていないと絶望していた。
心も身体も疲弊したことから生きることを諦め、川に身を投げ入れようとした矢先、眉目秀麗な男性に助けられる。
そして今、その男性に『君は鬼である自分の花嫁だ』と言われ抱きしめられている。
千冬は突然のことに頭が混乱し、灯璃と名乗る男性の言っているのを全く理解しないまま手で身体を押し返す。
相手は格上の鬼の当主であるため、そこまで強くは出来ないが。
しかも男性に抱きしめられるのは初めてで恥ずかしさで身体中が熱い。
数回、口をパクパクとさせやっとの思いで声が出る。
「あのっ、何が何だか……」
先ほどからの展開が早く、理解が追いつかない。
妹の依鈴と比べられ、要領も悪いと継母達から散々言われてきた千冬なら尚更だった。
「話は聞いたことがないか?あやかしは時に人間の娘から花嫁を選ぶと」
「わ、わたしがその花嫁……ということですか?」
「ああ。そうだ」
女性なら誰しも憧れるあやかしの花嫁という存在。
その中でも鬼の花嫁になりたいと願いは多い。
やっと理解した。
自分は鬼の中でも本家である鬼城家の当主の花嫁に選ばれたのだと。
選ばれた女性は生涯にわたり愛され、何不自由なく幸せに暮らせる。
夢のような出来事に千冬の顔に浮かんでいたのは笑みではなかった。
「違います……!」
「え?」
千冬は立ち上がり、一歩後ろへ下がった。
大人しそうだと思っていた花嫁が突然、声を大きくし灯璃は意表を突かれたがすぐに立ち上がり向き合う。
顔を俯かせ、こちらと瞳を合わせようとしない。
よく見ると繊細さを感じさせる手が小刻みに震えているのが分かった。
「わたしが花嫁だなんて何かの間違いです」
拒絶にも聞こえるような声色。
『嬉しい』と微笑んでほしかったがその想いも虚しく正反対の反応だった。
しかしそれでめげるようでは鬼城家の当主は務まらない。
その閉ざした心に寄り添うように灯璃は軽く膝を曲げ目線を合わせた。
「間違いではない。君の瞳を見て花嫁だと確信したんだ」
「鬼城さまは古来から伝わる話は知っていますか?わたしの瞳は祟り神と同じ、紫紺色なのです」
もし知らなければ、きっとそのような呪われた花嫁など迎えられないと諦めるだろう。
(鬼城さまは知らずにわたしに慈悲を与えてくださったのだわ)
灯璃の『やはり花嫁はお前ではなかった』という言葉を聞くことを俯きながら待っていると……。
「そんな馬鹿げた話を信じるわけないだろう」
「……え」
予想外の反応に思わず顔を上げると真剣な赤い瞳がこちらを射抜く。
屋敷中の誰もが気味悪がっており仮に外に出たとしても皆、同じ反応だと勝手に想像していた。
「で、でもこの瞳のせいで本当に不幸なことが起きたのです」
病気が回復してきたはずの母の突然の急死、妹の婚約の破棄。
身近にいる人を苦しめて悲しませてきた。
それは紛れもない事実でこれから先は誰一人として傷つけないように孤独に生きてゆく。
「もう誰かを不幸にしたくないのです。だから鬼城さまもわたしなんかの傍にいない方が……」
お願いだから自分から離れて。
もう目の前で悪夢のような出来事を見るのは耐えられない。
自分でもわかるほど声が震えており、こうして人を突き放すことがどれだけつらいか。
でもそれが千冬にとって最善なのだ。
ここまで全てを話せばきっと考えを改めてくれる、そう思っていると。
「……!」
引き寄せられたかと思えば気づけば千冬は灯璃の腕の中にいた。
もう離さないとでもいうようにと強く抱きしめている。
予想に反する灯璃の行動に驚かされ心臓が煩いくらいに鳴っている。
「君が言うその不幸も偶然起きたものだ。私はくだらない言い伝えなど信じない。だって私は君に出逢えてこんなにも幸せなのだから」
その声はとても温かくて嘘偽りなど少しもないのだと分かった。
この先、歩む道は真っ暗闇で光はないと全てを諦めていた千冬もどこかで誰かに必要とされたい、愛されたいと願っていたなだと今の言葉を聞いて気がついた。
「生きていて、貴方の傍にいて良いのですか……?」
声を詰まらせながら涙を流す千冬。
灯璃はその頬に伝う涙を指でそっと拭うと千冬の顔を上へ向かせる。
「ああ、ずっと傍にいてほしい。私の愛おしい花嫁。して君の名を聞かせてくれないか」
こんなにも自分を想ってくれる人は他にいないだろうと不思議と確信できる。
幸せになることが許されるのなら、この奇跡を手放したくない。
「嶺木……千冬です」
「千冬……。愛らしい名だ」
二人の身体を風が撫でる。
春の夜の風でも今はなぜか寒さを感じなかった。
灯璃から伝わる体温が温かく心地良い。
夜空に浮かぶ満月の月明かりが千冬の嫁入りを祝福するように二人を照らしていた。
心も身体も疲弊したことから生きることを諦め、川に身を投げ入れようとした矢先、眉目秀麗な男性に助けられる。
そして今、その男性に『君は鬼である自分の花嫁だ』と言われ抱きしめられている。
千冬は突然のことに頭が混乱し、灯璃と名乗る男性の言っているのを全く理解しないまま手で身体を押し返す。
相手は格上の鬼の当主であるため、そこまで強くは出来ないが。
しかも男性に抱きしめられるのは初めてで恥ずかしさで身体中が熱い。
数回、口をパクパクとさせやっとの思いで声が出る。
「あのっ、何が何だか……」
先ほどからの展開が早く、理解が追いつかない。
妹の依鈴と比べられ、要領も悪いと継母達から散々言われてきた千冬なら尚更だった。
「話は聞いたことがないか?あやかしは時に人間の娘から花嫁を選ぶと」
「わ、わたしがその花嫁……ということですか?」
「ああ。そうだ」
女性なら誰しも憧れるあやかしの花嫁という存在。
その中でも鬼の花嫁になりたいと願いは多い。
やっと理解した。
自分は鬼の中でも本家である鬼城家の当主の花嫁に選ばれたのだと。
選ばれた女性は生涯にわたり愛され、何不自由なく幸せに暮らせる。
夢のような出来事に千冬の顔に浮かんでいたのは笑みではなかった。
「違います……!」
「え?」
千冬は立ち上がり、一歩後ろへ下がった。
大人しそうだと思っていた花嫁が突然、声を大きくし灯璃は意表を突かれたがすぐに立ち上がり向き合う。
顔を俯かせ、こちらと瞳を合わせようとしない。
よく見ると繊細さを感じさせる手が小刻みに震えているのが分かった。
「わたしが花嫁だなんて何かの間違いです」
拒絶にも聞こえるような声色。
『嬉しい』と微笑んでほしかったがその想いも虚しく正反対の反応だった。
しかしそれでめげるようでは鬼城家の当主は務まらない。
その閉ざした心に寄り添うように灯璃は軽く膝を曲げ目線を合わせた。
「間違いではない。君の瞳を見て花嫁だと確信したんだ」
「鬼城さまは古来から伝わる話は知っていますか?わたしの瞳は祟り神と同じ、紫紺色なのです」
もし知らなければ、きっとそのような呪われた花嫁など迎えられないと諦めるだろう。
(鬼城さまは知らずにわたしに慈悲を与えてくださったのだわ)
灯璃の『やはり花嫁はお前ではなかった』という言葉を聞くことを俯きながら待っていると……。
「そんな馬鹿げた話を信じるわけないだろう」
「……え」
予想外の反応に思わず顔を上げると真剣な赤い瞳がこちらを射抜く。
屋敷中の誰もが気味悪がっており仮に外に出たとしても皆、同じ反応だと勝手に想像していた。
「で、でもこの瞳のせいで本当に不幸なことが起きたのです」
病気が回復してきたはずの母の突然の急死、妹の婚約の破棄。
身近にいる人を苦しめて悲しませてきた。
それは紛れもない事実でこれから先は誰一人として傷つけないように孤独に生きてゆく。
「もう誰かを不幸にしたくないのです。だから鬼城さまもわたしなんかの傍にいない方が……」
お願いだから自分から離れて。
もう目の前で悪夢のような出来事を見るのは耐えられない。
自分でもわかるほど声が震えており、こうして人を突き放すことがどれだけつらいか。
でもそれが千冬にとって最善なのだ。
ここまで全てを話せばきっと考えを改めてくれる、そう思っていると。
「……!」
引き寄せられたかと思えば気づけば千冬は灯璃の腕の中にいた。
もう離さないとでもいうようにと強く抱きしめている。
予想に反する灯璃の行動に驚かされ心臓が煩いくらいに鳴っている。
「君が言うその不幸も偶然起きたものだ。私はくだらない言い伝えなど信じない。だって私は君に出逢えてこんなにも幸せなのだから」
その声はとても温かくて嘘偽りなど少しもないのだと分かった。
この先、歩む道は真っ暗闇で光はないと全てを諦めていた千冬もどこかで誰かに必要とされたい、愛されたいと願っていたなだと今の言葉を聞いて気がついた。
「生きていて、貴方の傍にいて良いのですか……?」
声を詰まらせながら涙を流す千冬。
灯璃はその頬に伝う涙を指でそっと拭うと千冬の顔を上へ向かせる。
「ああ、ずっと傍にいてほしい。私の愛おしい花嫁。して君の名を聞かせてくれないか」
こんなにも自分を想ってくれる人は他にいないだろうと不思議と確信できる。
幸せになることが許されるのなら、この奇跡を手放したくない。
「嶺木……千冬です」
「千冬……。愛らしい名だ」
二人の身体を風が撫でる。
春の夜の風でも今はなぜか寒さを感じなかった。
灯璃から伝わる体温が温かく心地良い。
夜空に浮かぶ満月の月明かりが千冬の嫁入りを祝福するように二人を照らしていた。