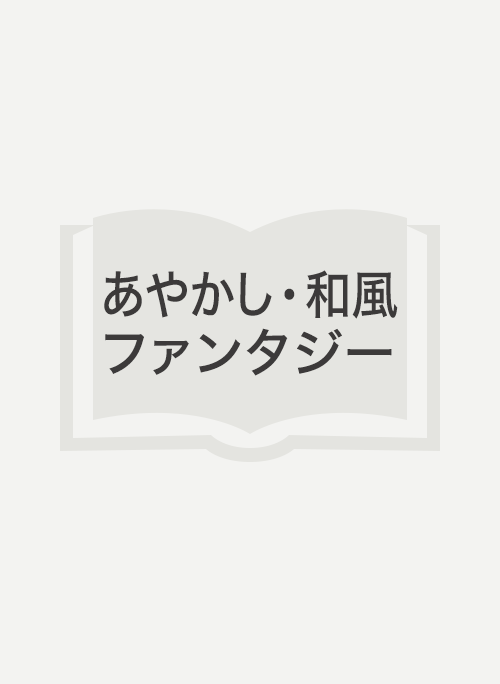かくりよ國を統べている鬼、鬼城灯璃。
鬼の一族の本家である鬼城家は古来から他の追随を許さない強き力をもっていることから別名、鬼帝とも言われていた。
灯璃は手腕が認められ、二十七歳という若さで鬼城家の当主を受け継いだ。
彼の仕事は一族の取りまとめだけではない。
『妖特務部隊』というあやかしやその花嫁が関わって発生した事件などを担当する部隊の隊長でもあるのだ。
部隊には鬼だけではなく妖狐、猫又、雪女など様々なあやかしで構成されている。
大昔、花嫁を狙った身代金目的の誘拐事件が起きたのをきっかけに妖特務部隊が発足された。
月に一度、帝都で人間側の警備隊との会合が開かれる。
会合が開かれる今日、隊長の灯璃は同じ鬼の一族で筆頭分家の時期当主、鬼崎蓮司《おにさき れんじ》と共に参加していた。
「……以上で本日の会合はこれで終了となります」
進行を務めていた蓮司がそう言うと椅子に座っていた警備隊の隊員達が立ち上がり議長席に鎮座する灯璃に向かって頭を下げる。
「お疲れ様でした!」
「ああ。ご苦労だった」
灯璃が返事をすると隊員達は書類を片付けて議会場を出て行く。
灯璃も束ねた書類を蓮司に渡すと壁に掛けてある時計に視線を向ける。
(もうこんな時間か……)
会合が始まってから数時間が経過しており、窓から外を見ると辺りは暗闇に包まれていた。
灯璃にとって夜遅くまで仕事をするのは、そう珍しいことではない。
鬼城家に生まれた宿命だと昔から心得ている。
最近は激務続きだが当主たるのも一度も弱音を吐いたことはなかった。
ジッと外を見ていた灯璃に蓮司は心配そうに声をかける。
「灯璃さま、いかがなさいましたか?」
「……いや、何でもない。私達も帰ろう」
踵を返し、扉へ向かっていく灯璃を蓮司は慌てて追いかけた。
「鬼城さま」
二人が外に出て門の前に待たせていた自動車に乗り込もうとしたとき、会合に参加していた隊員の中年男性が近づき、声をかけてきた。
視線を向けるとその男性の隣に若い女性が立っていた。
白いワンピースとヒールでかなり気合いを入れてお洒落をしていて、灯璃を見るなり頬を赤らめて恥ずかしそうにしている。
「どのようなご用件でしょう?」
灯璃の代わりに蓮司が前に出て応える。
しかし、わざわざ聞かなくてもどうして男性が声をかけてきたのか二人は知っていた。
「実は鬼城さまに私の娘を紹介させていただきたく……」
「こんばんは」
娘だと紹介された女性は上目遣いをしながら熱視線を灯璃に送る。
明らかな好意にため息をつきそうになるが必死に堪えた。
こうして帝都に来るたびに必ずといっていいほど女性を紹介される。
ほとんどが親の権力と財力狙いで自分の娘を連れてきてあわよくば結婚させ恩恵を受けたいと思っているようだ。
どんな娘も鬼に会えると聞くと精一杯のお洒落をして色目を使う。
しかしそんなものに灯璃が騙されることはない。
親子のその欲望まみれの瞳はお見通しだ。
瞳を見れば花嫁かどうかはすぐにわかるのに会う者皆、諦めが悪い。
どうにかならないかと頭を悩ませるが人間との関係を壊すわけにもいかない。
まだあやかしの女性の方が自分の立場をわきまえているので必要以上に話しかけてこない。
見習ってほしいくらいだが、そんなこと言えるはずがない。
「もしよろしければ今度お食事にでも……」
女性の誘いもこれで何回目だろう。
考えるだけで疲れるので数えたことはないが。
「すまないが、花嫁でない女性と食事に行く暇はない」
きっぱりと言い切ると傍に控えていた蓮司が自動車のドアを開けて灯璃が乗り込む。
「お、お待ちください!」
慌てて父親の男性が引き止めるが灯璃が振り返ることはなかった。
「失礼します」
蓮司も一礼すると反対側のドアから乗り込み、自動車は親子を置いて走り出したのだった。
車窓から帝都のモダンな町並みを見ていると時間帯もあってか、肩を寄せ合いながら歩く男女の姿が何組も見られた。
幸せそうにしているのを見て灯璃は羨ましいとは思わなかった。
鬼城家の当主として果たすべきものがあるから色恋にうつつを抜かしている暇はない。
年内までに人間の花嫁が見つからなければ同じ一族の婚約者との結婚が決まっている。
両親との約束でもうよい年齢なのだから身を固め、妻となる女性に世継ぎを産んでほしいと懇願されていた。
本人もそれは承知していて、約束を破るつもりは毛頭ない。
結婚をして子を成すことは当主として当然のことだ。
しかし以前、人間の花嫁を見つけたあやかし達から話を聞いたことがあった。
花嫁となる女性の瞳を見た瞬間に本能がこの人だと何度も呼ぶそうで、恋い焦がれた感情になるらしい。
また自然と涙を流す者もいるようでそれはとても幸せで歓喜に満ちるのだと。
その話を聞いて少しだけ興味が湧いた。
鬼の当主とはいえど、人間のようにある程度は喜び、怒り、悲しみなどの感情を知ってきた。
しかし花嫁を見つけたときの名前をつけるのでさえ難しい、未知なる感情はどのようなものなのか気になる。
鬼が人間の花嫁を迎え入れた事例はここ数十年間一度もない。
もう諦めているが、もし奇跡が起こり運命の女性に出逢えたのならこの空虚な人生が変わるだろうか。
珍しく物思いにふけていると、車窓から見える景色でもうすぐかくりよ國に到着することが分かった。
「灯璃さま、やはりどこか具合が悪いのですか?」
先ほどからの様子を見て普段と違うのを感じ取ったのか蓮司が再び声をかける。
昔から共に過ごしているからか、こういった些細な変化にもすぐに気がつく。
観察力が鋭いのは仕事で役に立つし頼もしいが彼は少々、心配性なところがある。
鬼崎家は代々、鬼城家に仕える家系のため、あるじに何かあれば一大事だと認識しているのだろう。
部下に心配させてしまうなんて一族を率いる者としてまだまだだと反省しながら口を開く。
「いや、何でも……」
『何でもない』そう言おうとしたとき。
窓からかくりよ國と帝都を架ける橋に一人の女性が立っているのが見えた。
昼間なら、お互いの町に往き来する者などで人通りはあるがこの遅い時間に誰かいるのは珍しい。
あやかしの花嫁ならば護衛をつけるはず。
花嫁を一人で外出させるわけがない。
普段は人に興味をもたない灯璃だが今はなぜか、その女性を凝視してしまう。
女性が僅かに動いて近くに立っている街灯の灯りに照らされたとき、少し伸びた前髪から紫紺色の瞳を覗かせた。
宝石のような美しさなのに伏せてあるまつげでどこか憂いを帯びている。
その瞳を捉えた瞬間、急に鼓動が高鳴った。
感じたことのない心臓の速さに灯璃はぐっと胸元を抑える。
速まる鼓動に加え荒くなっていく呼吸で身体は苦しいはずなのに頭の中はなぜか彼女への愛おしさ、強く惹かれる感情が溢れてくる。
そんな灯璃の変化を蓮司はいち早く気がついた。
「灯璃さま!?大丈夫ですか!?」
心臓の位置を手で抑えながら背を丸まらせ、額が僅かに汗ばんでいる姿は明らかに体調不良であることがわかる。
やはり最近の仕事が忙しいせいで無理がたたってしまったのだと、もっと強く休暇を勧めればよかったと後悔する蓮司だが、悔やむのはあとだ。
傍で支える者として動揺はしたくないが初めて見る直属の上司のそんな様子に蓮司は顔を青ざめさせ困惑してしまう。
そんな二人に運転手も気がつき慌てて自動車を路肩に寄せ、ブレーキをかけた。
「いかがなさいましたか?」
何か当主の身に起こったのかとまさに車内は騒然としている状態だった。
「灯璃さまが……」
「ここで待っていろ」
灯璃は蓮司の言葉を遮ると、自動車のドアを開け降りていく。
「と、灯璃さま!?お待ちください!」
蓮司は引き止めるが灯璃は足早に歩いて行ってしまう。
突然の行動に車内には呆気にとられた二人が残っていた。
悲しそうに、寂しそうな表情で橋の上に佇む女性が視界に入る。
距離が近づくたび、初めて会うはずなのに彼女に対する恋い焦がれた感情が奥底から溢れ出す。
灯璃は確信した。
あの女性が花嫁なのだと。
人間の花嫁を迎え入れたあやかし達の話通りだ。
運命の女性に会えば歓喜に満ちるとは、このことだったのかと実感して、『君が花嫁だ』と伝えたい。
灯璃は、はやる気持ちを抑えられなかった。
しかし喜ぶ灯璃とは反対に女性はひどく暗い。
着ている着物もくたびれており、明らかに事情があるようだった。
(なぜそんな顔をしている)
悲しみに暮れさせる理由を知ってそれを取り除きたい。
全身全霊で害となるものから守り、笑顔にしたい。
灯璃は真っ直ぐに熱い視線を向けるが女性はそれに気がつかず、橋の下の激流の川をじっと見つめている。
灯璃は頭の中で信じたくないほどの嫌な考えが浮かんでしまい、ふと歩みを止めた。
今すぐ消えてしまいそうな儚い姿、なぜ一人でこんな時間に橋の上にいるのか、理由が全てが線で繋がる。
(自殺を図ろうとしているのか……!)
花嫁を見つけたと思った矢先、この世からいなくなろうとしている現実に怖くなった。
怖いと思うなんていつぶりだろう。
もしかしたら物心ついてから初めてかもしれない。
鬼城家の当主として不安や怖さなど要らない感情だと思ったからだ。
弱っている者に誰もついていきたいと思わないだろう。
色々な思いが駆け巡るが、ただ一つだけはっきりとわかる。
見つけた愛おしい花嫁を失いたくないということ。
灯璃は地面を蹴り、思い切り駆けだした。
予想していた通りに少女は欄干から身を乗り出す。
すぐに腕を伸ばし背後から抱きかかえ自分の方へ引っ張り、後ろに倒れ込んだ。
「やめるんだ」
もう心臓が止まりそうな行動はやめてほしい、大切な人がいなくなるのは耐えられないんだという想いを込めて耳元で話す。
灯璃が間に合ったことに安堵したのも束の間。
「嫌っ!離して……!」
少女は邪魔されたことに気が障ったのか腕を振り払おうと暴れる。
外見でも気にはなっていたが、抱きしめて再確認した。
首許や手首、腕がかなり細すぎる。
そんな身体で普段から鍛えている灯璃の腕から抜け出すことなど出来るはずなく。
「落ち着きなさい」
柔らかく言葉を紡いでそっと少女の頭に手を置くと少しずつ抵抗するのをやめていった。
「もう大丈夫だ」
どんな出来事が彼女をこれほどまでに追い詰めたのだろう。
もし誰かが心や身体に傷を負わせたのだとしたら断固として許せない。
(君を怖がらせるもの全てから守る)
優しく頭を撫でると完全に暴れるのをやめた。
様子を見てきっともう、あんな真似はしないだろうと思った灯璃はゆっくり腕を離す。
まだ花嫁だと伝えていないため、あまり長く抱きしめていると逆に警戒心を与えかねない。
雲間から満月が現れ、月光が降り注いだとき少女がこちらへ振り向いた。
例えるなら穏やかに光を放つ宝石。
紫紺色の瞳と視線が絡み、その吸い込まれそうな美しさに息をするのも忘れるほど。
少女もこちらを見るなり、ぴたりと動きを止めて目を丸くさせている。
驚く理由は分かっていた。
鬼である証、赤い瞳を見たからだ。
鬼は他のあやかし達と比べて、そう人前に姿を見せない。
人間と会うのは今日のような会合など大切な仕事のときくらいだ。
しかも灯璃はその中で一番といっていいほど他人と関わろうとしない鬼。
世間話のような会話は、相手に応じてだが必要最低限に答え、己の利益しか考えない人物に時間を割くなど言語道断。
だが愛おしい花嫁は特別だ。
小さな唇がおそるおそるといった様子で開かれた。
「あの、貴方は……?」
鈴の音のような声が耳に届き灯璃は内心、浮かれていた。
やっと花嫁の声が聞けたのだから。
「私は鬼城灯璃。鬼だ」
自己紹介をするなり少女は慌てたように礼と謝罪を言った。
鬼に会うのは初めてでも、鬼城家の話は聞いたことがあったのだろう。
(そんな申し訳なさそうに謝らなくても良いのに)
これからはお互いの家の地位などは関係のない、対等な存在になるのだから。
だけど彼女の奥ゆかしさにも惹かれている自分もいる。
「花嫁を助けるのは当たり前だろう」
思ったことをそのまま言葉にして伝えると少女はつぶらな瞳をぱちりと瞬かせた。
「はな、よめ……?」
言葉の意味が分からず首を傾げている少女に灯璃はしっかりと頷いた。
やっと伝えられる。
鬼の花嫁だと知ったらどんな表情をするだろうか。
どうか怖がらないで、この手をとってほしいと願いながら口を開いた。
「君は私の……鬼城家の当主の花嫁だ」
灯璃は少女の細い身体を引き寄せ、奇跡の出逢いを噛みしめながら抱きしめた。
鬼の一族の本家である鬼城家は古来から他の追随を許さない強き力をもっていることから別名、鬼帝とも言われていた。
灯璃は手腕が認められ、二十七歳という若さで鬼城家の当主を受け継いだ。
彼の仕事は一族の取りまとめだけではない。
『妖特務部隊』というあやかしやその花嫁が関わって発生した事件などを担当する部隊の隊長でもあるのだ。
部隊には鬼だけではなく妖狐、猫又、雪女など様々なあやかしで構成されている。
大昔、花嫁を狙った身代金目的の誘拐事件が起きたのをきっかけに妖特務部隊が発足された。
月に一度、帝都で人間側の警備隊との会合が開かれる。
会合が開かれる今日、隊長の灯璃は同じ鬼の一族で筆頭分家の時期当主、鬼崎蓮司《おにさき れんじ》と共に参加していた。
「……以上で本日の会合はこれで終了となります」
進行を務めていた蓮司がそう言うと椅子に座っていた警備隊の隊員達が立ち上がり議長席に鎮座する灯璃に向かって頭を下げる。
「お疲れ様でした!」
「ああ。ご苦労だった」
灯璃が返事をすると隊員達は書類を片付けて議会場を出て行く。
灯璃も束ねた書類を蓮司に渡すと壁に掛けてある時計に視線を向ける。
(もうこんな時間か……)
会合が始まってから数時間が経過しており、窓から外を見ると辺りは暗闇に包まれていた。
灯璃にとって夜遅くまで仕事をするのは、そう珍しいことではない。
鬼城家に生まれた宿命だと昔から心得ている。
最近は激務続きだが当主たるのも一度も弱音を吐いたことはなかった。
ジッと外を見ていた灯璃に蓮司は心配そうに声をかける。
「灯璃さま、いかがなさいましたか?」
「……いや、何でもない。私達も帰ろう」
踵を返し、扉へ向かっていく灯璃を蓮司は慌てて追いかけた。
「鬼城さま」
二人が外に出て門の前に待たせていた自動車に乗り込もうとしたとき、会合に参加していた隊員の中年男性が近づき、声をかけてきた。
視線を向けるとその男性の隣に若い女性が立っていた。
白いワンピースとヒールでかなり気合いを入れてお洒落をしていて、灯璃を見るなり頬を赤らめて恥ずかしそうにしている。
「どのようなご用件でしょう?」
灯璃の代わりに蓮司が前に出て応える。
しかし、わざわざ聞かなくてもどうして男性が声をかけてきたのか二人は知っていた。
「実は鬼城さまに私の娘を紹介させていただきたく……」
「こんばんは」
娘だと紹介された女性は上目遣いをしながら熱視線を灯璃に送る。
明らかな好意にため息をつきそうになるが必死に堪えた。
こうして帝都に来るたびに必ずといっていいほど女性を紹介される。
ほとんどが親の権力と財力狙いで自分の娘を連れてきてあわよくば結婚させ恩恵を受けたいと思っているようだ。
どんな娘も鬼に会えると聞くと精一杯のお洒落をして色目を使う。
しかしそんなものに灯璃が騙されることはない。
親子のその欲望まみれの瞳はお見通しだ。
瞳を見れば花嫁かどうかはすぐにわかるのに会う者皆、諦めが悪い。
どうにかならないかと頭を悩ませるが人間との関係を壊すわけにもいかない。
まだあやかしの女性の方が自分の立場をわきまえているので必要以上に話しかけてこない。
見習ってほしいくらいだが、そんなこと言えるはずがない。
「もしよろしければ今度お食事にでも……」
女性の誘いもこれで何回目だろう。
考えるだけで疲れるので数えたことはないが。
「すまないが、花嫁でない女性と食事に行く暇はない」
きっぱりと言い切ると傍に控えていた蓮司が自動車のドアを開けて灯璃が乗り込む。
「お、お待ちください!」
慌てて父親の男性が引き止めるが灯璃が振り返ることはなかった。
「失礼します」
蓮司も一礼すると反対側のドアから乗り込み、自動車は親子を置いて走り出したのだった。
車窓から帝都のモダンな町並みを見ていると時間帯もあってか、肩を寄せ合いながら歩く男女の姿が何組も見られた。
幸せそうにしているのを見て灯璃は羨ましいとは思わなかった。
鬼城家の当主として果たすべきものがあるから色恋にうつつを抜かしている暇はない。
年内までに人間の花嫁が見つからなければ同じ一族の婚約者との結婚が決まっている。
両親との約束でもうよい年齢なのだから身を固め、妻となる女性に世継ぎを産んでほしいと懇願されていた。
本人もそれは承知していて、約束を破るつもりは毛頭ない。
結婚をして子を成すことは当主として当然のことだ。
しかし以前、人間の花嫁を見つけたあやかし達から話を聞いたことがあった。
花嫁となる女性の瞳を見た瞬間に本能がこの人だと何度も呼ぶそうで、恋い焦がれた感情になるらしい。
また自然と涙を流す者もいるようでそれはとても幸せで歓喜に満ちるのだと。
その話を聞いて少しだけ興味が湧いた。
鬼の当主とはいえど、人間のようにある程度は喜び、怒り、悲しみなどの感情を知ってきた。
しかし花嫁を見つけたときの名前をつけるのでさえ難しい、未知なる感情はどのようなものなのか気になる。
鬼が人間の花嫁を迎え入れた事例はここ数十年間一度もない。
もう諦めているが、もし奇跡が起こり運命の女性に出逢えたのならこの空虚な人生が変わるだろうか。
珍しく物思いにふけていると、車窓から見える景色でもうすぐかくりよ國に到着することが分かった。
「灯璃さま、やはりどこか具合が悪いのですか?」
先ほどからの様子を見て普段と違うのを感じ取ったのか蓮司が再び声をかける。
昔から共に過ごしているからか、こういった些細な変化にもすぐに気がつく。
観察力が鋭いのは仕事で役に立つし頼もしいが彼は少々、心配性なところがある。
鬼崎家は代々、鬼城家に仕える家系のため、あるじに何かあれば一大事だと認識しているのだろう。
部下に心配させてしまうなんて一族を率いる者としてまだまだだと反省しながら口を開く。
「いや、何でも……」
『何でもない』そう言おうとしたとき。
窓からかくりよ國と帝都を架ける橋に一人の女性が立っているのが見えた。
昼間なら、お互いの町に往き来する者などで人通りはあるがこの遅い時間に誰かいるのは珍しい。
あやかしの花嫁ならば護衛をつけるはず。
花嫁を一人で外出させるわけがない。
普段は人に興味をもたない灯璃だが今はなぜか、その女性を凝視してしまう。
女性が僅かに動いて近くに立っている街灯の灯りに照らされたとき、少し伸びた前髪から紫紺色の瞳を覗かせた。
宝石のような美しさなのに伏せてあるまつげでどこか憂いを帯びている。
その瞳を捉えた瞬間、急に鼓動が高鳴った。
感じたことのない心臓の速さに灯璃はぐっと胸元を抑える。
速まる鼓動に加え荒くなっていく呼吸で身体は苦しいはずなのに頭の中はなぜか彼女への愛おしさ、強く惹かれる感情が溢れてくる。
そんな灯璃の変化を蓮司はいち早く気がついた。
「灯璃さま!?大丈夫ですか!?」
心臓の位置を手で抑えながら背を丸まらせ、額が僅かに汗ばんでいる姿は明らかに体調不良であることがわかる。
やはり最近の仕事が忙しいせいで無理がたたってしまったのだと、もっと強く休暇を勧めればよかったと後悔する蓮司だが、悔やむのはあとだ。
傍で支える者として動揺はしたくないが初めて見る直属の上司のそんな様子に蓮司は顔を青ざめさせ困惑してしまう。
そんな二人に運転手も気がつき慌てて自動車を路肩に寄せ、ブレーキをかけた。
「いかがなさいましたか?」
何か当主の身に起こったのかとまさに車内は騒然としている状態だった。
「灯璃さまが……」
「ここで待っていろ」
灯璃は蓮司の言葉を遮ると、自動車のドアを開け降りていく。
「と、灯璃さま!?お待ちください!」
蓮司は引き止めるが灯璃は足早に歩いて行ってしまう。
突然の行動に車内には呆気にとられた二人が残っていた。
悲しそうに、寂しそうな表情で橋の上に佇む女性が視界に入る。
距離が近づくたび、初めて会うはずなのに彼女に対する恋い焦がれた感情が奥底から溢れ出す。
灯璃は確信した。
あの女性が花嫁なのだと。
人間の花嫁を迎え入れたあやかし達の話通りだ。
運命の女性に会えば歓喜に満ちるとは、このことだったのかと実感して、『君が花嫁だ』と伝えたい。
灯璃は、はやる気持ちを抑えられなかった。
しかし喜ぶ灯璃とは反対に女性はひどく暗い。
着ている着物もくたびれており、明らかに事情があるようだった。
(なぜそんな顔をしている)
悲しみに暮れさせる理由を知ってそれを取り除きたい。
全身全霊で害となるものから守り、笑顔にしたい。
灯璃は真っ直ぐに熱い視線を向けるが女性はそれに気がつかず、橋の下の激流の川をじっと見つめている。
灯璃は頭の中で信じたくないほどの嫌な考えが浮かんでしまい、ふと歩みを止めた。
今すぐ消えてしまいそうな儚い姿、なぜ一人でこんな時間に橋の上にいるのか、理由が全てが線で繋がる。
(自殺を図ろうとしているのか……!)
花嫁を見つけたと思った矢先、この世からいなくなろうとしている現実に怖くなった。
怖いと思うなんていつぶりだろう。
もしかしたら物心ついてから初めてかもしれない。
鬼城家の当主として不安や怖さなど要らない感情だと思ったからだ。
弱っている者に誰もついていきたいと思わないだろう。
色々な思いが駆け巡るが、ただ一つだけはっきりとわかる。
見つけた愛おしい花嫁を失いたくないということ。
灯璃は地面を蹴り、思い切り駆けだした。
予想していた通りに少女は欄干から身を乗り出す。
すぐに腕を伸ばし背後から抱きかかえ自分の方へ引っ張り、後ろに倒れ込んだ。
「やめるんだ」
もう心臓が止まりそうな行動はやめてほしい、大切な人がいなくなるのは耐えられないんだという想いを込めて耳元で話す。
灯璃が間に合ったことに安堵したのも束の間。
「嫌っ!離して……!」
少女は邪魔されたことに気が障ったのか腕を振り払おうと暴れる。
外見でも気にはなっていたが、抱きしめて再確認した。
首許や手首、腕がかなり細すぎる。
そんな身体で普段から鍛えている灯璃の腕から抜け出すことなど出来るはずなく。
「落ち着きなさい」
柔らかく言葉を紡いでそっと少女の頭に手を置くと少しずつ抵抗するのをやめていった。
「もう大丈夫だ」
どんな出来事が彼女をこれほどまでに追い詰めたのだろう。
もし誰かが心や身体に傷を負わせたのだとしたら断固として許せない。
(君を怖がらせるもの全てから守る)
優しく頭を撫でると完全に暴れるのをやめた。
様子を見てきっともう、あんな真似はしないだろうと思った灯璃はゆっくり腕を離す。
まだ花嫁だと伝えていないため、あまり長く抱きしめていると逆に警戒心を与えかねない。
雲間から満月が現れ、月光が降り注いだとき少女がこちらへ振り向いた。
例えるなら穏やかに光を放つ宝石。
紫紺色の瞳と視線が絡み、その吸い込まれそうな美しさに息をするのも忘れるほど。
少女もこちらを見るなり、ぴたりと動きを止めて目を丸くさせている。
驚く理由は分かっていた。
鬼である証、赤い瞳を見たからだ。
鬼は他のあやかし達と比べて、そう人前に姿を見せない。
人間と会うのは今日のような会合など大切な仕事のときくらいだ。
しかも灯璃はその中で一番といっていいほど他人と関わろうとしない鬼。
世間話のような会話は、相手に応じてだが必要最低限に答え、己の利益しか考えない人物に時間を割くなど言語道断。
だが愛おしい花嫁は特別だ。
小さな唇がおそるおそるといった様子で開かれた。
「あの、貴方は……?」
鈴の音のような声が耳に届き灯璃は内心、浮かれていた。
やっと花嫁の声が聞けたのだから。
「私は鬼城灯璃。鬼だ」
自己紹介をするなり少女は慌てたように礼と謝罪を言った。
鬼に会うのは初めてでも、鬼城家の話は聞いたことがあったのだろう。
(そんな申し訳なさそうに謝らなくても良いのに)
これからはお互いの家の地位などは関係のない、対等な存在になるのだから。
だけど彼女の奥ゆかしさにも惹かれている自分もいる。
「花嫁を助けるのは当たり前だろう」
思ったことをそのまま言葉にして伝えると少女はつぶらな瞳をぱちりと瞬かせた。
「はな、よめ……?」
言葉の意味が分からず首を傾げている少女に灯璃はしっかりと頷いた。
やっと伝えられる。
鬼の花嫁だと知ったらどんな表情をするだろうか。
どうか怖がらないで、この手をとってほしいと願いながら口を開いた。
「君は私の……鬼城家の当主の花嫁だ」
灯璃は少女の細い身体を引き寄せ、奇跡の出逢いを噛みしめながら抱きしめた。