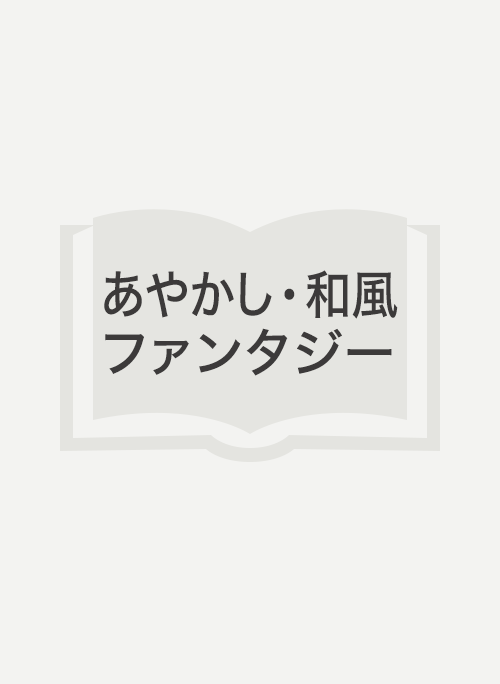夜空に浮かぶ大きな満月が帝都の町並みを照らしている……。
屋敷を出た千冬は西の方角に向かって歩いていた。
帝都を出た西側に、あやかしと花嫁が暮らす、かくりよ國がある。
帝都とかくりよ國の境界には大きな川があると千冬は耳にしたことがある。
そしてその川に身を投げ入れようと決めた。
古いお仕着せ姿で帝都を歩く少女に時折、人々は怪訝そうな顔で見るが千冬は全く気にしなかった。
もう自分は死ぬのだから、恥ずかしさも怖さも感じない。
もうすぐ母に会えると思うと自然と動かす足も早くなった。
帝都の中心部を抜けると頼りになるのは等間隔に立っている街灯の灯りだけ。
千冬は無我夢中で目的地の川まで歩き続けた。
歩き始めてからどれくらいの時間が経っただろう。
息を切らし、ふと顔を上げると先に見えてきたのは大きな川と橋。
その奥には幻想的な雰囲気を放つ町並みがあった。
(あそこがかくりよ國……)
何年も屋敷から出たことのない千冬でもすぐにわかった。
帝都よりもはるかに規模が広く、いくつもの純和風の屋敷が見える。
かくりよ國の周囲には結界が張られており認められた者しか入ることが許されない。
あの町に住むことは女性にとって憧れのようだがこれから死ぬ千冬には関係のない話で自嘲してしまう。
時間帯もあるのか、周囲には誰もいない。
下手に騒ぎになるのは嫌だったのでその方が千冬にとって都合が良かった。
石造りの橋までたどり着くと、そっと下を覗き込む。
昨晩、大雨が降ったせいか川は水位が高く、流れも早かった。
(これだったら、きっとすぐに……)
小さく息を吐き夜空を見上げる。
何も遮るものはなく、不思議と星が近くに見えた。
瞳を閉じて天にいる母を想う。
(今、逝きます)
そっと瞳を開けると橋の欄干から身を乗り出す。
足が地面から離れたとき。
「っ!」
目下にある川に向かって傾いていた身体が急に後ろへ引っ張られる。
そのまま勢いよく倒れ込む。
千冬は一瞬何が起きたのか分からなかった。
「やめるんだ」
低い男性の声が耳に届いたとき理解した。
自分は誰かに助けられたのだと。
千冬はなぜか安堵などせず、自分がやろうとしていたことを邪魔されたような気がして悔しくなった。
「嫌っ!離して……!」
後ろから自分を抱きしめる腕を必死に解こうとする。
初めて誰かに声をあげて抵抗したと思う。
すでに決めたことだから事情も知らない初めて会う人に関わらないでほしい。
男性は片腕を解き、暴れる千冬の頭にそっと手を置いた。
「落ち着きなさい」
その優しい一言がまるで、まじないのように胸にストンと落ちた。
静かになっていく千冬を見て男性は慰めるように頭を撫でた。
「もう大丈夫だ」
こんな風に人に優しくされるのはいつぶりだろう。
おそらく母が亡くなってから初めてだ。
それがこんなにも嬉しいのだと千冬は感情が溢れ出し涙を流した。
自分はなんてことをしようとしていたのだろうと今になって思えてくる。
母からもらった命を自ら絶とうとするなんて。
しかも見ず知らずの人に助けてもらい、迷惑をかけてしまった。
落ち着いてきた千冬を見計らって男性は抱きしめていた腕を離す。
それに気づいた千冬は礼と謝罪をしようと少し距離をとり振り向く。
振り向いた瞬間、男性の視線と合う。
千冬は思わずピタリと動きを止まらせてしまった。
なぜなら、その男性の瞳は血のように赤かったからだ。
少ない街灯の灯りだけでも分かる、艶やかな黒髪にシミ一つ無い陶器のような肌、色香漂う唇。
黒や紺色に近い色の軍服のような衣服を身に纏っており、その人間離れした美しさに、つい魅入ってしまう。
「あの、貴方は……?」
先に名乗らず、礼や謝罪も言っていないのに聞いてしまうのは失礼だと承知している。
だが見目麗しい彼を見てどうしても聞かずにはいられなかった。
男性は怒るどころか優美な笑みを浮かべ、切れ長の瞳を細めると口を開いた。
「私は鬼城灯璃。《きじょう とうり》鬼だ」
(鬼……!?)
この國に暮らす誰もが知っている。
あやかしの中で最も霊力が強く位が高いのは鬼だと。
そんな鬼の一族を率いているのは本家である鬼城家。
圧倒的な権力と財力に右に出る者はおらず、帝都を裏で牛耳っているとも言われていた。
そんな自分とは住む世界が違う格上の人物に助けられたのだということに気がつき、千冬は慌てて頭を下げた。
「助けてくださりありがとうございます……!ご迷惑をおかけして申し訳ありません!」
普段から継母達にこうして謝っていたのでお辞儀は出来る方だと思う。
地面に添えている手から、石の冷たさが伝わるがそんなことは気にしていられない。
お手入れもしていない髪に、みすぼらしいお仕着せ姿なんて見せてしまって自分が情けない。
(会話が終わったら、すぐにどこかへ行ってしまおう)
一晩くらい野宿でも何とかなるはず。
朝になったら帝都に戻り、住み込みで働ける仕事場を探そうと思案していると……。
「花嫁を助けるのは当たり前だろう」
灯璃の手が千冬の頬に触れ、ゆっくりと上に向かせる。
もう一度、赤い瞳と視線が絡み合う。
「はな、よめ……?」
言葉の意味が分からず首を傾げる千冬に灯璃は頷いた。
「君は私の……鬼城家の当主の花嫁だ」
灯璃は自分の花嫁をそっと引き寄せて存在を確かめるように抱きしめた。
屋敷を出た千冬は西の方角に向かって歩いていた。
帝都を出た西側に、あやかしと花嫁が暮らす、かくりよ國がある。
帝都とかくりよ國の境界には大きな川があると千冬は耳にしたことがある。
そしてその川に身を投げ入れようと決めた。
古いお仕着せ姿で帝都を歩く少女に時折、人々は怪訝そうな顔で見るが千冬は全く気にしなかった。
もう自分は死ぬのだから、恥ずかしさも怖さも感じない。
もうすぐ母に会えると思うと自然と動かす足も早くなった。
帝都の中心部を抜けると頼りになるのは等間隔に立っている街灯の灯りだけ。
千冬は無我夢中で目的地の川まで歩き続けた。
歩き始めてからどれくらいの時間が経っただろう。
息を切らし、ふと顔を上げると先に見えてきたのは大きな川と橋。
その奥には幻想的な雰囲気を放つ町並みがあった。
(あそこがかくりよ國……)
何年も屋敷から出たことのない千冬でもすぐにわかった。
帝都よりもはるかに規模が広く、いくつもの純和風の屋敷が見える。
かくりよ國の周囲には結界が張られており認められた者しか入ることが許されない。
あの町に住むことは女性にとって憧れのようだがこれから死ぬ千冬には関係のない話で自嘲してしまう。
時間帯もあるのか、周囲には誰もいない。
下手に騒ぎになるのは嫌だったのでその方が千冬にとって都合が良かった。
石造りの橋までたどり着くと、そっと下を覗き込む。
昨晩、大雨が降ったせいか川は水位が高く、流れも早かった。
(これだったら、きっとすぐに……)
小さく息を吐き夜空を見上げる。
何も遮るものはなく、不思議と星が近くに見えた。
瞳を閉じて天にいる母を想う。
(今、逝きます)
そっと瞳を開けると橋の欄干から身を乗り出す。
足が地面から離れたとき。
「っ!」
目下にある川に向かって傾いていた身体が急に後ろへ引っ張られる。
そのまま勢いよく倒れ込む。
千冬は一瞬何が起きたのか分からなかった。
「やめるんだ」
低い男性の声が耳に届いたとき理解した。
自分は誰かに助けられたのだと。
千冬はなぜか安堵などせず、自分がやろうとしていたことを邪魔されたような気がして悔しくなった。
「嫌っ!離して……!」
後ろから自分を抱きしめる腕を必死に解こうとする。
初めて誰かに声をあげて抵抗したと思う。
すでに決めたことだから事情も知らない初めて会う人に関わらないでほしい。
男性は片腕を解き、暴れる千冬の頭にそっと手を置いた。
「落ち着きなさい」
その優しい一言がまるで、まじないのように胸にストンと落ちた。
静かになっていく千冬を見て男性は慰めるように頭を撫でた。
「もう大丈夫だ」
こんな風に人に優しくされるのはいつぶりだろう。
おそらく母が亡くなってから初めてだ。
それがこんなにも嬉しいのだと千冬は感情が溢れ出し涙を流した。
自分はなんてことをしようとしていたのだろうと今になって思えてくる。
母からもらった命を自ら絶とうとするなんて。
しかも見ず知らずの人に助けてもらい、迷惑をかけてしまった。
落ち着いてきた千冬を見計らって男性は抱きしめていた腕を離す。
それに気づいた千冬は礼と謝罪をしようと少し距離をとり振り向く。
振り向いた瞬間、男性の視線と合う。
千冬は思わずピタリと動きを止まらせてしまった。
なぜなら、その男性の瞳は血のように赤かったからだ。
少ない街灯の灯りだけでも分かる、艶やかな黒髪にシミ一つ無い陶器のような肌、色香漂う唇。
黒や紺色に近い色の軍服のような衣服を身に纏っており、その人間離れした美しさに、つい魅入ってしまう。
「あの、貴方は……?」
先に名乗らず、礼や謝罪も言っていないのに聞いてしまうのは失礼だと承知している。
だが見目麗しい彼を見てどうしても聞かずにはいられなかった。
男性は怒るどころか優美な笑みを浮かべ、切れ長の瞳を細めると口を開いた。
「私は鬼城灯璃。《きじょう とうり》鬼だ」
(鬼……!?)
この國に暮らす誰もが知っている。
あやかしの中で最も霊力が強く位が高いのは鬼だと。
そんな鬼の一族を率いているのは本家である鬼城家。
圧倒的な権力と財力に右に出る者はおらず、帝都を裏で牛耳っているとも言われていた。
そんな自分とは住む世界が違う格上の人物に助けられたのだということに気がつき、千冬は慌てて頭を下げた。
「助けてくださりありがとうございます……!ご迷惑をおかけして申し訳ありません!」
普段から継母達にこうして謝っていたのでお辞儀は出来る方だと思う。
地面に添えている手から、石の冷たさが伝わるがそんなことは気にしていられない。
お手入れもしていない髪に、みすぼらしいお仕着せ姿なんて見せてしまって自分が情けない。
(会話が終わったら、すぐにどこかへ行ってしまおう)
一晩くらい野宿でも何とかなるはず。
朝になったら帝都に戻り、住み込みで働ける仕事場を探そうと思案していると……。
「花嫁を助けるのは当たり前だろう」
灯璃の手が千冬の頬に触れ、ゆっくりと上に向かせる。
もう一度、赤い瞳と視線が絡み合う。
「はな、よめ……?」
言葉の意味が分からず首を傾げる千冬に灯璃は頷いた。
「君は私の……鬼城家の当主の花嫁だ」
灯璃は自分の花嫁をそっと引き寄せて存在を確かめるように抱きしめた。