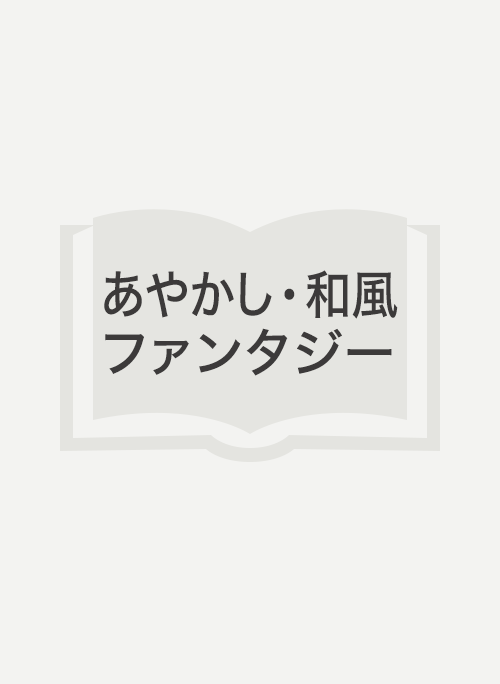掃除をする千冬を残して宗一は仕事に、依里恵と依鈴は百貨店へ出かけていった。
どうやら依鈴は女学校が始まる前に新しい着物が欲しいらしい。
依鈴は千冬と違い、器量も良く愛嬌がある。
欲しい物があるとねだればすぐに手に入った。
普段から優美に着飾る妹とは反対に千冬は古びたお仕着せ姿だった。
私物もほとんどなく、日用品などは全て他の使用人から譲ってもらったお下がり。
呪いの証である紫紺色の瞳をもっていることを周囲に知られたくないのか町に外出すること自体も禁じられていた。
幼い頃は憧れもあったが虐げられているうちにそういった希望もなくなったので特には困っていない。
嶺木家は頻繁に来客があるため、継母達は千冬を庭さえも出ることを許さなかった。
病弱で部屋から出られないという嘘をつくり屋敷で働く使用人達にも他言しないよう口止めをしていた。
そんな千冬がやることは基本的に屋敷の中の家事。
水で濡れた髪を手ぬぐいで拭いたあと、中庭に面した廊下の掃除をしていた。
季節は春といえ、時折吹く風は冷たい。身体が冷えていくのがわかるが手は止めない。
継母達が帰宅する前に頼まれていた家事を全て済ませていないと、また怒鳴られるからだ。
怒鳴られるだけならまだ良い。
機嫌が悪いと食事を抜かれるのだ。
千冬が前回食事をしたのは昨日の朝。
最初の頃は空腹感を感じたが今では不思議とそれすらも分からなくなった。
その時に勘づいた。
もしかしたらもうすぐ栄養失調と寝不足で死ぬかもしれないと。
目の前に死を感じても千冬は怖くなかった。
こんな生活を送るのなら天にいる母の元へ逝ける方がずっと良いから。
(もうわたしには幸せな未来は待っていない。ただお母さまの元へ早く逝けるよう息をするだけ)
もう何も期待しない。
何かを願うことすら千冬にとって無駄なのだ。
夕刻までに家事を間に合わせようとあかぎれだらけの手で必死に雑巾を動かしていると玄関から声がした。
「ごめんください」
男性の声に他の使用人が反応し玄関へ足早に向かう。
来客があっても人に会えない千冬は手を止めなかった。
(この声は時田さまね)
声の主、時田清二《ときた しんじ》は依鈴の婚約者。
嶺木家に次ぐ名家の次男で依鈴の女学校卒業後は婿になる予定だ。
人と断固として会わせようとしない継母達がいるためもちろん千冬は清二と会ったことがない。
どれだけ病気という嘘で誤魔化し続けられるのだろう。
しかしその嘘がばれる前にきっとそれが現実になるのが先だと思う。
「これは時田さま、ようこそいらっしゃいました」
「こんにちは。依鈴はいる?」
「申し訳ありません。依鈴さまは外出されておりまして……」
「いや、僕も近くに用があって。せっかくだから顔を見に寄っていこうと思ったんだ」
その時、強い風が吹きつけ桜の花びらが舞う。
ゆっくりと落ちてくる一枚の桃色の花びらを清二はそっと手にとる。
「嶺木家の中庭にある桜の木は立派だよね」
「ええ。今年も美しく満開に咲きました。もしよろしければ近くで見ていかれますか?」
「じゃあお言葉に甘えて。せっかくだから」
二人の会話が耳に届き、千冬はぴたりと動きを止めた。
今いる場所は中庭に面している廊下。
桜の木はすぐそこにあるため清二が来たら紫紺の瞳を見られてしまう。
慌てて立ち上がりこの場を離れようとしたとき。
(あっ……!)
足が滑り、転んだはずみで水汲み桶を倒し中身を全てこぼしてしまった。
桶が廊下から外へ転がってしまうが近くに清二がいるため拾いにも行けない。
「今、大きい音がしたけれど……」
音に反応して玄関にいた清二が不思議そうに中庭の方へ視線を向ける。
「何の音でしょうか」
使用人も気になったようで二人の足音がこちらへ少しずつ近づいてくる。
自分の鈍くささに嫌気がさすが今は落ち込んでいられない。
(早く行かないと……!)
再び立ち上がろうと足に力を入れるがまともに食事をとっていないせいか視界がぐらりと揺れる。
気持ち悪さをおぼえたとき。
「ひっ……!」
まるで化け物を見たような声が耳に届く。
ああ、やってしまった。
今まで必死に貫き通してきた嘘がばれてしまったのだ。
千冬が少しだけ中庭に視線を向けると青白い顔で身体を小刻みに震わせている清二の姿があった。
彼についてきた使用人もまさか千冬が近くにいたとは知らなかったのだろう。
口元を抑え最悪の事態に混乱しているようだった。
「ち、千冬さま……!」
思わず発した小さな使用人の声を清二は聞き逃さなかった。
「千冬?まさかあいつが依鈴の姉……!?」
ただ働き同然の貧しい使用人だと嘘をついてすぐに解雇するとでも言えば良いのにその場にいる誰もがそんな気の利いた考えすら思い浮かばない。
「姉が紫紺色の瞳をもっているとは聞いていないぞ!ちっ、僕は帰る!!」
「時田さま……!」
清二は騙されていたことに腹が立ったのか顔を真っ赤にして中庭から去って行く。
慌てて使用人も追いかけるが表門の前に止めてあった自動車に乗り込むとすぐに走らせてしまった。
千冬は雑巾を持ったまま立ち尽くす。
恐れていたことがついに現実になってしまったと血の気が引いていく感覚がした。
その後、頼まれていた家事は全く身が入らず、これほど継母達が帰宅するのが怖かったことは一度もなかった。
どうやら依鈴は女学校が始まる前に新しい着物が欲しいらしい。
依鈴は千冬と違い、器量も良く愛嬌がある。
欲しい物があるとねだればすぐに手に入った。
普段から優美に着飾る妹とは反対に千冬は古びたお仕着せ姿だった。
私物もほとんどなく、日用品などは全て他の使用人から譲ってもらったお下がり。
呪いの証である紫紺色の瞳をもっていることを周囲に知られたくないのか町に外出すること自体も禁じられていた。
幼い頃は憧れもあったが虐げられているうちにそういった希望もなくなったので特には困っていない。
嶺木家は頻繁に来客があるため、継母達は千冬を庭さえも出ることを許さなかった。
病弱で部屋から出られないという嘘をつくり屋敷で働く使用人達にも他言しないよう口止めをしていた。
そんな千冬がやることは基本的に屋敷の中の家事。
水で濡れた髪を手ぬぐいで拭いたあと、中庭に面した廊下の掃除をしていた。
季節は春といえ、時折吹く風は冷たい。身体が冷えていくのがわかるが手は止めない。
継母達が帰宅する前に頼まれていた家事を全て済ませていないと、また怒鳴られるからだ。
怒鳴られるだけならまだ良い。
機嫌が悪いと食事を抜かれるのだ。
千冬が前回食事をしたのは昨日の朝。
最初の頃は空腹感を感じたが今では不思議とそれすらも分からなくなった。
その時に勘づいた。
もしかしたらもうすぐ栄養失調と寝不足で死ぬかもしれないと。
目の前に死を感じても千冬は怖くなかった。
こんな生活を送るのなら天にいる母の元へ逝ける方がずっと良いから。
(もうわたしには幸せな未来は待っていない。ただお母さまの元へ早く逝けるよう息をするだけ)
もう何も期待しない。
何かを願うことすら千冬にとって無駄なのだ。
夕刻までに家事を間に合わせようとあかぎれだらけの手で必死に雑巾を動かしていると玄関から声がした。
「ごめんください」
男性の声に他の使用人が反応し玄関へ足早に向かう。
来客があっても人に会えない千冬は手を止めなかった。
(この声は時田さまね)
声の主、時田清二《ときた しんじ》は依鈴の婚約者。
嶺木家に次ぐ名家の次男で依鈴の女学校卒業後は婿になる予定だ。
人と断固として会わせようとしない継母達がいるためもちろん千冬は清二と会ったことがない。
どれだけ病気という嘘で誤魔化し続けられるのだろう。
しかしその嘘がばれる前にきっとそれが現実になるのが先だと思う。
「これは時田さま、ようこそいらっしゃいました」
「こんにちは。依鈴はいる?」
「申し訳ありません。依鈴さまは外出されておりまして……」
「いや、僕も近くに用があって。せっかくだから顔を見に寄っていこうと思ったんだ」
その時、強い風が吹きつけ桜の花びらが舞う。
ゆっくりと落ちてくる一枚の桃色の花びらを清二はそっと手にとる。
「嶺木家の中庭にある桜の木は立派だよね」
「ええ。今年も美しく満開に咲きました。もしよろしければ近くで見ていかれますか?」
「じゃあお言葉に甘えて。せっかくだから」
二人の会話が耳に届き、千冬はぴたりと動きを止めた。
今いる場所は中庭に面している廊下。
桜の木はすぐそこにあるため清二が来たら紫紺の瞳を見られてしまう。
慌てて立ち上がりこの場を離れようとしたとき。
(あっ……!)
足が滑り、転んだはずみで水汲み桶を倒し中身を全てこぼしてしまった。
桶が廊下から外へ転がってしまうが近くに清二がいるため拾いにも行けない。
「今、大きい音がしたけれど……」
音に反応して玄関にいた清二が不思議そうに中庭の方へ視線を向ける。
「何の音でしょうか」
使用人も気になったようで二人の足音がこちらへ少しずつ近づいてくる。
自分の鈍くささに嫌気がさすが今は落ち込んでいられない。
(早く行かないと……!)
再び立ち上がろうと足に力を入れるがまともに食事をとっていないせいか視界がぐらりと揺れる。
気持ち悪さをおぼえたとき。
「ひっ……!」
まるで化け物を見たような声が耳に届く。
ああ、やってしまった。
今まで必死に貫き通してきた嘘がばれてしまったのだ。
千冬が少しだけ中庭に視線を向けると青白い顔で身体を小刻みに震わせている清二の姿があった。
彼についてきた使用人もまさか千冬が近くにいたとは知らなかったのだろう。
口元を抑え最悪の事態に混乱しているようだった。
「ち、千冬さま……!」
思わず発した小さな使用人の声を清二は聞き逃さなかった。
「千冬?まさかあいつが依鈴の姉……!?」
ただ働き同然の貧しい使用人だと嘘をついてすぐに解雇するとでも言えば良いのにその場にいる誰もがそんな気の利いた考えすら思い浮かばない。
「姉が紫紺色の瞳をもっているとは聞いていないぞ!ちっ、僕は帰る!!」
「時田さま……!」
清二は騙されていたことに腹が立ったのか顔を真っ赤にして中庭から去って行く。
慌てて使用人も追いかけるが表門の前に止めてあった自動車に乗り込むとすぐに走らせてしまった。
千冬は雑巾を持ったまま立ち尽くす。
恐れていたことがついに現実になってしまったと血の気が引いていく感覚がした。
その後、頼まれていた家事は全く身が入らず、これほど継母達が帰宅するのが怖かったことは一度もなかった。