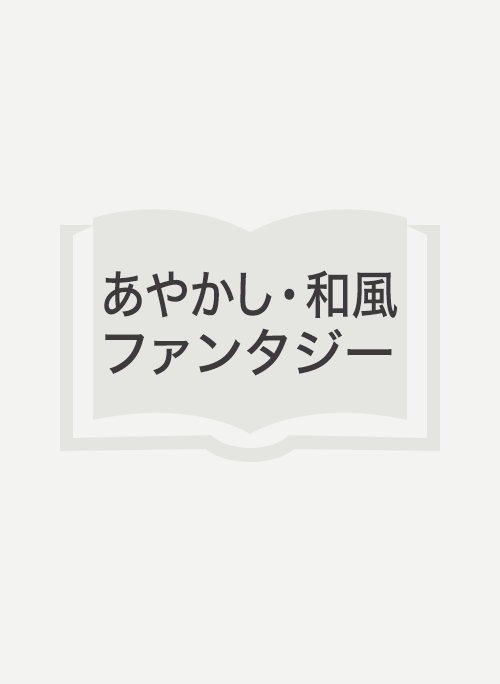窓から見える流れる景色にはいくつもの巨大な屋敷が建ち並び、壮観だ。
灯璃と出逢ったあの日の夜にも、自動車から町の様子を見たが、また違った印象を受ける。
あのときは、まだそこまで余裕もなかったし、暗闇に包まれていたので、はっきりとはわからなかった。
やはり、あやかしとその花嫁が住む國だけあって、どの建物や僅かに覗かせる庭も立派だ。
夢中になって外の景色を見ている姿を微笑ましそうに見られていたのを千冬は知らなかった。
自動車に乗り込み、屋敷を出発してから数分後。
「ここでいい」
「かしこまりました」
灯璃は運転手にそう伝えると自動車はゆっくりと路肩に止まった。
先に降りた灯璃が手を差し伸べてくれる。
「足元、気をつけなさい」
「ありがとうございます」
自動車から降りると少し先には人が行き交って賑わう様子が見える。
人だけではなく、あやかしもいるが。
あやかしの外見は人間と同じだが感じる雰囲気が違う。
千冬でもその違いが何となくだがわかる。
灯璃だけではない。
鬼城家の使用人たちもそうだ。
言葉にするのが難しく、言うなれば神秘的さが溢れているというべきだろうか。
(あの場所が、かくりよ國の中心部かしら)
未知なる世界に飛び込むようで鼓動が早くなる。
期待と少しの不安が入り交じり、そわそわしている千冬を見て灯璃はくすりと笑う。
「迎えの時間は念話で伝える」
運転手は「かしこまりました」と言い頭を下げると再び自動車に乗り込み、去っていった。
少しずつ小さくなる自動車を見ていると。
「では行こうか」
「はい」
千冬は灯璃の隣に立ち、町の中心部に向かって歩き出した。
歩き始めてすぐに店が建ち並ぶ通りへ到着した。
書店や洋裁店、呉服屋に食事処などがあり千冬にとって、その珍しさに思わず辺りを見渡してしまう。
そして行き交うのは、あやかしやその花嫁の女性でとても美しく気品に溢れている。
そして、それをはるかに上回る輝きを放つ灯璃の存在に周囲はすぐに気がついた。
「もしかして、あの御方は鬼城さま?」
「まあ、町へお出向きになられるなんて珍しいわね」
「あちらのご令嬢はもしかして……」
周囲が灯璃から千冬に視線を移す。
ぎょっとして目を見開く者、興味深そうにジッと見る者などが複数いる。
やはり、かくりよ國でも言い伝えや噂などは少なからず知られているようだ。
想定内の反応とはいえ、実際に目の当たりにするとつらい。
向けられる好奇な視線に耐えきれず顔を俯かせる。
(せっかく鬼城さまが誘ってくださったのに……。このお化粧だって詩乃さんが……)
彼らの優しさを無下にしてしまっているように感じて、町は賑わっているはずなのに何故か静寂に包まれたように思える。
千冬は薄々気がついてはいた。
灯璃は自分を励まして元気にさせようとしているのだと。
しかし、こんな視線を浴びながらでは町を歩けない。
彼に迷惑をかける前に屋敷へ引き返した方がよいと思った千冬はそっと灯璃を見る。
「あの鬼城さま。やはり屋敷へ帰り……」
「千冬はどこへ行きたい?」
千冬が言い切る前に灯璃の言葉が重なる。
そして肩を抱き寄せられて二人の身体がぴたりと触れ合った。
まさか外の大勢のひとたちの前でこんな大胆なことをするとは思っておらず一瞬、頭が真っ白になった。
周囲がざわめくのが聞こえてはっと我に返る。
「この瞳のせいで視線を感じるのは鬼城さまは嫌ではありませんか?」
「私を気遣ってくれているのか?千冬は優しいな。私なら全く問題ない」
頭をゆっくりと撫でてくれる手が沈んでいた気持ちを起こしてくれる。
その温かな声色に彼が嘘をついていないことがすぐにわかった。
千冬を見つめたあと、灯璃はちらりと周囲を見やる。
「わたしの愛する花嫁に好奇な視線を向けるのなど、誰であっても許さない」
少しだけ声を大きくして言い放つと周囲がさらにざわめく。
花嫁が見つかったことは鬼の一族には通知されたが他のあやかしたちは知らない。
薫子との結婚が噂されていた灯璃が人間の花嫁を迎え入れたことは一大事だ。
そして灯璃の隣にいる女性こそ鬼帝の妻になるのだと理解したとたん、慌てて頭を下げる。
「えっ……!?」
先ほどとうって変わった態度に困惑してしまう。
灯璃だけは冷静で、呆れたように周囲の人々を見ると一つ息をついた。
「やっと立場をわきまえたか。私が隣に連れている女性など花嫁に決まっているだろう」
「わたしなどに頭など下げなくても……」
恭しい扱いをされる資格など自分にはない。
ほんの数日前までは使用人以下同然の存在で今、頭を下げているあやかしたちの方が立場が上だったのだ。
先日、灯璃にも堂々としていて良いのだと教えられたが、謝ることや意見を言わずに遠慮することが身体に染みついていて簡単に直すのはできない。
「あやかしたちの頂点に立つ存在、鬼の花嫁に頭を下げるのは彼らにとって当たり前なんだ。するとしないのでは未来が変わってくる。不敬にあたり命がなくなるも同然」
「そう……ですか」
ここは帝都ではない、人間たちから尊ばれ位が高い者が集まるかくりよ國。
郷に入っては郷に従う、そのことわざ通りしきたりなどがあれば守ろうとそれ以上言うのは諦めた。
「そう暗い顔はするな。しばらくすれば慣れる」
(多分、慣れるまで鬼城さまが思われている数倍は時間がかかると思うけれど)
もしかしたら一生……とも考えてしまったが、灯璃の妻として威厳を保たなければいけないのに、いつまでも弱々しいのは駄目だ。
口にするのはやめて、ぐっと呑み込んだ。
そして千冬の肩を抱き寄せたまま灯璃は歩き始める。
ちらりと周囲の人々を見ると二人が遠ざかっていくにつれて各々頭を上げて散っていった。
皆から絶大な信頼を集めている鬼城家の当主が連れている女性、ということもあるのかそれ以降は好奇な視線を向けられることはなかった。
少しずつ建ち並ぶ店を見渡す余裕も出てきた千冬に灯璃は気がつくと、ふと足を止めた。
「千冬は何か欲しいものはあるか?」
「いえ……。特にございません」
「遠慮はしなくて良いんだ。宝飾品や着物、洋服などはどうだ?」
「わたしはすでに頂いているもので十分ですし鬼城さまが行きたいところへついていきます」
遠慮というより本当に物欲がないのだ。
宝飾品も綺麗だとは思うけれどそんな高価なものは素朴な容姿の自分には似合わないし着物も狐森呉服屋に現在進行形で仕立ててもらっている。
雑誌で洋装姿の女性の絵を見たがワンピースと呼ばれるものは足を出すと知り、想像しただけで恥ずかしくなったので無理だった。
特に行き先を決めないまま歩き続けるのも灯璃にとって退屈だろう。
そもそも、かくりよ國については、まったくの無知なので灯璃に案内してもらった方が助かる。
「それにわたしはまだ鬼城さまのことを詳しく知りません。どのような物や場所がお好きなのか知りたいです」
「……っ」
思ったままのことを言葉にした瞬間、灯璃は口元を手で隠す。
視線もパッと逸らし、僅かに見える頬はほんのり赤い。
珍しい彼の姿に千冬は瞳を数回、瞬かせた。
「鬼城さま?どうかされましたか?もしかして熱があるのでは……」
先ほどまでは顔色も良く、こちらから見ても何の違和感もなかったのだが。
しかし彼は鬼帝として多忙な毎日を過ごしているので、いつ体調を崩してしまってもおかしくはないと日々案じていた。
疲れているのに自分を楽しませようと無理をしているのだったら嫌だ。
眉を下げて心から心配している千冬を見て灯璃はすぐに口を開く。
「いや、私はいたって元気だ。ただ、千冬が愛らしいことを言うから照れてしまった」
「あ、愛らしっ……!?どこがでしょう?」
自分の言葉を思い返してみるが特に何も変わったことは言っていない。
夫となる相手について何も知らないのは、かなりまずいと思ったまでだ。
千冬が戸惑っていると灯璃はくすりと笑みをこぼした。
「無自覚か……。これは手強いな」
「え?わたしが手強い?」
(わたしなんかに鬼帝である御方が苦戦しているというの……?一体どういうことかしら)
話の本質がまったく見えず千冬は首を傾げるばかり。
一生懸命考えている姿を見て灯璃は楽しそうにくっと喉を鳴らせた。
「いや、いいんだ。千冬は今のままでいてくれたら」
「は、はい……」
結局、何もわからぬまま頷いてしまった。
今までは自分の意思すらまともに言えず、器量や要領も妹と比べて悪い性格など嫌いだった。
しかし誰かに「そのままでいてほしい」と言われたのは初めてで無理に変えようとしなくても良いのだと教えてもらったような気がする。
「私も中心部の町へ来たのは久しぶりだ。千冬が良ければ以前によく行っていた店に案内しよう」
「はい。お願いします」
灯璃が通っていた店というのを聞いて一段と興味がわく。
非番で屋敷にいるときは書物を読んでいることが多いが、他には何が好きなのか知らない。
会話はほとんど灯璃から切り出す。
あまり話をするのが得意ではない千冬はいつも受け身だ。
灯璃と出逢ってまだ一ヶ月も経っていないので距離感が難しい。
(今日一日で少しでも近づけたら良いのだけど)
こっそりと灯璃に視線を向ける。
店に行く順番を考えているのか顎に手を添えている姿は様になっている。
「では一つ目の店に行こうか。こちらだ」
「は、はい」
見蕩れてしまっていたことに気がつき、千冬は慌てて少し先を歩き出した灯璃のあとを追ったのだった。
「着いたぞ。この店だ」
歩き始めて数分。
足を止めて掲げられている看板を見上げると『狐寺屋』の文字。
店の外に設置されている椅子には女学生とみられる二人組が手に持っている団子を美味しそうに食べている。
(お団子を食べているということは、ここは甘味処かしら?)
辺りは香ばしく甘い香りやお茶の香りが漂い、鼻を抜ける。
店の中へ入ると食器を片付けていた老婦がこちらへ気がつく。
「まあまあ!坊ちゃま、お久しぶりでございます」
柔和な笑顔で目尻を細めて嬉しそうにしている。
「久しぶりだな。それと八重子さん、私はもう坊ちゃまと言われるような年齢ではない」
「ふふっ。申し訳ありません。つい嬉しくて」
八重子と呼ばれた女性は灯璃の隣にいる千冬に視線を向ける。
しっかりと目が合ってしまい、奥底から恐怖心が出てきてしまう。
何かまた言われるかもしれないと肩を僅かに震わせる。
しかしその瞬間を灯璃は見逃さずに千冬に「大丈夫だ」と言うように背中に手を添えてくれた。
(堂々としなくちゃ……)
千冬は気持ちを鼓舞して老婦を見据えた。
「そちらのご令嬢はもしかして……」
「ああ、私の花嫁だ」
「左様でございますか!坊ちゃまがついに……!」
「だから坊ちゃまと呼ぶのは……」
「あなた!坊ちゃまが花嫁さまと一緒にお見えになりましたよ!」
灯璃が自分の呼び名を訂正しようとしたが厨房にいる誰かに声をかける八重子の耳
には届かないようだった。
「相変わらずだな、八重子さんは……」
ぽつりと呟き、ひとつため息をはいていたが、困ったように笑う灯璃の表情は初めて見る。
(町の親しい方とはこんな表情もするのね)
新たな一面を知れたような気がして嬉しくなっていると厨房から一人の老夫が出てきた。
「これはこれは坊ちゃん!よくおいでくださいました」
親しみやすそうな、にこやかな笑みを浮かべる姿は八重子とそっくりだ。
「真太郎さんも元気そうでなりよりだよ」
「お陰さまで夫婦共々、大きな病気をすることなくやっています」
八重子が厨房に「あなた」と呼んでいた時点で何となく察しはついていたが二人は夫婦のようだ。
「そうか。私は今日、かくりよ國の町を千冬に案内しているんだ。まずは狐寺屋のあんみつを食べてもらいたいと思って」
「まあ、それは嬉しゅうございます!今、お茶をお持ちしますね。奥の席へどうぞ」
真太郎は厨房へ戻り、八重子は二人を奥の席に案内するとお茶が入った湯呑みを運んできてくれた。
「坊ちゃんもあんみつでよろしいですか?」
「ああ。頼む」
「少々お待ちくださいませ」
軽く頭を下げるとお盆を抱えて厨房へ戻っていった。
目の前に置かれた湯呑みを持ち、温かいお茶を一口飲む。
ちらりと店内を見渡せば老舗を感じさせながらも置かれている椅子や洋卓も手入れが行き届いていて綺麗に整えられており落ち着く雰囲気だった。
「鬼城さまとお店のご夫婦はとても仲がよろしいのですね」
「この店は私が幼い頃から家族とよく来ていたんだ。だから二人は未だに私を坊ちゃんと呼ぶ。人前ではやめてほしいのだが……」
流石に花嫁の前で坊ちゃんという呼び名は恥ずかしいのか灯璃はやめてほしいそうだ。
しかし千冬から見ると、灯璃と老夫婦二人からは特別な絆のようなもので繋がっているような気がして少し羨ましくもあった。
「そう、でしょうか?ご夫婦は鬼城さまのことをとても可愛がられていらっしゃるのですね」
「二人から見れば私はまだ子供なのだろう」
灯璃は二十七歳という大の大人だが幼い頃から彼を見ている夫婦にとっては、もしかしたらいつまでも可愛い子供なのかもしれない。
「お待たせしました。あんみつ二つです」
他愛のない話をしていると八重子がお盆にあんみつをのせて運んできた。
目の前に置かれた器の中には、あんこと寒天の他に色付きの求肥や果物などが乗っていて想像していたより色鮮やかなものだっだ。
「わぁ……!」
あんみつを見て瞳を輝かせている千冬に八重子はくすりと笑った。
「坊ちゃんも初めてあんみつを見たときは花嫁さまと同じような反応でしたよ。それはもう瞳を輝かせて可愛らしい笑顔で……」
「お、おい。その話はやめろ」
すぐに止めに入った灯璃を見ると彼の頬は若干赤く染まっていた。
どうやら今の彼と昔の彼は少し違っているようで思い出話をされるのは苦手らしい。
(幼い頃の鬼城さま、気になるかも……。やはり年相応で無邪気だったのかしら)
冷静で物静かな今の灯璃には想像しづらいが彼にもそんな時期があったのだろう。
そう思いながら二人のやり取りを眺めていると。
「千冬、もしかして私の幼少期の想像をしてはいないか?」
「へっ……!?」
図星をつかれ思わず変な声が出てしまった。
深く考えていたわけではない。
少しだけ、ぼんやりと幼少期の灯璃を想像してしまった。
きっと勝手に想像されるのは、あまり良い気分ではなかったのだと反省する。
「あ、の……。申し訳ありません……」
誤魔化すことはせずに素直に謝罪をした。
「謝ることはない。千冬の頭の中では今、私のことを考えているのだろう?花嫁にそれだけ思われているのは嬉しい」
「……っ」
灯璃は切れ長の瞳を細め、まるでこの上ない幸せを感じているかのような笑みを浮かべている。
あやかしは花嫁を存分に愛すとは噂程度に聞いたことがあった。
しかし、ただ相手のことを考えているだけで喜ぶのだとは予想外だった。
その熱を含んだ瞳がこちらを射抜き、鼓動が跳ねるのがわかった。
灯璃は照れている千冬の表情をこっそり堪能したあと匙を持つ。
「さあ、あんみつを食べよう。美味いぞ」
「は、はい」
頬の熱を冷ますように、ぱたぱたと手で仰ぐと千冬も匙を持った。
「いただきます」
二人で同時に手を合わせて挨拶をすると、あんこと寒天を匙にのせて口に運ぶ。
上品な甘さが口いっぱいに広がり、食べたことのない味に感動で思わず、あんみつを見つめる。
「美味しい……!」
そう呟くと、次は器からあんこと果物をすくって一口食べる。
先ほどとは違う、果物の酸味も加わった美味しさになる。
(料理人の方たちが作られる甘味も美味しいけれど、このあんみつも負けないくらい美味しいわ)
次は求肥と一緒に……と匙ですくおうとしたとき目の前から視線を感じた。
ふと顔を上げると灯璃が優しい笑みでこちらを見ていた。
「あ……」
美味しさのあまり、自分がつい次から次へと夢中になって食べていたことに気がつき、我に返る。
急激に恥ずかしくなり先ほどとは違う意味で頬に熱をもつ。
(わ、わたしったら何をしているの!)
格式高い屋敷の主人、そして男性と食事をしているのに、自分が思うまま食べてしまっていた。
花嫁になるのだからしっかりしたいのにこれでは完全に甘味に夢中な子供だ。
「す、すみません……」
語尾になるにつれて小さく消えそうな声。
感情を抑えてもっと上品に食べればよかったと今になって反省をする。
良妻賢母を目指す決意をしたのに早速この有様だ。
羞恥心やら自己嫌悪やらで俯き、口をつぐんでいると。
「食欲があってよかった。千冬は食が細いから心配していたんだ」
「え……?」
灯璃はまったく怪訝そうな顔などしておらず、むしろ安堵したような表情をしていた。
(もしかして鬼城さまはずっとわたしのことを心配してくださっていたの?)
鬼城家での食事はいつも、少なめでお願いをしている。
決して料理が美味しくないとか、そんなわけではない。
嶺木家での食生活の影響だろう。
ただ一回出される量でやっと食べきれられるのだ。
残したら申し訳ないと思い、初めての夕食のあと、こっそりお世話係である詩乃にお願いをしていた。
灯璃はそんな千冬の状態をすでに見抜いており、心配してくれていたのだ。
以前に一度、「千冬に出す食事の量が少なくないか」とお膳立てをしている使用人に怪訝そうな顔を見せていたが、すぐに千冬がわたしがお願いしたのだと伝えて納得してくれた。
少量の食事が続いていたため、灯璃の心配も拭われなかったのだろう。
あんみつをどんどん食べ進める千冬を笑顔で見つめていた。
「遠慮することはない。それでいい」
「でも、もっとゆっくり丁寧に食べないと……」
「今は二人の時間だ。それに千冬の食事の作法も十分、綺麗だ」
昔、実母が亡くなる前に作法を教えてもらったような気がするがほとんど記憶に残っていない。
使用人として扱われていたときも当然のごとく勉強することはできず、父と継母、女学校に通っている依鈴だけが完璧に身につけていた。
灯璃が優しいのは嬉しいが、ただ甘やかされているだけでは成長できないと思う。
「わたし、屋敷に帰ったらお勉強をもっと頑張ります」
現状で満足してはいけないと、灯璃の隣に立って相応しい女性になりたいと決意に満ちる目が彼を射抜く。
そんな千冬を見て灯璃は少し目を見開いて驚いたような表情を浮かべたあと頷いた。
「わかった。マナーに関する書物も用意しよう。必要となれば講師も呼ぶからいつでも言いなさい」
「ありがとうございます……!」
千冬に笑顔が戻り再び二人は、あんみつを食べ始めた。
店内には穏やかな時間が流れており、八重子と真太郎夫婦が微笑ましそうに見ていた。
自分が外の世界で食事をすることができる日がきたこと、勉学に励めることに感謝をしながら、千冬はあんみつが載った匙を口元に運ぶのだった。
灯璃と出逢ったあの日の夜にも、自動車から町の様子を見たが、また違った印象を受ける。
あのときは、まだそこまで余裕もなかったし、暗闇に包まれていたので、はっきりとはわからなかった。
やはり、あやかしとその花嫁が住む國だけあって、どの建物や僅かに覗かせる庭も立派だ。
夢中になって外の景色を見ている姿を微笑ましそうに見られていたのを千冬は知らなかった。
自動車に乗り込み、屋敷を出発してから数分後。
「ここでいい」
「かしこまりました」
灯璃は運転手にそう伝えると自動車はゆっくりと路肩に止まった。
先に降りた灯璃が手を差し伸べてくれる。
「足元、気をつけなさい」
「ありがとうございます」
自動車から降りると少し先には人が行き交って賑わう様子が見える。
人だけではなく、あやかしもいるが。
あやかしの外見は人間と同じだが感じる雰囲気が違う。
千冬でもその違いが何となくだがわかる。
灯璃だけではない。
鬼城家の使用人たちもそうだ。
言葉にするのが難しく、言うなれば神秘的さが溢れているというべきだろうか。
(あの場所が、かくりよ國の中心部かしら)
未知なる世界に飛び込むようで鼓動が早くなる。
期待と少しの不安が入り交じり、そわそわしている千冬を見て灯璃はくすりと笑う。
「迎えの時間は念話で伝える」
運転手は「かしこまりました」と言い頭を下げると再び自動車に乗り込み、去っていった。
少しずつ小さくなる自動車を見ていると。
「では行こうか」
「はい」
千冬は灯璃の隣に立ち、町の中心部に向かって歩き出した。
歩き始めてすぐに店が建ち並ぶ通りへ到着した。
書店や洋裁店、呉服屋に食事処などがあり千冬にとって、その珍しさに思わず辺りを見渡してしまう。
そして行き交うのは、あやかしやその花嫁の女性でとても美しく気品に溢れている。
そして、それをはるかに上回る輝きを放つ灯璃の存在に周囲はすぐに気がついた。
「もしかして、あの御方は鬼城さま?」
「まあ、町へお出向きになられるなんて珍しいわね」
「あちらのご令嬢はもしかして……」
周囲が灯璃から千冬に視線を移す。
ぎょっとして目を見開く者、興味深そうにジッと見る者などが複数いる。
やはり、かくりよ國でも言い伝えや噂などは少なからず知られているようだ。
想定内の反応とはいえ、実際に目の当たりにするとつらい。
向けられる好奇な視線に耐えきれず顔を俯かせる。
(せっかく鬼城さまが誘ってくださったのに……。このお化粧だって詩乃さんが……)
彼らの優しさを無下にしてしまっているように感じて、町は賑わっているはずなのに何故か静寂に包まれたように思える。
千冬は薄々気がついてはいた。
灯璃は自分を励まして元気にさせようとしているのだと。
しかし、こんな視線を浴びながらでは町を歩けない。
彼に迷惑をかける前に屋敷へ引き返した方がよいと思った千冬はそっと灯璃を見る。
「あの鬼城さま。やはり屋敷へ帰り……」
「千冬はどこへ行きたい?」
千冬が言い切る前に灯璃の言葉が重なる。
そして肩を抱き寄せられて二人の身体がぴたりと触れ合った。
まさか外の大勢のひとたちの前でこんな大胆なことをするとは思っておらず一瞬、頭が真っ白になった。
周囲がざわめくのが聞こえてはっと我に返る。
「この瞳のせいで視線を感じるのは鬼城さまは嫌ではありませんか?」
「私を気遣ってくれているのか?千冬は優しいな。私なら全く問題ない」
頭をゆっくりと撫でてくれる手が沈んでいた気持ちを起こしてくれる。
その温かな声色に彼が嘘をついていないことがすぐにわかった。
千冬を見つめたあと、灯璃はちらりと周囲を見やる。
「わたしの愛する花嫁に好奇な視線を向けるのなど、誰であっても許さない」
少しだけ声を大きくして言い放つと周囲がさらにざわめく。
花嫁が見つかったことは鬼の一族には通知されたが他のあやかしたちは知らない。
薫子との結婚が噂されていた灯璃が人間の花嫁を迎え入れたことは一大事だ。
そして灯璃の隣にいる女性こそ鬼帝の妻になるのだと理解したとたん、慌てて頭を下げる。
「えっ……!?」
先ほどとうって変わった態度に困惑してしまう。
灯璃だけは冷静で、呆れたように周囲の人々を見ると一つ息をついた。
「やっと立場をわきまえたか。私が隣に連れている女性など花嫁に決まっているだろう」
「わたしなどに頭など下げなくても……」
恭しい扱いをされる資格など自分にはない。
ほんの数日前までは使用人以下同然の存在で今、頭を下げているあやかしたちの方が立場が上だったのだ。
先日、灯璃にも堂々としていて良いのだと教えられたが、謝ることや意見を言わずに遠慮することが身体に染みついていて簡単に直すのはできない。
「あやかしたちの頂点に立つ存在、鬼の花嫁に頭を下げるのは彼らにとって当たり前なんだ。するとしないのでは未来が変わってくる。不敬にあたり命がなくなるも同然」
「そう……ですか」
ここは帝都ではない、人間たちから尊ばれ位が高い者が集まるかくりよ國。
郷に入っては郷に従う、そのことわざ通りしきたりなどがあれば守ろうとそれ以上言うのは諦めた。
「そう暗い顔はするな。しばらくすれば慣れる」
(多分、慣れるまで鬼城さまが思われている数倍は時間がかかると思うけれど)
もしかしたら一生……とも考えてしまったが、灯璃の妻として威厳を保たなければいけないのに、いつまでも弱々しいのは駄目だ。
口にするのはやめて、ぐっと呑み込んだ。
そして千冬の肩を抱き寄せたまま灯璃は歩き始める。
ちらりと周囲の人々を見ると二人が遠ざかっていくにつれて各々頭を上げて散っていった。
皆から絶大な信頼を集めている鬼城家の当主が連れている女性、ということもあるのかそれ以降は好奇な視線を向けられることはなかった。
少しずつ建ち並ぶ店を見渡す余裕も出てきた千冬に灯璃は気がつくと、ふと足を止めた。
「千冬は何か欲しいものはあるか?」
「いえ……。特にございません」
「遠慮はしなくて良いんだ。宝飾品や着物、洋服などはどうだ?」
「わたしはすでに頂いているもので十分ですし鬼城さまが行きたいところへついていきます」
遠慮というより本当に物欲がないのだ。
宝飾品も綺麗だとは思うけれどそんな高価なものは素朴な容姿の自分には似合わないし着物も狐森呉服屋に現在進行形で仕立ててもらっている。
雑誌で洋装姿の女性の絵を見たがワンピースと呼ばれるものは足を出すと知り、想像しただけで恥ずかしくなったので無理だった。
特に行き先を決めないまま歩き続けるのも灯璃にとって退屈だろう。
そもそも、かくりよ國については、まったくの無知なので灯璃に案内してもらった方が助かる。
「それにわたしはまだ鬼城さまのことを詳しく知りません。どのような物や場所がお好きなのか知りたいです」
「……っ」
思ったままのことを言葉にした瞬間、灯璃は口元を手で隠す。
視線もパッと逸らし、僅かに見える頬はほんのり赤い。
珍しい彼の姿に千冬は瞳を数回、瞬かせた。
「鬼城さま?どうかされましたか?もしかして熱があるのでは……」
先ほどまでは顔色も良く、こちらから見ても何の違和感もなかったのだが。
しかし彼は鬼帝として多忙な毎日を過ごしているので、いつ体調を崩してしまってもおかしくはないと日々案じていた。
疲れているのに自分を楽しませようと無理をしているのだったら嫌だ。
眉を下げて心から心配している千冬を見て灯璃はすぐに口を開く。
「いや、私はいたって元気だ。ただ、千冬が愛らしいことを言うから照れてしまった」
「あ、愛らしっ……!?どこがでしょう?」
自分の言葉を思い返してみるが特に何も変わったことは言っていない。
夫となる相手について何も知らないのは、かなりまずいと思ったまでだ。
千冬が戸惑っていると灯璃はくすりと笑みをこぼした。
「無自覚か……。これは手強いな」
「え?わたしが手強い?」
(わたしなんかに鬼帝である御方が苦戦しているというの……?一体どういうことかしら)
話の本質がまったく見えず千冬は首を傾げるばかり。
一生懸命考えている姿を見て灯璃は楽しそうにくっと喉を鳴らせた。
「いや、いいんだ。千冬は今のままでいてくれたら」
「は、はい……」
結局、何もわからぬまま頷いてしまった。
今までは自分の意思すらまともに言えず、器量や要領も妹と比べて悪い性格など嫌いだった。
しかし誰かに「そのままでいてほしい」と言われたのは初めてで無理に変えようとしなくても良いのだと教えてもらったような気がする。
「私も中心部の町へ来たのは久しぶりだ。千冬が良ければ以前によく行っていた店に案内しよう」
「はい。お願いします」
灯璃が通っていた店というのを聞いて一段と興味がわく。
非番で屋敷にいるときは書物を読んでいることが多いが、他には何が好きなのか知らない。
会話はほとんど灯璃から切り出す。
あまり話をするのが得意ではない千冬はいつも受け身だ。
灯璃と出逢ってまだ一ヶ月も経っていないので距離感が難しい。
(今日一日で少しでも近づけたら良いのだけど)
こっそりと灯璃に視線を向ける。
店に行く順番を考えているのか顎に手を添えている姿は様になっている。
「では一つ目の店に行こうか。こちらだ」
「は、はい」
見蕩れてしまっていたことに気がつき、千冬は慌てて少し先を歩き出した灯璃のあとを追ったのだった。
「着いたぞ。この店だ」
歩き始めて数分。
足を止めて掲げられている看板を見上げると『狐寺屋』の文字。
店の外に設置されている椅子には女学生とみられる二人組が手に持っている団子を美味しそうに食べている。
(お団子を食べているということは、ここは甘味処かしら?)
辺りは香ばしく甘い香りやお茶の香りが漂い、鼻を抜ける。
店の中へ入ると食器を片付けていた老婦がこちらへ気がつく。
「まあまあ!坊ちゃま、お久しぶりでございます」
柔和な笑顔で目尻を細めて嬉しそうにしている。
「久しぶりだな。それと八重子さん、私はもう坊ちゃまと言われるような年齢ではない」
「ふふっ。申し訳ありません。つい嬉しくて」
八重子と呼ばれた女性は灯璃の隣にいる千冬に視線を向ける。
しっかりと目が合ってしまい、奥底から恐怖心が出てきてしまう。
何かまた言われるかもしれないと肩を僅かに震わせる。
しかしその瞬間を灯璃は見逃さずに千冬に「大丈夫だ」と言うように背中に手を添えてくれた。
(堂々としなくちゃ……)
千冬は気持ちを鼓舞して老婦を見据えた。
「そちらのご令嬢はもしかして……」
「ああ、私の花嫁だ」
「左様でございますか!坊ちゃまがついに……!」
「だから坊ちゃまと呼ぶのは……」
「あなた!坊ちゃまが花嫁さまと一緒にお見えになりましたよ!」
灯璃が自分の呼び名を訂正しようとしたが厨房にいる誰かに声をかける八重子の耳
には届かないようだった。
「相変わらずだな、八重子さんは……」
ぽつりと呟き、ひとつため息をはいていたが、困ったように笑う灯璃の表情は初めて見る。
(町の親しい方とはこんな表情もするのね)
新たな一面を知れたような気がして嬉しくなっていると厨房から一人の老夫が出てきた。
「これはこれは坊ちゃん!よくおいでくださいました」
親しみやすそうな、にこやかな笑みを浮かべる姿は八重子とそっくりだ。
「真太郎さんも元気そうでなりよりだよ」
「お陰さまで夫婦共々、大きな病気をすることなくやっています」
八重子が厨房に「あなた」と呼んでいた時点で何となく察しはついていたが二人は夫婦のようだ。
「そうか。私は今日、かくりよ國の町を千冬に案内しているんだ。まずは狐寺屋のあんみつを食べてもらいたいと思って」
「まあ、それは嬉しゅうございます!今、お茶をお持ちしますね。奥の席へどうぞ」
真太郎は厨房へ戻り、八重子は二人を奥の席に案内するとお茶が入った湯呑みを運んできてくれた。
「坊ちゃんもあんみつでよろしいですか?」
「ああ。頼む」
「少々お待ちくださいませ」
軽く頭を下げるとお盆を抱えて厨房へ戻っていった。
目の前に置かれた湯呑みを持ち、温かいお茶を一口飲む。
ちらりと店内を見渡せば老舗を感じさせながらも置かれている椅子や洋卓も手入れが行き届いていて綺麗に整えられており落ち着く雰囲気だった。
「鬼城さまとお店のご夫婦はとても仲がよろしいのですね」
「この店は私が幼い頃から家族とよく来ていたんだ。だから二人は未だに私を坊ちゃんと呼ぶ。人前ではやめてほしいのだが……」
流石に花嫁の前で坊ちゃんという呼び名は恥ずかしいのか灯璃はやめてほしいそうだ。
しかし千冬から見ると、灯璃と老夫婦二人からは特別な絆のようなもので繋がっているような気がして少し羨ましくもあった。
「そう、でしょうか?ご夫婦は鬼城さまのことをとても可愛がられていらっしゃるのですね」
「二人から見れば私はまだ子供なのだろう」
灯璃は二十七歳という大の大人だが幼い頃から彼を見ている夫婦にとっては、もしかしたらいつまでも可愛い子供なのかもしれない。
「お待たせしました。あんみつ二つです」
他愛のない話をしていると八重子がお盆にあんみつをのせて運んできた。
目の前に置かれた器の中には、あんこと寒天の他に色付きの求肥や果物などが乗っていて想像していたより色鮮やかなものだっだ。
「わぁ……!」
あんみつを見て瞳を輝かせている千冬に八重子はくすりと笑った。
「坊ちゃんも初めてあんみつを見たときは花嫁さまと同じような反応でしたよ。それはもう瞳を輝かせて可愛らしい笑顔で……」
「お、おい。その話はやめろ」
すぐに止めに入った灯璃を見ると彼の頬は若干赤く染まっていた。
どうやら今の彼と昔の彼は少し違っているようで思い出話をされるのは苦手らしい。
(幼い頃の鬼城さま、気になるかも……。やはり年相応で無邪気だったのかしら)
冷静で物静かな今の灯璃には想像しづらいが彼にもそんな時期があったのだろう。
そう思いながら二人のやり取りを眺めていると。
「千冬、もしかして私の幼少期の想像をしてはいないか?」
「へっ……!?」
図星をつかれ思わず変な声が出てしまった。
深く考えていたわけではない。
少しだけ、ぼんやりと幼少期の灯璃を想像してしまった。
きっと勝手に想像されるのは、あまり良い気分ではなかったのだと反省する。
「あ、の……。申し訳ありません……」
誤魔化すことはせずに素直に謝罪をした。
「謝ることはない。千冬の頭の中では今、私のことを考えているのだろう?花嫁にそれだけ思われているのは嬉しい」
「……っ」
灯璃は切れ長の瞳を細め、まるでこの上ない幸せを感じているかのような笑みを浮かべている。
あやかしは花嫁を存分に愛すとは噂程度に聞いたことがあった。
しかし、ただ相手のことを考えているだけで喜ぶのだとは予想外だった。
その熱を含んだ瞳がこちらを射抜き、鼓動が跳ねるのがわかった。
灯璃は照れている千冬の表情をこっそり堪能したあと匙を持つ。
「さあ、あんみつを食べよう。美味いぞ」
「は、はい」
頬の熱を冷ますように、ぱたぱたと手で仰ぐと千冬も匙を持った。
「いただきます」
二人で同時に手を合わせて挨拶をすると、あんこと寒天を匙にのせて口に運ぶ。
上品な甘さが口いっぱいに広がり、食べたことのない味に感動で思わず、あんみつを見つめる。
「美味しい……!」
そう呟くと、次は器からあんこと果物をすくって一口食べる。
先ほどとは違う、果物の酸味も加わった美味しさになる。
(料理人の方たちが作られる甘味も美味しいけれど、このあんみつも負けないくらい美味しいわ)
次は求肥と一緒に……と匙ですくおうとしたとき目の前から視線を感じた。
ふと顔を上げると灯璃が優しい笑みでこちらを見ていた。
「あ……」
美味しさのあまり、自分がつい次から次へと夢中になって食べていたことに気がつき、我に返る。
急激に恥ずかしくなり先ほどとは違う意味で頬に熱をもつ。
(わ、わたしったら何をしているの!)
格式高い屋敷の主人、そして男性と食事をしているのに、自分が思うまま食べてしまっていた。
花嫁になるのだからしっかりしたいのにこれでは完全に甘味に夢中な子供だ。
「す、すみません……」
語尾になるにつれて小さく消えそうな声。
感情を抑えてもっと上品に食べればよかったと今になって反省をする。
良妻賢母を目指す決意をしたのに早速この有様だ。
羞恥心やら自己嫌悪やらで俯き、口をつぐんでいると。
「食欲があってよかった。千冬は食が細いから心配していたんだ」
「え……?」
灯璃はまったく怪訝そうな顔などしておらず、むしろ安堵したような表情をしていた。
(もしかして鬼城さまはずっとわたしのことを心配してくださっていたの?)
鬼城家での食事はいつも、少なめでお願いをしている。
決して料理が美味しくないとか、そんなわけではない。
嶺木家での食生活の影響だろう。
ただ一回出される量でやっと食べきれられるのだ。
残したら申し訳ないと思い、初めての夕食のあと、こっそりお世話係である詩乃にお願いをしていた。
灯璃はそんな千冬の状態をすでに見抜いており、心配してくれていたのだ。
以前に一度、「千冬に出す食事の量が少なくないか」とお膳立てをしている使用人に怪訝そうな顔を見せていたが、すぐに千冬がわたしがお願いしたのだと伝えて納得してくれた。
少量の食事が続いていたため、灯璃の心配も拭われなかったのだろう。
あんみつをどんどん食べ進める千冬を笑顔で見つめていた。
「遠慮することはない。それでいい」
「でも、もっとゆっくり丁寧に食べないと……」
「今は二人の時間だ。それに千冬の食事の作法も十分、綺麗だ」
昔、実母が亡くなる前に作法を教えてもらったような気がするがほとんど記憶に残っていない。
使用人として扱われていたときも当然のごとく勉強することはできず、父と継母、女学校に通っている依鈴だけが完璧に身につけていた。
灯璃が優しいのは嬉しいが、ただ甘やかされているだけでは成長できないと思う。
「わたし、屋敷に帰ったらお勉強をもっと頑張ります」
現状で満足してはいけないと、灯璃の隣に立って相応しい女性になりたいと決意に満ちる目が彼を射抜く。
そんな千冬を見て灯璃は少し目を見開いて驚いたような表情を浮かべたあと頷いた。
「わかった。マナーに関する書物も用意しよう。必要となれば講師も呼ぶからいつでも言いなさい」
「ありがとうございます……!」
千冬に笑顔が戻り再び二人は、あんみつを食べ始めた。
店内には穏やかな時間が流れており、八重子と真太郎夫婦が微笑ましそうに見ていた。
自分が外の世界で食事をすることができる日がきたこと、勉学に励めることに感謝をしながら、千冬はあんみつが載った匙を口元に運ぶのだった。