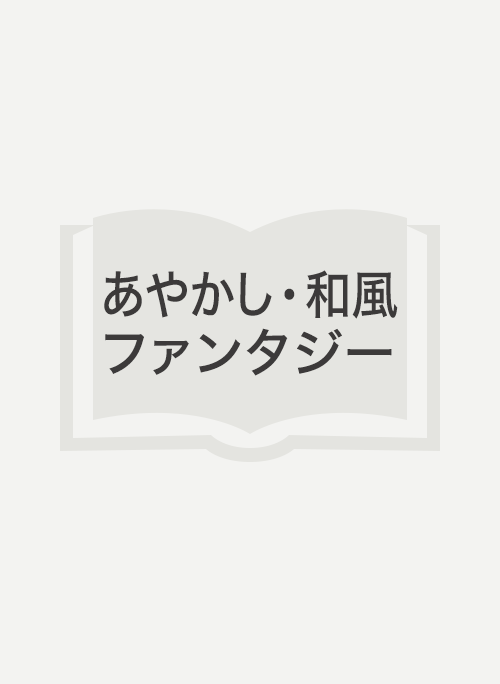一足早く身支度を済ませた灯璃は玄関で千冬を待っていた。
(千冬はまだ外の世界に慣れていない。無理をさせないよう、気をつけなければ)
今までほとんど外出したことがない千冬は緊張しているのか、今朝の朝食もあまり箸が進んでいなかった。
元々、食が細い方だとは思っていたが普段なら残さずに食べていたものを今日は「申し訳ありません」と謝って食べなかった。
食欲がないのなら無理する必要はないし、それで怒らない。
「具合が悪いのか」と尋ねると違うとすぐに否定して首を横に振った。
「町へ出掛けるのは久しぶりなので少し緊張してしまって……」
そう困ったように笑う表情はどこか寂しい儚さがある。
千冬は嶺木の人間に虐げられていたことを話さない。
外出を禁じられていたとは言わず、身体が弱かったからと誤魔化していた。
蓮司からの調査報告で千冬が実家でどのような扱いを受けていたか灯璃は知っている。
本人は灯璃がすべて内情を把握しているとは思ってもいないだろう。
当初、話してくれないことに少しの寂しさを覚えたが心配をかけたくない千冬の気持ちもわかる。
負担になりたくないと考えてくれているのだろう。
(私も嶺木家について調べていたことを彼女に話してつらい出来事を思い出させたくないからな)
誰しも話したくないことはあるから、むやみに聞いたりしないが、できるのであれば、もっと甘えてほしいと思う。
いつか本人の口から聞ける日が来るだろうか、そんな思いを抱いていると。
「鬼城さま、お待たせしました」
「いや、大丈夫……」
灯璃は振り返り、千冬を見た瞬間、息を呑んだ。
さらりとした髪に、耳上には花の飾りがついている。
元々、素肌でも綺麗だったがお粉ではたいたのか、さらに美しさが増している。
ぷるんとした小さな唇には口紅が塗られていて色香を感じる。
いつもとはまったく違う千冬の姿に灯璃は魅入っていた。
何も言わずにただジッとこちらを見ている灯璃を不思議に思い、首を傾げる。
「あの……?」
そこでようやく我に返り慌てて口を開いた。
「……すまない。千冬が綺麗で見蕩れていた」
「えっ……!?」
素直に思ったことを伝えると千冬の頬は徐々に赤く染まっていく。
視線を彷徨わせて、うろたえる姿は何とも可愛らしく気がつけば灯璃は腕を伸ばし、引き寄せていた。
「とても素敵だよ」
耳元で囁けば身体をびくりと跳ねさせる。
千冬は恥ずかしさのあまり目を合わせることができないのか視線を下げたまま、か細い声で言葉を紡ぐ。
「こ、これは詩乃さんがお化粧をしてくださったおかげで……」
「そうか。しかし、こんなにも美しくなられては町で他の男の視線を集めてしまう。このまま隠しておきたいくらいだ」
「えっ……!?わ、わたしなんか誰も見たりしませんよ」
ただこの瞳を除いて。
ここ数日で何となく気がついたことがある。
灯璃や使用人たちとの会話で紫紺色の瞳の言い伝えは、あやかしたちの間では帝都と比べてそこまで広まっていないということだ。
鬼帝である灯璃の花嫁になるにあたって、それが僅かな救いとなる。
自分だけならまだしも鬼城家や贔屓にしている呉服屋、狐森まで嫌な目で見られたり噂を流されるのは心苦しい。
何でも話してほしいと言われてはいるが、そこまでは伝えられていない。
俯いているおかげで灯璃にそこまで考えていることに気づかれてはいなかった。
「千冬は自分が思っている以上に魅力的な女性だ。卑下することはない」
「……っ」
顎に手を添えられ、上を向かせられる。
灯璃の顔が間近にあり、今にも唇が触れそうな距離に胸が高鳴った。
「本当はこの艶やかな唇に口づけをしたいくらいだ。しかし今すると口紅が落ちてしまう。それに……」
そこで言葉を切ると千冬を抱きしめる腕を解いた。
その瞬間、離れていく体温に千冬の心の中で寂しさに似た感情が生まれた。
(あれ……?わたし今……)
感じたことのない感情に違和感を覚えたがその名前がわかる前にすぐに頭上から言葉が降ってきた。
「それはもう少し先にする。千冬の心の準備ができるまで」
「鬼城さま……」
恋愛経験などない自分を気遣ってくれる優しさが嬉しい。
きっと灯璃の年齢ならば今すぐにでも結婚をして子供を作りたいはず。
(わたしも、きちんと考えないと)
使用人たちが、灯璃がここにいることを許してくれるのなら、これから先の将来についても考えないといけない。
「そろそろ出掛けようか」
「はい」
二人が一旦、距離をとり草履を履き始めたのを見計らってか詩乃をはじめとした使用人たちが見送りに来た。
「いってらっしゃいませ。灯璃さま、千冬さま」
「ああ。いってくる」
「いって参ります」
千冬は頭を下げると灯璃と共に外に止めてある自動車へ向かった。
(千冬はまだ外の世界に慣れていない。無理をさせないよう、気をつけなければ)
今までほとんど外出したことがない千冬は緊張しているのか、今朝の朝食もあまり箸が進んでいなかった。
元々、食が細い方だとは思っていたが普段なら残さずに食べていたものを今日は「申し訳ありません」と謝って食べなかった。
食欲がないのなら無理する必要はないし、それで怒らない。
「具合が悪いのか」と尋ねると違うとすぐに否定して首を横に振った。
「町へ出掛けるのは久しぶりなので少し緊張してしまって……」
そう困ったように笑う表情はどこか寂しい儚さがある。
千冬は嶺木の人間に虐げられていたことを話さない。
外出を禁じられていたとは言わず、身体が弱かったからと誤魔化していた。
蓮司からの調査報告で千冬が実家でどのような扱いを受けていたか灯璃は知っている。
本人は灯璃がすべて内情を把握しているとは思ってもいないだろう。
当初、話してくれないことに少しの寂しさを覚えたが心配をかけたくない千冬の気持ちもわかる。
負担になりたくないと考えてくれているのだろう。
(私も嶺木家について調べていたことを彼女に話してつらい出来事を思い出させたくないからな)
誰しも話したくないことはあるから、むやみに聞いたりしないが、できるのであれば、もっと甘えてほしいと思う。
いつか本人の口から聞ける日が来るだろうか、そんな思いを抱いていると。
「鬼城さま、お待たせしました」
「いや、大丈夫……」
灯璃は振り返り、千冬を見た瞬間、息を呑んだ。
さらりとした髪に、耳上には花の飾りがついている。
元々、素肌でも綺麗だったがお粉ではたいたのか、さらに美しさが増している。
ぷるんとした小さな唇には口紅が塗られていて色香を感じる。
いつもとはまったく違う千冬の姿に灯璃は魅入っていた。
何も言わずにただジッとこちらを見ている灯璃を不思議に思い、首を傾げる。
「あの……?」
そこでようやく我に返り慌てて口を開いた。
「……すまない。千冬が綺麗で見蕩れていた」
「えっ……!?」
素直に思ったことを伝えると千冬の頬は徐々に赤く染まっていく。
視線を彷徨わせて、うろたえる姿は何とも可愛らしく気がつけば灯璃は腕を伸ばし、引き寄せていた。
「とても素敵だよ」
耳元で囁けば身体をびくりと跳ねさせる。
千冬は恥ずかしさのあまり目を合わせることができないのか視線を下げたまま、か細い声で言葉を紡ぐ。
「こ、これは詩乃さんがお化粧をしてくださったおかげで……」
「そうか。しかし、こんなにも美しくなられては町で他の男の視線を集めてしまう。このまま隠しておきたいくらいだ」
「えっ……!?わ、わたしなんか誰も見たりしませんよ」
ただこの瞳を除いて。
ここ数日で何となく気がついたことがある。
灯璃や使用人たちとの会話で紫紺色の瞳の言い伝えは、あやかしたちの間では帝都と比べてそこまで広まっていないということだ。
鬼帝である灯璃の花嫁になるにあたって、それが僅かな救いとなる。
自分だけならまだしも鬼城家や贔屓にしている呉服屋、狐森まで嫌な目で見られたり噂を流されるのは心苦しい。
何でも話してほしいと言われてはいるが、そこまでは伝えられていない。
俯いているおかげで灯璃にそこまで考えていることに気づかれてはいなかった。
「千冬は自分が思っている以上に魅力的な女性だ。卑下することはない」
「……っ」
顎に手を添えられ、上を向かせられる。
灯璃の顔が間近にあり、今にも唇が触れそうな距離に胸が高鳴った。
「本当はこの艶やかな唇に口づけをしたいくらいだ。しかし今すると口紅が落ちてしまう。それに……」
そこで言葉を切ると千冬を抱きしめる腕を解いた。
その瞬間、離れていく体温に千冬の心の中で寂しさに似た感情が生まれた。
(あれ……?わたし今……)
感じたことのない感情に違和感を覚えたがその名前がわかる前にすぐに頭上から言葉が降ってきた。
「それはもう少し先にする。千冬の心の準備ができるまで」
「鬼城さま……」
恋愛経験などない自分を気遣ってくれる優しさが嬉しい。
きっと灯璃の年齢ならば今すぐにでも結婚をして子供を作りたいはず。
(わたしも、きちんと考えないと)
使用人たちが、灯璃がここにいることを許してくれるのなら、これから先の将来についても考えないといけない。
「そろそろ出掛けようか」
「はい」
二人が一旦、距離をとり草履を履き始めたのを見計らってか詩乃をはじめとした使用人たちが見送りに来た。
「いってらっしゃいませ。灯璃さま、千冬さま」
「ああ。いってくる」
「いって参ります」
千冬は頭を下げると灯璃と共に外に止めてある自動車へ向かった。