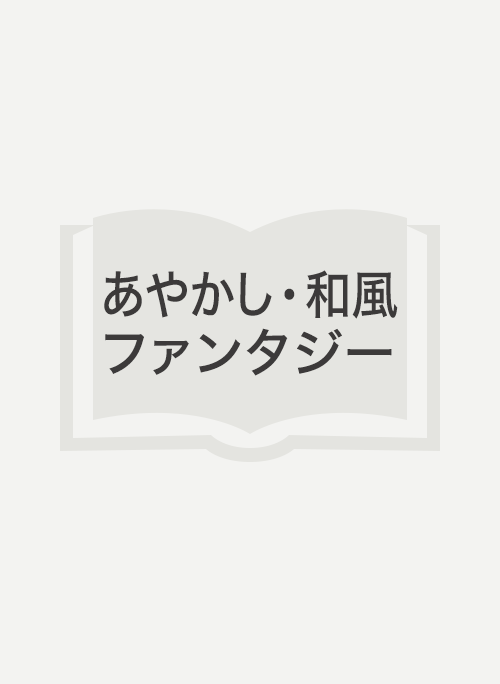千冬と灯璃が出逢って数日が経過し初めての週末。
今日は灯璃が所属する妖特務部隊の仕事は非番らしく先日から町へ出掛けようと約束をしていたのだ。
雲一つない青空が広がり、爽やかな風が吹くお出掛けに最適な日和だ。
朝食を済ませた千冬は一旦、自室へ戻り準備をする。
桜色の着物を着て、櫛で髪を梳く。
風呂場に置かれている手入れ道具のおかげで以前より髪が艶やかになったような気がする。
こうして使っている櫛なども灯璃や使用人達に用意してもらって感謝しかない。
箪笥の中から桜の花びらが刺繍された桃色の巾着を取り出す。
昨晩、仕事から帰った灯璃を出迎えた際に『受け取ってほしい』と言われて貰ったものだ。
何も持たずに嶺木家を出てきたので、外出用の巾着なども当然持っていない。
最初は申し訳なかったが、助かるのが本音でもある。
素直に受け取ると、灯璃は柔らかく目を細めて微笑んでいた。
こうして誰かの喜ぶ顔を見られるのは嬉しくて、もっと見てみたいとも思う。
この数日間で灯璃はほぼ毎日、贈り物をしてくれている。
巾着のような物の他にも和菓子や流行りの洋菓子などの食べ物も買ってきてくれているのだ。
お祝いごとでもないのに、美しい和紙に包まれた箱を手渡されると、かなり驚いてしまう。
妹の依鈴でも両親にこんなにも贈り物をしてもらっているのは見たことがない。
想いを無下にするのも気が引けて、ありがたくいただくのだが。
(今度わたしも何かお礼がしたいわ)
皆は否定するが、やはり急に鬼城家に暮らすことになって迷惑をかけてしまっているのではないかと思う。
(何がよろしいのかしら)
自分のお金を持っていない千冬は手作りの贈り物を考える。
(確か最近借りた雑誌に手芸の欄が掲載されていたような……)
しかし鬼城家にある調度品や食器、小物など全てが一流。
手作りの物を渡して誰かに笑われたりしないか不安だ。
(でも、そんなことを考えていたらいつまで経ってもお礼ができないわ)
町へ行ったら何か参考になるものが見られるかもしれない。
手が止まってしまったことに気がついて慌てて準備を再開する。
巾着に最低限の物だけ入れて鏡台を見ながら身だしなみを整えていると襖の外から声がかかった。
「千冬さま、入ってもよろしいですか?」
「はい、どうぞ」
襖が開けられると、そこにいたのは詩乃で何やら手には小箱を持っていた。
千冬の隣に座ると、その小箱を鏡台の上に置いた。
「せっかくの灯璃さまとのお出掛けですから、もしよろしければお化粧をしてみてはいかがですか?」
「お化粧……わたし、したことがないです」
もちろん継母や年頃の依鈴は毎日していたし、買い物に行けば新しいお化粧の道具を買っていた。
口紅やお粉など外に出ることのない自分には一生、縁がないものだと思っていた。
「そのままの千冬さまも十分、素敵ですがさらにお綺麗になって灯璃さまを驚かせてみませんか?」
詩乃は小箱から化粧道具を取り出し千冬に見せる。
(似合うかわからないけれど、町で鬼城さまのお隣を歩くのにお化粧はしておかないと……)
仮に紫紺色の瞳ではなかったとしても、素朴な容姿の自分が灯璃の隣で歩くと考えるだけで周囲の視線はあらかた想像できる。
相応しいのはきっと依鈴のような華やかさがある女性だ。
優しい灯璃はきっと気にする必要はないと言ってくれると思うが俯いて歩く自信しかない。
でも今日は約束していた町へ行く日。
不安もありながらも、どんなお店があるのか気になっている自分もいる。
やはり書物や雑誌を読むだけでは町を知ることはできないし憧れを抑えられない。
(お化粧をすれば少しは前を向けるかしら)
詩乃が手に持っている化粧道具はとても魅力的に見えた。
それを使ってどのように変わるのか興味もある。
千冬は俯いていた顔を上げると詩乃に頭を下げた。
「では、よろしくお願いします」
「はい。お任せください」
詩乃は嬉しそうに微笑みながら頷くと化粧をするため隣へ座る。
小箱を開けて準備を始めると化粧品特有の香りが鼻腔をくすぐる。
千冬は若干、胸を高まらせながら鏡に映る自分を見つめた。
今日は灯璃が所属する妖特務部隊の仕事は非番らしく先日から町へ出掛けようと約束をしていたのだ。
雲一つない青空が広がり、爽やかな風が吹くお出掛けに最適な日和だ。
朝食を済ませた千冬は一旦、自室へ戻り準備をする。
桜色の着物を着て、櫛で髪を梳く。
風呂場に置かれている手入れ道具のおかげで以前より髪が艶やかになったような気がする。
こうして使っている櫛なども灯璃や使用人達に用意してもらって感謝しかない。
箪笥の中から桜の花びらが刺繍された桃色の巾着を取り出す。
昨晩、仕事から帰った灯璃を出迎えた際に『受け取ってほしい』と言われて貰ったものだ。
何も持たずに嶺木家を出てきたので、外出用の巾着なども当然持っていない。
最初は申し訳なかったが、助かるのが本音でもある。
素直に受け取ると、灯璃は柔らかく目を細めて微笑んでいた。
こうして誰かの喜ぶ顔を見られるのは嬉しくて、もっと見てみたいとも思う。
この数日間で灯璃はほぼ毎日、贈り物をしてくれている。
巾着のような物の他にも和菓子や流行りの洋菓子などの食べ物も買ってきてくれているのだ。
お祝いごとでもないのに、美しい和紙に包まれた箱を手渡されると、かなり驚いてしまう。
妹の依鈴でも両親にこんなにも贈り物をしてもらっているのは見たことがない。
想いを無下にするのも気が引けて、ありがたくいただくのだが。
(今度わたしも何かお礼がしたいわ)
皆は否定するが、やはり急に鬼城家に暮らすことになって迷惑をかけてしまっているのではないかと思う。
(何がよろしいのかしら)
自分のお金を持っていない千冬は手作りの贈り物を考える。
(確か最近借りた雑誌に手芸の欄が掲載されていたような……)
しかし鬼城家にある調度品や食器、小物など全てが一流。
手作りの物を渡して誰かに笑われたりしないか不安だ。
(でも、そんなことを考えていたらいつまで経ってもお礼ができないわ)
町へ行ったら何か参考になるものが見られるかもしれない。
手が止まってしまったことに気がついて慌てて準備を再開する。
巾着に最低限の物だけ入れて鏡台を見ながら身だしなみを整えていると襖の外から声がかかった。
「千冬さま、入ってもよろしいですか?」
「はい、どうぞ」
襖が開けられると、そこにいたのは詩乃で何やら手には小箱を持っていた。
千冬の隣に座ると、その小箱を鏡台の上に置いた。
「せっかくの灯璃さまとのお出掛けですから、もしよろしければお化粧をしてみてはいかがですか?」
「お化粧……わたし、したことがないです」
もちろん継母や年頃の依鈴は毎日していたし、買い物に行けば新しいお化粧の道具を買っていた。
口紅やお粉など外に出ることのない自分には一生、縁がないものだと思っていた。
「そのままの千冬さまも十分、素敵ですがさらにお綺麗になって灯璃さまを驚かせてみませんか?」
詩乃は小箱から化粧道具を取り出し千冬に見せる。
(似合うかわからないけれど、町で鬼城さまのお隣を歩くのにお化粧はしておかないと……)
仮に紫紺色の瞳ではなかったとしても、素朴な容姿の自分が灯璃の隣で歩くと考えるだけで周囲の視線はあらかた想像できる。
相応しいのはきっと依鈴のような華やかさがある女性だ。
優しい灯璃はきっと気にする必要はないと言ってくれると思うが俯いて歩く自信しかない。
でも今日は約束していた町へ行く日。
不安もありながらも、どんなお店があるのか気になっている自分もいる。
やはり書物や雑誌を読むだけでは町を知ることはできないし憧れを抑えられない。
(お化粧をすれば少しは前を向けるかしら)
詩乃が手に持っている化粧道具はとても魅力的に見えた。
それを使ってどのように変わるのか興味もある。
千冬は俯いていた顔を上げると詩乃に頭を下げた。
「では、よろしくお願いします」
「はい。お任せください」
詩乃は嬉しそうに微笑みながら頷くと化粧をするため隣へ座る。
小箱を開けて準備を始めると化粧品特有の香りが鼻腔をくすぐる。
千冬は若干、胸を高まらせながら鏡に映る自分を見つめた。