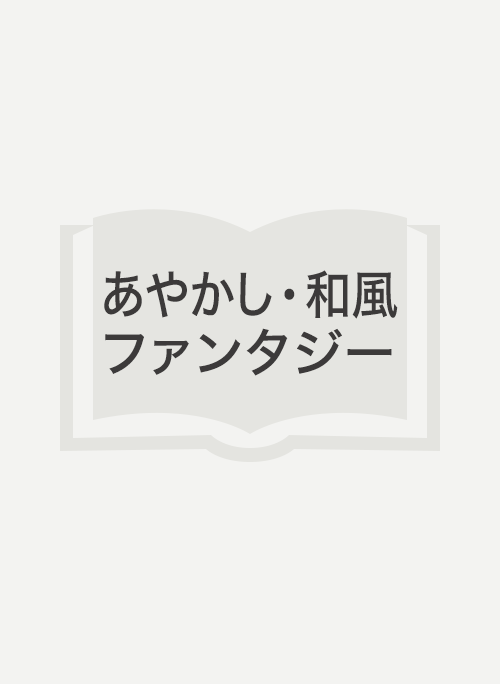時を同じくして、鬼川家の屋敷では嶺木家の調査報告をするため従者が薫子の元へ向かっていた。
今朝、情報収集を頼まれていたが夜には終わったようだ。
十分早いが灯璃の秘書である蓮司と比べるとまだまだだ。
「薫子さま、失礼致します」
「ええ」
中から短く返事をする。
一見、冷たいようにも聞こえるが鬼川家ではいつもこのような感じで従者からすれば慣れたものだ。
ノックをして入出してきた従者には目もくれず、ソファに座って腿の上に乗った飼い猫を撫でている。
猫は気持ちよさそうにしながら目を閉じてのんびりと寝ている。
「嶺木家についての調査報告に参りました」
その言葉に薫子が猫を撫でていた手をぴたりと止める。
従者は足早にそして静かに薫子の元へ近づくと手に持っている書類の束に目を通しながら報告を始めた。
「灯璃さまのお相手である花嫁は、嶺木千冬という十八の女性であることが判明しました」
「嶺木?」
その名字に心当たりがあるのか、さらに詳しく説明を求めるように薫子はそこでようやく従者へ視線を向けた。
「はい。薫子さまもお察しの通り、嶺木家は帝都ではの有名な由緒正しい家柄です。千冬という娘はその家の長女であるそうです。ただ……」
「ただ?」
何か引っかかった点があるのか従者はそこで一旦言葉を切ると書類を一枚めくった。
まるで口にするのが、ためらうほど何かに怯えるようにして口を開いた。
「その娘は紫紺色の瞳をもっていることから周囲には虐げられていたそうです。特に継母や妹は酷く彼女を恨んでいます。令嬢としてではなく使用人としてでの扱いを受けていたようで……」
薫子も嶺木家についての情報は頭に入っている。
鬼川家の娘としてもあやかしだけではなく人間たちについての知識も知っておくのは当然だ。
帝都でも名高い名家で社交界ではいつも名前が飛び交う。
鬼城家に次ぐ家柄である鬼川家に比べたら全く脅威にもならないと余裕しゃくしゃくでいたが、まさかその家の娘が花嫁に選ばれるのは想定外だった。
しかし従者の報告を聞くと、訳ありの花嫁のようだ。
(噂では聞いたことがあるけれどまさか本当に紫紺色の瞳の者が実在したなんて。灯璃さまはそれでもいいって言うの?)
これが普通の瞳をもつ令嬢ならば諦めもついたかもしれない。
家柄では劣るが、大事に育てられていればきっと多くの習い事をして振る舞いも特に問題はないのだろう。
しかし祟り神と同じ紫紺色の瞳は不の象徴。
それが原因で鬼城家、灯璃に何かあってからでは遅い。
鬼帝である彼が危機に見舞われると、かくりよ國や帝都においてとてつもない損失だ。
彼女に鬼の花嫁になるという覚悟があるのだろうか。
家や國が大切なのはもちろんだが、薫子が心配をしているのは灯璃自身。
今日から彼の婚約者だと両親から伝えられたその日から良妻賢母になるための花嫁修業をしてきたのだ。
鬼帝である彼は一瞬の隙さえ見せない。
しかし妻として力になれることも多々あるだろう。
そんな彼に相応しく隣で支えられるのが自分自身だけだと胸をはって言える。
(私の方が立派に妻として努めが果たせるのに虐げられてきた娘にそれができるはずないじゃない)
またふつふつと怒りが沸いてきて、腿の上に乗っていた猫も何かを感じ取ったのか絨毯に降りてどこかへ行ってしまった。
(今までの努力は灯璃さまのためなの。それが水の泡になるなんてそうはさせない)
何か手はないかと考えていると頭に思い浮かんだのは従者から聞いた継母と妹という言葉。
(その二人なら利用できるかもしれないわ)
同じような恨みを抱く彼女たちなら灯璃と花嫁を引き裂くことができるかもしれない。
自分でも恐ろしく感じるほどの案に思わずほくそ笑む。
開けた窓から入る風は鬼城家と同じはずなのにこちらは突き刺すような寒さ。
何かを企んでいる薫子の表情と相まって何かを感じた従者は「失礼致します」と頭を下げると足早に部屋を出て行った。
今朝、情報収集を頼まれていたが夜には終わったようだ。
十分早いが灯璃の秘書である蓮司と比べるとまだまだだ。
「薫子さま、失礼致します」
「ええ」
中から短く返事をする。
一見、冷たいようにも聞こえるが鬼川家ではいつもこのような感じで従者からすれば慣れたものだ。
ノックをして入出してきた従者には目もくれず、ソファに座って腿の上に乗った飼い猫を撫でている。
猫は気持ちよさそうにしながら目を閉じてのんびりと寝ている。
「嶺木家についての調査報告に参りました」
その言葉に薫子が猫を撫でていた手をぴたりと止める。
従者は足早にそして静かに薫子の元へ近づくと手に持っている書類の束に目を通しながら報告を始めた。
「灯璃さまのお相手である花嫁は、嶺木千冬という十八の女性であることが判明しました」
「嶺木?」
その名字に心当たりがあるのか、さらに詳しく説明を求めるように薫子はそこでようやく従者へ視線を向けた。
「はい。薫子さまもお察しの通り、嶺木家は帝都ではの有名な由緒正しい家柄です。千冬という娘はその家の長女であるそうです。ただ……」
「ただ?」
何か引っかかった点があるのか従者はそこで一旦言葉を切ると書類を一枚めくった。
まるで口にするのが、ためらうほど何かに怯えるようにして口を開いた。
「その娘は紫紺色の瞳をもっていることから周囲には虐げられていたそうです。特に継母や妹は酷く彼女を恨んでいます。令嬢としてではなく使用人としてでの扱いを受けていたようで……」
薫子も嶺木家についての情報は頭に入っている。
鬼川家の娘としてもあやかしだけではなく人間たちについての知識も知っておくのは当然だ。
帝都でも名高い名家で社交界ではいつも名前が飛び交う。
鬼城家に次ぐ家柄である鬼川家に比べたら全く脅威にもならないと余裕しゃくしゃくでいたが、まさかその家の娘が花嫁に選ばれるのは想定外だった。
しかし従者の報告を聞くと、訳ありの花嫁のようだ。
(噂では聞いたことがあるけれどまさか本当に紫紺色の瞳の者が実在したなんて。灯璃さまはそれでもいいって言うの?)
これが普通の瞳をもつ令嬢ならば諦めもついたかもしれない。
家柄では劣るが、大事に育てられていればきっと多くの習い事をして振る舞いも特に問題はないのだろう。
しかし祟り神と同じ紫紺色の瞳は不の象徴。
それが原因で鬼城家、灯璃に何かあってからでは遅い。
鬼帝である彼が危機に見舞われると、かくりよ國や帝都においてとてつもない損失だ。
彼女に鬼の花嫁になるという覚悟があるのだろうか。
家や國が大切なのはもちろんだが、薫子が心配をしているのは灯璃自身。
今日から彼の婚約者だと両親から伝えられたその日から良妻賢母になるための花嫁修業をしてきたのだ。
鬼帝である彼は一瞬の隙さえ見せない。
しかし妻として力になれることも多々あるだろう。
そんな彼に相応しく隣で支えられるのが自分自身だけだと胸をはって言える。
(私の方が立派に妻として努めが果たせるのに虐げられてきた娘にそれができるはずないじゃない)
またふつふつと怒りが沸いてきて、腿の上に乗っていた猫も何かを感じ取ったのか絨毯に降りてどこかへ行ってしまった。
(今までの努力は灯璃さまのためなの。それが水の泡になるなんてそうはさせない)
何か手はないかと考えていると頭に思い浮かんだのは従者から聞いた継母と妹という言葉。
(その二人なら利用できるかもしれないわ)
同じような恨みを抱く彼女たちなら灯璃と花嫁を引き裂くことができるかもしれない。
自分でも恐ろしく感じるほどの案に思わずほくそ笑む。
開けた窓から入る風は鬼城家と同じはずなのにこちらは突き刺すような寒さ。
何かを企んでいる薫子の表情と相まって何かを感じた従者は「失礼致します」と頭を下げると足早に部屋を出て行った。