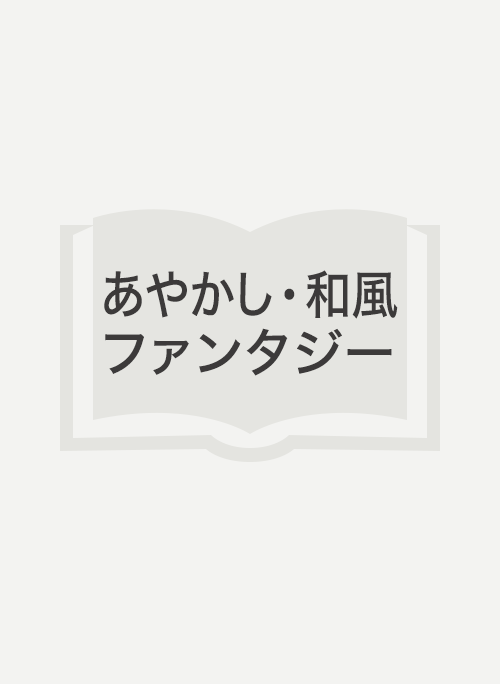日もすっかり暮れてから帰宅すると、出迎えにきたらしい千冬が使用人達と共に頭を下げた。
「おかえりなさいませ、鬼城さま」
「ただいま、千冬」
靴を脱ぐと鞄を使用人に預け、千冬を抱きしめる。
小さく細い身体はいとも簡単に腕の中へおさまる。
これでは、いつ他の男に襲われてもおかしくはない、しっかりと守らなければと千冬の肩に顔をうずめながらこっそり決意する。
「……!」
華奢な身体をビクリと震わせ、戸惑っている千冬がとても愛らしく感じる灯璃。
使用人達に助けを求めようとしたのか視線を向けるが二人の仲睦まじい様子に微笑み、邪魔にならないよう、そっとその場を離れた。
シンと辺りが静まり返る。
千冬が腕の中で少し身じろぐと顔をこちらへ向ける。
か弱い力でもぞもぞと動く姿はまるで小動物のようだ。
「あの、わたし泣いたり悲しんだりしておりませんよ?」
確かに美しい紫紺色の瞳に涙は浮かんでいないし顔色も朝より随分良い。
きっと、働かないでゆっくり過ごすという約束を守ったのだろう。
まだ完全に回復したとはいえなさそうだが昨夜と比べて良好に見える。
もし、帰宅しても顔色が悪ければ医者を呼ぼうとしたが、その必要はなさそうだ。
まあ、真面目な千冬が約束を反故するとは思っていないが。
なぜ自分が抱きしめられているのかわからないのか瞳をぱちくりとさせている。
(私が昨日から泣いている千冬を抱きしめているから何か誤解をしているのか)
灯璃は喉をくっと鳴らすと口を開いた。
「千冬が愛おしいと思ったから抱きしめているんだ。いつでも花嫁に触れたいと思うのは当然のことなんだよ」
低く甘い声が届き、鼓膜を揺らす。
さらりと髪が揺れて僅かな隙間から見える耳も赤い。
「えっと……」
数秒間、千冬は腕の中で身体を硬直して何か言わなくてはと口を何度もパクパクとさせる。
(抱きしめるだけでこんなにも恥ずかしがるなんて。まあ、慣れているようでも逆に困るが)
この状態だと、先まで進もうとすれば千冬は倒れてしまうのではないかと心配してしまう。
結婚をすれば自然とそういったこともして子を成す……。
灯璃は現在、二十七歳。
結婚をするには遅すぎるくらいで、子供がいても全くおかしくない。
周囲のあやかしは既婚者がほとんど。
半分以上が一族同士の政略結婚で残りが人間の花嫁との結婚。
両親には早く身を固めなさいと言われてきたが会う女性は皆、欲望の塊のように見えて、なかなか結婚へ気が進まなかった。
一応、婚約者の薫子という存在はいたが特に興味もなく、一族の繁栄のためだと理解はしていた。
定められた期限内に人間の花嫁に出逢うのは難しいだろうと思っていたが、美しい月が夜空に浮かぶ昨夜、千冬を見つけた。
千冬は今まで出逢ったどんな女性より魅力的で初々しい。
普通ならば、なるべく早く結婚をして子供を作るという流れが鬼城家に生まれた者としての努めだとも思う。
しかし千冬にそんな無理をさせてはいけないと考えがすぐに変わった。
(私達は私達らしく、少しずつ前に進んでいけば良い)
焦っても、ただ千冬を困らせるだけ。
灯璃は彼女をこの世で一番幸せな花嫁にしたいと固く胸に誓う。
千冬はきっとそこまで気がついていないと思うが、いつか話すときがくるだろう、そんなことを考えていると……。
「鬼城さま」
そう呟くと、するりと千冬の両手が伸びる。
そして、もう恥ずかしさの限界というように千冬は灯璃の胸元を手で押し返した。
「ゆ、夕食の準備が出来ているみたいです」
千冬の視線にちらりと見ると使用人達が夕食を居間へ運び終わったところだった。
彼女が一歩後ろへ下がり少しだけ距離ができた。
どんな恋仲でも、どちらかにこのように距離をとられたら嫌だろう。
しかし灯璃は悲しそうな表情は一切見せず、優美に微笑んだ。
「そうみたいだな。ではいこうか」
灯璃がゆっくりと歩き出したのを見て千冬は胸を撫で下ろす。
夕食の良い香りがふわりと漂う。
千冬は遅れないように彼のあとを追ったのだった。
居間に入ると座卓には料理人達が腕を振るって作られた食事が並んでいた。
炊きたての白米にわかめと油揚げの味噌汁と複数の小鉢、そして……。
「これは何でしょう……?」
中央には献立の主役であろう黄金色の揚げ物が皿に載っている。
見たことのない料理に首を傾げると灯璃が口を開く。
「それはポークカツレツだ」
「ぽーくかつれつ?」
初めて耳にする単語にさらに疑問が深まる。
千冬が聞き返すと灯璃は頷いた。
「ポークカツレツは西洋の料理だ。和食以外の料理も時々、座卓に並ぶ。千冬は初めてか?」
「はい。西洋のお料理は初めて食べます」
「そうか。では早速食べるか」
二人は手を合わせ、「いただきます」と言うと箸でポークカツレツの一切れを持ち上げる。
黄金色の衣にまとわれた肉からじゅわりと油が溢れる。
一口食べると噛む度に旨味が広がる。
「美味しい……!」
素直な感想がこぼれ、気づけば頬が緩んでいた。
「それは良かった。料理人達に伝えたらきっと喜ぶぞ」
「食後に伝えてみます」
誰かと他愛ない話をしながら食事をする幸せをゆっくりと噛みしめながら千冬は箸を進めた。
食後、厨房へ向かい、空になった皿を片付けていた料理人達に感想を伝えると、それはもう飛び跳ねそうなほど喜んでいた。
中には瞳を潤ませ、今にも泣きそうになっている人もいて、千冬は少しだけ驚いたができるときはこうして伝えようと思った。
居間に戻ると灯璃はすぐ近くの縁側に座っていた。
詩乃が用意してくれたのかお盆に載った湯呑みと急須がある。
「ここに座るといい」
灯璃は自分が座っている隣の縁側を手でポンポンと示す。
「はい」
千冬はそっと腰かけると急須を手に取った。
「鬼城さま、お茶をどうぞ」
「ありがとう」
灯璃の湯呑みに注いだあと自分のものにも注ぐ。
千冬は湯呑みを持ちながら夜空を見上げる。
かくりよ國も人間が暮らす帝都のように高い建物はあるが、鬼城家がある場所はひらけていて空が大きく感じた。
そのため昼には青空が、夜には星もしっかり見える。
嶺木家にいた頃は空の大きさなんて考える余裕はなかったけれど、今は夜空に浮かぶ星を見て綺麗だと思えた。
それも全て灯璃が救ってくれたから。
鬼帝であることから周囲に恐れられていると噂で聞いたこともあったが実際にはまったく違う。
同じく夜空を見上げている彼は凜々しくもありながらも誰もが目に引く赤い瞳を優しげに細めていた。
帝都には多くの人がいる分、それだけ事実の話がどこかで変わってしまい、変な噂も錯綜してしまうのだろう。
(とてもお優しい方なのに)
そう思った瞬間、星を見ていたはずの瞳が急にこちらへ向けられた。
「……どうした?」
ついジッと見入ってしまっていて、その視線に気づいたのか灯璃は不思議そうな表情を浮かべた。
「あの、えっと……」
本音をそのまま話す勇気はなくて何と言おうか慌てて考えを巡らせる。
「き、鬼城さまのお仕事が気になって」
「仕事?」
灯璃はその答えは予想していなかったのか瞳を瞬かせた。
垣間見たその表情は初めて見るもので少しだけ幼く感じたのは心に秘めておく。
「はい。鬼城さまは確か、妖特務部隊の隊長であられるのですよね?どういったことをさられているのかと思ったのです」
この話も嶺木家の使用人たちが話していたのを耳にしたとは程度。
慌てて話題を探して切り出したのもあるが、花嫁になるという選択をしたのだから基本的な情報は知っておきたかった。
「確かに今では出動要請も減っていて人間たちは部隊のことをあまり知らないだろう。もちろん千冬が興味があるというならば教えるよ」
灯璃は湯呑みをお盆の上に戻すと妖特務部隊について丁寧に話してくれた。
「妖特務部隊はあやかしや花嫁が関わる事件や争いなどを未然に防いだり解決に導くための組織だ。それらに花嫁以外の人間も絡んでいれば人間たちで構成されている、帝都警備隊と協力をするという場合もある。昔は人間によるあやかしの花嫁を狙った身代金目的の誘拐事件も多発していたが現在、そういった犯罪は起こってはいない」
「誘拐……」
物騒で恐ろしい言葉に身体が震えるのがわかった。
あやかし達の財力はとてつもない。
それは凄まじく一生、尽きることのないほど。
そんなあやかしが誘拐などはしないだろう。
しかし人間たちは貧困層というものがある。
過去に捕まった者の中には嶺木家のような名家をはじめとしたお金持ちではない一般庶民以下の者が多いのだと教えてくれた。
犯罪だけではなく、種族同士の争いも起きた場合、身を挺してやめさせるらしい。
現在は起きていないとはいえ、過去に発生したのは事実。
日頃から妖術や護身術の訓練などを行っているらしい。
「最近は書類仕事も多いから、そろそろ訓練量も増やそうかと検討をしていた。出動要請がないのは良いことだが」
「わたしが言う資格などありませんが、あまり無理をなさらないほうがよろしいのでは……」
灯璃の仕事は妖特務部隊だけではない。
鬼帝としてあやかし全体の取り纏めを行わなくてはいけない。
夕食を済ませて使用人達が食器を片づける際、書類を持った使用人と何やら真面目な顔で話し込んでいた。
邪魔をしないように静かにしていたが時々、『分家との会合』や『新当主との挨拶』などといった単語が出てきて、あやかしの知識など皆無な千冬でも何となく一族について話し合っているのだと理解できた。
(今日だってお帰りが遅かったし、さらに忙しくなったらお身体が心配だわ)
もし、まともに睡眠がとれなかったら。
もし、食事を疎かにしてしまったら。
もし、自分のことで何か手間をかけさせてしまったら。
いくつもの不安が頭を過る。
実家ではそれが何一つできておらず、誰かを慮る資格などないのだが。
ただ、紫紺色の瞳に恐れず親切にしてくれた人が苦しくつらい思いをする姿を見たくない、それだけの一心だった。
灯璃は少し間をあけて心配そうに眉を下げている千冬の頭をそっと撫でた。
「ありがとう、心配してくれて。確かに今と比較すると大変にはなるが私は大丈夫だ」
そこで一旦区切ると、頭の上に置かれた手は頬へすべり落ちる。
灯璃の人さし指がつうっと千冬の白い肌を撫でて、その甘い感触はまるで背中に電流が走ったよう。
「千冬がいれば、いくらでも頑張れるから」
屈託のない笑みと凛とした声に嘘は見受けられない。
生まれてこなければと否定され続けてきた千冬にとって、その言葉が何よりも嬉しくて、心がじんわりと温かくなった。
灯璃に触れられると恥ずかしさのあまり飛び退いてしまいそうになるが不思議と今は平気だった。
「わたし、鬼城さまをお支えできるよう頑張ります。助けてくださった恩返しもできるように」
決意を言葉に込めて一つ一つ丁寧に紡ぐ。
瞳を逸らさずに伝えると灯璃は千冬をそっと引き寄せて唇を耳元へ寄せた。
急に近づいた距離に一瞬、息をするのを忘れてしまった。
すぐ近くに端正な顔があって少しでも動けば灯璃の唇が千冬の耳に触れてしまいそうだ。
動いてはいけないと必死に身体に力を込める。
表情が見えないので、そんな千冬に気づいているのかいないのかわからない。
「ありがとう、嬉しい。ただ無理はするなよ?」
「そ、それは鬼城さまも同じです」
「ふっ、そうだな。では約束だ」
そう言うと小指を差し出される。
「指切りしよう。お互い無理はしない。つらいときは必ず伝えること。いいな?」
「はい」
千冬も自身の小指を差し出して灯璃の指と絡める。
指切りげんまんを灯璃が提案するのは意外で驚いたが、したことのない千冬は胸が弾んだ。
触れている箇所から伝わる僅かな体温がとても心地良くてやや冷たい春の夜風が火照った頬を撫でたのだった。
「おかえりなさいませ、鬼城さま」
「ただいま、千冬」
靴を脱ぐと鞄を使用人に預け、千冬を抱きしめる。
小さく細い身体はいとも簡単に腕の中へおさまる。
これでは、いつ他の男に襲われてもおかしくはない、しっかりと守らなければと千冬の肩に顔をうずめながらこっそり決意する。
「……!」
華奢な身体をビクリと震わせ、戸惑っている千冬がとても愛らしく感じる灯璃。
使用人達に助けを求めようとしたのか視線を向けるが二人の仲睦まじい様子に微笑み、邪魔にならないよう、そっとその場を離れた。
シンと辺りが静まり返る。
千冬が腕の中で少し身じろぐと顔をこちらへ向ける。
か弱い力でもぞもぞと動く姿はまるで小動物のようだ。
「あの、わたし泣いたり悲しんだりしておりませんよ?」
確かに美しい紫紺色の瞳に涙は浮かんでいないし顔色も朝より随分良い。
きっと、働かないでゆっくり過ごすという約束を守ったのだろう。
まだ完全に回復したとはいえなさそうだが昨夜と比べて良好に見える。
もし、帰宅しても顔色が悪ければ医者を呼ぼうとしたが、その必要はなさそうだ。
まあ、真面目な千冬が約束を反故するとは思っていないが。
なぜ自分が抱きしめられているのかわからないのか瞳をぱちくりとさせている。
(私が昨日から泣いている千冬を抱きしめているから何か誤解をしているのか)
灯璃は喉をくっと鳴らすと口を開いた。
「千冬が愛おしいと思ったから抱きしめているんだ。いつでも花嫁に触れたいと思うのは当然のことなんだよ」
低く甘い声が届き、鼓膜を揺らす。
さらりと髪が揺れて僅かな隙間から見える耳も赤い。
「えっと……」
数秒間、千冬は腕の中で身体を硬直して何か言わなくてはと口を何度もパクパクとさせる。
(抱きしめるだけでこんなにも恥ずかしがるなんて。まあ、慣れているようでも逆に困るが)
この状態だと、先まで進もうとすれば千冬は倒れてしまうのではないかと心配してしまう。
結婚をすれば自然とそういったこともして子を成す……。
灯璃は現在、二十七歳。
結婚をするには遅すぎるくらいで、子供がいても全くおかしくない。
周囲のあやかしは既婚者がほとんど。
半分以上が一族同士の政略結婚で残りが人間の花嫁との結婚。
両親には早く身を固めなさいと言われてきたが会う女性は皆、欲望の塊のように見えて、なかなか結婚へ気が進まなかった。
一応、婚約者の薫子という存在はいたが特に興味もなく、一族の繁栄のためだと理解はしていた。
定められた期限内に人間の花嫁に出逢うのは難しいだろうと思っていたが、美しい月が夜空に浮かぶ昨夜、千冬を見つけた。
千冬は今まで出逢ったどんな女性より魅力的で初々しい。
普通ならば、なるべく早く結婚をして子供を作るという流れが鬼城家に生まれた者としての努めだとも思う。
しかし千冬にそんな無理をさせてはいけないと考えがすぐに変わった。
(私達は私達らしく、少しずつ前に進んでいけば良い)
焦っても、ただ千冬を困らせるだけ。
灯璃は彼女をこの世で一番幸せな花嫁にしたいと固く胸に誓う。
千冬はきっとそこまで気がついていないと思うが、いつか話すときがくるだろう、そんなことを考えていると……。
「鬼城さま」
そう呟くと、するりと千冬の両手が伸びる。
そして、もう恥ずかしさの限界というように千冬は灯璃の胸元を手で押し返した。
「ゆ、夕食の準備が出来ているみたいです」
千冬の視線にちらりと見ると使用人達が夕食を居間へ運び終わったところだった。
彼女が一歩後ろへ下がり少しだけ距離ができた。
どんな恋仲でも、どちらかにこのように距離をとられたら嫌だろう。
しかし灯璃は悲しそうな表情は一切見せず、優美に微笑んだ。
「そうみたいだな。ではいこうか」
灯璃がゆっくりと歩き出したのを見て千冬は胸を撫で下ろす。
夕食の良い香りがふわりと漂う。
千冬は遅れないように彼のあとを追ったのだった。
居間に入ると座卓には料理人達が腕を振るって作られた食事が並んでいた。
炊きたての白米にわかめと油揚げの味噌汁と複数の小鉢、そして……。
「これは何でしょう……?」
中央には献立の主役であろう黄金色の揚げ物が皿に載っている。
見たことのない料理に首を傾げると灯璃が口を開く。
「それはポークカツレツだ」
「ぽーくかつれつ?」
初めて耳にする単語にさらに疑問が深まる。
千冬が聞き返すと灯璃は頷いた。
「ポークカツレツは西洋の料理だ。和食以外の料理も時々、座卓に並ぶ。千冬は初めてか?」
「はい。西洋のお料理は初めて食べます」
「そうか。では早速食べるか」
二人は手を合わせ、「いただきます」と言うと箸でポークカツレツの一切れを持ち上げる。
黄金色の衣にまとわれた肉からじゅわりと油が溢れる。
一口食べると噛む度に旨味が広がる。
「美味しい……!」
素直な感想がこぼれ、気づけば頬が緩んでいた。
「それは良かった。料理人達に伝えたらきっと喜ぶぞ」
「食後に伝えてみます」
誰かと他愛ない話をしながら食事をする幸せをゆっくりと噛みしめながら千冬は箸を進めた。
食後、厨房へ向かい、空になった皿を片付けていた料理人達に感想を伝えると、それはもう飛び跳ねそうなほど喜んでいた。
中には瞳を潤ませ、今にも泣きそうになっている人もいて、千冬は少しだけ驚いたができるときはこうして伝えようと思った。
居間に戻ると灯璃はすぐ近くの縁側に座っていた。
詩乃が用意してくれたのかお盆に載った湯呑みと急須がある。
「ここに座るといい」
灯璃は自分が座っている隣の縁側を手でポンポンと示す。
「はい」
千冬はそっと腰かけると急須を手に取った。
「鬼城さま、お茶をどうぞ」
「ありがとう」
灯璃の湯呑みに注いだあと自分のものにも注ぐ。
千冬は湯呑みを持ちながら夜空を見上げる。
かくりよ國も人間が暮らす帝都のように高い建物はあるが、鬼城家がある場所はひらけていて空が大きく感じた。
そのため昼には青空が、夜には星もしっかり見える。
嶺木家にいた頃は空の大きさなんて考える余裕はなかったけれど、今は夜空に浮かぶ星を見て綺麗だと思えた。
それも全て灯璃が救ってくれたから。
鬼帝であることから周囲に恐れられていると噂で聞いたこともあったが実際にはまったく違う。
同じく夜空を見上げている彼は凜々しくもありながらも誰もが目に引く赤い瞳を優しげに細めていた。
帝都には多くの人がいる分、それだけ事実の話がどこかで変わってしまい、変な噂も錯綜してしまうのだろう。
(とてもお優しい方なのに)
そう思った瞬間、星を見ていたはずの瞳が急にこちらへ向けられた。
「……どうした?」
ついジッと見入ってしまっていて、その視線に気づいたのか灯璃は不思議そうな表情を浮かべた。
「あの、えっと……」
本音をそのまま話す勇気はなくて何と言おうか慌てて考えを巡らせる。
「き、鬼城さまのお仕事が気になって」
「仕事?」
灯璃はその答えは予想していなかったのか瞳を瞬かせた。
垣間見たその表情は初めて見るもので少しだけ幼く感じたのは心に秘めておく。
「はい。鬼城さまは確か、妖特務部隊の隊長であられるのですよね?どういったことをさられているのかと思ったのです」
この話も嶺木家の使用人たちが話していたのを耳にしたとは程度。
慌てて話題を探して切り出したのもあるが、花嫁になるという選択をしたのだから基本的な情報は知っておきたかった。
「確かに今では出動要請も減っていて人間たちは部隊のことをあまり知らないだろう。もちろん千冬が興味があるというならば教えるよ」
灯璃は湯呑みをお盆の上に戻すと妖特務部隊について丁寧に話してくれた。
「妖特務部隊はあやかしや花嫁が関わる事件や争いなどを未然に防いだり解決に導くための組織だ。それらに花嫁以外の人間も絡んでいれば人間たちで構成されている、帝都警備隊と協力をするという場合もある。昔は人間によるあやかしの花嫁を狙った身代金目的の誘拐事件も多発していたが現在、そういった犯罪は起こってはいない」
「誘拐……」
物騒で恐ろしい言葉に身体が震えるのがわかった。
あやかし達の財力はとてつもない。
それは凄まじく一生、尽きることのないほど。
そんなあやかしが誘拐などはしないだろう。
しかし人間たちは貧困層というものがある。
過去に捕まった者の中には嶺木家のような名家をはじめとしたお金持ちではない一般庶民以下の者が多いのだと教えてくれた。
犯罪だけではなく、種族同士の争いも起きた場合、身を挺してやめさせるらしい。
現在は起きていないとはいえ、過去に発生したのは事実。
日頃から妖術や護身術の訓練などを行っているらしい。
「最近は書類仕事も多いから、そろそろ訓練量も増やそうかと検討をしていた。出動要請がないのは良いことだが」
「わたしが言う資格などありませんが、あまり無理をなさらないほうがよろしいのでは……」
灯璃の仕事は妖特務部隊だけではない。
鬼帝としてあやかし全体の取り纏めを行わなくてはいけない。
夕食を済ませて使用人達が食器を片づける際、書類を持った使用人と何やら真面目な顔で話し込んでいた。
邪魔をしないように静かにしていたが時々、『分家との会合』や『新当主との挨拶』などといった単語が出てきて、あやかしの知識など皆無な千冬でも何となく一族について話し合っているのだと理解できた。
(今日だってお帰りが遅かったし、さらに忙しくなったらお身体が心配だわ)
もし、まともに睡眠がとれなかったら。
もし、食事を疎かにしてしまったら。
もし、自分のことで何か手間をかけさせてしまったら。
いくつもの不安が頭を過る。
実家ではそれが何一つできておらず、誰かを慮る資格などないのだが。
ただ、紫紺色の瞳に恐れず親切にしてくれた人が苦しくつらい思いをする姿を見たくない、それだけの一心だった。
灯璃は少し間をあけて心配そうに眉を下げている千冬の頭をそっと撫でた。
「ありがとう、心配してくれて。確かに今と比較すると大変にはなるが私は大丈夫だ」
そこで一旦区切ると、頭の上に置かれた手は頬へすべり落ちる。
灯璃の人さし指がつうっと千冬の白い肌を撫でて、その甘い感触はまるで背中に電流が走ったよう。
「千冬がいれば、いくらでも頑張れるから」
屈託のない笑みと凛とした声に嘘は見受けられない。
生まれてこなければと否定され続けてきた千冬にとって、その言葉が何よりも嬉しくて、心がじんわりと温かくなった。
灯璃に触れられると恥ずかしさのあまり飛び退いてしまいそうになるが不思議と今は平気だった。
「わたし、鬼城さまをお支えできるよう頑張ります。助けてくださった恩返しもできるように」
決意を言葉に込めて一つ一つ丁寧に紡ぐ。
瞳を逸らさずに伝えると灯璃は千冬をそっと引き寄せて唇を耳元へ寄せた。
急に近づいた距離に一瞬、息をするのを忘れてしまった。
すぐ近くに端正な顔があって少しでも動けば灯璃の唇が千冬の耳に触れてしまいそうだ。
動いてはいけないと必死に身体に力を込める。
表情が見えないので、そんな千冬に気づいているのかいないのかわからない。
「ありがとう、嬉しい。ただ無理はするなよ?」
「そ、それは鬼城さまも同じです」
「ふっ、そうだな。では約束だ」
そう言うと小指を差し出される。
「指切りしよう。お互い無理はしない。つらいときは必ず伝えること。いいな?」
「はい」
千冬も自身の小指を差し出して灯璃の指と絡める。
指切りげんまんを灯璃が提案するのは意外で驚いたが、したことのない千冬は胸が弾んだ。
触れている箇所から伝わる僅かな体温がとても心地良くてやや冷たい春の夜風が火照った頬を撫でたのだった。