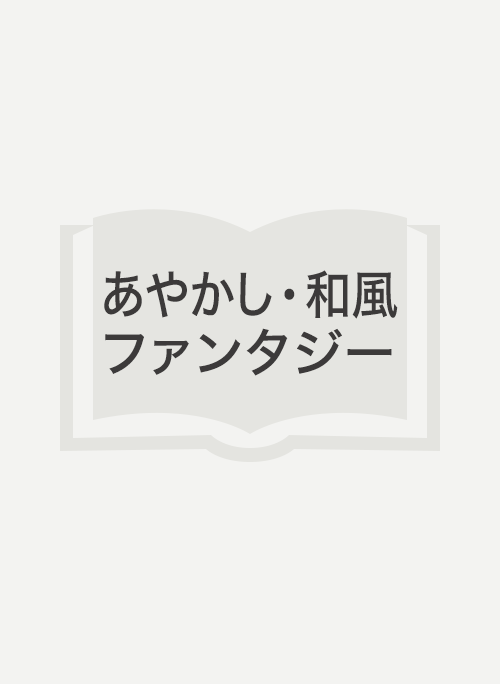橙色の陽射しが人や建物を照らし始めた夕刻。
仕事終わりの灯璃が乗った自動車が嶺木家の門前で止まった。
降りて門をくぐると玄関の前には当主の宗一と妻の依里恵、娘の依鈴が立って出迎えた。
三人は灯璃、もといあやかしに会うのははじめてで、その人間離れした美貌に見蕩れていた。
女性だけでなく男性も虜にさせる魅力が彼にはあり、他のあやかしとは違う点だ。
艶やかな黒髪に真紅の瞳、白く透き通るような肌に勝る者はいない。
パーティーなどの社交場で人との交流が多い継母達も灯璃の噂は耳にしていたが、彼は華やかな場に滅多に姿を見せないので会って話がしたいと連絡がきたときは驚きを隠せなかった。
しかし帝都に名を轟かせる嶺木家と鬼帝である灯璃が会うのは必然だとも思っていた。
特に依鈴は灯璃が我が家に来ると知って普段より一段とお洒落と化粧をしている。
もしかしたら花嫁に選ばれるかもしれないと思ったからだ。
妻になれば、今よりも強大な権力と財力が手に入り高い地位へ就ける。
あわよくば、かくりよ國も我が手に治めたいと欲望が渦めく。
今でも十分に良い待遇を受けているのに、どこまでも欲深い自分に笑みがこぼれてしまう。
そして灯璃が目の前に立ち、はっきりとその美しい姿を見て依鈴は頬を赤く染め、瞳をとろけさせている。
しかしそれとは反対に灯璃は三人を見て嫌悪感を増幅させた。
(当主とその妻に用があると連絡したはずだが、なぜ娘までいる)
千冬を虐げていた者が視界に入るだけで殺意に似た感情が湧き出る。
(用件を済ませたら、すぐに千冬の元へ帰ろう)
愛おしい花嫁のことを考えても邪魔をする鬱陶しいほどの視線。
彼女は自分に好意を抱いているのだと聞かなくてもわかる。
女性と会うといつもこうで嫌気が差す。
(お前を想うことは天地がひっくり返ってもないというのに馬鹿な娘だ)
あやかしが花嫁を裏切ることなど絶対ありえない。
そんな話は有名なのに、諦めが悪い女性たちを見るたびに時間を無駄にしていると思う。
「これは、これは鬼城さま。ようこそおいでくださいました。私、当主の……」
「自己紹介など不要だ。さっさと話がしたい」
「は、はい。どうぞ中へ」
予想外の冷たい声に三人は驚くが、すぐに切り替えて屋敷の中へ招き入れた。
客間に通され、ソファには灯璃と宗一、依里恵が座っている。
当然のごとく依鈴も客間に入ろうとしたが話があるのは両親だけだと、バッサリ断られてしまった。
「わざわざ鬼城さまにご足労いただいて申し訳ありません。して、ご用件は?」
媚びるような笑顔に反吐が出そうだった。
灯璃は躊躇することなく本題を切り出した。
「千冬がいなくなったというのに、お前達はどうしてそうも呑気でいられる」
嶺木家の人間以外、知らない事実をなぜ灯璃が知っているのか。
そしてすべてを見透かすような眼差しに二人は身体をビクリと震わせる。
「な、何のことでしょう。千冬は病で床に伏せておりますが……」
「では会わせろ。私は鬼である故、身体は丈夫だ。うつる心配はない」
「しかし……」
灯璃は二人の実際の本性を見抜くため、ハッタリをかましたのだ。
しかし額に汗をかきながら、いつまでも誤魔化そうとしている。
千冬はこんな両親のもとで一人頑張っていたのだと思うとさらに彼らへの憎悪感が増す。
客間に案内されている間に屋敷で働く使用人達の様子を見たが千冬を捜索しているような雰囲気はなかった。
「そんな嘘は通用しない。千冬は今、鬼城家の屋敷にいるのだから」
「え……!?」
二人は目を丸くし衝撃の事実に動揺を隠せないようだ。
使用人から千冬がいなくなったと報告を受けたときはすぐに帝都中を総出で探させた。
依鈴の婚約を駄目にした罰を受けさせるため、何としてでも千冬を探し出せと命令を下したのだ。
しかしそれは今日の午前中まで。
どれだけ探しても見つからない千冬は野垂れ死んだかほつき歩いていた男性に襲われたのだろうと、捜索を諦めたのだ。
使用人達が探し始めた頃には千冬はもう灯璃と出逢っていたことは知らない。
「千冬は私の花嫁になった。金輪際、彼女に手を出すな」
「花嫁……!?」
まさか虐げていた自分の娘があやかしの中で最高位に君臨する鬼城家の当主の花嫁に選ばれたことに、にわかに信じられないようだ。
「本人は嶺木家での生活について何も言わないが調べればすぐにわかる。お前達は私の花嫁に非道な言動をとっていたようだな」
「……っ。私たちは何もしておりません」
「自らの過ちに気づかないのか。醜いな。これ以上の会話は時間の無駄だ」
灯璃はソファから立ち上がり、二人を見下す。
「今後、千冬に手を出すならば容赦はしない。覚悟しておけ」
ギロリと睨まれた二人は、その殺気を含んだ瞳に身体が硬直し唾を呑み込んだ。
「お、お待ちください!」
客間から出て行こうとする灯璃を宗一は慌てて引き止める。
千冬がいる鬼城家の屋敷へ一秒でも早く帰りたいのに、それを阻もうとするなど苛つかせるだけだ。
「私達が今後一切千冬に関与しなければ鬼城家と嶺木家の繋がりはできますよね?」
灯璃は足を止め、ちらりと宗一へ視線を向ける。
「そんなわけないだろう。縁は切り、お前たちが千冬に謝罪をしなければ嶺木家は私が潰す」
「そ、そんな……」
宗一はその場に膝から崩れ落ち、灯璃はそのまま客間を退出しようと襖を開ける。
開けると客間への入出を断られて会話を聞こうと聞き耳を立てていた依鈴が道を塞いでいた。
「邪魔だ、どけ」
「……っ」
もしかしたら千冬が花嫁に選ばれたのは何かの間違いで本当は自分なのではと淡い期待を込めながら灯璃を見つめる。
(紫紺色の瞳をもつお姉さまが花嫁だなんて、ありえないわ)
冷酷な瞳に負けず、そこを退こうとしない依鈴。
「聞こえないのか?どけと言っているんだ」
さらに増した氷のように凍てつく声色と鋭い眼差しに耐えきれず、そっと横に避ける。
灯璃が足早に去っていくのをただ呆然と見送ることしかできない。
姿が見えなくなると依鈴は客間に入り、両親の元へ駆け寄る。
「お父さま、お母さま!今の話は本当なの?」
「……ああ」
いつもは堂々とした風格の父が顔を青ざめさせ力なくうなだれている。
母も普段は自信に満ち溢れているのに、現在は動揺しているのか、何も言葉を発さず、見るに堪えないほど弱々しい。
そんな両親の姿を見て事実なのだと思いしらされる。
「そんな……」
客間に静寂が訪れる。
いつも屋敷には楽しい笑い声が響き、気に食わない者には制裁を与える、何不自由のない生活を送ってきた。
しかし、まるでこの世の終わりのような空気が漂う。
(嶺木の家はこのまま潰されてしまうの?)
依鈴はこんなにも悔しさや不安で心が満ちるのは初めてだった。
仕事終わりの灯璃が乗った自動車が嶺木家の門前で止まった。
降りて門をくぐると玄関の前には当主の宗一と妻の依里恵、娘の依鈴が立って出迎えた。
三人は灯璃、もといあやかしに会うのははじめてで、その人間離れした美貌に見蕩れていた。
女性だけでなく男性も虜にさせる魅力が彼にはあり、他のあやかしとは違う点だ。
艶やかな黒髪に真紅の瞳、白く透き通るような肌に勝る者はいない。
パーティーなどの社交場で人との交流が多い継母達も灯璃の噂は耳にしていたが、彼は華やかな場に滅多に姿を見せないので会って話がしたいと連絡がきたときは驚きを隠せなかった。
しかし帝都に名を轟かせる嶺木家と鬼帝である灯璃が会うのは必然だとも思っていた。
特に依鈴は灯璃が我が家に来ると知って普段より一段とお洒落と化粧をしている。
もしかしたら花嫁に選ばれるかもしれないと思ったからだ。
妻になれば、今よりも強大な権力と財力が手に入り高い地位へ就ける。
あわよくば、かくりよ國も我が手に治めたいと欲望が渦めく。
今でも十分に良い待遇を受けているのに、どこまでも欲深い自分に笑みがこぼれてしまう。
そして灯璃が目の前に立ち、はっきりとその美しい姿を見て依鈴は頬を赤く染め、瞳をとろけさせている。
しかしそれとは反対に灯璃は三人を見て嫌悪感を増幅させた。
(当主とその妻に用があると連絡したはずだが、なぜ娘までいる)
千冬を虐げていた者が視界に入るだけで殺意に似た感情が湧き出る。
(用件を済ませたら、すぐに千冬の元へ帰ろう)
愛おしい花嫁のことを考えても邪魔をする鬱陶しいほどの視線。
彼女は自分に好意を抱いているのだと聞かなくてもわかる。
女性と会うといつもこうで嫌気が差す。
(お前を想うことは天地がひっくり返ってもないというのに馬鹿な娘だ)
あやかしが花嫁を裏切ることなど絶対ありえない。
そんな話は有名なのに、諦めが悪い女性たちを見るたびに時間を無駄にしていると思う。
「これは、これは鬼城さま。ようこそおいでくださいました。私、当主の……」
「自己紹介など不要だ。さっさと話がしたい」
「は、はい。どうぞ中へ」
予想外の冷たい声に三人は驚くが、すぐに切り替えて屋敷の中へ招き入れた。
客間に通され、ソファには灯璃と宗一、依里恵が座っている。
当然のごとく依鈴も客間に入ろうとしたが話があるのは両親だけだと、バッサリ断られてしまった。
「わざわざ鬼城さまにご足労いただいて申し訳ありません。して、ご用件は?」
媚びるような笑顔に反吐が出そうだった。
灯璃は躊躇することなく本題を切り出した。
「千冬がいなくなったというのに、お前達はどうしてそうも呑気でいられる」
嶺木家の人間以外、知らない事実をなぜ灯璃が知っているのか。
そしてすべてを見透かすような眼差しに二人は身体をビクリと震わせる。
「な、何のことでしょう。千冬は病で床に伏せておりますが……」
「では会わせろ。私は鬼である故、身体は丈夫だ。うつる心配はない」
「しかし……」
灯璃は二人の実際の本性を見抜くため、ハッタリをかましたのだ。
しかし額に汗をかきながら、いつまでも誤魔化そうとしている。
千冬はこんな両親のもとで一人頑張っていたのだと思うとさらに彼らへの憎悪感が増す。
客間に案内されている間に屋敷で働く使用人達の様子を見たが千冬を捜索しているような雰囲気はなかった。
「そんな嘘は通用しない。千冬は今、鬼城家の屋敷にいるのだから」
「え……!?」
二人は目を丸くし衝撃の事実に動揺を隠せないようだ。
使用人から千冬がいなくなったと報告を受けたときはすぐに帝都中を総出で探させた。
依鈴の婚約を駄目にした罰を受けさせるため、何としてでも千冬を探し出せと命令を下したのだ。
しかしそれは今日の午前中まで。
どれだけ探しても見つからない千冬は野垂れ死んだかほつき歩いていた男性に襲われたのだろうと、捜索を諦めたのだ。
使用人達が探し始めた頃には千冬はもう灯璃と出逢っていたことは知らない。
「千冬は私の花嫁になった。金輪際、彼女に手を出すな」
「花嫁……!?」
まさか虐げていた自分の娘があやかしの中で最高位に君臨する鬼城家の当主の花嫁に選ばれたことに、にわかに信じられないようだ。
「本人は嶺木家での生活について何も言わないが調べればすぐにわかる。お前達は私の花嫁に非道な言動をとっていたようだな」
「……っ。私たちは何もしておりません」
「自らの過ちに気づかないのか。醜いな。これ以上の会話は時間の無駄だ」
灯璃はソファから立ち上がり、二人を見下す。
「今後、千冬に手を出すならば容赦はしない。覚悟しておけ」
ギロリと睨まれた二人は、その殺気を含んだ瞳に身体が硬直し唾を呑み込んだ。
「お、お待ちください!」
客間から出て行こうとする灯璃を宗一は慌てて引き止める。
千冬がいる鬼城家の屋敷へ一秒でも早く帰りたいのに、それを阻もうとするなど苛つかせるだけだ。
「私達が今後一切千冬に関与しなければ鬼城家と嶺木家の繋がりはできますよね?」
灯璃は足を止め、ちらりと宗一へ視線を向ける。
「そんなわけないだろう。縁は切り、お前たちが千冬に謝罪をしなければ嶺木家は私が潰す」
「そ、そんな……」
宗一はその場に膝から崩れ落ち、灯璃はそのまま客間を退出しようと襖を開ける。
開けると客間への入出を断られて会話を聞こうと聞き耳を立てていた依鈴が道を塞いでいた。
「邪魔だ、どけ」
「……っ」
もしかしたら千冬が花嫁に選ばれたのは何かの間違いで本当は自分なのではと淡い期待を込めながら灯璃を見つめる。
(紫紺色の瞳をもつお姉さまが花嫁だなんて、ありえないわ)
冷酷な瞳に負けず、そこを退こうとしない依鈴。
「聞こえないのか?どけと言っているんだ」
さらに増した氷のように凍てつく声色と鋭い眼差しに耐えきれず、そっと横に避ける。
灯璃が足早に去っていくのをただ呆然と見送ることしかできない。
姿が見えなくなると依鈴は客間に入り、両親の元へ駆け寄る。
「お父さま、お母さま!今の話は本当なの?」
「……ああ」
いつもは堂々とした風格の父が顔を青ざめさせ力なくうなだれている。
母も普段は自信に満ち溢れているのに、現在は動揺しているのか、何も言葉を発さず、見るに堪えないほど弱々しい。
そんな両親の姿を見て事実なのだと思いしらされる。
「そんな……」
客間に静寂が訪れる。
いつも屋敷には楽しい笑い声が響き、気に食わない者には制裁を与える、何不自由のない生活を送ってきた。
しかし、まるでこの世の終わりのような空気が漂う。
(嶺木の家はこのまま潰されてしまうの?)
依鈴はこんなにも悔しさや不安で心が満ちるのは初めてだった。