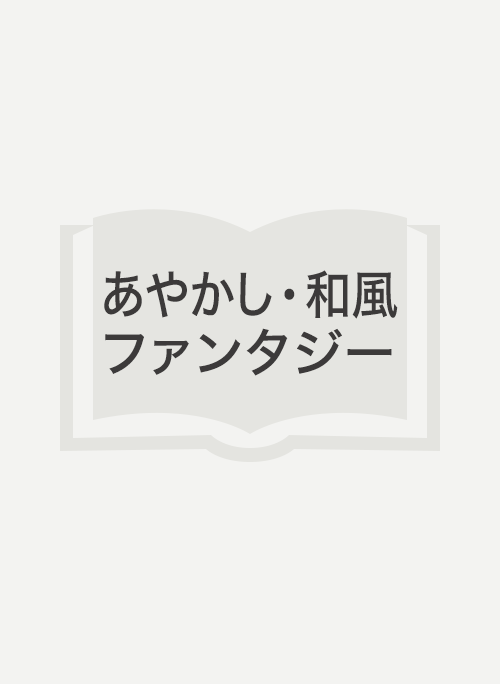弁当を作り終えて居間へ向かうと隊服姿の灯璃が座って待っていた。
襟元をくつろげていても様になっている。
入ってきた千冬に気がつくと呼んでいた新聞を閉じた。
「弁当作りは終わったのか?」
「はい。お出かけになる前にお渡しします」
千冬が座卓に座ったと同時に詩乃をはじめとした使用人達が朝食を運んできた。
いくつかのおかずの他に炊きたての白米とわかめと豆腐の味噌汁が置かれると少しだけ緊張した。
灯璃の口に合うだろうか、丁寧に出汁はとったけれど自己流だから……とお椀によそられているのを見るとさらに不安になる。
すべての料理が並べ終わると使用人達は「失礼致します」と言って居間から出て行った。
「いただきます」
灯璃が手を合わせるのを見て、考えこんでいた千冬も慌てて倣う。
「白米と味噌汁は千冬が作ったのだろう?」
「は、はい」
頷くと灯璃はお椀を持ち、味噌汁を一口飲む。
どうしても味が気になってしまい、じっと彼を見つめた。
そっと口元からお椀を離すと視線を千冬に向ける。
それはとても優しい微笑みだった。
自分には眩しすぎるくらいの光のようにも思える。
「美味い」
一番欲しかった感想が耳に届く。
その一言がどれだけ千冬にとって救いとなるか。
胸にじんわりと染みわたる。
「……!あ、ありがとうございます」
こうして褒められたのはいつぶりだろう。
継母たちにお茶を入れても何かしら文句をつけられ、「渋すぎる」「こんな不味いものを飲ませないで」と怒号を浴びるくらいだった。
何の変哲もない普通の料理一つを褒められただけでも浮かれてしまう。
緩みそうになる頬を引き締めながら千冬も箸を進める。
灯璃もそこまで口数が多くはないようで居間は静かだったが、不思議と心地が良かった。
茶碗とお椀が空になると、「おかわりをしたい」と傍に控えていた使用人に渡す。
それだけ気に入ってくれたのだとさらに嬉しくなった。
すると灯璃はそっと箸を置く。
「今日は私の帰りが遅くなる」
「かしこまりました。夕食は召し上がられますか?」
「ああ。用事を済ませたらすぐに帰るから千冬と共に食事をしたい」
「はい。もちろんです」
元々、この屋敷のあるじより先に食事をするつもりなど毛頭ないのだけれど。
「千冬はまだ身体が本調子ではないのだから一日、屋敷の中でゆっくり休むといい」
「し、しかしわたしも何かお手伝いを……」
屋敷が広い分、掃除をはじめとした家事も一苦労だろう。
何か一つくらい手伝えることがきっとあるはず。
それに、あるじが働いているのに自分だけがゆっくり休むなんて、とてもできない。
懇願するように、じっと灯璃を見つめると困ったように眉を下げた。
「千冬の願いは何でも叶えてあげたいが今日ばかりは駄目だ。また元気になったらその時は考える」
「そう、ですか……」
灯璃が駄目と言っているのだ。
これ以上お願いするのはやめようと口をつぐむ。
明らかにしょんぼりと肩を落とす千冬を見て灯璃はすぐさま次の話題を切り出した。
「千冬、今度の週末にかくりよ國の町へ出掛けないか」
「え……」
思わぬ提案に目を丸くする。
かくりよ國には人間たちが暮らす帝都と同様に書店や甘味処、デパートメントがある。
嶺木家の屋敷から出られなかった千冬は町から帰った継母達が楽しそうに話をしているのを耳にしたことがある。
お洒落をして色々な店を回る。
そんな夢と憧れが詰まった町へ行けるとなれば普通、嬉しくてすぐに頷きたいところだが千冬はその真逆で戸惑っていた。
(この瞳を見たら周りの人たちを怖がらせてしまうわ)
屋敷内でも不気味がられていたのに大勢の人が行き交う町中に出たら、どのような視線を向けられるのかわからない。
陰口を言われるのが簡単に想像できてしまう。
それは継母達からの言葉やされてきた行動が身体に染みついて今でも囚われているように感じているからだ。
「怖いか?」
「……っ」
黙り込む千冬を見て灯璃は席から立ち上がり隣へ座った。
繊細でありながら男らしい手が頭に置かれる。
「無理にとは言わない。だが、少しでも興味があれば人通りの少ない道を案内するし何があっても千冬を守る」
興味がないといったら嘘になる。
実母が亡くなる前はいつか瞳を見られることを気にせずに帝都を堂々と歩いてみたいと願ったこともある。
僅かな勇気を振り絞って口を開いた。
「行ってみたいです」
千冬の返事に灯璃は頭を撫でてくれた。
まるで勇気を出したことを褒めてくれるように。
「そうか。週末が楽しみだな」
千冬にとって初めての町へのお出掛け、世に言うデエトだ。
デエトなんていう言葉は少しだけ耳にしたことがあるくらいで自分にとっては大胆すぎて何だか恥ずかしくなる。
灯璃から提案されたときは不安でいっぱいだったが、彼が隣にいてくれるのなら前へ進めそうだと思えた。
二人で微笑み合う朝はとても静かで庭からは鳥のさえずりが聞こえる。
こんなにも穏やかな一日の始まりは経験したことはなかった。
襟元をくつろげていても様になっている。
入ってきた千冬に気がつくと呼んでいた新聞を閉じた。
「弁当作りは終わったのか?」
「はい。お出かけになる前にお渡しします」
千冬が座卓に座ったと同時に詩乃をはじめとした使用人達が朝食を運んできた。
いくつかのおかずの他に炊きたての白米とわかめと豆腐の味噌汁が置かれると少しだけ緊張した。
灯璃の口に合うだろうか、丁寧に出汁はとったけれど自己流だから……とお椀によそられているのを見るとさらに不安になる。
すべての料理が並べ終わると使用人達は「失礼致します」と言って居間から出て行った。
「いただきます」
灯璃が手を合わせるのを見て、考えこんでいた千冬も慌てて倣う。
「白米と味噌汁は千冬が作ったのだろう?」
「は、はい」
頷くと灯璃はお椀を持ち、味噌汁を一口飲む。
どうしても味が気になってしまい、じっと彼を見つめた。
そっと口元からお椀を離すと視線を千冬に向ける。
それはとても優しい微笑みだった。
自分には眩しすぎるくらいの光のようにも思える。
「美味い」
一番欲しかった感想が耳に届く。
その一言がどれだけ千冬にとって救いとなるか。
胸にじんわりと染みわたる。
「……!あ、ありがとうございます」
こうして褒められたのはいつぶりだろう。
継母たちにお茶を入れても何かしら文句をつけられ、「渋すぎる」「こんな不味いものを飲ませないで」と怒号を浴びるくらいだった。
何の変哲もない普通の料理一つを褒められただけでも浮かれてしまう。
緩みそうになる頬を引き締めながら千冬も箸を進める。
灯璃もそこまで口数が多くはないようで居間は静かだったが、不思議と心地が良かった。
茶碗とお椀が空になると、「おかわりをしたい」と傍に控えていた使用人に渡す。
それだけ気に入ってくれたのだとさらに嬉しくなった。
すると灯璃はそっと箸を置く。
「今日は私の帰りが遅くなる」
「かしこまりました。夕食は召し上がられますか?」
「ああ。用事を済ませたらすぐに帰るから千冬と共に食事をしたい」
「はい。もちろんです」
元々、この屋敷のあるじより先に食事をするつもりなど毛頭ないのだけれど。
「千冬はまだ身体が本調子ではないのだから一日、屋敷の中でゆっくり休むといい」
「し、しかしわたしも何かお手伝いを……」
屋敷が広い分、掃除をはじめとした家事も一苦労だろう。
何か一つくらい手伝えることがきっとあるはず。
それに、あるじが働いているのに自分だけがゆっくり休むなんて、とてもできない。
懇願するように、じっと灯璃を見つめると困ったように眉を下げた。
「千冬の願いは何でも叶えてあげたいが今日ばかりは駄目だ。また元気になったらその時は考える」
「そう、ですか……」
灯璃が駄目と言っているのだ。
これ以上お願いするのはやめようと口をつぐむ。
明らかにしょんぼりと肩を落とす千冬を見て灯璃はすぐさま次の話題を切り出した。
「千冬、今度の週末にかくりよ國の町へ出掛けないか」
「え……」
思わぬ提案に目を丸くする。
かくりよ國には人間たちが暮らす帝都と同様に書店や甘味処、デパートメントがある。
嶺木家の屋敷から出られなかった千冬は町から帰った継母達が楽しそうに話をしているのを耳にしたことがある。
お洒落をして色々な店を回る。
そんな夢と憧れが詰まった町へ行けるとなれば普通、嬉しくてすぐに頷きたいところだが千冬はその真逆で戸惑っていた。
(この瞳を見たら周りの人たちを怖がらせてしまうわ)
屋敷内でも不気味がられていたのに大勢の人が行き交う町中に出たら、どのような視線を向けられるのかわからない。
陰口を言われるのが簡単に想像できてしまう。
それは継母達からの言葉やされてきた行動が身体に染みついて今でも囚われているように感じているからだ。
「怖いか?」
「……っ」
黙り込む千冬を見て灯璃は席から立ち上がり隣へ座った。
繊細でありながら男らしい手が頭に置かれる。
「無理にとは言わない。だが、少しでも興味があれば人通りの少ない道を案内するし何があっても千冬を守る」
興味がないといったら嘘になる。
実母が亡くなる前はいつか瞳を見られることを気にせずに帝都を堂々と歩いてみたいと願ったこともある。
僅かな勇気を振り絞って口を開いた。
「行ってみたいです」
千冬の返事に灯璃は頭を撫でてくれた。
まるで勇気を出したことを褒めてくれるように。
「そうか。週末が楽しみだな」
千冬にとって初めての町へのお出掛け、世に言うデエトだ。
デエトなんていう言葉は少しだけ耳にしたことがあるくらいで自分にとっては大胆すぎて何だか恥ずかしくなる。
灯璃から提案されたときは不安でいっぱいだったが、彼が隣にいてくれるのなら前へ進めそうだと思えた。
二人で微笑み合う朝はとても静かで庭からは鳥のさえずりが聞こえる。
こんなにも穏やかな一日の始まりは経験したことはなかった。