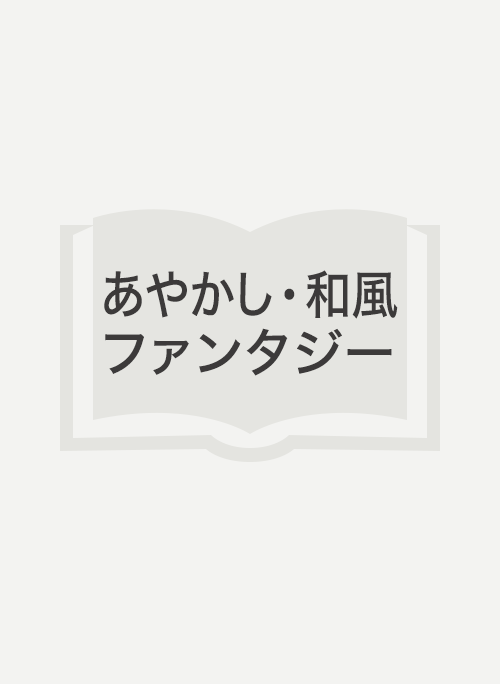「よし……」
菜箸で弁当箱の空いていた箇所に卵焼きを詰める。
弁当作りを頼まれたときは不安だったがおおむね満足する出来映えになった。
白米のおむすびに塩鮭、漬け物と卵焼き。
「とても美味しそうですね」
隣で朝食を作っていた一人の料理人が完成した弁当を覗き込む。
千冬も先ほどここで働く料理人達が、元は老舗の高級料亭で修業をしていたことを知り驚くと共に昨夜の食事の味を思い出し納得した。
そんな凄い腕をもつ料理人に褒められたのが素直に嬉しく頬が緩む。
他人から見ても美味しそうに見えるのだと胸を撫で下ろした。
「ありがとうございます。喜んでくださると良いのですが……」
「花嫁さまが一生懸命、お作りになられたのですからきっと大丈夫ですよ」
穏やかな笑みと言葉に嘘はなく、背中を押してくれる。
嶺木家の使用人たちも千冬を虐めたりはしなかったものの、深く関わろうとはせず会話も必要最小限だった。
しかし長い間、会話をまともにしてこなかったからか、やはり人の目を見て話すのは苦手で直視はできない。
もう年齢的にも立場上でも、しっかりしなくてはいけないのに紫紺色の瞳を見られるのが怖くて時々、視線が逸れてしまう。
こんな調子だと相手が相手なら気分を不快にさせてしまうだろう。
この瞳を見ても怖がらない鬼城家の使用人達の本音が知りたくて千冬は口を開く。
「あの……皆さまはわたしの瞳を見て怖がらないのですか?」
『呪われた子』『不幸を招く』と言われ続け、それは実母が亡くなってから拍車をかけるように酷くなった。
実際、それが現実になってしまったこともあるのに彼らは一向に嫌悪した姿を見せない。
嬉しいことなのに戸惑う気持ちの方が大きい。
自分でも呆れるほどの、か細い声は相手に届いたかわからない。
「こんなにも美しい瞳なのに怖いだなんて思いませんよ」
料理人の男性は怯えるどころか、にこやかな表情でこちらを見つめている。
きっと言い伝えを知らないのだろう。
このまま隠していても知られるのは時間の問題だ。
千冬は嫌われる覚悟で口を開いた。
「あの、紫紺色の瞳にまつわる言い伝えをご存知ではないですか?」
「言い伝え……。ああ!私はそのようなものなどまったく信じていませんよ」
千冬の言葉にやっと思い出したようだったが灯璃と同様、信じていなかった。
嶺木家の者たちや妹の婚約者とは違う反応。
言い伝えの内容自体は耳にしているようだが、なぜ気にせずにいられるのが不明だ。
もし言い伝えが事実ならば、鬼城家にとっても痛手になるだろう。
あやかしたちが強い霊力をもっているのも知っているし有事の際は余裕で対処できるはずだと分かってはいるのだけれど。
言葉の真意が知りたくて何も言わず静かに待った。
「灯璃さまが選ばれた御方ですから、私達は信じます。それに花嫁さまを見ていれば、そのようなことをする方ではないとわかります」
「……!」
言葉に含まれる熱量と真剣な瞳を見て、あるじを信頼しているのが伝わる。
二人の会話が聞こえたのか他の料理人たちも近くに寄ってきた。
「もし周囲に何か言われても我々や使用人たちもお支えいたします」
「何より灯璃さまがいらっしゃいます。ご安心ください」
「……ありがとうございます」
彼らの言葉で胸に抱えていた靄が晴れたような気がして前に進むための自信になる。
「花嫁さま、朝食も間もなく出来上がります。お米とお味噌汁を先に作ってくださって助かりました」
「いいえ、そんな……。でも昨夜のお礼がしたかったので喜んでいただけて嬉しいです。わたしもお弁当も包んだら終わりです」
「ではこちらをお使いください」
紺色の弁当包みを受け取り、喜んでもらえますようにと願いをこめて蓋を閉めた。
菜箸で弁当箱の空いていた箇所に卵焼きを詰める。
弁当作りを頼まれたときは不安だったがおおむね満足する出来映えになった。
白米のおむすびに塩鮭、漬け物と卵焼き。
「とても美味しそうですね」
隣で朝食を作っていた一人の料理人が完成した弁当を覗き込む。
千冬も先ほどここで働く料理人達が、元は老舗の高級料亭で修業をしていたことを知り驚くと共に昨夜の食事の味を思い出し納得した。
そんな凄い腕をもつ料理人に褒められたのが素直に嬉しく頬が緩む。
他人から見ても美味しそうに見えるのだと胸を撫で下ろした。
「ありがとうございます。喜んでくださると良いのですが……」
「花嫁さまが一生懸命、お作りになられたのですからきっと大丈夫ですよ」
穏やかな笑みと言葉に嘘はなく、背中を押してくれる。
嶺木家の使用人たちも千冬を虐めたりはしなかったものの、深く関わろうとはせず会話も必要最小限だった。
しかし長い間、会話をまともにしてこなかったからか、やはり人の目を見て話すのは苦手で直視はできない。
もう年齢的にも立場上でも、しっかりしなくてはいけないのに紫紺色の瞳を見られるのが怖くて時々、視線が逸れてしまう。
こんな調子だと相手が相手なら気分を不快にさせてしまうだろう。
この瞳を見ても怖がらない鬼城家の使用人達の本音が知りたくて千冬は口を開く。
「あの……皆さまはわたしの瞳を見て怖がらないのですか?」
『呪われた子』『不幸を招く』と言われ続け、それは実母が亡くなってから拍車をかけるように酷くなった。
実際、それが現実になってしまったこともあるのに彼らは一向に嫌悪した姿を見せない。
嬉しいことなのに戸惑う気持ちの方が大きい。
自分でも呆れるほどの、か細い声は相手に届いたかわからない。
「こんなにも美しい瞳なのに怖いだなんて思いませんよ」
料理人の男性は怯えるどころか、にこやかな表情でこちらを見つめている。
きっと言い伝えを知らないのだろう。
このまま隠していても知られるのは時間の問題だ。
千冬は嫌われる覚悟で口を開いた。
「あの、紫紺色の瞳にまつわる言い伝えをご存知ではないですか?」
「言い伝え……。ああ!私はそのようなものなどまったく信じていませんよ」
千冬の言葉にやっと思い出したようだったが灯璃と同様、信じていなかった。
嶺木家の者たちや妹の婚約者とは違う反応。
言い伝えの内容自体は耳にしているようだが、なぜ気にせずにいられるのが不明だ。
もし言い伝えが事実ならば、鬼城家にとっても痛手になるだろう。
あやかしたちが強い霊力をもっているのも知っているし有事の際は余裕で対処できるはずだと分かってはいるのだけれど。
言葉の真意が知りたくて何も言わず静かに待った。
「灯璃さまが選ばれた御方ですから、私達は信じます。それに花嫁さまを見ていれば、そのようなことをする方ではないとわかります」
「……!」
言葉に含まれる熱量と真剣な瞳を見て、あるじを信頼しているのが伝わる。
二人の会話が聞こえたのか他の料理人たちも近くに寄ってきた。
「もし周囲に何か言われても我々や使用人たちもお支えいたします」
「何より灯璃さまがいらっしゃいます。ご安心ください」
「……ありがとうございます」
彼らの言葉で胸に抱えていた靄が晴れたような気がして前に進むための自信になる。
「花嫁さま、朝食も間もなく出来上がります。お米とお味噌汁を先に作ってくださって助かりました」
「いいえ、そんな……。でも昨夜のお礼がしたかったので喜んでいただけて嬉しいです。わたしもお弁当も包んだら終わりです」
「ではこちらをお使いください」
紺色の弁当包みを受け取り、喜んでもらえますようにと願いをこめて蓋を閉めた。