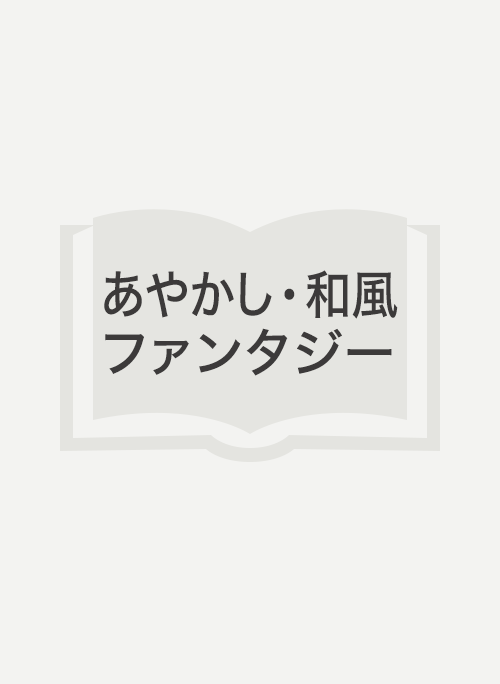千冬が灯璃へのお弁当を作り始めた頃。
各分家の屋敷には花嫁が見つかったとの旨が書かれた書状が届いていた。
誰しもが灯璃は婚約者の薫子と結婚をするだろうと思っていたため、かなりの騒ぎになっていた。
それもそのはず。
人間の娘から鬼の花嫁になる者はここ数十年間、現れていなかったから。
その書状はもちろん薫子の元にも届いていた。
「薫子さま、灯璃さまからこちらが届きました」
異国情緒を感じさせる豪奢な部屋にある革張りのソファで優雅に紅茶を飲んでいる薫子に使用人は書状を手渡す。
朝日を受けてさらに艶やかになる長い黒髪。
白く透き通るような肌に桜唇、そして鬼の証である赤い瞳をもつ姿は精巧に作られた人形のよう。
『灯璃』という名前を聞いて薫子は満開の笑みを浮かべ、ティーカップを置いた。
「まあ!灯璃さまから?」
頬を染めて喜ぶ姿はまさしく恋する乙女で、すぐに使用人から書状を受け取る。
「灯璃さまから送られてくるなんてはじめてだわ。もしかして祝言の日取りかしら」
はやる心を抑えながら丁寧に開き、文面に目を通す。
しばらくして書状をすべて読み終えると薫子は手にしていた書状を突然、クシャリと握りしめた。
「か、薫子さま?どうされましたか?」
傍に控えていた使用人は書状を握ったまま身体を震わせ、俯いている薫子におそるおそる声をかける。
「花嫁さまが見つかったから私との婚約は白紙にすると」
「そんな……!」
薫子が幼い頃から仕えてきた使用人は彼女が灯璃に恋心を抱いていたのを知っていた。
灯璃の花嫁が決められた期限までに見つからなければ結婚をすると両親から伝えられたときは、それはもう共に泣いて喜んだ。
薫子は来るべき未来のために花嫁修業にも取り組んできた。
多くの習い事をこなし、かくりよ國にある女学院でも優秀な成績を修め、これで良妻賢母になれると自信をもっていた。
忙しい灯璃と会えるのは年に数回。
パーティーなどで会って多少会話を交わしてわかる。
灯璃は自分に恋愛感情は抱いていないと。
それでも良かった。
彼の隣にいて愛する人との子を成せるなら。
期限も残りわずか。
来年には鬼城家の女主人に、灯璃の妻になれる。
しかしそんな想いも呆気なく散った。
今までの努力もすべて恋い慕っていた灯璃のため。
あやかしたちは人間の花嫁にすべての愛を捧げる。
これからは自分に見向きもしなくなると考えただけで、やるせない。
薫子は顔を上げ、真っ直ぐ前を見たまま口を開いた。
「その花嫁だという娘についてすぐに調べて」
「か、かしこまりました」
使用人が足早に部屋を出て行くとシンと辺りが静まり返る。
薫子は丸めた書状を敷いてある絨毯に放ると足で踏みつけた。
「灯璃さまに相応しいのは、この私ですわ」
冷たい声は誰にも聞かれることはない。
怒りに満ちた瞳はまるで燃え上がるよう炎のよう。
薫子は再びソーサーからカップを持ち上げ口にするが、紅茶を飲んでも湧き出る花嫁への憎しみが落ち着くことはなかった。
各分家の屋敷には花嫁が見つかったとの旨が書かれた書状が届いていた。
誰しもが灯璃は婚約者の薫子と結婚をするだろうと思っていたため、かなりの騒ぎになっていた。
それもそのはず。
人間の娘から鬼の花嫁になる者はここ数十年間、現れていなかったから。
その書状はもちろん薫子の元にも届いていた。
「薫子さま、灯璃さまからこちらが届きました」
異国情緒を感じさせる豪奢な部屋にある革張りのソファで優雅に紅茶を飲んでいる薫子に使用人は書状を手渡す。
朝日を受けてさらに艶やかになる長い黒髪。
白く透き通るような肌に桜唇、そして鬼の証である赤い瞳をもつ姿は精巧に作られた人形のよう。
『灯璃』という名前を聞いて薫子は満開の笑みを浮かべ、ティーカップを置いた。
「まあ!灯璃さまから?」
頬を染めて喜ぶ姿はまさしく恋する乙女で、すぐに使用人から書状を受け取る。
「灯璃さまから送られてくるなんてはじめてだわ。もしかして祝言の日取りかしら」
はやる心を抑えながら丁寧に開き、文面に目を通す。
しばらくして書状をすべて読み終えると薫子は手にしていた書状を突然、クシャリと握りしめた。
「か、薫子さま?どうされましたか?」
傍に控えていた使用人は書状を握ったまま身体を震わせ、俯いている薫子におそるおそる声をかける。
「花嫁さまが見つかったから私との婚約は白紙にすると」
「そんな……!」
薫子が幼い頃から仕えてきた使用人は彼女が灯璃に恋心を抱いていたのを知っていた。
灯璃の花嫁が決められた期限までに見つからなければ結婚をすると両親から伝えられたときは、それはもう共に泣いて喜んだ。
薫子は来るべき未来のために花嫁修業にも取り組んできた。
多くの習い事をこなし、かくりよ國にある女学院でも優秀な成績を修め、これで良妻賢母になれると自信をもっていた。
忙しい灯璃と会えるのは年に数回。
パーティーなどで会って多少会話を交わしてわかる。
灯璃は自分に恋愛感情は抱いていないと。
それでも良かった。
彼の隣にいて愛する人との子を成せるなら。
期限も残りわずか。
来年には鬼城家の女主人に、灯璃の妻になれる。
しかしそんな想いも呆気なく散った。
今までの努力もすべて恋い慕っていた灯璃のため。
あやかしたちは人間の花嫁にすべての愛を捧げる。
これからは自分に見向きもしなくなると考えただけで、やるせない。
薫子は顔を上げ、真っ直ぐ前を見たまま口を開いた。
「その花嫁だという娘についてすぐに調べて」
「か、かしこまりました」
使用人が足早に部屋を出て行くとシンと辺りが静まり返る。
薫子は丸めた書状を敷いてある絨毯に放ると足で踏みつけた。
「灯璃さまに相応しいのは、この私ですわ」
冷たい声は誰にも聞かれることはない。
怒りに満ちた瞳はまるで燃え上がるよう炎のよう。
薫子は再びソーサーからカップを持ち上げ口にするが、紅茶を飲んでも湧き出る花嫁への憎しみが落ち着くことはなかった。