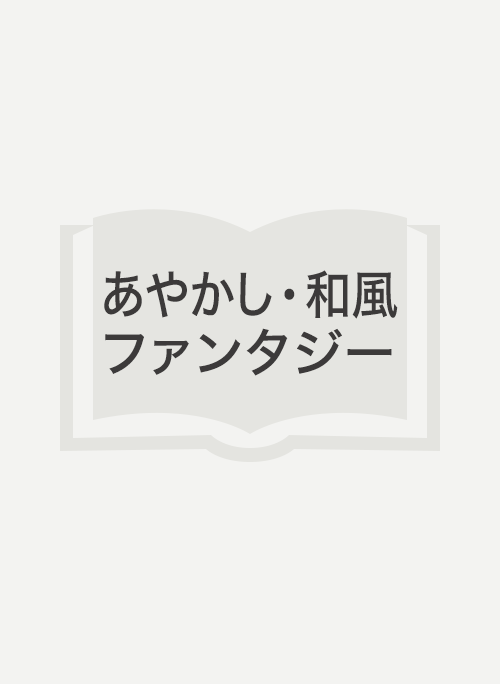「……ん」
部屋を朝日が障子越しに白く照らす。
僅かに感じた眩しさにそっと瞼を開けると視界に入る普段とは違う木目の天井に一瞬、混沌としてしまう。
慌てて身体を起こし、辺りをそっと見渡す。
どうして実家ではない場所にいるのか必死に記憶を手繰り寄せる。
(あ……)
ふと綺麗に畳んで隅に置いてあるお仕着せ服を見て昨夜の出来事を思い出した。
人生に絶望をして川に身を投げ入れようとしたけれど一人の男性に助けられて……。
その男性はあやかしの頂点である鬼、鬼城灯璃で、自分を花嫁だと言う彼の屋敷で共に暮らすことになったのだと。
とても信じられないような話だが、広い部屋と上等な調度品が夢ではなく現実なのだと思わせる。
(そろそろ起きて朝食作りのお手伝いをしないと)
嶺木家では継母達が起床する前には台所に立っていなくてはいけなかった。
この屋敷にいるということは花嫁に、いずれは妻になるということ。
その立場になるためには、足りないものが多すぎる。
千冬の実の母である千鶴は生前、娘に習い事をさせたいと父に頼んでいたが紫紺色の瞳を講師に見られたくないと頑なに拒否していた。
一般的な令嬢が身につけているお花やお琴、社交ダンスはだめでも、せめて家事だけは。
(勝手に台所を使ったら迷惑かしら)
きっともうすぐ通いの使用人や料理人達も出勤してくる。
献立も決めているはずで置いてある食材を使って良いのか、ためらってしまう。
だけど何もせず、じっとしているのも無理だ。
咎められたらそのときは素直に謝罪しよう、そう考えながら立ち上がり布団を畳む。
違う環境でも体内時計はそのままだったようで、いつもと変わらない時間に起床できた。
布団を押し入れにしまって箪笥の中から貰った着物を取り出す。
いくつかある中、選んだのは淡い緑色の着物。
呉服店の店主は『お下がりなので多少、丈が合わないかもしれない』と言っていたが、着付けが終わり姿見を見ると、自分のために仕立てられたかのようにぴったりだった。
(皆さんに助けてもらってばかり。わたしの瞳を見て怖くないのかしら……)
紫紺色の瞳をもつ者は祟り神に呪われているという言い伝えは誰しも耳にはしたことがあるはず。
それなのに灯璃をはじめ、ここで働く使用人は不気味がったり怖がったりしない。
そんな人たちに出逢ったことのない千冬は親切に接してくれる彼女たちに感謝しながらも戸惑っていた。
紫紺色の瞳をもつ女性が花嫁になったからといって無理をしていないだろうかと。
もし言い伝え自体を知らなくて自分を見る目が変わってしまったらと思うと聞く勇気もでない。
着替えがすべて終わり、ぼんやりとした頭のまま襖を開けて部屋を出る。
辺りを見渡しながら長い廊下を歩き、台所を目指す。
(台所は確かこっちのはず)
昨夜、部屋まで案内されるときに灯璃の書斎や台所の場所もある程度だが教えてもらったのだ。
おぼろげな記憶をたどりに歩いていくと無事に台所に到着し安堵する。
やはり、まだ時間が早いせいか使用人や料理人も来ていない。
(まずはお米を炊いて……あとはお味噌汁も)
おかずは他人が口にするとなると少し自信がない。
昨夜に料理人達が調理した料理を食べたからか尚更だった。
せめて白米と味噌汁の準備くらいはと千冬は置いてあった食材を手に取り、調理を始めた。
しばらく調理をしていると、そっと台所の扉が開いて灯璃が顔を出した。
「……千冬?」
「おはようございます、鬼城さま」
「朝食を作ってくれているのか?」
野菜を切っている途中の千冬を見て僅かに目を大きくしている。
「はい。……あの勝手をして申し訳ありません」
「千冬はこの屋敷の女主人になるのだから自由に使ってくれて構わない。だが、身体はもう平気なのか?」
おそらく昨夜にあんな出来事があって、あまり眠らずに早朝から朝食作りをする千冬の負担を考えてくれているのだろう。
しかし夕食と風呂、使い心地の良い布団のおかげで身体が軽くなった千冬は安心させるように笑って頷いた。
「大丈夫です。疲れもなく、体調もいいです」
「そうか、なら良かった」
優しさに満ちた瞳が向けられる。
もしかしたら花嫁が炊事を行うなど相応しくないと咎められるかもしれないと思っていたが、その心配は不要だったようだ。
「まだ作り終わるまで時間がかかるので、もうしばらくお待ちくだ……」
「灯璃さま、花嫁さま……!?」
すると、出勤時間になったのか料理人であろう男性、数名が台所の入り口に立っていた灯璃の後ろから顔を見せる。
千冬がおたまを片手に持ち、釜や鍋から湯気が立ち上る様子に料理人達は血相を変えた。
「も、もしかして朝食をお作りになられているのですか?」
「は、はい。勝手をしてしまって申し訳ありません」
彼らのうろたえる姿を見て、やはりまずいことをしてしまったと後悔が押し寄せる。
この屋敷のあるじである灯璃は許可をしたが、大事な仕事を奪ってしまったのだと。
深々と頭を下げて謝罪している千冬に料理人達は、さらに顔色を青ざめさせた。
「ど、どうか顔をお上げください!私達こそ花嫁さまのお手を煩わせてしまって申し訳ありません……!」
「そんなことないです……!わたし、昨日のお礼をしたくて。きっと皆さまには皆さまなりの手順もあるのですよね。本当に申し訳ありません」
何か役に立ちたいと必死になっていて、よかれと思ってやったことが、むしろ迷惑になっていたかもしれないと思った千冬はいたたまれなくなる。
こんな自分を大切に思ってくれる人たちにせっかく出逢えたのに嫌われてしまったら、また一人になってしまったら……。
頭を下げながら嶺木家での孤独感を思い出す。
「千冬」
震える肩に灯璃の手が置かれて、ようやく千冬は顔を上げた。
そこには灯璃をはじめ、穏やかに微笑む料理人達の姿があった。
「千冬は皆のために手伝ってくれたのだろう?謝る必要はない。むしろ私達が感謝を伝えるべきだ。ありがとう」
「ありがとうございます、花嫁さま!」
「我々もとても助かります!」
起こったり呆れたりするどころか、次々と挙がる心からの感謝の声に胸の奥から安堵と嬉しさが入り交じった感情が生まれる。
「皆さま……」
嶺木家で向けられていた眼差しとはまるで違う。
暗く沈んでいても手を差し伸べてくれる温かさに救われる。
そんな笑顔が戻った千冬に灯璃は戸棚に置いてある弁当箱を指し示す。
「朝食作りは彼らに任せて、もしよければ千冬に私の弁当を作ってもらいたいのだが」
「は、はい。もちろんです。ですが、わたしの腕では立派なものは作れないかと……」
父や継母は外食がほとんどで妹の依鈴は料理人が作る豪華なお弁当だった。
鬼帝である灯璃が満足する弁当を作れるかわからない。
それに千冬の食事はいつも余り物の食材を使用して自ら調理するか、食べられないかのどちらかだった。
誰かに弁当を作るのは初めて、そこまで立派なものを作れるか不安になる。
しかし灯璃の提案に一番驚いたのは料理人達だった。
「灯璃さまがお弁当を……!?」
「やっと……!」
驚きで身体が固まる者や中には涙ぐむ者までいる。
なぜ弁当を頼むだけで一大事が起きたかのような反応をするのか分からず、千冬は首を傾げる。
「あの……?」
話がまったく見えなくて困惑していると料理人の一人が、そんな千冬に気がついた。
「ああ、花嫁さま申し訳ありません。食に興味などなかった灯璃さまが弁当を頼むなんてはじめてのことでつい……」
「仕事が忙しいと食事も疎かになられますから」
(だから……。皆さま嬉しそう)
多事多端な上に食事も疎かになると体調面でも心配になる。
まあ、千冬も人のことを言える立場ではないのだけれど。
「おい、しゃべりすぎだ」
自分のことをベラベラと話されたことに、もしくは千冬と彼らの距離が近いことに怒っているのか、鋭い眼光を向ける。
もちろん料理人達だけに。
「も、申し訳ありません」
あるじに怒られた彼らは笑顔から一変、先ほどと同様の表情に戻ってしまう。
灯璃はため息をつき一瞥すると、千冬に向き直る。
もうそこには怒りなど微塵も残っておらず、ただ優しさに満ち溢れた眼差しだった。
「立派な料理を、などと無理しなくていい。私は千冬の手料理が食べてみたい。お願いできるか?」
「鬼城さま……。はい、かしこまりました」
素人の料理に満足させられるか気がかりだったが、彼の想いに気持ちが晴れていく。
そんな二人を料理人達は微笑ましそうに見ていたのだった。
部屋を朝日が障子越しに白く照らす。
僅かに感じた眩しさにそっと瞼を開けると視界に入る普段とは違う木目の天井に一瞬、混沌としてしまう。
慌てて身体を起こし、辺りをそっと見渡す。
どうして実家ではない場所にいるのか必死に記憶を手繰り寄せる。
(あ……)
ふと綺麗に畳んで隅に置いてあるお仕着せ服を見て昨夜の出来事を思い出した。
人生に絶望をして川に身を投げ入れようとしたけれど一人の男性に助けられて……。
その男性はあやかしの頂点である鬼、鬼城灯璃で、自分を花嫁だと言う彼の屋敷で共に暮らすことになったのだと。
とても信じられないような話だが、広い部屋と上等な調度品が夢ではなく現実なのだと思わせる。
(そろそろ起きて朝食作りのお手伝いをしないと)
嶺木家では継母達が起床する前には台所に立っていなくてはいけなかった。
この屋敷にいるということは花嫁に、いずれは妻になるということ。
その立場になるためには、足りないものが多すぎる。
千冬の実の母である千鶴は生前、娘に習い事をさせたいと父に頼んでいたが紫紺色の瞳を講師に見られたくないと頑なに拒否していた。
一般的な令嬢が身につけているお花やお琴、社交ダンスはだめでも、せめて家事だけは。
(勝手に台所を使ったら迷惑かしら)
きっともうすぐ通いの使用人や料理人達も出勤してくる。
献立も決めているはずで置いてある食材を使って良いのか、ためらってしまう。
だけど何もせず、じっとしているのも無理だ。
咎められたらそのときは素直に謝罪しよう、そう考えながら立ち上がり布団を畳む。
違う環境でも体内時計はそのままだったようで、いつもと変わらない時間に起床できた。
布団を押し入れにしまって箪笥の中から貰った着物を取り出す。
いくつかある中、選んだのは淡い緑色の着物。
呉服店の店主は『お下がりなので多少、丈が合わないかもしれない』と言っていたが、着付けが終わり姿見を見ると、自分のために仕立てられたかのようにぴったりだった。
(皆さんに助けてもらってばかり。わたしの瞳を見て怖くないのかしら……)
紫紺色の瞳をもつ者は祟り神に呪われているという言い伝えは誰しも耳にはしたことがあるはず。
それなのに灯璃をはじめ、ここで働く使用人は不気味がったり怖がったりしない。
そんな人たちに出逢ったことのない千冬は親切に接してくれる彼女たちに感謝しながらも戸惑っていた。
紫紺色の瞳をもつ女性が花嫁になったからといって無理をしていないだろうかと。
もし言い伝え自体を知らなくて自分を見る目が変わってしまったらと思うと聞く勇気もでない。
着替えがすべて終わり、ぼんやりとした頭のまま襖を開けて部屋を出る。
辺りを見渡しながら長い廊下を歩き、台所を目指す。
(台所は確かこっちのはず)
昨夜、部屋まで案内されるときに灯璃の書斎や台所の場所もある程度だが教えてもらったのだ。
おぼろげな記憶をたどりに歩いていくと無事に台所に到着し安堵する。
やはり、まだ時間が早いせいか使用人や料理人も来ていない。
(まずはお米を炊いて……あとはお味噌汁も)
おかずは他人が口にするとなると少し自信がない。
昨夜に料理人達が調理した料理を食べたからか尚更だった。
せめて白米と味噌汁の準備くらいはと千冬は置いてあった食材を手に取り、調理を始めた。
しばらく調理をしていると、そっと台所の扉が開いて灯璃が顔を出した。
「……千冬?」
「おはようございます、鬼城さま」
「朝食を作ってくれているのか?」
野菜を切っている途中の千冬を見て僅かに目を大きくしている。
「はい。……あの勝手をして申し訳ありません」
「千冬はこの屋敷の女主人になるのだから自由に使ってくれて構わない。だが、身体はもう平気なのか?」
おそらく昨夜にあんな出来事があって、あまり眠らずに早朝から朝食作りをする千冬の負担を考えてくれているのだろう。
しかし夕食と風呂、使い心地の良い布団のおかげで身体が軽くなった千冬は安心させるように笑って頷いた。
「大丈夫です。疲れもなく、体調もいいです」
「そうか、なら良かった」
優しさに満ちた瞳が向けられる。
もしかしたら花嫁が炊事を行うなど相応しくないと咎められるかもしれないと思っていたが、その心配は不要だったようだ。
「まだ作り終わるまで時間がかかるので、もうしばらくお待ちくだ……」
「灯璃さま、花嫁さま……!?」
すると、出勤時間になったのか料理人であろう男性、数名が台所の入り口に立っていた灯璃の後ろから顔を見せる。
千冬がおたまを片手に持ち、釜や鍋から湯気が立ち上る様子に料理人達は血相を変えた。
「も、もしかして朝食をお作りになられているのですか?」
「は、はい。勝手をしてしまって申し訳ありません」
彼らのうろたえる姿を見て、やはりまずいことをしてしまったと後悔が押し寄せる。
この屋敷のあるじである灯璃は許可をしたが、大事な仕事を奪ってしまったのだと。
深々と頭を下げて謝罪している千冬に料理人達は、さらに顔色を青ざめさせた。
「ど、どうか顔をお上げください!私達こそ花嫁さまのお手を煩わせてしまって申し訳ありません……!」
「そんなことないです……!わたし、昨日のお礼をしたくて。きっと皆さまには皆さまなりの手順もあるのですよね。本当に申し訳ありません」
何か役に立ちたいと必死になっていて、よかれと思ってやったことが、むしろ迷惑になっていたかもしれないと思った千冬はいたたまれなくなる。
こんな自分を大切に思ってくれる人たちにせっかく出逢えたのに嫌われてしまったら、また一人になってしまったら……。
頭を下げながら嶺木家での孤独感を思い出す。
「千冬」
震える肩に灯璃の手が置かれて、ようやく千冬は顔を上げた。
そこには灯璃をはじめ、穏やかに微笑む料理人達の姿があった。
「千冬は皆のために手伝ってくれたのだろう?謝る必要はない。むしろ私達が感謝を伝えるべきだ。ありがとう」
「ありがとうございます、花嫁さま!」
「我々もとても助かります!」
起こったり呆れたりするどころか、次々と挙がる心からの感謝の声に胸の奥から安堵と嬉しさが入り交じった感情が生まれる。
「皆さま……」
嶺木家で向けられていた眼差しとはまるで違う。
暗く沈んでいても手を差し伸べてくれる温かさに救われる。
そんな笑顔が戻った千冬に灯璃は戸棚に置いてある弁当箱を指し示す。
「朝食作りは彼らに任せて、もしよければ千冬に私の弁当を作ってもらいたいのだが」
「は、はい。もちろんです。ですが、わたしの腕では立派なものは作れないかと……」
父や継母は外食がほとんどで妹の依鈴は料理人が作る豪華なお弁当だった。
鬼帝である灯璃が満足する弁当を作れるかわからない。
それに千冬の食事はいつも余り物の食材を使用して自ら調理するか、食べられないかのどちらかだった。
誰かに弁当を作るのは初めて、そこまで立派なものを作れるか不安になる。
しかし灯璃の提案に一番驚いたのは料理人達だった。
「灯璃さまがお弁当を……!?」
「やっと……!」
驚きで身体が固まる者や中には涙ぐむ者までいる。
なぜ弁当を頼むだけで一大事が起きたかのような反応をするのか分からず、千冬は首を傾げる。
「あの……?」
話がまったく見えなくて困惑していると料理人の一人が、そんな千冬に気がついた。
「ああ、花嫁さま申し訳ありません。食に興味などなかった灯璃さまが弁当を頼むなんてはじめてのことでつい……」
「仕事が忙しいと食事も疎かになられますから」
(だから……。皆さま嬉しそう)
多事多端な上に食事も疎かになると体調面でも心配になる。
まあ、千冬も人のことを言える立場ではないのだけれど。
「おい、しゃべりすぎだ」
自分のことをベラベラと話されたことに、もしくは千冬と彼らの距離が近いことに怒っているのか、鋭い眼光を向ける。
もちろん料理人達だけに。
「も、申し訳ありません」
あるじに怒られた彼らは笑顔から一変、先ほどと同様の表情に戻ってしまう。
灯璃はため息をつき一瞥すると、千冬に向き直る。
もうそこには怒りなど微塵も残っておらず、ただ優しさに満ち溢れた眼差しだった。
「立派な料理を、などと無理しなくていい。私は千冬の手料理が食べてみたい。お願いできるか?」
「鬼城さま……。はい、かしこまりました」
素人の料理に満足させられるか気がかりだったが、彼の想いに気持ちが晴れていく。
そんな二人を料理人達は微笑ましそうに見ていたのだった。